2025年7月1日
日本鉄リサイクル工業会は、きょう7月1日で創立50周年を迎えた。1975年に前身の社団法人日本鉄屑工業会が発足し、鉄スクラップのリサイクルに取り組むことで経済発展に貢献しながら、地球環境の保全に努めてきた。2050年のカーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーの実現に向け、鉄スクラップが果たす役割は高まっている。第8代会長の木谷謙介氏(シマブンコーポレーション社長)に今後の展望などを聞いた。
――50周年を迎えた感想を。
「数々の先人や会員の皆さんのご支援、ご協力のたまもの。各支部・委員会のメンバーはボランティアで活動しているが、積極的に工業会活動に参加し意見を出し合ってくれている。本当に感謝している」
――この1年の活動を振り返って。
「22年の会長就任時に掲げた4つの活動の方向性は変わらず、対内的に(1)全国7支部8委員会を通じた会員企業の現状および課題の把握(2)把握した課題の解決に向けた方策の検討・実施、対外的には(3)鉄スクラップの一層の循環促進について行政や関連団体との議論・協議(4)鉄スクラップ業界の社会的認知度向上に向けた活動――について取り組んできた」
――具体的には。
「(1)会員企業の現状と課題の把握では、運営委員会を年に4回開催しているほか、各支部の部会などに本部として積極的に出席し、極力会員の生の声を拾うようにしている。(2)課題の解決に向けた方策の実施では、23年5月に適正ヤード推進委員会を立ち上げ、これまで計7回開催している。当会の委員や主管する経済産業省のほか、警察庁・環境省にもオブザーバーとして参加いただいている」
――各省庁は関連法規制の整備を進めている。
「警察庁は24年9月から25年1月まで金属盗対策に関する検討会を開き、環境省は24年10月からヤード環境対策検討会を開催している。警察庁が進める、いわゆる『金属盗対策法案』は閣議決定され、本年6月に成立した。両検討会には当会もオブザーバー参加しており、困っている実態などをお伝えしている。不適正ヤードに対する包囲網は着実に出来上がりつつある」
――一方、地方自治体が進めている屋外保管条例は基準が行き過ぎているとの声がある。
「19年の神奈川県綾瀬市から始まり、千葉市、茨城県境町、埼玉県川口市、千葉県袖ケ浦市、埼玉県、千葉県、さいたま市、茨城県常陸大宮市、茨城県、山梨県と続いている屋外保管条例の制定は、住民の環境保全を目的としており、一部自治体では行き過ぎた規制の検討も見受けられる。法令を順守している事業者でも守れないほど厳しいものについては、当会として業を圧迫することのないよう各自治体に率直な意見表明を行っている」
――他の委員会活動は。
「環境委員会は25年3月に『鉄リサイクル業におけるCO2削減のための省エネ・再エネガイドブック』を作成、配布したほか、環境講演会を開催した。また、24年度と25年度の事業として一般向けの環境PRコンテンツを制作中で、広報委員会と連携し、検討・制作に着手しており、26年3月末までに完成する予定。港湾委員会はリサイクルポート推進協議会と合同会議を開催した」
「業務対策委員会では27年に育成就労法が施行されることを受け、24年9月に下部組織として育成就労対応小委員会を設置し検討を行った。24年8月に危険体験学習会を開催したほか、24年度の労働災害事故事例調査や安全衛生対策の優良事例を会員ページに掲載した。他には従来紙ベースだった金属リサイクル伝票の電子化を進めており、25年7月以降、順次電子化への切り替えを進め稼働する予定」
――対外的な取り組みについて。
「(3)行政や関連団体との連携では、鉄スクラップの利活用拡大の検討を進める活動として、経産省・サーキュラーパートナーズ(CPs)に領域別WG『鉄鋼ワーキンググループ』が新設された。24年から日本鉄鋼連盟の連携団体として、特殊鋼倶楽部、普通鋼電炉工業会とともに参画している」
「サーキュラーエコノミーを鉄鋼の観点から見ると、今のところ鉄スクラップの高度利用の一択になる。鉄スクラップをどう有効利用するか、遊休化しているが解体していない生産設備などの再鉄源化に向けた把握、海外で解体されている船舶の国内回帰など、高炉メーカーも含めてさまざまな角度から議論している。まさに時代の変化を感じる」
「(4)社会的認知度の向上に向けた活動では、広報委員会で『鉄スクラップの環境価値~CO2マイナス1・39トン』のPR動画を動画共有サイトユーチューブや日経電子版などで広告配信を実施。自動車リサイクル法委員会は廃プラを主眼に置いた資源回収インセンティブについて関連業界団体などと連携して活動している」
――世界のリサイクル業界の団体との連携を強化している。
「24年10月にシンガポールで開かれた欧州最大のリサイクル業界団体BIRの国際会議に出席したほか、米国のリサイクル業界団体ReMA(旧ISRI)の会長と意見交換した。中国や韓国のリサイクル団体とも連絡を取り合っており、引き続き各国のリサイクル団体と連携を密に継続する」
――25年度の活動計画は。
「対内的、対外的な4つの活動の方向性に変わりはない。25年9月にワシントンのReMA本部を訪問する予定。当会として初めての訪問で、互いの取り組みや考え方などを意見交換したい。BIRは25年もアジアで国際会議を開く予定で、当会としても出席する方向で検討している」
「広報委員会は日本鉄鋼連盟から鉄スクラップの環境価値について新しい数値が発表されたことを受け、『CO2マイナス1・28トン』を打ち出した新PR動画を制作し、ユーチューブと民放各局制作テレビ番組の視聴サイトTVerで6月5日から7月7日まで配信している。他には、CO2マイナス1・28トンをかたどったピンバッジの会員への配布や、当会の創立50周年を記念して刷新した会員各社で掲示する金属製の会員章の制作、送付を進めている」
「鉄スクラップ」改称検討/グリーンで不可欠な資源
 ――先日開催した全国大会で、鉄スクラップの名称変更を検討することにつき4つの観点から提案した。
――先日開催した全国大会で、鉄スクラップの名称変更を検討することにつき4つの観点から提案した。
「今回、われわれが出荷する製品について新たな名称の検討を提案した理由は4つ。一つ目は、われわれが選別加工処理し出荷する商品について、鉄スクラップ(くず)という名前はふさわしくない。くずを広辞苑で引くと役に立たないものと書かれているが、われわれが鉄鋼メーカーへ納めるものは、製鋼原料であり溶解用冷鉄源であるということ」
「二つ目は、時代の変化に伴う言葉の意味合いやイメージの変化。昭和中期までは、鉄はリサイクルが当たり前の素材で、貴重なものだった。リサイクル原料としての『屑(くず)』はネガティブな意味合いはなかった。しかし、高度経済成長を経て、大量生産・大量消費社会が到来すると、さまざまな製品が使い捨てされるようになり、その過程で『屑』や『スクラップ』という言葉がネガティブな印象を持つようになったと思われる。当会も創立時は『日本鉄屑工業会』という名称で『鉄屑』を冠していたが、91年に日本鉄リサイクル工業会に名称変更した経緯がある」
「三つ目になるが、世界的な流れが挙げられる。欧米では鉄スクラップのことを『リサイクルドスチール』や『リサイクルドマテリアル』と呼ぶようになっている。世界的なリサイクル団体もスクラップの名称を使用しなくなった。米国のリサイクル団体ReMA(Recycled Materials Association)は、もともとISRI(Institute of Scrap Recycling Industries)だったが、24年に団体名からスクラップを外した。昨年BIRの総会に参加した際、当会がスチールスクラップと表現すると、『BIRの会議ではスクラップと呼称すると罰金だ』と冗談めいて言われた。各団体がこれらの動きをとった理由を調べると、鉄スクラップは重要な製鋼原料で、CО2の排出が少ないグリーンで必要不可欠な資源であり、使用が拡大すれば天然資源の保全にも貢献できるということを一般の方にも理解してもらい、魅力的で共感できる商品として認知されることを目指しているという。同じアジアの中国も21年から『再生鋼鉄原料』を規格として採用している」
「最後は、高炉メーカーが新たに大型電気炉を導入し高機能鋼材を製造する計画だが、そこで使用する鉄スクラップは含有成分値などを厳しく問われることになる可能性がある。成分保証までされた商品を鉄スクラップと呼ぶべきではないと考えている。今後1年かけて議論を深めたい」
――これからの50年に向けて。
「世界の鉄鋼蓄積量は30年に400億トン、50年に600億トンになると言われている。仮に回収率2%で試算すると30年に老廃スクラップとして8億トン発生することになる。50年にカーボンニュートラルを実現する上で、水素還元製鉄の開発・実装をメインで考えるとしても、移行期間における鉄スクラップの重要性を考えると、鉄スクラップの確保と有効利用のための政策対応が有用であることは間違いない。仮に、水素還元製鉄の実装の遅れや断念といった事態に陥った場合にも、鉄スクラップの増使用によりある程度のCO2削減を実現できることから、50年に向けてのサブシナリオとして、鉄スクラップの国内での確保ならびに有効利用・高度利用のための政策対応について、具体的な検討および早期の実施が必要だと考えており、現状の経産省のCPsの動きは心強い。今後も鉄リサイクルの需要は続く。貴重な資源を次世代に引き継ぐため、引き続き安定的な再資源化活動に取り組んでいきたい」(深田 政之)

――50周年を迎えた感想を。
「数々の先人や会員の皆さんのご支援、ご協力のたまもの。各支部・委員会のメンバーはボランティアで活動しているが、積極的に工業会活動に参加し意見を出し合ってくれている。本当に感謝している」
――この1年の活動を振り返って。
「22年の会長就任時に掲げた4つの活動の方向性は変わらず、対内的に(1)全国7支部8委員会を通じた会員企業の現状および課題の把握(2)把握した課題の解決に向けた方策の検討・実施、対外的には(3)鉄スクラップの一層の循環促進について行政や関連団体との議論・協議(4)鉄スクラップ業界の社会的認知度向上に向けた活動――について取り組んできた」
――具体的には。
「(1)会員企業の現状と課題の把握では、運営委員会を年に4回開催しているほか、各支部の部会などに本部として積極的に出席し、極力会員の生の声を拾うようにしている。(2)課題の解決に向けた方策の実施では、23年5月に適正ヤード推進委員会を立ち上げ、これまで計7回開催している。当会の委員や主管する経済産業省のほか、警察庁・環境省にもオブザーバーとして参加いただいている」
――各省庁は関連法規制の整備を進めている。
「警察庁は24年9月から25年1月まで金属盗対策に関する検討会を開き、環境省は24年10月からヤード環境対策検討会を開催している。警察庁が進める、いわゆる『金属盗対策法案』は閣議決定され、本年6月に成立した。両検討会には当会もオブザーバー参加しており、困っている実態などをお伝えしている。不適正ヤードに対する包囲網は着実に出来上がりつつある」
――一方、地方自治体が進めている屋外保管条例は基準が行き過ぎているとの声がある。
「19年の神奈川県綾瀬市から始まり、千葉市、茨城県境町、埼玉県川口市、千葉県袖ケ浦市、埼玉県、千葉県、さいたま市、茨城県常陸大宮市、茨城県、山梨県と続いている屋外保管条例の制定は、住民の環境保全を目的としており、一部自治体では行き過ぎた規制の検討も見受けられる。法令を順守している事業者でも守れないほど厳しいものについては、当会として業を圧迫することのないよう各自治体に率直な意見表明を行っている」
――他の委員会活動は。
「環境委員会は25年3月に『鉄リサイクル業におけるCO2削減のための省エネ・再エネガイドブック』を作成、配布したほか、環境講演会を開催した。また、24年度と25年度の事業として一般向けの環境PRコンテンツを制作中で、広報委員会と連携し、検討・制作に着手しており、26年3月末までに完成する予定。港湾委員会はリサイクルポート推進協議会と合同会議を開催した」
「業務対策委員会では27年に育成就労法が施行されることを受け、24年9月に下部組織として育成就労対応小委員会を設置し検討を行った。24年8月に危険体験学習会を開催したほか、24年度の労働災害事故事例調査や安全衛生対策の優良事例を会員ページに掲載した。他には従来紙ベースだった金属リサイクル伝票の電子化を進めており、25年7月以降、順次電子化への切り替えを進め稼働する予定」
――対外的な取り組みについて。
「(3)行政や関連団体との連携では、鉄スクラップの利活用拡大の検討を進める活動として、経産省・サーキュラーパートナーズ(CPs)に領域別WG『鉄鋼ワーキンググループ』が新設された。24年から日本鉄鋼連盟の連携団体として、特殊鋼倶楽部、普通鋼電炉工業会とともに参画している」
「サーキュラーエコノミーを鉄鋼の観点から見ると、今のところ鉄スクラップの高度利用の一択になる。鉄スクラップをどう有効利用するか、遊休化しているが解体していない生産設備などの再鉄源化に向けた把握、海外で解体されている船舶の国内回帰など、高炉メーカーも含めてさまざまな角度から議論している。まさに時代の変化を感じる」
「(4)社会的認知度の向上に向けた活動では、広報委員会で『鉄スクラップの環境価値~CO2マイナス1・39トン』のPR動画を動画共有サイトユーチューブや日経電子版などで広告配信を実施。自動車リサイクル法委員会は廃プラを主眼に置いた資源回収インセンティブについて関連業界団体などと連携して活動している」
――世界のリサイクル業界の団体との連携を強化している。
「24年10月にシンガポールで開かれた欧州最大のリサイクル業界団体BIRの国際会議に出席したほか、米国のリサイクル業界団体ReMA(旧ISRI)の会長と意見交換した。中国や韓国のリサイクル団体とも連絡を取り合っており、引き続き各国のリサイクル団体と連携を密に継続する」
――25年度の活動計画は。
「対内的、対外的な4つの活動の方向性に変わりはない。25年9月にワシントンのReMA本部を訪問する予定。当会として初めての訪問で、互いの取り組みや考え方などを意見交換したい。BIRは25年もアジアで国際会議を開く予定で、当会としても出席する方向で検討している」
「広報委員会は日本鉄鋼連盟から鉄スクラップの環境価値について新しい数値が発表されたことを受け、『CO2マイナス1・28トン』を打ち出した新PR動画を制作し、ユーチューブと民放各局制作テレビ番組の視聴サイトTVerで6月5日から7月7日まで配信している。他には、CO2マイナス1・28トンをかたどったピンバッジの会員への配布や、当会の創立50周年を記念して刷新した会員各社で掲示する金属製の会員章の制作、送付を進めている」
「鉄スクラップ」改称検討/グリーンで不可欠な資源
 ――先日開催した全国大会で、鉄スクラップの名称変更を検討することにつき4つの観点から提案した。
――先日開催した全国大会で、鉄スクラップの名称変更を検討することにつき4つの観点から提案した。「今回、われわれが出荷する製品について新たな名称の検討を提案した理由は4つ。一つ目は、われわれが選別加工処理し出荷する商品について、鉄スクラップ(くず)という名前はふさわしくない。くずを広辞苑で引くと役に立たないものと書かれているが、われわれが鉄鋼メーカーへ納めるものは、製鋼原料であり溶解用冷鉄源であるということ」
「二つ目は、時代の変化に伴う言葉の意味合いやイメージの変化。昭和中期までは、鉄はリサイクルが当たり前の素材で、貴重なものだった。リサイクル原料としての『屑(くず)』はネガティブな意味合いはなかった。しかし、高度経済成長を経て、大量生産・大量消費社会が到来すると、さまざまな製品が使い捨てされるようになり、その過程で『屑』や『スクラップ』という言葉がネガティブな印象を持つようになったと思われる。当会も創立時は『日本鉄屑工業会』という名称で『鉄屑』を冠していたが、91年に日本鉄リサイクル工業会に名称変更した経緯がある」
「三つ目になるが、世界的な流れが挙げられる。欧米では鉄スクラップのことを『リサイクルドスチール』や『リサイクルドマテリアル』と呼ぶようになっている。世界的なリサイクル団体もスクラップの名称を使用しなくなった。米国のリサイクル団体ReMA(Recycled Materials Association)は、もともとISRI(Institute of Scrap Recycling Industries)だったが、24年に団体名からスクラップを外した。昨年BIRの総会に参加した際、当会がスチールスクラップと表現すると、『BIRの会議ではスクラップと呼称すると罰金だ』と冗談めいて言われた。各団体がこれらの動きをとった理由を調べると、鉄スクラップは重要な製鋼原料で、CО2の排出が少ないグリーンで必要不可欠な資源であり、使用が拡大すれば天然資源の保全にも貢献できるということを一般の方にも理解してもらい、魅力的で共感できる商品として認知されることを目指しているという。同じアジアの中国も21年から『再生鋼鉄原料』を規格として採用している」
「最後は、高炉メーカーが新たに大型電気炉を導入し高機能鋼材を製造する計画だが、そこで使用する鉄スクラップは含有成分値などを厳しく問われることになる可能性がある。成分保証までされた商品を鉄スクラップと呼ぶべきではないと考えている。今後1年かけて議論を深めたい」
――これからの50年に向けて。
「世界の鉄鋼蓄積量は30年に400億トン、50年に600億トンになると言われている。仮に回収率2%で試算すると30年に老廃スクラップとして8億トン発生することになる。50年にカーボンニュートラルを実現する上で、水素還元製鉄の開発・実装をメインで考えるとしても、移行期間における鉄スクラップの重要性を考えると、鉄スクラップの確保と有効利用のための政策対応が有用であることは間違いない。仮に、水素還元製鉄の実装の遅れや断念といった事態に陥った場合にも、鉄スクラップの増使用によりある程度のCO2削減を実現できることから、50年に向けてのサブシナリオとして、鉄スクラップの国内での確保ならびに有効利用・高度利用のための政策対応について、具体的な検討および早期の実施が必要だと考えており、現状の経産省のCPsの動きは心強い。今後も鉄リサイクルの需要は続く。貴重な資源を次世代に引き継ぐため、引き続き安定的な再資源化活動に取り組んでいきたい」(深田 政之)















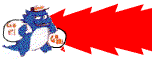

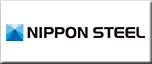

















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ


















