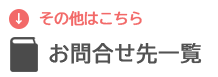2017年8月9日
目指すは日本版静脈メジャー:リサイクル4社共同出資会社 「RUN」の挑戦【下】 生き残るための覚悟/能力発揮し欧米レベルへ発展
――包括業務提携を結ぶ7社グループの名称を「ROSE」に決めた。RUNを設立した4社と、エンビプロ・ホールディングス、イボキン、中特ホールディングスを含めた7社でどのように提携を強化していくのか(敬称略)。
鈴木「7社グループは合計売上高が1000億円規模で、事業所数は全国76に及ぶ。ROSEは『The Recycle Organization for Sustainable Earth』を意味し、持続可能な社会の実現を目的に事業を展開する。統一のネーミングを作成し、活用にすることで、この共通理念の下で活動できる。当面は勉強会が中心になるが、トラックや作業服にロゴマークを使用することで、ROSEグループとしての信用を高めことができる。7社全社でなくても、構成メンバー同士での共同作業もでき、共通の『ROSE営業』もあり得るだろう。加盟社数も増える可能性があり、参加を打診している企業も出ている」
 ――国内外リサイクル産業の現状と、将来の展望をどう捉える。
――国内外リサイクル産業の現状と、将来の展望をどう捉える。
鈴木「人口減少や少子高齢化によって、国内マーケットが縮小するのは間違いない。10年先、20年先を見据えた場合、どのように舵を切ればいいのかが大きな課題になる。先進国はモノが飽和しており、高度循環型社会にシフトするのは必然といえる。国内の静脈産業は縮んでいくものの、その社会的役割は決定的なものになる。われわれも役割を果たすためにはこれまでの中小規模、しかも孤立した状態では難しく、統廃合によって、100%リサイクルに向けての研究開発、広域集荷などを実施できるメジャー化が求められる」
――マテック、青南商事は地域の雄であり、市場シェアも高い。包括業務提携に参加する意義はあるのか。
安東「東北では東日本大震災以降、人口減少、少子高齢化が加速度的に進行しており、将来に対する危機感が強い。生き残るには強烈な寡占化が必要になるが、軋轢(あつれき)を生み、中期的には自社に相当なダメージを受ける可能性がある。中国企業が欧州静脈メジャーを買収するなど、日本国内の静脈産業にも外資が入り込んでいる。見えないところでダイナミックな動きが起きており、横の連携で生き残りを図る以外に手段はない。情報の収集・分析、戦略立案などの面で提携は必須と思う」
――外資系が参入する動きがある。日本の静脈産業には魅力があるのか。
鈴木「中国資本、欧州資本が日本企業を買収する可能性は現実的にある。日本には鉄スクラップを含めて経済全体の物質的な蓄積量があり、魅力がある」
安東「また、日本はアジア諸国でも廃棄物関連の法整備がしっかりしており、ビジネスで明確なプランを立てやすいのも利点なのだと思う。中国や東南アジアの市場自体は魅力的だが、法整備が明確でないのはリスクだ」
――最後に、日本版静脈メジャー確立への意気込みを。
鈴木「私はリサイクル業に従事して約50年になるが、前半は成長期で、後半は下降期と分析している。90年までは右肩上がりの成長期で、この時期は誰もが成功できる。ところがこの成長が止まると、それぞれのエリアでの変化を捉えて、経営トップが変化に対する処方箋を書けないのであれば衰退していく。この25年で市場が縮小し、経営者の能力が見え、地域チャンピオンが登場した。今後は地域チャンピオン同士がより広域のチャンピオンを形成する、いわば戦国時代に似てきた。今はそのプロセスにある」
鈴木「日本の静脈産業は未成熟であり、今後、急速に発展させることで欧州、米国の静脈メジャーと遜色のない日本版静脈メジャーを作り上げるという目標を7年前に定めた。最終的には経営トップの覚悟の問題と考えており、われわれの能力を発揮すれば実現は可能と思っている。安東さんに社長を押し付けた形になったが、スズトクホールディングスを除く3社経営トップ(次期社長の山口大介・やまたけ常務取締役を含む)の平均年齢は46歳であり、彼らの若いセンスで日本版静脈メジャーを構築しなければならないと感じているためだ。時代は世代で変わってくる」
安東「私自身も最近、覚悟という言葉を用いるが、これから劇的に環境変化が起き、鉄スクラップだけを捉えても世界的に大きな波が来る。現に中国動向次第で状況が大きく変化する時代。コンペティターも変わり、姿が見えない相手とも戦う必要があり、日本国内もかつて経験したことがない人口減少や市場縮小に直面する。鉄スクラップの発生も伸び悩みが予想される。われわれは生き残るために覚悟を決めて、ありとあらゆる対策を練り、全方位で展開することがRUNの戦略になる。社長を引き受けた以上は本気で、日本版静脈メジャーを必ず達成する。環境は決して追い風ではないが悲観的になりすぎず、初めての取り組みでもあるし、わくわく感をもって進めていきたい」
(濱坂 浩司)

鈴木「7社グループは合計売上高が1000億円規模で、事業所数は全国76に及ぶ。ROSEは『The Recycle Organization for Sustainable Earth』を意味し、持続可能な社会の実現を目的に事業を展開する。統一のネーミングを作成し、活用にすることで、この共通理念の下で活動できる。当面は勉強会が中心になるが、トラックや作業服にロゴマークを使用することで、ROSEグループとしての信用を高めことができる。7社全社でなくても、構成メンバー同士での共同作業もでき、共通の『ROSE営業』もあり得るだろう。加盟社数も増える可能性があり、参加を打診している企業も出ている」

安東社長
鈴木「人口減少や少子高齢化によって、国内マーケットが縮小するのは間違いない。10年先、20年先を見据えた場合、どのように舵を切ればいいのかが大きな課題になる。先進国はモノが飽和しており、高度循環型社会にシフトするのは必然といえる。国内の静脈産業は縮んでいくものの、その社会的役割は決定的なものになる。われわれも役割を果たすためにはこれまでの中小規模、しかも孤立した状態では難しく、統廃合によって、100%リサイクルに向けての研究開発、広域集荷などを実施できるメジャー化が求められる」
――マテック、青南商事は地域の雄であり、市場シェアも高い。包括業務提携に参加する意義はあるのか。
安東「東北では東日本大震災以降、人口減少、少子高齢化が加速度的に進行しており、将来に対する危機感が強い。生き残るには強烈な寡占化が必要になるが、軋轢(あつれき)を生み、中期的には自社に相当なダメージを受ける可能性がある。中国企業が欧州静脈メジャーを買収するなど、日本国内の静脈産業にも外資が入り込んでいる。見えないところでダイナミックな動きが起きており、横の連携で生き残りを図る以外に手段はない。情報の収集・分析、戦略立案などの面で提携は必須と思う」
――外資系が参入する動きがある。日本の静脈産業には魅力があるのか。
鈴木「中国資本、欧州資本が日本企業を買収する可能性は現実的にある。日本には鉄スクラップを含めて経済全体の物質的な蓄積量があり、魅力がある」
安東「また、日本はアジア諸国でも廃棄物関連の法整備がしっかりしており、ビジネスで明確なプランを立てやすいのも利点なのだと思う。中国や東南アジアの市場自体は魅力的だが、法整備が明確でないのはリスクだ」
――最後に、日本版静脈メジャー確立への意気込みを。
鈴木「私はリサイクル業に従事して約50年になるが、前半は成長期で、後半は下降期と分析している。90年までは右肩上がりの成長期で、この時期は誰もが成功できる。ところがこの成長が止まると、それぞれのエリアでの変化を捉えて、経営トップが変化に対する処方箋を書けないのであれば衰退していく。この25年で市場が縮小し、経営者の能力が見え、地域チャンピオンが登場した。今後は地域チャンピオン同士がより広域のチャンピオンを形成する、いわば戦国時代に似てきた。今はそのプロセスにある」
鈴木「日本の静脈産業は未成熟であり、今後、急速に発展させることで欧州、米国の静脈メジャーと遜色のない日本版静脈メジャーを作り上げるという目標を7年前に定めた。最終的には経営トップの覚悟の問題と考えており、われわれの能力を発揮すれば実現は可能と思っている。安東さんに社長を押し付けた形になったが、スズトクホールディングスを除く3社経営トップ(次期社長の山口大介・やまたけ常務取締役を含む)の平均年齢は46歳であり、彼らの若いセンスで日本版静脈メジャーを構築しなければならないと感じているためだ。時代は世代で変わってくる」
安東「私自身も最近、覚悟という言葉を用いるが、これから劇的に環境変化が起き、鉄スクラップだけを捉えても世界的に大きな波が来る。現に中国動向次第で状況が大きく変化する時代。コンペティターも変わり、姿が見えない相手とも戦う必要があり、日本国内もかつて経験したことがない人口減少や市場縮小に直面する。鉄スクラップの発生も伸び悩みが予想される。われわれは生き残るために覚悟を決めて、ありとあらゆる対策を練り、全方位で展開することがRUNの戦略になる。社長を引き受けた以上は本気で、日本版静脈メジャーを必ず達成する。環境は決して追い風ではないが悲観的になりすぎず、初めての取り組みでもあるし、わくわく感をもって進めていきたい」
(濱坂 浩司)

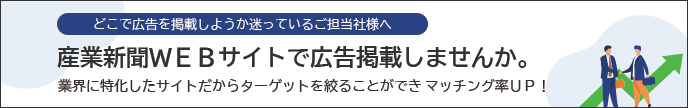














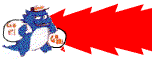











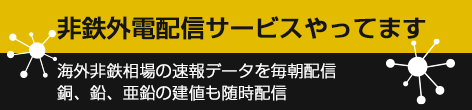




 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ