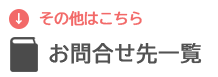2022年8月8日
愛知・あま市アートヴィレッジを行く/金属が彩る芸術「尾張七宝」/宝石よりも美しく、繊細で鮮やか/叩きとなまし、何度も繰り返し成形
愛知県あま市周辺では江戸末期以降、金属を用いて制作される七宝焼の製法の研究開発が進み、その作品は1867年のパリ万国博覧会にも作品が出展され、海外からも高い評価を受けている。1995年には「尾張七宝」として経済産業省から伝統的工芸品に指定され、現在もその技術は脈々と受け継がれている。今回、中日本ネットワークの夏季特集に当たり、あま市七宝町にある「あま市七宝焼アートヴィレッジ(以下、ヴィレッジ)」を訪れ、金属を素材に芸術を生み出す七宝焼の魅力について取材した。
◇ ◇
ヴィレッジは2004年、あま市の前身、七宝町時代に設立された。七宝町は文字通り七宝焼から名が取られており、七宝焼が地域に根付いた産業であったことが分かる。現在でも同地はあま市七宝町と呼ばれており、七宝の名が駅名など周辺各所に残っている。
ヴィレッジを訪れると最初に銅色の壁が印象的な、七宝焼ふれあい伝承館が目に入ってくる。同館では七宝焼の作品を鑑賞するだけでなく、職人の制作風景の見学や、体験教室で実際に七宝焼を制作することもでき、大人から子供まで楽しめる施設となっている。
ヴィレッジの施設長を務める、あま市役所建設産業部商工観光課の内山智美主幹によると、七宝焼の「七宝」とは仏教の経典にある7つの宝物「金・銀・瑠璃・硨磲(しゃこ、大型の2枚貝)・瑪瑙・真珠・玫瑰(まいかい、中国人で取れたきれいな赤い石)」のことを指し、七宝焼は、それら7種類の宝石よりも美しいことから、その名がつけられたと言われている。
七宝焼の歴史は古く、その技法は紀元前1700―1800年ごろの古代メソポタミアや、紀元前1500年ごろの古代エジプトまでさかのぼる。そこで作られた作品や技術が欧州に渡り、シルクロードなどを通じて中国や朝鮮半島、日本へと伝わったとされる。日本で最も古い七宝の宝物は、7世紀に造られた奈良県明日香村にある古墳から出土した飾り金具や、正倉院南倉に収められた宝物などが知られる。
その後、近世に入るとキリスト教文化の伝来などとともに、七宝の技術が日本で再び活発に使用されるようになってきた。豊臣秀吉が建てた聚楽第で使用された釘隠のほか桂離宮、日光東照宮、名古屋城などでも七宝が用いられた。当時の七宝は「象嵌七宝」と呼ばれ、銅板に模様を彫り込んでできた溝に釉薬を差す手法で作成されたものが主流であった。
江戸期に入ると、京都の七宝師であった平田道仁が幕府のお抱え技師となり、平田家は13代にわたって鍔(つば)などの刀剣小道具に七宝の飾りを付ける仕事を行った。その技術は一子相伝の秘術として伝わり、一般に七宝の技術が知られることはなかった。明治期に入っても平田家は造幣局からの依頼を受け、日本初の勲章「旭日章」の制作を行ったことでも知られている。
近代日本の七宝は、江戸時代末期に 海東郡服部村(名古屋市中川区服部)の鍍金工であった梶常吉が登場したことから始まる。梶はオランダ船が運んできた七宝焼を手に入れ、砕いて調べたところ「欧州から運ばれてきた七宝焼が、銅の土台の上にガラス質の釉薬を焼き付けて作られた、有線七宝の技術が用いられてることを知ったと伝えられている」(内山施設長)。
 梶はその後も研鑽を重ね、1833年には遂に直径約15センチの七宝の盃を完成させた。これにより日本の七宝焼の主流技術は、従来の象嵌七宝から有線七宝へと転換することになり、日本の七宝技術の大きな転換点となった。また、当時の七宝は釉薬が不透明でつやがなく、濁った色合いをしているため「泥七宝」とも呼ばれている。
梶はその後も研鑽を重ね、1833年には遂に直径約15センチの七宝の盃を完成させた。これにより日本の七宝焼の主流技術は、従来の象嵌七宝から有線七宝へと転換することになり、日本の七宝技術の大きな転換点となった。また、当時の七宝は釉薬が不透明でつやがなく、濁った色合いをしているため「泥七宝」とも呼ばれている。
その後、海部郡遠島村(現在のあま市七宝町)に生まれた林庄五郎が、梶から七宝焼の製法を学んだ。その製法を同じく遠島村の塚本貝介や塚本儀三郎らに伝えたことで、尾張七宝は広がりを見せていった。
その1人である塚本貝介は、ドイツ人化学者のワグネルと共に釉薬の研究に取り組み、つやのある鮮やかな釉薬の開発に成功した。これにより作品の美しさが各段に高まり、日本の七宝技術が飛躍し、世界最高峰となる一因となった。そうした努力の結果、海外の人々の間で日本の七宝焼が評判となり、日本政府も外貨獲得の輸出品として七宝焼に注目、生産を奨励することになっていった。
それに伴い、七宝焼の産地として遠島村周辺での七宝の生産が盛んになり、1880年から1910年ごろまでの30年間は七宝界の黄金期を迎えたと言われている。最盛期には職人の数も700人に達し、地域は七宝産業で隆盛を見せた。各窯ごとでも競うように独自の釉薬を生み出し、さまざまな七宝焼の作品が世に出ていった。
1887年には当地の七宝製造業者らが集まり、七宝組合を設立。94年には遠島に七宝焼の職人を養成する遠安工業補習学校が設立された。修業年限2年の夜間制で、七宝制作の基礎となる知識や技能が教えられた。
だが、その後、七宝焼の需要は徐々に減少していった。朝鮮戦争後には七宝業者の廃業が相次ぎ、現在では、あま市に残る窯元の数はわずか8軒にまで減っている。七宝の地に根付いた七宝の歴史と技術を後世に継承していくため、ヴィレッジが作られ、現在に至っている。
◇ ◇
その七宝焼の製造工程は7つの工程からなる。最初に銅などの金属製の板を叩いて成形する。旋盤と鉄製の棒「ヘラ」を用いて作る機械絞りと、手作業で行う手絞りがある。手絞りの場合は厚さ0・4―0・5ミリの銅板を筒状に曲げて、何度も叩きとなましを繰り返しながら少しずつ成形していく。
七宝の地で3代続く七宝焼職人である堀木道夫氏は、は素地の絞りについて「時間はかかるが、手作業の方が、より繊細な加工が可能になる」と語る。堀木氏は、実際にあて木で固定した銅板の素地を、リズミカルに木槌で叩きながら形を整えていく姿を見せてくれた。手絞りの場合「3日間ほどで完成する」とのことだ。なお、使用する銅板は市中の「伸銅品問屋から仕入れている」と教えてくれた。
記者も手絞りを体験させてもらったが、これがなかなかに難しい。記者が木槌で叩いても叩いても、銅板には無様な凹凸ができるばかりだった。絞り一つを取っても、実際に体験することで培ってきた技術の奥深さが感じられる。
成形した素地は直接または、釉薬を付けて下焼きしたものに下絵を描いていく。その下書きした絵柄に、銀や真鍮などの金属線を植え付ける。その際、野生のランである紫蘭の根を乾燥させて細かくすりつぶした「白芨」を、のりとして用い接着する。
植線を終えた素地は、ウマと呼ばれる台に固定され、線と線の間に釉薬を差す施釉と呼ばれる工程に入る。七宝焼の基本となる釉薬は硝石、硅石、鉛丹が主原料になる。それらをルツボで1200―1300度に熱すれば、「白透(しろすけ)」と呼ばれる透明な釉薬が出来上がる。
「白透」にさまざまな酸化金属を投入して色を整えていく。例えば金を混ぜれば「赤」、紅柄を混ぜれば「茶」、コバルトを混ぜれば「紺」へと変化していく。ここで加える金属の配合比率で色が決まるため配合比率は各窯の秘伝で、窯毎の違いを生み出す特色にもなっている。
施釉が終われば、窯に入れ800-850度の熱で焼き上げる。現在では窯は電気炉が用いられているが、過去は木炭を原料に焼いていた。その後、砥石や朴炭、工業ダイヤモンドなどで研磨する。最後に花瓶の口と底の部分に銀や、真鍮(黄銅)に銀めっきしたリングを締めて完成となる。
◇ ◇
こうして生み出された尾張七宝の作品は名作が多く、ヴィレッジにもさまざまな作品が展示されている。その一部を紹介したい。
 展示されている作品の中で最も目立つのが、高さ152センチと一際大きい「間取花鳥文大花瓶」だ。現在では再現が難しいほど細やかな植線されており、熟練した職人が長時間かけて作成したものとみられている。素地の銅板は温度を上げると柔らかくなり自重で潰れてしまうため、負荷がかかりやすい下部のくびれ部分は、高度な技術で制作されている。
展示されている作品の中で最も目立つのが、高さ152センチと一際大きい「間取花鳥文大花瓶」だ。現在では再現が難しいほど細やかな植線されており、熟練した職人が長時間かけて作成したものとみられている。素地の銅板は温度を上げると柔らかくなり自重で潰れてしまうため、負荷がかかりやすい下部のくびれ部分は、高度な技術で制作されている。
また、表面が輝く「茶金石古代六角面取り大香炉」も実際に目にしてほしい一品だ。銅の結晶が入った鉱石「茶金石」を細かく砕いて釉薬と混ぜたものが用いられている。銅の結晶がキラキラと反射して美しく輝き、作品の価値を高めている。
七宝焼は金属が生み出した芸術であり、尾張七宝は一部の権力者の芸術であった七宝を、一般の人も楽しめる芸術へと昇華してくれた。七宝の技術を後世につなげることは、金属業界の責務とも言えよう。読者各位におかれては夏の思い出にヴィレッジを訪れ、七宝を鑑賞、体験してみてはいかがだろうか。(服部 友裕)

◇ ◇
ヴィレッジは2004年、あま市の前身、七宝町時代に設立された。七宝町は文字通り七宝焼から名が取られており、七宝焼が地域に根付いた産業であったことが分かる。現在でも同地はあま市七宝町と呼ばれており、七宝の名が駅名など周辺各所に残っている。
ヴィレッジを訪れると最初に銅色の壁が印象的な、七宝焼ふれあい伝承館が目に入ってくる。同館では七宝焼の作品を鑑賞するだけでなく、職人の制作風景の見学や、体験教室で実際に七宝焼を制作することもでき、大人から子供まで楽しめる施設となっている。
ヴィレッジの施設長を務める、あま市役所建設産業部商工観光課の内山智美主幹によると、七宝焼の「七宝」とは仏教の経典にある7つの宝物「金・銀・瑠璃・硨磲(しゃこ、大型の2枚貝)・瑪瑙・真珠・玫瑰(まいかい、中国人で取れたきれいな赤い石)」のことを指し、七宝焼は、それら7種類の宝石よりも美しいことから、その名がつけられたと言われている。
七宝焼の歴史は古く、その技法は紀元前1700―1800年ごろの古代メソポタミアや、紀元前1500年ごろの古代エジプトまでさかのぼる。そこで作られた作品や技術が欧州に渡り、シルクロードなどを通じて中国や朝鮮半島、日本へと伝わったとされる。日本で最も古い七宝の宝物は、7世紀に造られた奈良県明日香村にある古墳から出土した飾り金具や、正倉院南倉に収められた宝物などが知られる。
その後、近世に入るとキリスト教文化の伝来などとともに、七宝の技術が日本で再び活発に使用されるようになってきた。豊臣秀吉が建てた聚楽第で使用された釘隠のほか桂離宮、日光東照宮、名古屋城などでも七宝が用いられた。当時の七宝は「象嵌七宝」と呼ばれ、銅板に模様を彫り込んでできた溝に釉薬を差す手法で作成されたものが主流であった。
江戸期に入ると、京都の七宝師であった平田道仁が幕府のお抱え技師となり、平田家は13代にわたって鍔(つば)などの刀剣小道具に七宝の飾りを付ける仕事を行った。その技術は一子相伝の秘術として伝わり、一般に七宝の技術が知られることはなかった。明治期に入っても平田家は造幣局からの依頼を受け、日本初の勲章「旭日章」の制作を行ったことでも知られている。
近代日本の七宝は、江戸時代末期に 海東郡服部村(名古屋市中川区服部)の鍍金工であった梶常吉が登場したことから始まる。梶はオランダ船が運んできた七宝焼を手に入れ、砕いて調べたところ「欧州から運ばれてきた七宝焼が、銅の土台の上にガラス質の釉薬を焼き付けて作られた、有線七宝の技術が用いられてることを知ったと伝えられている」(内山施設長)。
 梶はその後も研鑽を重ね、1833年には遂に直径約15センチの七宝の盃を完成させた。これにより日本の七宝焼の主流技術は、従来の象嵌七宝から有線七宝へと転換することになり、日本の七宝技術の大きな転換点となった。また、当時の七宝は釉薬が不透明でつやがなく、濁った色合いをしているため「泥七宝」とも呼ばれている。
梶はその後も研鑽を重ね、1833年には遂に直径約15センチの七宝の盃を完成させた。これにより日本の七宝焼の主流技術は、従来の象嵌七宝から有線七宝へと転換することになり、日本の七宝技術の大きな転換点となった。また、当時の七宝は釉薬が不透明でつやがなく、濁った色合いをしているため「泥七宝」とも呼ばれている。その後、海部郡遠島村(現在のあま市七宝町)に生まれた林庄五郎が、梶から七宝焼の製法を学んだ。その製法を同じく遠島村の塚本貝介や塚本儀三郎らに伝えたことで、尾張七宝は広がりを見せていった。
その1人である塚本貝介は、ドイツ人化学者のワグネルと共に釉薬の研究に取り組み、つやのある鮮やかな釉薬の開発に成功した。これにより作品の美しさが各段に高まり、日本の七宝技術が飛躍し、世界最高峰となる一因となった。そうした努力の結果、海外の人々の間で日本の七宝焼が評判となり、日本政府も外貨獲得の輸出品として七宝焼に注目、生産を奨励することになっていった。
それに伴い、七宝焼の産地として遠島村周辺での七宝の生産が盛んになり、1880年から1910年ごろまでの30年間は七宝界の黄金期を迎えたと言われている。最盛期には職人の数も700人に達し、地域は七宝産業で隆盛を見せた。各窯ごとでも競うように独自の釉薬を生み出し、さまざまな七宝焼の作品が世に出ていった。
1887年には当地の七宝製造業者らが集まり、七宝組合を設立。94年には遠島に七宝焼の職人を養成する遠安工業補習学校が設立された。修業年限2年の夜間制で、七宝制作の基礎となる知識や技能が教えられた。
だが、その後、七宝焼の需要は徐々に減少していった。朝鮮戦争後には七宝業者の廃業が相次ぎ、現在では、あま市に残る窯元の数はわずか8軒にまで減っている。七宝の地に根付いた七宝の歴史と技術を後世に継承していくため、ヴィレッジが作られ、現在に至っている。
◇ ◇
その七宝焼の製造工程は7つの工程からなる。最初に銅などの金属製の板を叩いて成形する。旋盤と鉄製の棒「ヘラ」を用いて作る機械絞りと、手作業で行う手絞りがある。手絞りの場合は厚さ0・4―0・5ミリの銅板を筒状に曲げて、何度も叩きとなましを繰り返しながら少しずつ成形していく。
七宝の地で3代続く七宝焼職人である堀木道夫氏は、は素地の絞りについて「時間はかかるが、手作業の方が、より繊細な加工が可能になる」と語る。堀木氏は、実際にあて木で固定した銅板の素地を、リズミカルに木槌で叩きながら形を整えていく姿を見せてくれた。手絞りの場合「3日間ほどで完成する」とのことだ。なお、使用する銅板は市中の「伸銅品問屋から仕入れている」と教えてくれた。
記者も手絞りを体験させてもらったが、これがなかなかに難しい。記者が木槌で叩いても叩いても、銅板には無様な凹凸ができるばかりだった。絞り一つを取っても、実際に体験することで培ってきた技術の奥深さが感じられる。
成形した素地は直接または、釉薬を付けて下焼きしたものに下絵を描いていく。その下書きした絵柄に、銀や真鍮などの金属線を植え付ける。その際、野生のランである紫蘭の根を乾燥させて細かくすりつぶした「白芨」を、のりとして用い接着する。
植線を終えた素地は、ウマと呼ばれる台に固定され、線と線の間に釉薬を差す施釉と呼ばれる工程に入る。七宝焼の基本となる釉薬は硝石、硅石、鉛丹が主原料になる。それらをルツボで1200―1300度に熱すれば、「白透(しろすけ)」と呼ばれる透明な釉薬が出来上がる。
「白透」にさまざまな酸化金属を投入して色を整えていく。例えば金を混ぜれば「赤」、紅柄を混ぜれば「茶」、コバルトを混ぜれば「紺」へと変化していく。ここで加える金属の配合比率で色が決まるため配合比率は各窯の秘伝で、窯毎の違いを生み出す特色にもなっている。
施釉が終われば、窯に入れ800-850度の熱で焼き上げる。現在では窯は電気炉が用いられているが、過去は木炭を原料に焼いていた。その後、砥石や朴炭、工業ダイヤモンドなどで研磨する。最後に花瓶の口と底の部分に銀や、真鍮(黄銅)に銀めっきしたリングを締めて完成となる。
◇ ◇
こうして生み出された尾張七宝の作品は名作が多く、ヴィレッジにもさまざまな作品が展示されている。その一部を紹介したい。
 展示されている作品の中で最も目立つのが、高さ152センチと一際大きい「間取花鳥文大花瓶」だ。現在では再現が難しいほど細やかな植線されており、熟練した職人が長時間かけて作成したものとみられている。素地の銅板は温度を上げると柔らかくなり自重で潰れてしまうため、負荷がかかりやすい下部のくびれ部分は、高度な技術で制作されている。
展示されている作品の中で最も目立つのが、高さ152センチと一際大きい「間取花鳥文大花瓶」だ。現在では再現が難しいほど細やかな植線されており、熟練した職人が長時間かけて作成したものとみられている。素地の銅板は温度を上げると柔らかくなり自重で潰れてしまうため、負荷がかかりやすい下部のくびれ部分は、高度な技術で制作されている。また、表面が輝く「茶金石古代六角面取り大香炉」も実際に目にしてほしい一品だ。銅の結晶が入った鉱石「茶金石」を細かく砕いて釉薬と混ぜたものが用いられている。銅の結晶がキラキラと反射して美しく輝き、作品の価値を高めている。
七宝焼は金属が生み出した芸術であり、尾張七宝は一部の権力者の芸術であった七宝を、一般の人も楽しめる芸術へと昇華してくれた。七宝の技術を後世につなげることは、金属業界の責務とも言えよう。読者各位におかれては夏の思い出にヴィレッジを訪れ、七宝を鑑賞、体験してみてはいかがだろうか。(服部 友裕)

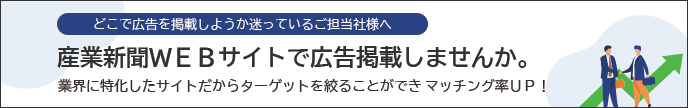













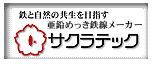
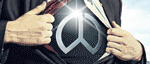













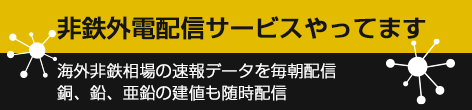




 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ