2025年2月28日
営業戦略を聞く/神戸製鋼所 宮崎庄司副社長/鉄鋼アルミ事業部門長/開発製品拡販し構成改善/北米・東南ア中心に事業強化
――中期経営計画初年の2024年度、鉄鋼アルミ事業部門の計画の進捗は。
「事業環境は非常に厳しく、自動車は認証不正問題などの影響を受け、その他分野も資機材価格の高騰や労働力不足が影響し、期初の需要見通しを下回っている。原燃料価格は前年より低く安定したが諸資材価格や保全費などコストが上がったために値上げ交渉を進め、お客様に理解をしていただいてきたが、コスト上昇分をみると鉄鋼、アルミ板とも不十分であり、値上げの必要性を粘り強く訴えていく。一方で自社のプロジェクトは計画通り取り組んでいる。厚板の仕上げミルを更新して昨年1月から本格稼働し、品質・歩留まり・生産性など期待以上の効果を上げている。立ち上げが順調でお客様からも評価をいただいている。薄板について高耐食めっき鋼板のKOBEMAGを自社で一貫生産することを決めた。薄板は自動車用ハイテン鋼が大きな柱だが、非自動車でもう一つ大きな柱を持つことは重要であり、設備を改造して早期に戦力化し、KOBEMAGの数量を伸ばしていく」
――厚板仕上げミルをリフレッシュし、21年には第3CGL(溶融亜鉛めっき設備)を稼働させるなど鋼板類の投資が具体化・戦力化している。強みの線条についての設備投資など事業強化策は。
「線条は17年の設備集約の際に物流含め大がかりな投資を行っており、新たな投資の計画はない。元々実力のある設備・事業であるが、看板商品なのでさらに利益を上げるために拡販活動を進めている。EV化の進展に対応した軟磁性材料や二次加工時のCO2発生量を抑える熱処理省略鋼をメニューに加えるなど多様な開発製品で販売量を伸ばす。ソリューションと新規メニューで拡販していく方針だ」
――海外事業は地域によって濃淡がみえる。
「米国のプロテックは新CGLが順調に稼働している。事業は好調で米国の自動車用鋼板の供給拠点として成長している。中国の鞍鋼神鋼冷延高張力自動車鋼板は日系自動車の数量・シェアが低下しているので苦労している。パートナーの鞍鋼とともに民族系自動車を開拓するなど数量を上積みしていく。中国の線条の各二次加工メーカーは日系向けが中心だが民族系自動車向けを増やそうとしており、拡販の取り組みがカギになる」
「ASEANはタイの経済情勢が低調なために特殊鋼線材製造のコベルコミルコンスチール(KMS)、線材二次加工のKCH、磨棒鋼製造のMKCLは苦労している。中長期的にはタイの鋼材需要は伸びる予測であり、非日系含め拡販が課題となる。圧延メーカーのKMSは競合他社にない強みであり、納期・品質対応のアドバンテージを生かしながらタイ、ASEAN市場で線条の事業を大事に守り成長させていく」
――25年度の需要をどう予想する。
「国内は底打ちの動きがみられ、自動車は前年度より上向くとみている。建設は下期から大型物件を中心に徐々に回復していく見通しだ。海外は中国の経済環境が短期に好転するとは思えず、ASEANも回復の兆しがみえない。粗鋼生産は24年度予想の600万トンから大きくは変わらないだろうが、製品構成は改善する見込みだ。25年度は開発製品の拡販などで構成を改善していく」
「アルミ板について缶材向けは薄肉材の新規採用など拡販の取り組みが少しずつ身を結び、自助努力も含め25年度は数量が回復することを期待する。ディスク材は足元のデータセンター向けの需要が続く見通し。半導体製造装置向け厚板の需要の回復時期は予想が難しい。いつでも要望に応えられるよう生産性を保つが、米中の通商摩擦の影響などを注視する必要がある」
――トランプ大統領の通商政策によって受ける影響は。
「米国経済が堅調を維持する政策を続けるとみられ、現地の事業会社の事業環境は大きくは変わらないだろう。懸念されるのは米国向けの直接・間接輸出への影響だ。当社の国別の鉄鋼輸出に占める米国の割合は大きい。日本政府が適用除外を申請しており、対応に期待したい」
――中計では鉄鋼事業の成長投資を示していないが、検討している計画は。
「意思決定したものはないが、鉄鋼事業の成長を考える上での大きなテーマは海外の地産地消のニーズにいかに応えていくかだ。米国やアジアで複数検討している。人口が増え、鋼材消費量が汎用鋼中心に増えるASEANの市場をどう捉えるかということも大きな課題だ。KCHやMKCLは現地で圧倒的なシェアを持つ日系車向けが中心だが、増えつつある非日系車への参入が必要となる。高級鋼の需要が多い北米、中国、タイでプレゼンスを維持強化することが重要であり、既存製品でソリューションを展開するとともに新規メニューを投入して価値を認めていただく戦略を優先する。そこから周辺諸国に広げていく方向だ」
――高い経済成長が続くインド、高級鋼の需要地である欧州向けの輸出や投資の考えは。
「インドの市場は現地のニーズと当社のアイテムがなかなか合致しないが、人口が多く、特殊鋼の需要が増えていくのでチャンスを探っていく。欧州向けはばね鋼など線条の輸出がある。日本の内需が減っていくのでメニューを多彩化し、欧州向けなど輸出を確保する必要がある。お客様のニーズに合わせて構成を最適化していく。薄板も含めメニューを増やしていくことが大事だ」
――宝山鋼鉄グループと自動車用アルミパネルの合弁会社を設立し、中国での同パネル事業を強化した。
「中国国内でクローズドループリサイクルができるのはアドバンテージだ。パートナーの宝山鋼鉄グループの営業力は強く、アルミパネルの拡販に貢献してくれると考えている。既存の神鋼汽車鋁材(天津)も受注量を伸ばす必要があり、民族系自動車向けに拡販していく上で宝鋼とのパートナーシップは大きな戦力となる。中長期的には中国の合弁事業がアルミ板事業の大きな柱になると考えている」
――神鋼汽車鋁材(天津)の原板の調達先が出資先の韓国ウルサン・アルミナムから中国国内での調達に変わることになる。ウルサンの余力の活用法は。
「お客様の承認を2-3年かけて取得していくが、将来的なウルサンの能力の活用方法について幅広い分野で検討する」
――グリーン素材のコベナブル・スチールに続き、コベナブル・アルミをブランド化した。
「グリーン鋼材は一定のコストアップが不可避であり、商品価値を認めてもらうことが必要だが徐々に浸透している。行政も使用促進の制度の整備を進めている。多くのグリーン鋼材が市場で必要になり、価格も製造に必要な水準となれば脱炭素を図る設備投資の大きな意思決定ができ、コベナブル・スチールを大量に提供できる。自動車や造船、建築などいろいろな分野で引き合いがあり、コベナブル・アルミもブランドを発表して間もないがお客様からの関心は非常に高い。具体的な案件を期待している」
――昨年にアルミ製品のロールマージン改定を発表した。今後も価格改定を続ける考えか。
「25年度も必要に応じて価格改定を検討する。社会全体で資機材コストが上がり、修理工事など保全コストも上がっており、事情を引き続き理解していただく。アルミ板に限らず、アルミ関連製品は自動車のモデルチェンジまで一定の価格で取引する商慣習があったが、副原料などの価格がモデルチェンジまでの間に上がり、コスト構造が変わってしまう。状況を一つ一つ丁寧に説明し、モデルチェンジ前でも価格の変更を可能としたのは大きな進歩だ。ただ、足元の価格の水準は十分ではなく、お客様と対話を続けていく」(植木美知也、増岡武秀)

「事業環境は非常に厳しく、自動車は認証不正問題などの影響を受け、その他分野も資機材価格の高騰や労働力不足が影響し、期初の需要見通しを下回っている。原燃料価格は前年より低く安定したが諸資材価格や保全費などコストが上がったために値上げ交渉を進め、お客様に理解をしていただいてきたが、コスト上昇分をみると鉄鋼、アルミ板とも不十分であり、値上げの必要性を粘り強く訴えていく。一方で自社のプロジェクトは計画通り取り組んでいる。厚板の仕上げミルを更新して昨年1月から本格稼働し、品質・歩留まり・生産性など期待以上の効果を上げている。立ち上げが順調でお客様からも評価をいただいている。薄板について高耐食めっき鋼板のKOBEMAGを自社で一貫生産することを決めた。薄板は自動車用ハイテン鋼が大きな柱だが、非自動車でもう一つ大きな柱を持つことは重要であり、設備を改造して早期に戦力化し、KOBEMAGの数量を伸ばしていく」
――厚板仕上げミルをリフレッシュし、21年には第3CGL(溶融亜鉛めっき設備)を稼働させるなど鋼板類の投資が具体化・戦力化している。強みの線条についての設備投資など事業強化策は。
「線条は17年の設備集約の際に物流含め大がかりな投資を行っており、新たな投資の計画はない。元々実力のある設備・事業であるが、看板商品なのでさらに利益を上げるために拡販活動を進めている。EV化の進展に対応した軟磁性材料や二次加工時のCO2発生量を抑える熱処理省略鋼をメニューに加えるなど多様な開発製品で販売量を伸ばす。ソリューションと新規メニューで拡販していく方針だ」
――海外事業は地域によって濃淡がみえる。
「米国のプロテックは新CGLが順調に稼働している。事業は好調で米国の自動車用鋼板の供給拠点として成長している。中国の鞍鋼神鋼冷延高張力自動車鋼板は日系自動車の数量・シェアが低下しているので苦労している。パートナーの鞍鋼とともに民族系自動車を開拓するなど数量を上積みしていく。中国の線条の各二次加工メーカーは日系向けが中心だが民族系自動車向けを増やそうとしており、拡販の取り組みがカギになる」
「ASEANはタイの経済情勢が低調なために特殊鋼線材製造のコベルコミルコンスチール(KMS)、線材二次加工のKCH、磨棒鋼製造のMKCLは苦労している。中長期的にはタイの鋼材需要は伸びる予測であり、非日系含め拡販が課題となる。圧延メーカーのKMSは競合他社にない強みであり、納期・品質対応のアドバンテージを生かしながらタイ、ASEAN市場で線条の事業を大事に守り成長させていく」
――25年度の需要をどう予想する。
「国内は底打ちの動きがみられ、自動車は前年度より上向くとみている。建設は下期から大型物件を中心に徐々に回復していく見通しだ。海外は中国の経済環境が短期に好転するとは思えず、ASEANも回復の兆しがみえない。粗鋼生産は24年度予想の600万トンから大きくは変わらないだろうが、製品構成は改善する見込みだ。25年度は開発製品の拡販などで構成を改善していく」
「アルミ板について缶材向けは薄肉材の新規採用など拡販の取り組みが少しずつ身を結び、自助努力も含め25年度は数量が回復することを期待する。ディスク材は足元のデータセンター向けの需要が続く見通し。半導体製造装置向け厚板の需要の回復時期は予想が難しい。いつでも要望に応えられるよう生産性を保つが、米中の通商摩擦の影響などを注視する必要がある」
――トランプ大統領の通商政策によって受ける影響は。
「米国経済が堅調を維持する政策を続けるとみられ、現地の事業会社の事業環境は大きくは変わらないだろう。懸念されるのは米国向けの直接・間接輸出への影響だ。当社の国別の鉄鋼輸出に占める米国の割合は大きい。日本政府が適用除外を申請しており、対応に期待したい」
――中計では鉄鋼事業の成長投資を示していないが、検討している計画は。
「意思決定したものはないが、鉄鋼事業の成長を考える上での大きなテーマは海外の地産地消のニーズにいかに応えていくかだ。米国やアジアで複数検討している。人口が増え、鋼材消費量が汎用鋼中心に増えるASEANの市場をどう捉えるかということも大きな課題だ。KCHやMKCLは現地で圧倒的なシェアを持つ日系車向けが中心だが、増えつつある非日系車への参入が必要となる。高級鋼の需要が多い北米、中国、タイでプレゼンスを維持強化することが重要であり、既存製品でソリューションを展開するとともに新規メニューを投入して価値を認めていただく戦略を優先する。そこから周辺諸国に広げていく方向だ」
――高い経済成長が続くインド、高級鋼の需要地である欧州向けの輸出や投資の考えは。
「インドの市場は現地のニーズと当社のアイテムがなかなか合致しないが、人口が多く、特殊鋼の需要が増えていくのでチャンスを探っていく。欧州向けはばね鋼など線条の輸出がある。日本の内需が減っていくのでメニューを多彩化し、欧州向けなど輸出を確保する必要がある。お客様のニーズに合わせて構成を最適化していく。薄板も含めメニューを増やしていくことが大事だ」
――宝山鋼鉄グループと自動車用アルミパネルの合弁会社を設立し、中国での同パネル事業を強化した。
「中国国内でクローズドループリサイクルができるのはアドバンテージだ。パートナーの宝山鋼鉄グループの営業力は強く、アルミパネルの拡販に貢献してくれると考えている。既存の神鋼汽車鋁材(天津)も受注量を伸ばす必要があり、民族系自動車向けに拡販していく上で宝鋼とのパートナーシップは大きな戦力となる。中長期的には中国の合弁事業がアルミ板事業の大きな柱になると考えている」
――神鋼汽車鋁材(天津)の原板の調達先が出資先の韓国ウルサン・アルミナムから中国国内での調達に変わることになる。ウルサンの余力の活用法は。
「お客様の承認を2-3年かけて取得していくが、将来的なウルサンの能力の活用方法について幅広い分野で検討する」
――グリーン素材のコベナブル・スチールに続き、コベナブル・アルミをブランド化した。
「グリーン鋼材は一定のコストアップが不可避であり、商品価値を認めてもらうことが必要だが徐々に浸透している。行政も使用促進の制度の整備を進めている。多くのグリーン鋼材が市場で必要になり、価格も製造に必要な水準となれば脱炭素を図る設備投資の大きな意思決定ができ、コベナブル・スチールを大量に提供できる。自動車や造船、建築などいろいろな分野で引き合いがあり、コベナブル・アルミもブランドを発表して間もないがお客様からの関心は非常に高い。具体的な案件を期待している」
――昨年にアルミ製品のロールマージン改定を発表した。今後も価格改定を続ける考えか。
「25年度も必要に応じて価格改定を検討する。社会全体で資機材コストが上がり、修理工事など保全コストも上がっており、事情を引き続き理解していただく。アルミ板に限らず、アルミ関連製品は自動車のモデルチェンジまで一定の価格で取引する商慣習があったが、副原料などの価格がモデルチェンジまでの間に上がり、コスト構造が変わってしまう。状況を一つ一つ丁寧に説明し、モデルチェンジ前でも価格の変更を可能としたのは大きな進歩だ。ただ、足元の価格の水準は十分ではなく、お客様と対話を続けていく」(植木美知也、増岡武秀)














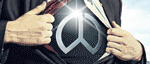
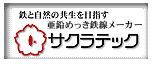

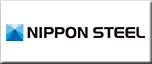

















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ


















