2025年5月29日
財務・経営戦略を聞く/JFEHD副社長/寺畑 雅史氏/高付加価値品 供給強化へ/業績予想、関税影響折り込み備え
――2024年度は国内外ともに事業環境が悪化し、鉄鋼事業の実力のセグメント利益は1373億円と前年比32%減少した。
「単独粗鋼生産は、国内外の想定以上の販売環境悪化などにより、2195万トンと150万トン減少した。コスト削減の効果は270億円だが、そのうちの250億円は構造改革によるものであり、操業改善など通常のコスト削減は20億円にとどまる。上期に天候影響30億円。下期に製造トラブル影響50億円があり、一過性の損失が発生したため。海外のグループ会社、特に印JSWスチール、米CSIは市場の不振や一過性要因で利益が大きく減少した。原料価格が下落し、棚卸資産評価差損を受けたが、販価改善活動や原料価格の販売価格への反映時期差からスプレッドは少し改善した。第7次中期経営計画(21―24年度)の施策実行で地力を高めたが、構造改革を行っていなければさらに大きな損失を被っていたことになる」
――25年度の市場はさらに厳しく、25年度の粗鋼生産を2100万トン程度と前年比95万トン減ると予想し、米国の関税政策の影響として50万トン程度を織り込んだ。
「関税影響は読み切れないところがあり、現時点で想定し得るリスクを織り込んだ。サプライチェーンがどう変わるかによって顧客や当社の位置づけが変わる。足元まだ大きな影響は出ていないが、米国の関税影響を粗鋼50万トン程度で120億円程度の減益を織り込んだ。残りは米国以外の通商リスクや鋼材市況の低迷により輸出が減少するリスクを織り込んだ。為替の変動や日本政府の米国との交渉の動向など不確定な要素は多く、注視していく。国内需要は土木建築に回復の兆しがみえない。製造業をみると、自動車生産は米国の関税政策の影響が懸念され、建機・産機も北米向け輸出中心に厳しさを増す可能性がある。海外は中国における鋼材の過剰生産と輸出増によってアジア圏のマーケットが低迷する構造は変わっていない。多くの国の中国材に対する通商措置に日本が巻き込まれるリスクがある」
 ――25年度の鉄鋼のセグメント利益は400億円と増益予想だが、実力ベースは1000億円と減益を予想する。
――25年度の鉄鋼のセグメント利益は400億円と増益予想だが、実力ベースは1000億円と減益を予想する。
「国内は販売環境の回復が見通せず、通商措置に伴う下押しリスクもあることから、減益を予想している。スプレッドは維持する方針だが、原料炭価格が下がる分、販売価格はマイナスに傾く可能性がある。為替は140円を想定し、円高による輸出採算の悪化が減益に大きく作用する。原料価格は一定程度で推移するとみている。グループ会社の利益は回復し、権益を取得した豪ブラックウォーター炭鉱の利益が入ってくる。海外のグループはJSW、CSIが戻してきている」
「グループ会社について国内は大きな変動はなく、マイナスが大きいのは海外だ。インド市場は安価な中国材の輸入が影響して鋼材市況が下がり、JSWは一過性のマイナス要因もあって大幅な減益となった。25年度はインド政府による通商措置が決まり、市況は上がっており、JSWの利益は改善するとみている。米国では3月から市況上昇も関税政策や景気動向など不透明感はある。CSIは回復に向かうと想定している」
――西日本製鉄所福山地区の高炉1基の休止を決めた。
「需要構造がドラスチックに変わり、前中計の構造改革時に見通していた粗鋼2600万トンの生産量を維持しきれない。新型コロナ禍後の市場をみると需要の戻りは期待しづらく、もう一段の対応として生産体制を見直すことを考え、福山第4高炉の休止を決めた。足元の対策として倉敷地区第3高炉のバンキング(休風)実施を4月に発表した。他の高炉の稼働率を上げ、1基少ない状態で同じ数量を生産するので変動費削減の効果を見込んでいる。27年度に福山第4高炉を止めた後は、倉敷第2高炉を革新電炉に切り替えるタイミングで、倉敷第3高炉の操業を再開する。高炉を止めてでも国内を強靭化しなければならない。技術の源泉は国内の製鉄所にあり、マザー工場としてしっかり運営し、海外進出含めソリューションビジネスやカーボンニュートラルの達成に向かう」
――第8次中期経営計画を開始した25年度の重要テーマは。
「生産体制をスリム化させることに加え、どれだけ高付加価値品を増やしていけるか。無方向性電磁鋼板は倉敷地区で生産能力を増強し、昨年下期から稼働している。方向性電磁鋼板は海外で需要が増えており、捕捉していく。洋上風力向けの大単重厚板は今後もしっかり需要が出てくる見込みだ。グリーン鋼材の拡販も重要な課題だ。中期経営計画で国内の製造基盤整備を掲げている。昨年の福山の原料系のトラブルは一定の対策を実行しており、さらに製造体制をしっかりと整備していく。諸物価が上がっているので価格交渉でしっかりスプレッドを確保していく。この数年取り組んでいるエキストラの改定は、引き続き小ロットの製品や輸送プレミアムを要するものなどを中心にきめ細かく取り組んでいく。高付加価値品の製造比率を上げていく中で最適な生産体制を築いていくことが中期計画の重要な課題だ」
 ――成長戦略の海外展開をどう強化していくか。
――成長戦略の海外展開をどう強化していくか。
「買収した方向性電磁鋼板(GO)製造のJ2ES Nashikの効果を上げていく。UAEのエミレーツとの直接還元鉄工場の建設については、倉敷の革新電炉建設時期も固まったので事業化調査を完了させ実施判断を行いたい。北米ではトランプ政権の政策の影響などを注視しつつ、ニューコアと引き続き様々な検討をしていく。JSWは内需の成長ともに事業が拡大し、GOの合弁会社、その次の施策をいろいろと検討していく。35年度の長期ビジョン達成に向け、JSWやニューコアとの協業は欠かせない」
――大和工業や淀川製鋼所との連携策をどのように進める考えか。
「大和工業とJFE条鋼、JFEスチールとの間で形鋼事業の改善策をこれから調査していく。淀川製鋼所とはJFE鋼板とJFEスチールでともに競争力の確保とプレゼンスの維持拡大に向けた検討を進めていく。自社だけで対応できないほど市場が変わってきている。国内のマーケットが小さくなる中で会社の壁を越え、同業他社との協業をいろいろな観点で考えなければならない」
――JFEエンジニアリングの利益は193億円と減益だが、受注は高位を維持した。
「笠岡のモノパイル工場が昨年に稼働を始めたが、発注時期が遅れていることで受注がなく、24年度は減益となった。25年度以降はWaste tо Resource分野などで受注が伸びていく。強化する化学プラント分野において、住友ケミカルエンジニアリングの株式を取得し、JFEプロジェクトワンとの相乗効果なども見込む。CN関係のプラントに力を入れ、M&Aを今後も続け、規模を大きくしていく。中計目標の350億円にはとどかなかったが、受注は安定しており、25年度は200億円、中計最終の27年度は420億円を見込んでいる」
――JFE商事は海外投資が効果を上げ、479億円と減益ながら中計目標(400億円)を達成し、25年度は500億円を見込む。
「買収したCEMCOやSTUDCOなど米国や豪州のインサイダーのビジネスは収益性が高い。これまで中国や東南アジアを重点地域として考えていたが、欧米やインドでインサイダーとして電磁鋼板や自動車用鋼板、建材関係のマーケットに入っていく。セルビアの電磁鋼板加工拠点も開所式を行い、7月に稼働を始める。他の地域含めJFEスチールと連動しながら長期ビジョンの利益1000億円目指してM&A含め事業を拡大していく」(植木 美知也)

「単独粗鋼生産は、国内外の想定以上の販売環境悪化などにより、2195万トンと150万トン減少した。コスト削減の効果は270億円だが、そのうちの250億円は構造改革によるものであり、操業改善など通常のコスト削減は20億円にとどまる。上期に天候影響30億円。下期に製造トラブル影響50億円があり、一過性の損失が発生したため。海外のグループ会社、特に印JSWスチール、米CSIは市場の不振や一過性要因で利益が大きく減少した。原料価格が下落し、棚卸資産評価差損を受けたが、販価改善活動や原料価格の販売価格への反映時期差からスプレッドは少し改善した。第7次中期経営計画(21―24年度)の施策実行で地力を高めたが、構造改革を行っていなければさらに大きな損失を被っていたことになる」
――25年度の市場はさらに厳しく、25年度の粗鋼生産を2100万トン程度と前年比95万トン減ると予想し、米国の関税政策の影響として50万トン程度を織り込んだ。
「関税影響は読み切れないところがあり、現時点で想定し得るリスクを織り込んだ。サプライチェーンがどう変わるかによって顧客や当社の位置づけが変わる。足元まだ大きな影響は出ていないが、米国の関税影響を粗鋼50万トン程度で120億円程度の減益を織り込んだ。残りは米国以外の通商リスクや鋼材市況の低迷により輸出が減少するリスクを織り込んだ。為替の変動や日本政府の米国との交渉の動向など不確定な要素は多く、注視していく。国内需要は土木建築に回復の兆しがみえない。製造業をみると、自動車生産は米国の関税政策の影響が懸念され、建機・産機も北米向け輸出中心に厳しさを増す可能性がある。海外は中国における鋼材の過剰生産と輸出増によってアジア圏のマーケットが低迷する構造は変わっていない。多くの国の中国材に対する通商措置に日本が巻き込まれるリスクがある」
 ――25年度の鉄鋼のセグメント利益は400億円と増益予想だが、実力ベースは1000億円と減益を予想する。
――25年度の鉄鋼のセグメント利益は400億円と増益予想だが、実力ベースは1000億円と減益を予想する。「国内は販売環境の回復が見通せず、通商措置に伴う下押しリスクもあることから、減益を予想している。スプレッドは維持する方針だが、原料炭価格が下がる分、販売価格はマイナスに傾く可能性がある。為替は140円を想定し、円高による輸出採算の悪化が減益に大きく作用する。原料価格は一定程度で推移するとみている。グループ会社の利益は回復し、権益を取得した豪ブラックウォーター炭鉱の利益が入ってくる。海外のグループはJSW、CSIが戻してきている」
「グループ会社について国内は大きな変動はなく、マイナスが大きいのは海外だ。インド市場は安価な中国材の輸入が影響して鋼材市況が下がり、JSWは一過性のマイナス要因もあって大幅な減益となった。25年度はインド政府による通商措置が決まり、市況は上がっており、JSWの利益は改善するとみている。米国では3月から市況上昇も関税政策や景気動向など不透明感はある。CSIは回復に向かうと想定している」
――西日本製鉄所福山地区の高炉1基の休止を決めた。
「需要構造がドラスチックに変わり、前中計の構造改革時に見通していた粗鋼2600万トンの生産量を維持しきれない。新型コロナ禍後の市場をみると需要の戻りは期待しづらく、もう一段の対応として生産体制を見直すことを考え、福山第4高炉の休止を決めた。足元の対策として倉敷地区第3高炉のバンキング(休風)実施を4月に発表した。他の高炉の稼働率を上げ、1基少ない状態で同じ数量を生産するので変動費削減の効果を見込んでいる。27年度に福山第4高炉を止めた後は、倉敷第2高炉を革新電炉に切り替えるタイミングで、倉敷第3高炉の操業を再開する。高炉を止めてでも国内を強靭化しなければならない。技術の源泉は国内の製鉄所にあり、マザー工場としてしっかり運営し、海外進出含めソリューションビジネスやカーボンニュートラルの達成に向かう」
――第8次中期経営計画を開始した25年度の重要テーマは。
「生産体制をスリム化させることに加え、どれだけ高付加価値品を増やしていけるか。無方向性電磁鋼板は倉敷地区で生産能力を増強し、昨年下期から稼働している。方向性電磁鋼板は海外で需要が増えており、捕捉していく。洋上風力向けの大単重厚板は今後もしっかり需要が出てくる見込みだ。グリーン鋼材の拡販も重要な課題だ。中期経営計画で国内の製造基盤整備を掲げている。昨年の福山の原料系のトラブルは一定の対策を実行しており、さらに製造体制をしっかりと整備していく。諸物価が上がっているので価格交渉でしっかりスプレッドを確保していく。この数年取り組んでいるエキストラの改定は、引き続き小ロットの製品や輸送プレミアムを要するものなどを中心にきめ細かく取り組んでいく。高付加価値品の製造比率を上げていく中で最適な生産体制を築いていくことが中期計画の重要な課題だ」
 ――成長戦略の海外展開をどう強化していくか。
――成長戦略の海外展開をどう強化していくか。「買収した方向性電磁鋼板(GO)製造のJ2ES Nashikの効果を上げていく。UAEのエミレーツとの直接還元鉄工場の建設については、倉敷の革新電炉建設時期も固まったので事業化調査を完了させ実施判断を行いたい。北米ではトランプ政権の政策の影響などを注視しつつ、ニューコアと引き続き様々な検討をしていく。JSWは内需の成長ともに事業が拡大し、GOの合弁会社、その次の施策をいろいろと検討していく。35年度の長期ビジョン達成に向け、JSWやニューコアとの協業は欠かせない」
――大和工業や淀川製鋼所との連携策をどのように進める考えか。
「大和工業とJFE条鋼、JFEスチールとの間で形鋼事業の改善策をこれから調査していく。淀川製鋼所とはJFE鋼板とJFEスチールでともに競争力の確保とプレゼンスの維持拡大に向けた検討を進めていく。自社だけで対応できないほど市場が変わってきている。国内のマーケットが小さくなる中で会社の壁を越え、同業他社との協業をいろいろな観点で考えなければならない」
――JFEエンジニアリングの利益は193億円と減益だが、受注は高位を維持した。
「笠岡のモノパイル工場が昨年に稼働を始めたが、発注時期が遅れていることで受注がなく、24年度は減益となった。25年度以降はWaste tо Resource分野などで受注が伸びていく。強化する化学プラント分野において、住友ケミカルエンジニアリングの株式を取得し、JFEプロジェクトワンとの相乗効果なども見込む。CN関係のプラントに力を入れ、M&Aを今後も続け、規模を大きくしていく。中計目標の350億円にはとどかなかったが、受注は安定しており、25年度は200億円、中計最終の27年度は420億円を見込んでいる」
――JFE商事は海外投資が効果を上げ、479億円と減益ながら中計目標(400億円)を達成し、25年度は500億円を見込む。
「買収したCEMCOやSTUDCOなど米国や豪州のインサイダーのビジネスは収益性が高い。これまで中国や東南アジアを重点地域として考えていたが、欧米やインドでインサイダーとして電磁鋼板や自動車用鋼板、建材関係のマーケットに入っていく。セルビアの電磁鋼板加工拠点も開所式を行い、7月に稼働を始める。他の地域含めJFEスチールと連動しながら長期ビジョンの利益1000億円目指してM&A含め事業を拡大していく」(植木 美知也)














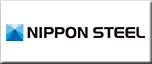

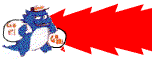


















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ


















