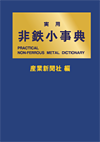2025年5月30日
商社の経営戦略 10年先を見据えて/住友商事 犬伏勝也専務 鉄鋼グループ CEO/強みを伸ばす投資推進/米関税影響、早期に軽減手立て
――2024年度の鉄鋼グループの利益は684億円と前年比1%減少した。計画を下回ったが、厳しい市場の中で微減にとどめたともみられる。
「年度当初に890億円の目標を掲げ、中間期に740億円に下方修正したが、そこにも届かなったのは残念だった。想定していた北米の鋼管市場の回復が遅れたことや鋼材市況も軟調が続いたのが主な要因。これまで石油を掘削するリグの稼働数と市中の在庫量をみていたが、リグ数が回復せずとも石油の生産量は高位で安定していた。既稼働リグが従来以上に深く広く掘るようになり、鋼管需要を支える状況だった。当社の販売量は4―9月に減少し、その後在庫調整が進んだことで徐々に戻ったが、価格がなかなか上がらなかった。輸入品も多く、ようやく価格が底を打ったのが今年3月。結果としては予測から1年ずれ込んだ恰好だ」
――鋼材の市場も厳しさを増した。
「中国中心に東アジア圏の需要が低迷し、鋼材価格が下落した。中国・ASEANで日系自動車の生産が低調となったことで鋼材需要も減ってしまった影響が響いた。一部の地域では事業撤退や滞留債権の処理などで一過性の費用も計上した。ただ、下方耐性を高め、グループ全体での基礎収益力が確実に積み上がることにもつながった。国内外とも大変厳しい逆風の中で業務改善を中心に利益を確保してくれた営業現場の皆さん、事業会社の皆さんには心から大変感謝したい。全体感としては、事業や地域のポートフォリオのバランスにより一部が低調でも他がリカバリーする下方耐性の結果と捉えている。前年度は特に国内鋼材事業会社各社の奮闘は大きく、住商メタルワン鋼管やNSステンレス、伊藤忠丸紅住商テクノスチール、各コイルセンターなど厳しい環境の中でも最大限の結果を発揮していただいた」
――中期経営計画2年目、25年度に取り組むテーマは。
「市場の先行きは正直見通し困難であり変化が大きいので、非常事態とまではいわないものの、危機管理モードとした基本に立ち返り、市場の変化を敏感に察知し、取るべきアクションを迅速に考え、実行するようメッセージを発している。無用な費用が生じないようにも気を引き締めていく。東京で開いた鉄鋼グループの戦略会議を国内外の鉄鋼グループ全社員にも配信し、具体的なアクションプランを伝え意思統一を図っている。全社員が自分の所属する部署の目標が何か、自分の役割は何かを把握し、一つ一つ大事に積み重ねることを実行しなければ計画は成し遂げられない。一人一人の役割、機能、実行が重要だ。市場は厳しいが、25年度の利益目標は760億円と挑戦シロを込めて高く設定した。当社ならではの機能を徹底的に追求していく。積み上げてきたものをしっかり守り、環境が好転した際に利益を上積みできるよう、準備をしておく。GXの種まきも着々と進める」
――米国は関税の引き上げで鋼管の輸入が減り、事業環境は改善に向かうのか。
「米国の鋼管輸入は1―3月に駆け込みで増えたが、4―5月が減少したのか、しばらくは動向を注視する必要がある。地場の鋼管メーカーは値上げを進めている。関税見合いで市場価格は上がると見ている。北米の鋼管の需要が増えるかどうかのポイントは油価だ。1バレル60ドルがベンチマークとみられ、60ドルを下回ると北米の開発業者は投資を控える可能性がある。当社の北米の鋼管事業は国内調達が多く、関税の直接的な影響をさほど受けない。油価下落や米国の景気後退による鉄鋼製品需要が減少する懸念の方が気がかりだ」
「北米以外の鋼管事業は長期契約が多く、またラインパイプの大型プロジェクト向けもあり堅調だった。特に中東は需要が旺盛。石炭火力発電の依存度が高いアジアや西南アジアがガス火力発電にシフトする動きも商機となる。欧州はスペイン・ポルトガルの停電で調整電源としての火力発電の必要性が再認識されたのではないか。油価による影響も当然考慮しながら市場の推移を注視していく」
――米国の自動車関税の影響をどうみる。
「当社にとってインパクトは薄板はじめ非常に大きい。自動車メーカーや鉄鋼メーカーとより密に意思疎通し、流通としてやらなければいけないこと、役立つことを考えていく。コイルセンター含め内部改善をさらに進める。在庫の持ち方や歩留まりの改善、自動車メーカーへの提案など困難を乗り越えるための方策を考え実行する。私自身も北米に足を運び、現地の状況を肌で感じ、内包するリスクを精査し、影響を軽減する手をできるだけ早く打っていくつもりだ」
――攻めの手も打っている。洋上風力向けモノパイル世界大手のEEWオフショア・ウィンド・ホールディング(EEW)に出資し、25年度は利益に貢献してくる。
「EEWの強み・弱みを分析した上で出資しており、順調に進んでいる。EEWのパートナーとも会話を続けているが、堅実な考え方をしており、当社とは理念が近いと感じている。既存事業のビジネス追求だけでなく、新たなビジネスも一緒に検討していく。1つの事業から2、3の事業へと広げられることが理想だ。今ある機能を磨き、手の届く範囲の中から新たな事業戦略、戦線拡大のための投資を目指す。既存ビジネスから遠く知見の乏しい『飛び地』の投資は控え、強みを伸ばす投資を進める。当社の機能を広げ、地域戦略が広がるような投資案件を探し、EEWのようなパートナーを増やしていきたい」
――国内の事業会社は需要の減少を受け効率化を進める方向に。
「単発の機能ではなく、複合機能を掛け合わせないと需要を集めるのは困難だろうと考える。自社機能と他社の持つ機能をかけ合わせ、さらには当社不動産部隊や物流部隊が取り組む開発とも更に連携を強化する取り組みも必要になろう。住友商事グローバルメタルズと鋼材事業SBUが住友商事グループとして戦略を描き、実行にあたって自社で進める分野、事業会社と連携して行う分野、パートナーと連携して行う分野などを鉄鋼メーカーの戦略ともかけ合わせ、考えていきたい。オーナー系の流通企業と組み、機能を強化・活用していくことも検討できるだろう。国内の各都市に営業拠点を配置している利点を生かし、地域ごとに流通企業と連携していく」
――成長地域のインド、さらに中東やアフリカなど有望視される地域でどう事業を展開していくか。
「インドは、潜在力は高いが容易に参入できる市場ではない。市場の動向を見極めつつ、まずは既存の事業会社を軸に展開しながら市場を見極めていく。特殊鋼製品を起点に顧客と深くつながり、新たなビジネスへの展開を考えていきたい。何がインドの将来に必要なものかよく考えながら事業を検討していく」
「地域によって攻め口を変える。中国の事業拠点は市場の構造変化に即して中国企業向けにも販売を増やすための体制を整えていく。中国企業がASEANでビジネスを既に増やしているので、ASEAN市場でも中国企業に通用できる機能や体制を意識したい。中国市場とASEAN市場を一体と見なしていくことになり、コミュニケーション能力と人のネットワーク力がさらに重要になる。私は今年も人脈をつくるために世界を回ろうと思っている」(植木 美知也)

「年度当初に890億円の目標を掲げ、中間期に740億円に下方修正したが、そこにも届かなったのは残念だった。想定していた北米の鋼管市場の回復が遅れたことや鋼材市況も軟調が続いたのが主な要因。これまで石油を掘削するリグの稼働数と市中の在庫量をみていたが、リグ数が回復せずとも石油の生産量は高位で安定していた。既稼働リグが従来以上に深く広く掘るようになり、鋼管需要を支える状況だった。当社の販売量は4―9月に減少し、その後在庫調整が進んだことで徐々に戻ったが、価格がなかなか上がらなかった。輸入品も多く、ようやく価格が底を打ったのが今年3月。結果としては予測から1年ずれ込んだ恰好だ」
――鋼材の市場も厳しさを増した。
「中国中心に東アジア圏の需要が低迷し、鋼材価格が下落した。中国・ASEANで日系自動車の生産が低調となったことで鋼材需要も減ってしまった影響が響いた。一部の地域では事業撤退や滞留債権の処理などで一過性の費用も計上した。ただ、下方耐性を高め、グループ全体での基礎収益力が確実に積み上がることにもつながった。国内外とも大変厳しい逆風の中で業務改善を中心に利益を確保してくれた営業現場の皆さん、事業会社の皆さんには心から大変感謝したい。全体感としては、事業や地域のポートフォリオのバランスにより一部が低調でも他がリカバリーする下方耐性の結果と捉えている。前年度は特に国内鋼材事業会社各社の奮闘は大きく、住商メタルワン鋼管やNSステンレス、伊藤忠丸紅住商テクノスチール、各コイルセンターなど厳しい環境の中でも最大限の結果を発揮していただいた」
――中期経営計画2年目、25年度に取り組むテーマは。
「市場の先行きは正直見通し困難であり変化が大きいので、非常事態とまではいわないものの、危機管理モードとした基本に立ち返り、市場の変化を敏感に察知し、取るべきアクションを迅速に考え、実行するようメッセージを発している。無用な費用が生じないようにも気を引き締めていく。東京で開いた鉄鋼グループの戦略会議を国内外の鉄鋼グループ全社員にも配信し、具体的なアクションプランを伝え意思統一を図っている。全社員が自分の所属する部署の目標が何か、自分の役割は何かを把握し、一つ一つ大事に積み重ねることを実行しなければ計画は成し遂げられない。一人一人の役割、機能、実行が重要だ。市場は厳しいが、25年度の利益目標は760億円と挑戦シロを込めて高く設定した。当社ならではの機能を徹底的に追求していく。積み上げてきたものをしっかり守り、環境が好転した際に利益を上積みできるよう、準備をしておく。GXの種まきも着々と進める」
――米国は関税の引き上げで鋼管の輸入が減り、事業環境は改善に向かうのか。
「米国の鋼管輸入は1―3月に駆け込みで増えたが、4―5月が減少したのか、しばらくは動向を注視する必要がある。地場の鋼管メーカーは値上げを進めている。関税見合いで市場価格は上がると見ている。北米の鋼管の需要が増えるかどうかのポイントは油価だ。1バレル60ドルがベンチマークとみられ、60ドルを下回ると北米の開発業者は投資を控える可能性がある。当社の北米の鋼管事業は国内調達が多く、関税の直接的な影響をさほど受けない。油価下落や米国の景気後退による鉄鋼製品需要が減少する懸念の方が気がかりだ」
「北米以外の鋼管事業は長期契約が多く、またラインパイプの大型プロジェクト向けもあり堅調だった。特に中東は需要が旺盛。石炭火力発電の依存度が高いアジアや西南アジアがガス火力発電にシフトする動きも商機となる。欧州はスペイン・ポルトガルの停電で調整電源としての火力発電の必要性が再認識されたのではないか。油価による影響も当然考慮しながら市場の推移を注視していく」
――米国の自動車関税の影響をどうみる。
「当社にとってインパクトは薄板はじめ非常に大きい。自動車メーカーや鉄鋼メーカーとより密に意思疎通し、流通としてやらなければいけないこと、役立つことを考えていく。コイルセンター含め内部改善をさらに進める。在庫の持ち方や歩留まりの改善、自動車メーカーへの提案など困難を乗り越えるための方策を考え実行する。私自身も北米に足を運び、現地の状況を肌で感じ、内包するリスクを精査し、影響を軽減する手をできるだけ早く打っていくつもりだ」
――攻めの手も打っている。洋上風力向けモノパイル世界大手のEEWオフショア・ウィンド・ホールディング(EEW)に出資し、25年度は利益に貢献してくる。
「EEWの強み・弱みを分析した上で出資しており、順調に進んでいる。EEWのパートナーとも会話を続けているが、堅実な考え方をしており、当社とは理念が近いと感じている。既存事業のビジネス追求だけでなく、新たなビジネスも一緒に検討していく。1つの事業から2、3の事業へと広げられることが理想だ。今ある機能を磨き、手の届く範囲の中から新たな事業戦略、戦線拡大のための投資を目指す。既存ビジネスから遠く知見の乏しい『飛び地』の投資は控え、強みを伸ばす投資を進める。当社の機能を広げ、地域戦略が広がるような投資案件を探し、EEWのようなパートナーを増やしていきたい」
――国内の事業会社は需要の減少を受け効率化を進める方向に。
「単発の機能ではなく、複合機能を掛け合わせないと需要を集めるのは困難だろうと考える。自社機能と他社の持つ機能をかけ合わせ、さらには当社不動産部隊や物流部隊が取り組む開発とも更に連携を強化する取り組みも必要になろう。住友商事グローバルメタルズと鋼材事業SBUが住友商事グループとして戦略を描き、実行にあたって自社で進める分野、事業会社と連携して行う分野、パートナーと連携して行う分野などを鉄鋼メーカーの戦略ともかけ合わせ、考えていきたい。オーナー系の流通企業と組み、機能を強化・活用していくことも検討できるだろう。国内の各都市に営業拠点を配置している利点を生かし、地域ごとに流通企業と連携していく」
――成長地域のインド、さらに中東やアフリカなど有望視される地域でどう事業を展開していくか。
「インドは、潜在力は高いが容易に参入できる市場ではない。市場の動向を見極めつつ、まずは既存の事業会社を軸に展開しながら市場を見極めていく。特殊鋼製品を起点に顧客と深くつながり、新たなビジネスへの展開を考えていきたい。何がインドの将来に必要なものかよく考えながら事業を検討していく」
「地域によって攻め口を変える。中国の事業拠点は市場の構造変化に即して中国企業向けにも販売を増やすための体制を整えていく。中国企業がASEANでビジネスを既に増やしているので、ASEAN市場でも中国企業に通用できる機能や体制を意識したい。中国市場とASEAN市場を一体と見なしていくことになり、コミュニケーション能力と人のネットワーク力がさらに重要になる。私は今年も人脈をつくるために世界を回ろうと思っている」(植木 美知也)

















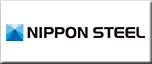

















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ