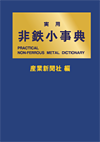2025年6月23日
シンニッタン、ファンド傘下で飛躍/平山泰行社長/仮設機材と鍛造融合 強み/スパークスと成長戦略描く
大手鍛造メーカー、シンニッタン(本社=茨城県高萩市)は、スパークス・グループが無限責任組合員をつとめる日本モノづくり未来投資事業有限責任組合(通称=日本モノづくり未来ファンド)によるTOB(株式公開買い付け)が2025年4月14日に成立し、5月26日付で非上場化した。TOBを受け入れた背景、今後の方針などを平山泰行社長に聞いた。
――日本モノづくり未来ファンドによるTOBに至った経緯から。
「主幹事証券会社を通じて、スパークス・グループ(スパークス)に会ったのが2023年の2月。その際にTOBや非上場化は提案されなかったが、鍛造業を取り巻く環境が急速に変化する中、上場している意義を問われたほか、非上場化を含めて当社が変革するための具体的な提案が行われたため、詳細な調査内容に驚くとともに、好印象を持った。当時、スパークスは当社の株を保有していなかったが、傘下に置く日本モノづくり未来ファンドは優れた技術・人財・サービスを有する国内モノづくり企業に投資して支援する理念を掲げており、この一環として当社に打診したと思う。同意なき買収も行われている中で現経営陣の意思を尊重し、伴走型で経営に携わるスタンスにも共感した」
――TOB実施まで2年の期間があった。
「その後、すぐにスパークスの提案を検討するには至らず、25年度から始動する次期中期経営計画の策定にあたって、どのような成長戦略を描くべきかを考えていた。その矢先、23年11月にいすゞ自動車が鋳造品などを手掛ける子会社・IJTTを売却すると発表。日本モノづくり未来ファンドがTOBを行う内容であり、いすゞ自動車は当社の主要顧客であったため、驚いた。その発表から間を置かないタイミングでスパークスと再会する機会を得た。東京証券取引所から『資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応』が求められ、『PBR(株価純資産倍率)1倍割れ企業』が問題視される中、前中計最終の24年度で業績下降局面に転じることが予想(結果的には営業赤字に転落)されたこともあり、成長戦略を描くプロセスでスパークスと頻繁に面会・協議するようになり、TOB・非上場化への流れが醸成されたと思う。非上場化に向けた準備を行う中で、一部の社外取締役で構成する特別委員会による前向きな結論を得たことで、25年2月28日に発表。主要株主への説明などを経て5月26日に上場を廃止し、5月28日付で日本モノづくり未来ファンドの100%子会社になったのが経緯だ」
――体制に変化は。
「日本モノづくり未来ファンドから非常勤取締役1人が派遣され、社外取締役4人を含む取締役5人が退任したが、従来の社内取締役4人は再任されるなど体制は大きく変わっていない。グループ企業を含めた社員、製造体制についても現時点で変更はない」
――非上場化のメリットをどう考えるか。
「経営環境が大きく変化する中、3カ月ごとに収益を開示したり、『資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応』などを常にモニタリングされている状況は当社の時間軸として馴染まず、非上場化によって日本モノづくり未来ファンドとともに経営ビジョンの策定・実行に腰を据えて取り組むことが可能になった。日本モノづくり未来ファンドはトヨタ自動車も出資しており、TPS(トヨタ生産方式)のメソッド導入などにも期待している」
――経営ビジョンをどのように策定するか。
「これから2カ月を費やして社員へのヒアリング、幹部らによる集中討議を行った後、100日かけて近未来の目標像を実現する経営ビジョンを描く。当社は『6つの事業インフラ改革』、『Re・Born計画』を掲げているが、日本モノづくり未来ファンドもこの内容に賛同しており、これを基軸に策定することになるだろう。大きな方向性でいえば鍛造事業は自動車分野の比率が大きく、ポートフォリオ再構築を踏まえて非自動車分野、1つ具体例を挙げれば需要拡大が見込まれる産業用ロボット分野に力を注ぐ。国内外グループ会社は乗用車向け、トラック向け鍛造品を手掛けている。足回り向けが多く、EV化による影響を大きく受けることは想定しにくいが、鍛造品の使用量は減る傾向にある。自動車分野に固執していては成長戦略を描くことができず、伸びる業界にも軸足を置く。すでに一部のギア周りで当社鍛鋼品が採用されているが、人手不足を解決する産業用ロボット分野で鍛造品の強靭性を生かしていきたい」
「宇宙分野は中・長期的に市場が拡大することから、鍛造品をアピールしていきたい分野。加えて仮設足場関連事業を持つ唯一の鍛造メーカーとして、仮設機材と鍛造品の融合思考を取り入れ、より強靭な製品を市場に投入して差別化を図る。将来・設備・人への投資を推進するとともに、QCDC(品質、価格、納期、脱炭素)に磨きをかけながら、生産性向上にも取り組むことで、顧客に高品質製品を適正な販売価格で提供する。CO2排出削減に注力することでスコープ3削減にも貢献する」
 ――「6つの事業インフラ改革」とは。
――「6つの事業インフラ改革」とは。
「グループ経営の深化を第一義とする。「まず『グループガバナンス強化』でグループ全体の最適経営を実現可能とする組織・人員体制を構築する。『グループ事業構造、製品ポートフォリオ変革』では抜本的な選択と集中を検討しながら、グループ内最適生産を追求する。また『グループ調達の推進』ではコストダウンを推進し、外国素材や非鉄材料の採用にも取り組む。『グループ一体型営業と物流の仕組み作り』や『グループDXの推進』、『グループでの脱炭素推進』も掲げている」
――「Re・Born計画」はどうか。
「『自動車・トラックメーカーとの取引適正化』をはじめ、産業用ロボットやEV部品ななど『成長分野への重点投資』、仮設機材への鍛造品取り入れをはじめ『他社差別化の追求』、『グループ内最適生産体制構築のための設備の集約と廃棄』、『鍛造プラスアルファの付加価値の追求~川上(設計力強化)と川下(機械加工など)の強化』、『的を絞った省人化・自動化投資の推進』、自動車OEMの内製取り込みなど『残存者メリットの追求』、『統合システムを活用したDX化による生産性向上』、『新素材、新技術、脱炭素に資する研究開発費の投入』が主要なテーマになる」
――金属製パレットの製造・販売を中心とした物流事業は継続するか。
「経営資源の選択と集中の議論はこれからになる。物流事業は2024年問題で注目され、これから能力を発揮できる分野。当社は自動車部品の輸送で培ってきた技術・ノウハウがあり、強化していきたいと考えている」
――グループ企業は。
「鍛造事業のセイタン(新潟県南魚沼市)と中部鍛工(愛知県新城市)、タイのサイアムメタルテクノロジー、また建機事業や物流事業の製造拠点であるエヌケーケー(茨城県結城市)と国内外に4社ある。各社それぞれに優れた点があり、良さを生かしていきたい。特に鍛造事業ではレジリエンスの観点から複数拠点が強みとなり、優位に働くと考えている」
――再上場の可能性は。
「日本モノづくり未来ファンドとともに決めることであるが、まだスタート台に立ったばかりであり現時点では未定。上場企業であれ、非上場企業であれ、『モノづくりを通じて顧客満足度を高めながら適正な利益を確保し、それを株主や従業員に還元する』。この究極的な目標の達成にまい進する」(濱坂浩司)

――日本モノづくり未来ファンドによるTOBに至った経緯から。
「主幹事証券会社を通じて、スパークス・グループ(スパークス)に会ったのが2023年の2月。その際にTOBや非上場化は提案されなかったが、鍛造業を取り巻く環境が急速に変化する中、上場している意義を問われたほか、非上場化を含めて当社が変革するための具体的な提案が行われたため、詳細な調査内容に驚くとともに、好印象を持った。当時、スパークスは当社の株を保有していなかったが、傘下に置く日本モノづくり未来ファンドは優れた技術・人財・サービスを有する国内モノづくり企業に投資して支援する理念を掲げており、この一環として当社に打診したと思う。同意なき買収も行われている中で現経営陣の意思を尊重し、伴走型で経営に携わるスタンスにも共感した」
――TOB実施まで2年の期間があった。
「その後、すぐにスパークスの提案を検討するには至らず、25年度から始動する次期中期経営計画の策定にあたって、どのような成長戦略を描くべきかを考えていた。その矢先、23年11月にいすゞ自動車が鋳造品などを手掛ける子会社・IJTTを売却すると発表。日本モノづくり未来ファンドがTOBを行う内容であり、いすゞ自動車は当社の主要顧客であったため、驚いた。その発表から間を置かないタイミングでスパークスと再会する機会を得た。東京証券取引所から『資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応』が求められ、『PBR(株価純資産倍率)1倍割れ企業』が問題視される中、前中計最終の24年度で業績下降局面に転じることが予想(結果的には営業赤字に転落)されたこともあり、成長戦略を描くプロセスでスパークスと頻繁に面会・協議するようになり、TOB・非上場化への流れが醸成されたと思う。非上場化に向けた準備を行う中で、一部の社外取締役で構成する特別委員会による前向きな結論を得たことで、25年2月28日に発表。主要株主への説明などを経て5月26日に上場を廃止し、5月28日付で日本モノづくり未来ファンドの100%子会社になったのが経緯だ」
――体制に変化は。
「日本モノづくり未来ファンドから非常勤取締役1人が派遣され、社外取締役4人を含む取締役5人が退任したが、従来の社内取締役4人は再任されるなど体制は大きく変わっていない。グループ企業を含めた社員、製造体制についても現時点で変更はない」
――非上場化のメリットをどう考えるか。
「経営環境が大きく変化する中、3カ月ごとに収益を開示したり、『資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応』などを常にモニタリングされている状況は当社の時間軸として馴染まず、非上場化によって日本モノづくり未来ファンドとともに経営ビジョンの策定・実行に腰を据えて取り組むことが可能になった。日本モノづくり未来ファンドはトヨタ自動車も出資しており、TPS(トヨタ生産方式)のメソッド導入などにも期待している」
――経営ビジョンをどのように策定するか。
「これから2カ月を費やして社員へのヒアリング、幹部らによる集中討議を行った後、100日かけて近未来の目標像を実現する経営ビジョンを描く。当社は『6つの事業インフラ改革』、『Re・Born計画』を掲げているが、日本モノづくり未来ファンドもこの内容に賛同しており、これを基軸に策定することになるだろう。大きな方向性でいえば鍛造事業は自動車分野の比率が大きく、ポートフォリオ再構築を踏まえて非自動車分野、1つ具体例を挙げれば需要拡大が見込まれる産業用ロボット分野に力を注ぐ。国内外グループ会社は乗用車向け、トラック向け鍛造品を手掛けている。足回り向けが多く、EV化による影響を大きく受けることは想定しにくいが、鍛造品の使用量は減る傾向にある。自動車分野に固執していては成長戦略を描くことができず、伸びる業界にも軸足を置く。すでに一部のギア周りで当社鍛鋼品が採用されているが、人手不足を解決する産業用ロボット分野で鍛造品の強靭性を生かしていきたい」
「宇宙分野は中・長期的に市場が拡大することから、鍛造品をアピールしていきたい分野。加えて仮設足場関連事業を持つ唯一の鍛造メーカーとして、仮設機材と鍛造品の融合思考を取り入れ、より強靭な製品を市場に投入して差別化を図る。将来・設備・人への投資を推進するとともに、QCDC(品質、価格、納期、脱炭素)に磨きをかけながら、生産性向上にも取り組むことで、顧客に高品質製品を適正な販売価格で提供する。CO2排出削減に注力することでスコープ3削減にも貢献する」
 ――「6つの事業インフラ改革」とは。
――「6つの事業インフラ改革」とは。「グループ経営の深化を第一義とする。「まず『グループガバナンス強化』でグループ全体の最適経営を実現可能とする組織・人員体制を構築する。『グループ事業構造、製品ポートフォリオ変革』では抜本的な選択と集中を検討しながら、グループ内最適生産を追求する。また『グループ調達の推進』ではコストダウンを推進し、外国素材や非鉄材料の採用にも取り組む。『グループ一体型営業と物流の仕組み作り』や『グループDXの推進』、『グループでの脱炭素推進』も掲げている」
――「Re・Born計画」はどうか。
「『自動車・トラックメーカーとの取引適正化』をはじめ、産業用ロボットやEV部品ななど『成長分野への重点投資』、仮設機材への鍛造品取り入れをはじめ『他社差別化の追求』、『グループ内最適生産体制構築のための設備の集約と廃棄』、『鍛造プラスアルファの付加価値の追求~川上(設計力強化)と川下(機械加工など)の強化』、『的を絞った省人化・自動化投資の推進』、自動車OEMの内製取り込みなど『残存者メリットの追求』、『統合システムを活用したDX化による生産性向上』、『新素材、新技術、脱炭素に資する研究開発費の投入』が主要なテーマになる」
――金属製パレットの製造・販売を中心とした物流事業は継続するか。
「経営資源の選択と集中の議論はこれからになる。物流事業は2024年問題で注目され、これから能力を発揮できる分野。当社は自動車部品の輸送で培ってきた技術・ノウハウがあり、強化していきたいと考えている」
――グループ企業は。
「鍛造事業のセイタン(新潟県南魚沼市)と中部鍛工(愛知県新城市)、タイのサイアムメタルテクノロジー、また建機事業や物流事業の製造拠点であるエヌケーケー(茨城県結城市)と国内外に4社ある。各社それぞれに優れた点があり、良さを生かしていきたい。特に鍛造事業ではレジリエンスの観点から複数拠点が強みとなり、優位に働くと考えている」
――再上場の可能性は。
「日本モノづくり未来ファンドとともに決めることであるが、まだスタート台に立ったばかりであり現時点では未定。上場企業であれ、非上場企業であれ、『モノづくりを通じて顧客満足度を高めながら適正な利益を確保し、それを株主や従業員に還元する』。この究極的な目標の達成にまい進する」(濱坂浩司)














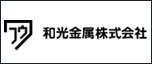

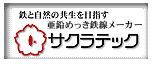
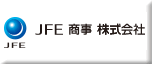

















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ