2025年4月14日
商社の経営戦略 ―需給・収益構造対策―/メタルワン渡邉善之社長/協調と競争 投資最適化/流通業務デジタル基盤 普及進む
――世界の鉄鋼需給構造が大きく変化しているが、まず国内の需要見通しについて。
「自動車、造船、建産機、電機など鉄鋼需要産業の海外生産シフト、少子高齢化などの影響で国内の鋼材消費量は縮小を続けてきた。米リーマン・ショック前の2007年度は内需が8000万トンで、内訳は製造業2600万トン、建設業2800万トン、間接輸出2600万トンだった。日本鉄鋼連盟は25年度の需要を前年度並みの5000万トン程度と見ている。内訳は製造業1500万トン、建設業1700万トン、間接輸出1800万トン。トランプ大統領が大規模な関税政策を打ち出していること、アジア諸国を含めて地産地消の流れが加速していることなどを踏まえると、間接輸出の下振れを想定しておく必要がある。一方で建設分野は、地震や豪雨・豪雪など自然災害に対する国土強靭化、直近で発生した下水道の破断など社会インフラの老朽化対策が待ったなしで、半導体工場、データセンター、物流施設、インバウンド対応宿泊施設などの計画も進んでいる。ところが2024年から建設業と輸送業における労働時間の規制が厳しくなり、資材高騰や構造的な人手不足も加わって、工期遅れや計画の見直しが続いており、こちらも決して楽観はできない。製造業分野では国内自動車メーカーの国内生産台数の行方も気になるところ。中長期的には内需が5000万トン以下で推移する可能性を否定できない」
――国内外の需給構造が変化する中、商社は事業構造転換を迫られている。
「メタルワンは設立時、『メタルマーケットメーカー』をビジョンに掲げ、金属産業に接するすべての産業・企業との連携強化による新たな市場の創造に取り組んできた。ミッションを『メタルバリュー・オプティマイザー』と定義づけ、産業と市場の最適化を図るためのバリューチェーンの革新に取り組んできた。このほど『世界中の“つくる"をつなぎ、価値創造を追求し続けることで、ものづくりの可能性を広げる』というパーパスを制定し、メタルワンの機能を明確化した」
――その狙いを。
「世界各地で地政学リスクが顕在化し、分断が鮮明になっている。社会的な課題も高度化、複雑化している。企業単独で課題を解決することが難しくなっている。こうした中、パーパスと併せて『金属素材を生み出す企業と、その素材を活かす企業。私たちは、サプライチェーン上に存在する本質的な課題に真摯に向き合い、ステークホルダーと共に新たなソリューションを創り出していきます』とのステイトメントを内外に公表した。メタルワングループの国内外の社員が一体となって、ビジネス、マーケット、技術をつなぐことで、新しいバリューを創出し、ものづくりの可能性を大きく広げていく」
――鉄鋼業は収益構造対策を迫られている。
「人口減少によって自動車や電機、住宅などの市場が縮小し、人手不足が人件費や物流費などのコスト上昇、建設の工期延長などを招いている。加工・流通分野においては、電話やファックス、メールなど様々な方法で注文内容が伝えられ、商社やコイルセンターが管理をして、鉄鋼メーカーや加工メーカーに様々な方法で伝達するところから始まり、膨大な労力が使われている。そこでメタルワンは、自動車産業の流通に関わる多くの企業がデータをシェアすることで、自動車鋼板流通の構造改革を可能とするデジタル・プラットフォーム『Metal X』を日本アイ・ビー・エムと共同開発した。発注者と受注者が直接入力する注文情報や出荷情報を一元管理することで、大幅な業務量の削減が可能となる。発注者、受注者が共有のプラットフォームにおいて注文・出荷情報をリアルタイムに把握できるため、高効率で持続可能なオペレーションが可能となり、コミュニケ―ションも円滑化できる。2023年4月の提供開始以来、自動車メーカー、部品メーカーはじめ数多くの取引先に導入頂き、新たな引き合いも続いている」
――「Metal X UP」も好評と聞いている。
「鉄鋼流通全体の業務効率化、高度化、コスト削減を図る、自社開発したデジタル・プラットフォーム。ミルシートの電子受け渡しや請求書の電子化、債権債務の金額照合、鋼材納期の進捗状況や注文履歴の確認など商社や問屋、加工流通の業務をワンストップで可能とする。23年に厚板分野から提供を開始し、24年4月には薄板、線材、鋼管分野へとクライアントを広げ、数百社の企業に活用いただいている」
 ――鉄鋼流通は需要構造転換と需要縮小への同時対応を求められている。
――鉄鋼流通は需要構造転換と需要縮小への同時対応を求められている。
「例えば、自動車のEV化に対応して電磁鋼板やモーターコアの加工能力の増強を迫られるが、コイルセンター各社が自前主義で対処すると過剰投資、能力過剰を招く。各社が投資コストとランニングコストを転嫁すると需要家の競争力が低下する。陸上輸送はドライバーの勤務時間短縮、ドライバー不足で輸送能力の増強が求められているが、流通各社がトラックを増やすと、能力過剰となり、ドライバー不足がより深刻化して人件費がさらに上昇する。鉄鋼メーカーが先行して生産設備の構造改革をダイナミックに進めている。鉄鋼流通においても業界全体で『協調』する分野と『競争』原理を生かす分野とを分けて投資や設備合理化を進めなければならない。まずはメタルワングループ内で最適化を図り、系列を超えた協業に踏み込んでいく」
――社長就任前、三菱商事・マテリアルソリューショングループの新規事業開発本部長として鉄鋼流通の業務効率化にも取り組んでいた。
「メタルワンは鉄鋼流通に係る競合先と直接的に『競争』することもあるが、三菱商事は鉄鋼流通に直接関与してない立場を活かし、業界全体の共通利益のための『協調』を提起しやすい」
――メタルワンクラブが名古屋、九州はじめ各地でネットワークを形成している。
「業界全体の業務効率化が、鋼材のコスト競争力につながる。競争と協調、リアルとデジタルを組み合わせながら、時代に見合ったサプライチェーンを構築し、バリューを最適化していくための提案はできると考えている」
――海外市場はエリアによって事情が大きく異なるが、中国は需給構造が大きく変化しており、収益構造改革が不可欠となっている。
「中国、米国、タイ・インドネシアをはじめとする東南アジアでネットワークを構築し、インドも歴史的に強い事業基盤を持っている。20年間を振り返ると、発足後の2003年からの15年間については、世界の工場として著しい成長を遂げてきた中国の収益貢献が大きく、日系を中心とした自動車分野、内需主導の建材についてもビジネスを拡充してきた。中国は成熟期に入ったが、市場規模は極めて大きいので、事業構造を柔軟に転換しながらビジネスを続けていく」
――米国は大きな事業基盤を持つ。
「先進国で人口が増加を続けており、鉄鋼需要も1億トン規模で安定している。商社機能、サービスの対価も認められている。持株会社のメタルワン・ホールディングス・アメリカ、トレーディングを行うメタルワン・アメリカとメタルワン・メキシコがあり、コイルセンターのコイルプラスはカナダ、メキシコを含めて9拠点、メタルワン・スチールサービス・メキシコが3拠点をそれぞれ展開している。自動車用ファスナーの在庫販売を行うナイファストが米国、カナダ、メキシコに拠点を持ち、カナダに鋼管問屋のカンタックがある。メタルワン・アメリカはシカゴ、デトロイト、ヒューストン、マイアミ、ナッシュビル、メタルワン・メキシコはメキシコシティ、アグアスカリエンテス、モンテレイにそれぞれ営業拠点を展開している。需要構造が変化する中、これらの事業基盤を最大限に活用して、自動車をはじめとする製造業、エネルギー分野のビジネスを拡大し、新たに建材・インフラ分野の需要を捕捉していきたい」
――米国の事業投資について検討を進めている。
「本社で検討を進めてきたメンバーがシカゴに拠点を移して、具体的な案件について事業化調査を進めている。トランプ政権の関税政策など予断を許さない事態はしばらく続くと思うが、中長期の視点に立ってビジネスチャンスを見極めていく」
――株主会社の現地事業とのシナジーも期待できる。
「三菱商事、双日ともに幅広い分野、地域でビジネスを展開している。米国は世界最大のデータセンター市場で、生成AIの普及に伴って需要が急拡大している。三菱商事は、米国のデータセンター事業に本格参入しており、建設鋼材や資機材のサプライチェーン構築などで連携する可能性も検討していきたい。エネルギー分野においても両株主と幅広い連携ができると見込んでおり、駐在員を増やして市場開拓を進める」
――インドは鉄鋼需要の拡大が本格化する。
「世界最大の人口があり、モディ政権も安定しており、建設、製造業ともに鉄鋼需要はまだまだ伸びていく。厚板溶断加工のIMOP、コイルセンターのマヒンドラ・スチールサービスセンター、マネサール・スチール・プロセシング、ナイファスト・インディアが現地事業を展開している。IMOPは、建機メーカー対応でフル操業を続けている。自動車分野ではマルチ・スズキに対し、メタルワングループとして部品メーカー対応を含めて安定供給体制の維持・強化に努めていく」
 ――市場開拓としては、遠景に中東・アフリカもある。
――市場開拓としては、遠景に中東・アフリカもある。
「ケニアのナイロビに分室を開設した。インド企業は、アフリカ諸国とのビジネスを幅広く展開しており、インドビジネスを通じた中東・アフリカ市場開拓のチャンスも探っていく」
――欧州への投資を実施した。
「欧州域内の大手変圧器コアメーカーのラゴアを昨年7月に子会社化した。イタリアのピエモンテ州に3工場を展開し、欧州域内の大手重電・変圧器メーカーに方向性電磁鋼板のコアを供給している。EVの需要拡大、大規模データセンターの新設が続く中、送電線網に使用される変圧器の需要が拡大している」
――グローバル事業部に電磁鋼板を扱う新しい組織を立ち上げる。
「これまで海外自動車・電機BUで自動車用鋼板と電磁鋼板を扱っていた。4月1日付で電磁・xEV推進BUを新設し、海外の電磁鋼板ビジネスを集約する。ラゴアを子会社化したことで、製造分野に進出することができて、方向性に加えて無方向性電磁鋼板のビジネスチャンスも広がっていくと期待している」
――欧州での次の展開は。
「三菱商事がドイツのエンジニアリングサービス会社であるFEVグループのFEVコンサルティングとビヨンド・マテリアルズを設立した。共同出資会社は、FEVコンサルティングが持つ自動車分野における設計・開発力と素材に関する知見、三菱商事が持つグローバルネットワークを掛け合わせて市場調査、開発支援・サービスを提供している。自動車産業の構造変化が続く中、メタルワンとしては、三菱商事とも連携して鋼材・部品サプライチェーンの関連からのシナジーも追求していきたいと考えている」
――アセアン・大洋州統括を4月1日付で新設する。
「北中米、南米、東アジア、南西アジアに加えて統括責任者を配置し、アセアン諸国と豪州、ニュージーランドを対象に域内運営を進める。自動車のEV化、中国からの生産拠点のシフト、コロナ後の経済活動回復などの潮流を踏まえて、タイ、インドネシア、ベトナムを中心に一体運営することで需給構造の変化にタイムリーに対応していく」
――「中期経営計画2024」では、『変革」と『成長』をメインテーマに掲げて事業・収益構造転換を図ってきた。
「国内鉄鋼需要の縮小、人手不足、物流問題などを産業課題と捉えて、デジタル技術を活用した鉄鋼流通の効率化に取り組んできた。不採算事業からの撤退、国内の鋼材価格上昇などを背景に連結純利益を底上げしてきた」
――次期中期経営計画のテーマは。
「パーパスの実現に向けて、『成長』に軸足を移し、未来への成長に焦点をあてた経営計画をまとめたいと考えている。そのための人材の育成、グローバル展開を強化していく」
――4月1日で役員体制も見直す。
「髙井執行役員にコーポレート担当として、次世代を見据えたメタルワングループ全体の人材戦略を推進してもらう。海外経験豊富な服部執行役員にもコーポレート担当として地域戦略を牽引してもらう。私は三菱商事の執行役員、尾藤副社長は双日の専務であり、株主会社との連携を強化しながら、新たなステージを目指して戦略を描き、実践していく」(谷藤 真澄)

「自動車、造船、建産機、電機など鉄鋼需要産業の海外生産シフト、少子高齢化などの影響で国内の鋼材消費量は縮小を続けてきた。米リーマン・ショック前の2007年度は内需が8000万トンで、内訳は製造業2600万トン、建設業2800万トン、間接輸出2600万トンだった。日本鉄鋼連盟は25年度の需要を前年度並みの5000万トン程度と見ている。内訳は製造業1500万トン、建設業1700万トン、間接輸出1800万トン。トランプ大統領が大規模な関税政策を打ち出していること、アジア諸国を含めて地産地消の流れが加速していることなどを踏まえると、間接輸出の下振れを想定しておく必要がある。一方で建設分野は、地震や豪雨・豪雪など自然災害に対する国土強靭化、直近で発生した下水道の破断など社会インフラの老朽化対策が待ったなしで、半導体工場、データセンター、物流施設、インバウンド対応宿泊施設などの計画も進んでいる。ところが2024年から建設業と輸送業における労働時間の規制が厳しくなり、資材高騰や構造的な人手不足も加わって、工期遅れや計画の見直しが続いており、こちらも決して楽観はできない。製造業分野では国内自動車メーカーの国内生産台数の行方も気になるところ。中長期的には内需が5000万トン以下で推移する可能性を否定できない」
――国内外の需給構造が変化する中、商社は事業構造転換を迫られている。
「メタルワンは設立時、『メタルマーケットメーカー』をビジョンに掲げ、金属産業に接するすべての産業・企業との連携強化による新たな市場の創造に取り組んできた。ミッションを『メタルバリュー・オプティマイザー』と定義づけ、産業と市場の最適化を図るためのバリューチェーンの革新に取り組んできた。このほど『世界中の“つくる"をつなぎ、価値創造を追求し続けることで、ものづくりの可能性を広げる』というパーパスを制定し、メタルワンの機能を明確化した」
――その狙いを。
「世界各地で地政学リスクが顕在化し、分断が鮮明になっている。社会的な課題も高度化、複雑化している。企業単独で課題を解決することが難しくなっている。こうした中、パーパスと併せて『金属素材を生み出す企業と、その素材を活かす企業。私たちは、サプライチェーン上に存在する本質的な課題に真摯に向き合い、ステークホルダーと共に新たなソリューションを創り出していきます』とのステイトメントを内外に公表した。メタルワングループの国内外の社員が一体となって、ビジネス、マーケット、技術をつなぐことで、新しいバリューを創出し、ものづくりの可能性を大きく広げていく」
――鉄鋼業は収益構造対策を迫られている。
「人口減少によって自動車や電機、住宅などの市場が縮小し、人手不足が人件費や物流費などのコスト上昇、建設の工期延長などを招いている。加工・流通分野においては、電話やファックス、メールなど様々な方法で注文内容が伝えられ、商社やコイルセンターが管理をして、鉄鋼メーカーや加工メーカーに様々な方法で伝達するところから始まり、膨大な労力が使われている。そこでメタルワンは、自動車産業の流通に関わる多くの企業がデータをシェアすることで、自動車鋼板流通の構造改革を可能とするデジタル・プラットフォーム『Metal X』を日本アイ・ビー・エムと共同開発した。発注者と受注者が直接入力する注文情報や出荷情報を一元管理することで、大幅な業務量の削減が可能となる。発注者、受注者が共有のプラットフォームにおいて注文・出荷情報をリアルタイムに把握できるため、高効率で持続可能なオペレーションが可能となり、コミュニケ―ションも円滑化できる。2023年4月の提供開始以来、自動車メーカー、部品メーカーはじめ数多くの取引先に導入頂き、新たな引き合いも続いている」
――「Metal X UP」も好評と聞いている。
「鉄鋼流通全体の業務効率化、高度化、コスト削減を図る、自社開発したデジタル・プラットフォーム。ミルシートの電子受け渡しや請求書の電子化、債権債務の金額照合、鋼材納期の進捗状況や注文履歴の確認など商社や問屋、加工流通の業務をワンストップで可能とする。23年に厚板分野から提供を開始し、24年4月には薄板、線材、鋼管分野へとクライアントを広げ、数百社の企業に活用いただいている」
 ――鉄鋼流通は需要構造転換と需要縮小への同時対応を求められている。
――鉄鋼流通は需要構造転換と需要縮小への同時対応を求められている。「例えば、自動車のEV化に対応して電磁鋼板やモーターコアの加工能力の増強を迫られるが、コイルセンター各社が自前主義で対処すると過剰投資、能力過剰を招く。各社が投資コストとランニングコストを転嫁すると需要家の競争力が低下する。陸上輸送はドライバーの勤務時間短縮、ドライバー不足で輸送能力の増強が求められているが、流通各社がトラックを増やすと、能力過剰となり、ドライバー不足がより深刻化して人件費がさらに上昇する。鉄鋼メーカーが先行して生産設備の構造改革をダイナミックに進めている。鉄鋼流通においても業界全体で『協調』する分野と『競争』原理を生かす分野とを分けて投資や設備合理化を進めなければならない。まずはメタルワングループ内で最適化を図り、系列を超えた協業に踏み込んでいく」
――社長就任前、三菱商事・マテリアルソリューショングループの新規事業開発本部長として鉄鋼流通の業務効率化にも取り組んでいた。
「メタルワンは鉄鋼流通に係る競合先と直接的に『競争』することもあるが、三菱商事は鉄鋼流通に直接関与してない立場を活かし、業界全体の共通利益のための『協調』を提起しやすい」
――メタルワンクラブが名古屋、九州はじめ各地でネットワークを形成している。
「業界全体の業務効率化が、鋼材のコスト競争力につながる。競争と協調、リアルとデジタルを組み合わせながら、時代に見合ったサプライチェーンを構築し、バリューを最適化していくための提案はできると考えている」
――海外市場はエリアによって事情が大きく異なるが、中国は需給構造が大きく変化しており、収益構造改革が不可欠となっている。
「中国、米国、タイ・インドネシアをはじめとする東南アジアでネットワークを構築し、インドも歴史的に強い事業基盤を持っている。20年間を振り返ると、発足後の2003年からの15年間については、世界の工場として著しい成長を遂げてきた中国の収益貢献が大きく、日系を中心とした自動車分野、内需主導の建材についてもビジネスを拡充してきた。中国は成熟期に入ったが、市場規模は極めて大きいので、事業構造を柔軟に転換しながらビジネスを続けていく」
――米国は大きな事業基盤を持つ。
「先進国で人口が増加を続けており、鉄鋼需要も1億トン規模で安定している。商社機能、サービスの対価も認められている。持株会社のメタルワン・ホールディングス・アメリカ、トレーディングを行うメタルワン・アメリカとメタルワン・メキシコがあり、コイルセンターのコイルプラスはカナダ、メキシコを含めて9拠点、メタルワン・スチールサービス・メキシコが3拠点をそれぞれ展開している。自動車用ファスナーの在庫販売を行うナイファストが米国、カナダ、メキシコに拠点を持ち、カナダに鋼管問屋のカンタックがある。メタルワン・アメリカはシカゴ、デトロイト、ヒューストン、マイアミ、ナッシュビル、メタルワン・メキシコはメキシコシティ、アグアスカリエンテス、モンテレイにそれぞれ営業拠点を展開している。需要構造が変化する中、これらの事業基盤を最大限に活用して、自動車をはじめとする製造業、エネルギー分野のビジネスを拡大し、新たに建材・インフラ分野の需要を捕捉していきたい」
――米国の事業投資について検討を進めている。
「本社で検討を進めてきたメンバーがシカゴに拠点を移して、具体的な案件について事業化調査を進めている。トランプ政権の関税政策など予断を許さない事態はしばらく続くと思うが、中長期の視点に立ってビジネスチャンスを見極めていく」
――株主会社の現地事業とのシナジーも期待できる。
「三菱商事、双日ともに幅広い分野、地域でビジネスを展開している。米国は世界最大のデータセンター市場で、生成AIの普及に伴って需要が急拡大している。三菱商事は、米国のデータセンター事業に本格参入しており、建設鋼材や資機材のサプライチェーン構築などで連携する可能性も検討していきたい。エネルギー分野においても両株主と幅広い連携ができると見込んでおり、駐在員を増やして市場開拓を進める」
――インドは鉄鋼需要の拡大が本格化する。
「世界最大の人口があり、モディ政権も安定しており、建設、製造業ともに鉄鋼需要はまだまだ伸びていく。厚板溶断加工のIMOP、コイルセンターのマヒンドラ・スチールサービスセンター、マネサール・スチール・プロセシング、ナイファスト・インディアが現地事業を展開している。IMOPは、建機メーカー対応でフル操業を続けている。自動車分野ではマルチ・スズキに対し、メタルワングループとして部品メーカー対応を含めて安定供給体制の維持・強化に努めていく」
 ――市場開拓としては、遠景に中東・アフリカもある。
――市場開拓としては、遠景に中東・アフリカもある。「ケニアのナイロビに分室を開設した。インド企業は、アフリカ諸国とのビジネスを幅広く展開しており、インドビジネスを通じた中東・アフリカ市場開拓のチャンスも探っていく」
――欧州への投資を実施した。
「欧州域内の大手変圧器コアメーカーのラゴアを昨年7月に子会社化した。イタリアのピエモンテ州に3工場を展開し、欧州域内の大手重電・変圧器メーカーに方向性電磁鋼板のコアを供給している。EVの需要拡大、大規模データセンターの新設が続く中、送電線網に使用される変圧器の需要が拡大している」
――グローバル事業部に電磁鋼板を扱う新しい組織を立ち上げる。
「これまで海外自動車・電機BUで自動車用鋼板と電磁鋼板を扱っていた。4月1日付で電磁・xEV推進BUを新設し、海外の電磁鋼板ビジネスを集約する。ラゴアを子会社化したことで、製造分野に進出することができて、方向性に加えて無方向性電磁鋼板のビジネスチャンスも広がっていくと期待している」
――欧州での次の展開は。
「三菱商事がドイツのエンジニアリングサービス会社であるFEVグループのFEVコンサルティングとビヨンド・マテリアルズを設立した。共同出資会社は、FEVコンサルティングが持つ自動車分野における設計・開発力と素材に関する知見、三菱商事が持つグローバルネットワークを掛け合わせて市場調査、開発支援・サービスを提供している。自動車産業の構造変化が続く中、メタルワンとしては、三菱商事とも連携して鋼材・部品サプライチェーンの関連からのシナジーも追求していきたいと考えている」
――アセアン・大洋州統括を4月1日付で新設する。
「北中米、南米、東アジア、南西アジアに加えて統括責任者を配置し、アセアン諸国と豪州、ニュージーランドを対象に域内運営を進める。自動車のEV化、中国からの生産拠点のシフト、コロナ後の経済活動回復などの潮流を踏まえて、タイ、インドネシア、ベトナムを中心に一体運営することで需給構造の変化にタイムリーに対応していく」
――「中期経営計画2024」では、『変革」と『成長』をメインテーマに掲げて事業・収益構造転換を図ってきた。
「国内鉄鋼需要の縮小、人手不足、物流問題などを産業課題と捉えて、デジタル技術を活用した鉄鋼流通の効率化に取り組んできた。不採算事業からの撤退、国内の鋼材価格上昇などを背景に連結純利益を底上げしてきた」
――次期中期経営計画のテーマは。
「パーパスの実現に向けて、『成長』に軸足を移し、未来への成長に焦点をあてた経営計画をまとめたいと考えている。そのための人材の育成、グローバル展開を強化していく」
――4月1日で役員体制も見直す。
「髙井執行役員にコーポレート担当として、次世代を見据えたメタルワングループ全体の人材戦略を推進してもらう。海外経験豊富な服部執行役員にもコーポレート担当として地域戦略を牽引してもらう。私は三菱商事の執行役員、尾藤副社長は双日の専務であり、株主会社との連携を強化しながら、新たなステージを目指して戦略を描き、実践していく」(谷藤 真澄)















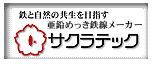
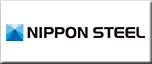
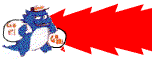

















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ


















