2025年6月4日
財務・経営戦略を聞く/日本製鉄副会長兼副社長/森 高弘氏/実力利益 関税影響でも6000億円超/輸入材対抗策に電炉鋼を活用
――2024年度は国内需要が約5000万トンに減り、輸出市場が悪化し、低水準の粗鋼生産の中で在庫評価差等除く実力の連結事業利益7937億円と高収益を維持した。25年度は米国の関税政策の影響が懸念されるが、市場の先行きをどう見通しているか。
「事業環境が厳しくなることを予測し、他社に先駆けて構造対策を打ち、ひも付き価格の是正を行い、海外事業を深化・拡大してきた。さらに厚みをもった事業構造を築こうと原料権益の投資やグループ会社の再編統合を進めてきた。こうした収益力強化策が功を奏し、24年度は未曽有の厳しい状況の中で利益を上げることができた。これまでの取り組みの成果と言える。25年度は建設分野や製造業の一部持ち直しを想定したが大きな回復は見込めず、米国の関税政策によって不透明感が増す中、内需は5000万トンを下回る可能性がある。日本の米国向け鋼材輸出は年100万トン程度で日本から購入せざるを得ない高級鋼が多く、直接の関税影響は大きくないが、国内外のお客様を経由し米国を最終消費地とする輸出が減少することにより鋼材需要が減少することの影響は甚大だ。これに他の国の鋼材輸出が米国向けからアジア向けに振り替わり、日本の輸入鋼材増加やアジア鋼材需給のさらなる緩和も大きな懸念材料だ」
――25年度の実力の連結事業利益は7000億円以上、米国の関税影響を考慮して6000億円以上を予想している。関税影響で単独粗鋼生産は100万トン程度減る可能性があるとのことだが。
「25年度の単独粗鋼の予想は公表していない。(100万トン減は)一定の参考値であり、米国関税の影響は読み切れない。インドのAM/NSインディアの増強工事が人手不足もあって遅れるが元々大きな利益を織り込んでおらず、鹿島地区の高炉休止や豪ブラックウォーター鉱山権益取得などで25年度に見込む1000億円程度のプラス効果は十分得られる。24年度に実力の利益を8000億円程度と設定し、25年度の対策効果1000億円を上乗せし9000億円を目指す計画だったが、中国の高生産・高輸出の影響が拡大していくため、25年度は7000億円以上を目指し、米国の関税影響を受けたとしても6000億円以上の利益を確保する。米国関税の影響は直接・間接輸出など最大で1000億円程度のマイナス影響を織り込むが、英国や中国に対する米国の動きをみるとそこまでマイナス影響を受けないかもしれない。トランプ政権の政策自体が大きく揺れており、鋼材のサプライチェーンへの影響を定量的に把握するのは現段階では意味がない。8月頃には関税影響について改めて見通したいが、そのためには政策動向はじめ状況をよく注視する必要がある」
――増え続ける輸入材への対抗策は。中山製鋼所との電炉合弁事業はその一つに。
「24年度の普通鋼鋼材輸入は500万トンと前年比4・9%増え、うち中国が24%増と突出している。中国の輸出圧力が高まり、各国・地域でアンチダンピング措置やセーフガードなど通商措置が相次いたことも影響し、日本の鋼材輸入は増加傾向にある。米国の関税政策の影響で鋼材がアジアに回ってくる可能性は高く、日本国内の需給がさらに悪化し、健全なサプライチェーンに悪影響を及ぼす恐れがある。日本鉄鋼連盟が鋼材の輸入に関する通商政策を日本政府に要望しており、政府によって効果的な対策がなされることを期待している。当社としては、いかなる環境下でも安定的に収益を上げるために国内の建材分野などの需要を取り込んでいく。中山製鋼所と電炉の合弁会社を設立し、これまでの品種高度化を中心とした取り組みを基軸としつつ、競争力のある電炉鋼の新たな商品ラインナップを拡充し、輸入対抗含め建材など取り込めていない分野に販売していく」
――山陽特殊製鋼の完全子会社化、日鉄ステンレス吸収合併、電縫鋼管事業再編を相次ぎ実施した。グループ再編のシナジーをどう発揮していく。
「山陽特殊製鋼とはグループとしての生産体制の最適化を指向していくが、完全子会社化によって営業面での協力も可能となる。加えて、ステンレス事業もそうだが、本社の技術リソースや海外展開のノウハウを活用でき、単独では難しいCN対応も進めやすくなる。原料の鉄スクラップのオペレーションについてもグループの総合力を活かせる。他に検討しているグループ再編については成案化できたものから公表していくが、利益予想に織り込んでいないので成案化し実行したところからプラス効果を上げていく」
――26年度開始の次期中期経営計画で想定する重点テーマは。
「これから議論するが、実行している施策や方向性は大きくは変わらないだろう。国内の課題は競争力の徹底的な強化だ。他社にコスト競争力で負けているところがあり、グループ再編統合のシナジーも追求して抜本的に競争力を引き上げる。成長する場は海外だ。世界最大の高級鋼市場を持つ米国と、中国の過剰生産・輸出の影響を比較的受けにくい成長するインドでの事業展開を強化していく。USスチールとの合併がクローズすればその瞬間から連結の収益に効いている。インドは能力拡張を進め、ホームマーケットのASEAN、特にタイは成長を取り込む施策を形にしていく。中東とアフリカの市場を視野に入れるが、その場合、インドの拠点から供給していくことが自然と考えている」
――USスチールとの合併計画は大統領判断の期日(6月5日)が近づいている。
「CFIUS(対米外国投資委員会)の勧告が大統領に5月21日に提出され、大統領の判断に委ねられている。米政府との交渉について具体的な内容には言及できないが、本取引の承認を目指してUSスチールと共同で取り組みを続けている」
――需要が減り、粗鋼生産が急減した際の高炉のバンキング(休風)あるいは追加の合理化策の可能性は。
「需要が大幅に減少した場合のバンキングの有無や追加の合理化策は次期中期計画で最も議論されることだと思う。ただ、簡単に能力を削減すべきとは思わない。失う限界利益が大きくなるなどマイナス影響が大きい。鹿島地区の高炉休止で単独粗鋼能力を4200万トンから3900万トンに落としたが、日鉄ステンレス統合で4000万トン程度となる。稼働率が上がった分は需要の変動に対応できる。体質強化とともに中山製鋼所との合弁事業で内需を取り込んでいくので単純に生産量が減るというわけではない」
――海外での成長戦略について。AM/NSインディアの新製鉄所建設は南部で用地を取得し、大きく前進した。
「西部のハジラ製鉄所の増強は建材向け高耐食めっき鋼板の投資効果を24年度以降に得ており、25年度は自動車向けの鋼板に本格参入する。第1期の能力増強に取り組み、鉄源一貫で拡張する新能力は26年度に立ち上がる。粗鋼能力を年1500万トンに増やした後、第2期の能力拡張に入る。さらに南部のアンドラプラデシュ州の土地を確保し、年産能力700万トン規模の鉄源一貫製鉄所を建設する。設計・工事に3年以上は要するだろうが、その前にハジラ製鉄所の能力を拡張して需要を捕捉する。市場が成長しているのにAM/NSインディアの収益貢献度が低いのは輸入材が影響している。輸入業者は海外材との価格差をみて輸入に動き、これが国内市況の下押し要因となっている。背景には、国内需要の伸びが鉄鋼生産能力の拡大ペースを上回っているという構造的な要因がある。生産能力は階段上にしか増強できず、その踊り場では供給が需要に追いつかず、輸入材が流入しやすい。AM/NSインディアの能力拡張を急ぎ、需要の伸びに対応していく」
――タイの電炉子会社G/GJスチールは中国材の影響を受けて苦戦していたが、対策の手を相当打っている。
「小川英樹常務執行役員がNS―SUSとG/GJスチールの社長に就いて、両社を一元的に統括することで、マネジメント体制を強化した。また、NS―SUSと営業部門を実質統合し、技術サービスを増強して総合的な営業力を発揮できるようにした。これにより、数量は増えていく見込みだ。さらに、室蘭地区や鹿島地区から鉄スクラップや銑鉄をG/GJに送り、タイの当社グループ会社で発生したスクラップも活用し、総合的・機動的な原料調達体制を構築した。新たな原料ソースを得たことで、タイ国内で鉄スクラップを有利に購入できている。電力原単位など変動費を下げる取り組みも進めている。低調な需要と中国材の輸入増が問題となっているが、タイ政府に働きかけて需要の喚起と通商対策に手を打っていただいており、状況は改善する見通し。当社グループはタイの薄板シェアの30%を持っている。高級鋼の自動車用鋼板やブリキなどは4―6割のシェアを持つ重要なマーケットだ。本国以外でこれだけのシェアを持つ国は他になく、海外市場でこれほどの存在感を示している例は他の鉄鋼企業ではあまりみられない。長年かけてリソースを投入しており、政府との関係は強く、地元の社員とも良好な関係を続けており、大事にしたい。グループ全体として総合力を発揮することを考え、実行していく。」(植木 美知也)

「事業環境が厳しくなることを予測し、他社に先駆けて構造対策を打ち、ひも付き価格の是正を行い、海外事業を深化・拡大してきた。さらに厚みをもった事業構造を築こうと原料権益の投資やグループ会社の再編統合を進めてきた。こうした収益力強化策が功を奏し、24年度は未曽有の厳しい状況の中で利益を上げることができた。これまでの取り組みの成果と言える。25年度は建設分野や製造業の一部持ち直しを想定したが大きな回復は見込めず、米国の関税政策によって不透明感が増す中、内需は5000万トンを下回る可能性がある。日本の米国向け鋼材輸出は年100万トン程度で日本から購入せざるを得ない高級鋼が多く、直接の関税影響は大きくないが、国内外のお客様を経由し米国を最終消費地とする輸出が減少することにより鋼材需要が減少することの影響は甚大だ。これに他の国の鋼材輸出が米国向けからアジア向けに振り替わり、日本の輸入鋼材増加やアジア鋼材需給のさらなる緩和も大きな懸念材料だ」
――25年度の実力の連結事業利益は7000億円以上、米国の関税影響を考慮して6000億円以上を予想している。関税影響で単独粗鋼生産は100万トン程度減る可能性があるとのことだが。
「25年度の単独粗鋼の予想は公表していない。(100万トン減は)一定の参考値であり、米国関税の影響は読み切れない。インドのAM/NSインディアの増強工事が人手不足もあって遅れるが元々大きな利益を織り込んでおらず、鹿島地区の高炉休止や豪ブラックウォーター鉱山権益取得などで25年度に見込む1000億円程度のプラス効果は十分得られる。24年度に実力の利益を8000億円程度と設定し、25年度の対策効果1000億円を上乗せし9000億円を目指す計画だったが、中国の高生産・高輸出の影響が拡大していくため、25年度は7000億円以上を目指し、米国の関税影響を受けたとしても6000億円以上の利益を確保する。米国関税の影響は直接・間接輸出など最大で1000億円程度のマイナス影響を織り込むが、英国や中国に対する米国の動きをみるとそこまでマイナス影響を受けないかもしれない。トランプ政権の政策自体が大きく揺れており、鋼材のサプライチェーンへの影響を定量的に把握するのは現段階では意味がない。8月頃には関税影響について改めて見通したいが、そのためには政策動向はじめ状況をよく注視する必要がある」
――増え続ける輸入材への対抗策は。中山製鋼所との電炉合弁事業はその一つに。
「24年度の普通鋼鋼材輸入は500万トンと前年比4・9%増え、うち中国が24%増と突出している。中国の輸出圧力が高まり、各国・地域でアンチダンピング措置やセーフガードなど通商措置が相次いたことも影響し、日本の鋼材輸入は増加傾向にある。米国の関税政策の影響で鋼材がアジアに回ってくる可能性は高く、日本国内の需給がさらに悪化し、健全なサプライチェーンに悪影響を及ぼす恐れがある。日本鉄鋼連盟が鋼材の輸入に関する通商政策を日本政府に要望しており、政府によって効果的な対策がなされることを期待している。当社としては、いかなる環境下でも安定的に収益を上げるために国内の建材分野などの需要を取り込んでいく。中山製鋼所と電炉の合弁会社を設立し、これまでの品種高度化を中心とした取り組みを基軸としつつ、競争力のある電炉鋼の新たな商品ラインナップを拡充し、輸入対抗含め建材など取り込めていない分野に販売していく」
――山陽特殊製鋼の完全子会社化、日鉄ステンレス吸収合併、電縫鋼管事業再編を相次ぎ実施した。グループ再編のシナジーをどう発揮していく。
「山陽特殊製鋼とはグループとしての生産体制の最適化を指向していくが、完全子会社化によって営業面での協力も可能となる。加えて、ステンレス事業もそうだが、本社の技術リソースや海外展開のノウハウを活用でき、単独では難しいCN対応も進めやすくなる。原料の鉄スクラップのオペレーションについてもグループの総合力を活かせる。他に検討しているグループ再編については成案化できたものから公表していくが、利益予想に織り込んでいないので成案化し実行したところからプラス効果を上げていく」
――26年度開始の次期中期経営計画で想定する重点テーマは。
「これから議論するが、実行している施策や方向性は大きくは変わらないだろう。国内の課題は競争力の徹底的な強化だ。他社にコスト競争力で負けているところがあり、グループ再編統合のシナジーも追求して抜本的に競争力を引き上げる。成長する場は海外だ。世界最大の高級鋼市場を持つ米国と、中国の過剰生産・輸出の影響を比較的受けにくい成長するインドでの事業展開を強化していく。USスチールとの合併がクローズすればその瞬間から連結の収益に効いている。インドは能力拡張を進め、ホームマーケットのASEAN、特にタイは成長を取り込む施策を形にしていく。中東とアフリカの市場を視野に入れるが、その場合、インドの拠点から供給していくことが自然と考えている」
――USスチールとの合併計画は大統領判断の期日(6月5日)が近づいている。
「CFIUS(対米外国投資委員会)の勧告が大統領に5月21日に提出され、大統領の判断に委ねられている。米政府との交渉について具体的な内容には言及できないが、本取引の承認を目指してUSスチールと共同で取り組みを続けている」
――需要が減り、粗鋼生産が急減した際の高炉のバンキング(休風)あるいは追加の合理化策の可能性は。
「需要が大幅に減少した場合のバンキングの有無や追加の合理化策は次期中期計画で最も議論されることだと思う。ただ、簡単に能力を削減すべきとは思わない。失う限界利益が大きくなるなどマイナス影響が大きい。鹿島地区の高炉休止で単独粗鋼能力を4200万トンから3900万トンに落としたが、日鉄ステンレス統合で4000万トン程度となる。稼働率が上がった分は需要の変動に対応できる。体質強化とともに中山製鋼所との合弁事業で内需を取り込んでいくので単純に生産量が減るというわけではない」
――海外での成長戦略について。AM/NSインディアの新製鉄所建設は南部で用地を取得し、大きく前進した。
「西部のハジラ製鉄所の増強は建材向け高耐食めっき鋼板の投資効果を24年度以降に得ており、25年度は自動車向けの鋼板に本格参入する。第1期の能力増強に取り組み、鉄源一貫で拡張する新能力は26年度に立ち上がる。粗鋼能力を年1500万トンに増やした後、第2期の能力拡張に入る。さらに南部のアンドラプラデシュ州の土地を確保し、年産能力700万トン規模の鉄源一貫製鉄所を建設する。設計・工事に3年以上は要するだろうが、その前にハジラ製鉄所の能力を拡張して需要を捕捉する。市場が成長しているのにAM/NSインディアの収益貢献度が低いのは輸入材が影響している。輸入業者は海外材との価格差をみて輸入に動き、これが国内市況の下押し要因となっている。背景には、国内需要の伸びが鉄鋼生産能力の拡大ペースを上回っているという構造的な要因がある。生産能力は階段上にしか増強できず、その踊り場では供給が需要に追いつかず、輸入材が流入しやすい。AM/NSインディアの能力拡張を急ぎ、需要の伸びに対応していく」
――タイの電炉子会社G/GJスチールは中国材の影響を受けて苦戦していたが、対策の手を相当打っている。
「小川英樹常務執行役員がNS―SUSとG/GJスチールの社長に就いて、両社を一元的に統括することで、マネジメント体制を強化した。また、NS―SUSと営業部門を実質統合し、技術サービスを増強して総合的な営業力を発揮できるようにした。これにより、数量は増えていく見込みだ。さらに、室蘭地区や鹿島地区から鉄スクラップや銑鉄をG/GJに送り、タイの当社グループ会社で発生したスクラップも活用し、総合的・機動的な原料調達体制を構築した。新たな原料ソースを得たことで、タイ国内で鉄スクラップを有利に購入できている。電力原単位など変動費を下げる取り組みも進めている。低調な需要と中国材の輸入増が問題となっているが、タイ政府に働きかけて需要の喚起と通商対策に手を打っていただいており、状況は改善する見通し。当社グループはタイの薄板シェアの30%を持っている。高級鋼の自動車用鋼板やブリキなどは4―6割のシェアを持つ重要なマーケットだ。本国以外でこれだけのシェアを持つ国は他になく、海外市場でこれほどの存在感を示している例は他の鉄鋼企業ではあまりみられない。長年かけてリソースを投入しており、政府との関係は強く、地元の社員とも良好な関係を続けており、大事にしたい。グループ全体として総合力を発揮することを考え、実行していく。」(植木 美知也)














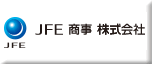


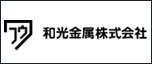

















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ


















