2025年6月5日
日本鉄リサイクル工業会 創立50周年/若手経営者座談会/変化に挑み 稼げる業界に/団結し海外で戦える実力を
日本鉄リサイクル工業会は、北海道、東北、関東、中部、関西、中四国、九州の7支部で構成される。このうち4支部が若手の会を持ち、30-40歳代の若手が勉強会や交流会などを行っている。産業新聞社はこのほど、関東支部錆年会の山下耕平会長(ヤマシタ社長)、関西支部青年交流会の澤将也会長(信和鋼材社長)、北海道支部青年部の斉藤孝治郎会長(斉藤商店社長)、中四国支部青年部会の槙岡達也部会長(こっこー社長)に参集願い、鉄リサイクル業界の課題を踏まえて未来を展望してもらう座談会を開催した。3時間弱にわたる座談の意見交換の話題は、ヤード運営規制条例への眼差し、採用活動の難しさ、次の世代への思い、そして鉄スクラップ国内循環の未来図など様々に及んだ。
――自己紹介と、各会の活動状況をお聞かせください。まずは関東支部から。
 山下「錆年会の第3代会長の山下です。当会を設立して7年がたち、これまでの期間で同業者間の信頼関係の構築や各社の強みを共有できたのではないかと感じています。最近はスクラップユーザーの声を聞きたいという声を受けて、千代田鋼鉄工業さん(以下、敬称略)や東京製鉄などの電炉メーカーをお呼びしてご講演いただいたり、当会の有志で東京製鉄の田原工場向けに鉄スクラップを内航船で出荷したり、一歩踏み込んだチャレンジをしています。本年度は海外の知識を深めるためにコンテナ輸送の勉強会や韓国の視察を検討しています」
山下「錆年会の第3代会長の山下です。当会を設立して7年がたち、これまでの期間で同業者間の信頼関係の構築や各社の強みを共有できたのではないかと感じています。最近はスクラップユーザーの声を聞きたいという声を受けて、千代田鋼鉄工業さん(以下、敬称略)や東京製鉄などの電炉メーカーをお呼びしてご講演いただいたり、当会の有志で東京製鉄の田原工場向けに鉄スクラップを内航船で出荷したり、一歩踏み込んだチャレンジをしています。本年度は海外の知識を深めるためにコンテナ輸送の勉強会や韓国の視察を検討しています」
 澤「関西支部青年交流会の澤です。6代目の会長になります。関西青年交流会は15年の歴史がありコロナ禍は活動が途絶えていたのですが、昨年の就任以降、自分が青年交流会で得た経験を若手に体験してもらおうと思い視察や研修などを再開しました。昨年11月には姫路のヤマトスチールとマキウラ鋼業、茨木金属商会の工場を見学させていただき、今年3月は錆年会との合同勉強会を企画して関東に出向き、扶和メタル東京ベイやナンセイスチールの千葉のヤードを見学させてもらいました。先月は津田聰一朗執行役員をはじめ東京製鉄の皆様を講師に招いて講習会を実施し、来年3月には海外視察を計画しています」
澤「関西支部青年交流会の澤です。6代目の会長になります。関西青年交流会は15年の歴史がありコロナ禍は活動が途絶えていたのですが、昨年の就任以降、自分が青年交流会で得た経験を若手に体験してもらおうと思い視察や研修などを再開しました。昨年11月には姫路のヤマトスチールとマキウラ鋼業、茨木金属商会の工場を見学させていただき、今年3月は錆年会との合同勉強会を企画して関東に出向き、扶和メタル東京ベイやナンセイスチールの千葉のヤードを見学させてもらいました。先月は津田聰一朗執行役員をはじめ東京製鉄の皆様を講師に招いて講習会を実施し、来年3月には海外視察を計画しています」
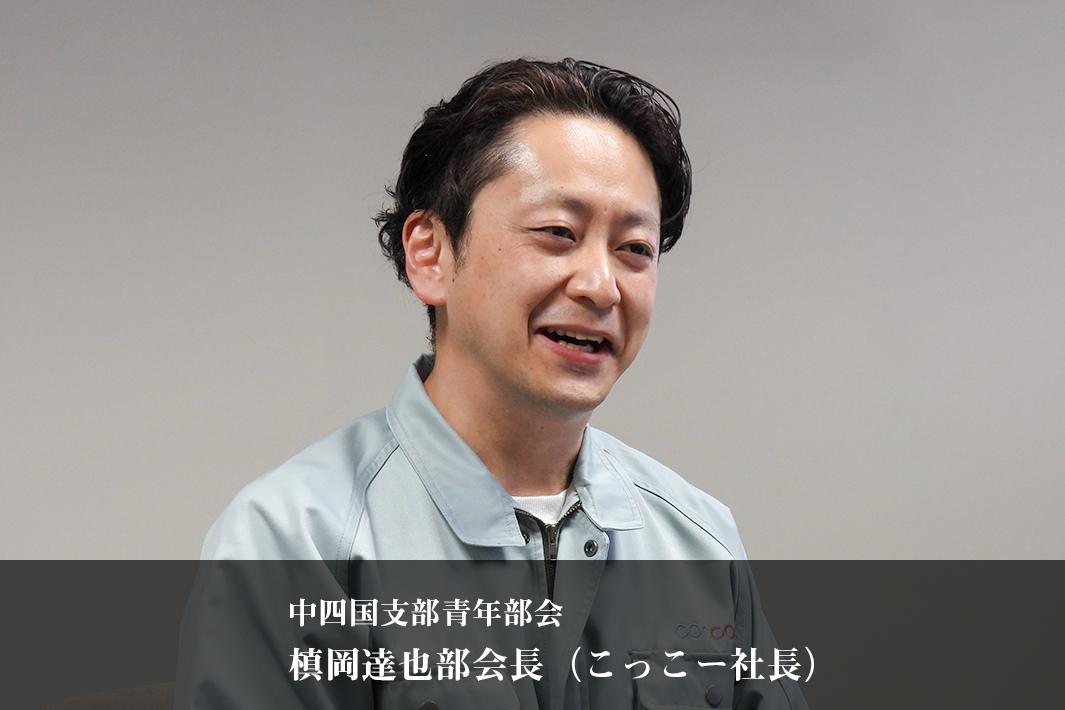 槙岡「中四国支部の槙岡です。この座談会にいらっしゃる方は、これまで当社に来ていただいたり私からお伺いしたり、そういったお付き合いのある方々ですが、改めて自己紹介します。当会は21年に発足し、私が初代会長です。前支部長の丸本陽章・丸本鋼材社長からの強いご指名を受けまして、そういう運びとなりました。同時に親会は平林実支部長(平林金属社長)が就任され、平林支部長の指導のもと活動しています。見事に諸先輩方の『策略』にはめられて今この場にいるのですが、お世話になった方々のご子息が当会に入られていることもあり『親から受けた恩は息子に返さないかん』と思っている次第です(笑)。とはいえ、この活動を通じて、たくさんの新たな経験と出会いがあったので、お二方には感謝しています。活動実績としては、今年2月に北海道のマテックや鈴木商会の工場見学を行いました。北海道支部の全国大会実行委員会の方々とも交流でき充実した3日間でした。ほかには、業界が抱える人手不足の課題を踏まえて広報に関する知識をつけようと、SNSで活躍中の『鉄くず兄さん』こと藤岡寛大・イチイ産業社長に話を聞く場を設けたり、錦麒産業の社長をお招きしたパネルディスカッションをしたりなど、青年部だからこそできる活動を行っています。年明けにベトナムを視察したいと検討しており、目下、とある商社さんと相談中です」
槙岡「中四国支部の槙岡です。この座談会にいらっしゃる方は、これまで当社に来ていただいたり私からお伺いしたり、そういったお付き合いのある方々ですが、改めて自己紹介します。当会は21年に発足し、私が初代会長です。前支部長の丸本陽章・丸本鋼材社長からの強いご指名を受けまして、そういう運びとなりました。同時に親会は平林実支部長(平林金属社長)が就任され、平林支部長の指導のもと活動しています。見事に諸先輩方の『策略』にはめられて今この場にいるのですが、お世話になった方々のご子息が当会に入られていることもあり『親から受けた恩は息子に返さないかん』と思っている次第です(笑)。とはいえ、この活動を通じて、たくさんの新たな経験と出会いがあったので、お二方には感謝しています。活動実績としては、今年2月に北海道のマテックや鈴木商会の工場見学を行いました。北海道支部の全国大会実行委員会の方々とも交流でき充実した3日間でした。ほかには、業界が抱える人手不足の課題を踏まえて広報に関する知識をつけようと、SNSで活躍中の『鉄くず兄さん』こと藤岡寛大・イチイ産業社長に話を聞く場を設けたり、錦麒産業の社長をお招きしたパネルディスカッションをしたりなど、青年部だからこそできる活動を行っています。年明けにベトナムを視察したいと検討しており、目下、とある商社さんと相談中です」
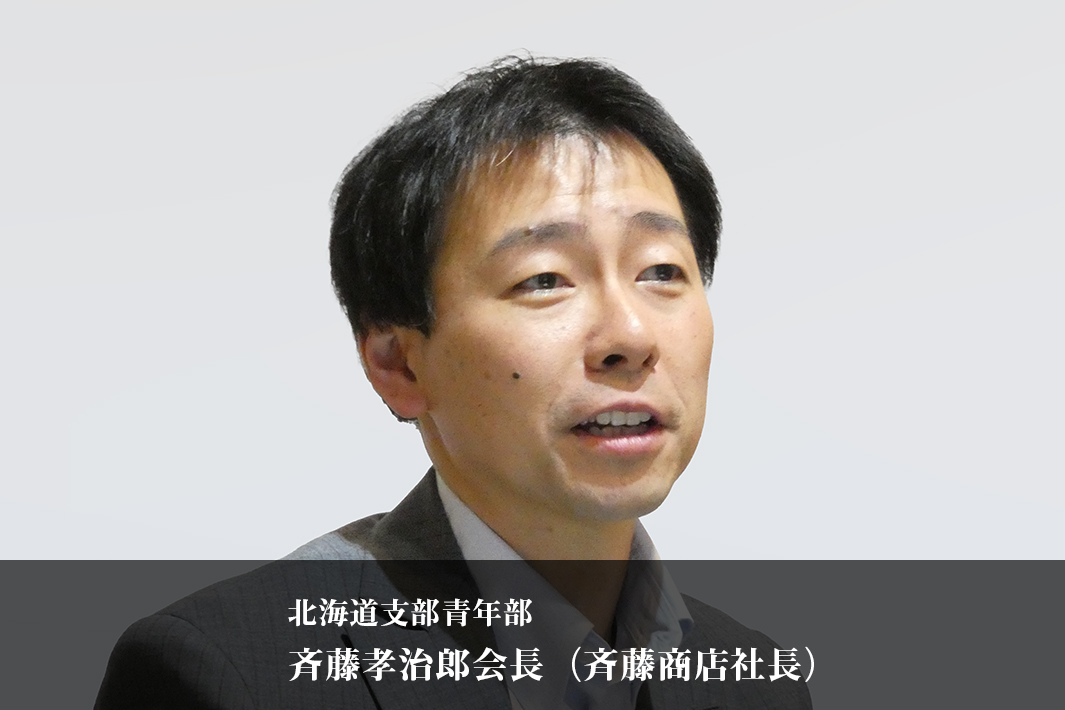 斉藤「北海道支部青年部長の斉藤商店、斉藤孝治郎です。北海道の東にある北見市でスクラップ屋を営んでおります。私が部長になったのは2023年。19年に工業会の全国大会が関西で行われた際、前日に青年部のパネルディスカッションがあり、それをきっかけに北海道も青年部を作ろうという機運が高まりました。コロナ禍の数年は活動が停滞していましたが23年から再始動し、中四国・中部・関東の各支部の方々と交流の場を設けました。今後も、道内の企業訪問や他支部との交流などの活動は続けていきたいですが、今のところは北海道支部主管の全国大会の総仕上げに尽力中という感じです(笑)」
斉藤「北海道支部青年部長の斉藤商店、斉藤孝治郎です。北海道の東にある北見市でスクラップ屋を営んでおります。私が部長になったのは2023年。19年に工業会の全国大会が関西で行われた際、前日に青年部のパネルディスカッションがあり、それをきっかけに北海道も青年部を作ろうという機運が高まりました。コロナ禍の数年は活動が停滞していましたが23年から再始動し、中四国・中部・関東の各支部の方々と交流の場を設けました。今後も、道内の企業訪問や他支部との交流などの活動は続けていきたいですが、今のところは北海道支部主管の全国大会の総仕上げに尽力中という感じです(笑)」
――親会との関係はいかがですか。
槙岡「中四国はしがらみなどは全く無いです。支部長の平林さんに『わしが責任を持ってやるから』とおっしゃっていただいているので、ありがたいことに自由にやらせてもらっています。これまで青年部の活動に対して『ご意見』を寄せられることもあったらしいのですが、平林さんから『わしのところで止めておくから』と言っていただいています。もちろん活動についてはいろいろな面から考えますが、現状ではやりたいことが実施できています」

澤「先ほど話した関東視察に関連するのですが、私が以前、錆年会に所属していたという経緯があり、関東の取り組み方を関西の会員にも是非知ってほしいという気持ちが強くありました。やりたいことは沢山あり、関東視察を実現したいという話も以前からしていたのですが、ゼロから業界の視察を企画したことがなかったのでどこまでやっていいかよくわかりませんでした。そんな折、業界の重鎮から『青年交流会じゃないとできないことやった方がいいよ』と後押ししていただいた。若手会としていろんな形を見せていけたらと思っています」
山下「私は実施後に反応を見ています(笑)。1年間活動して途中くらいから『錆年会の活動を関東支部の上の世代の方々が応援してくれている』という雰囲気を感じるようになりました。会費を年間40万円から80万円に倍増していただきたいということも理解してくださいました。谷平竜幸関東支部長をはじめとする方々に背中を押してもらい、『良い活動をしているね』というお言葉をいただいています」

斉藤「北海道は、スクラップ業者を取り巻く環境が他地区と少し違うところがあります。会員企業が広範囲に点在しているので、気軽に『数か月に1回集まろう』というのが難しく、どうしても前もって『何か月後のこの時に情報交換しましょう』という感じになってしまいます。北海道には大手業者が2社ありますが、その他は中小規模の会社が多い地区です。組織の力や会社のバックアップという面で他地区より恩恵を受け難い事情もあります。今のところ尖った企画を充分にできていないという反省がありますが、みなさん集まったら集まったで楽しく仕事の話をして交流できているのも事実です。まずはこのあたりを積み重ねていくことも大事だと思っています」
――海外視察の検討の話が出ましたが、今、注目している国はどこでしょうか。
澤「東南アジアで特にベトナムですかね」
山下「インドやトルコも気になります。関東は鉄スクラップの余剰地域なので、今後は大型船での船積みが輸出のトレンドになりそう。現実的に行けるかっていうと難しいですが錆年会で行けるなら面白いと思います」
澤「バングラデシュにも関心はありますが、会の事業として実施するにはハードルが高い。会員全員を安全に日本に帰すという責任を伴いますから。関西は実務の多い若手の方が多いので、必然的に自社の仕事を止めていられる期間も短くなる。休日を絡めて予定を組んで、かつ行き先の国の鉄鋼メーカーが稼働している日程で、となると長期視察は難しいかもしれないです」
――みなさんは商社など他の企業で働かれた経験はありますか。
澤「就職活動をして鉄鋼業とまったく関係ない包装会社で2年ほど働きました。その後、信和に転職し出向するかたちで三井物産メタルズ(現エムエム建材)にもお世話になりました」
山下「私は鉄鋼関係の仕事をしたいと思って就職活動をして大同特殊鋼グループの大同興業で働きました」
斉藤「産業振興で9年ほど。家業を特段意識せず普通に就活をして入社しました。結局はこうなっちゃったのですが(笑)」
槙岡「私は大卒後、毎日コミュニケーションズ (現:マイナビ)に入り、その後は日新製鋼(現:日本製鉄)の子会社の日新総合建材(現:日鉄鋼板)で約5年。その後、当社に入りました」
――企業風土の違いは感じますか。
斉藤「産業振興は鉄リサイクル業と近い会社ですが、会社の雰囲気や規模感は本当に真逆でした。複数の事業部制で運営されており従業員も1400人近くいます。コンプライアンスや組織運営などは自社に落とし込みにくいですが、安全面の取り組みなどは吸収しようと心がけています」
澤「スクラップ業界は同業者とコミュニケーションを積極的に取りますよね。これはかなり珍しいと思いました。前職の包装業界は同業団体がなかったですし、他の業者と仲良くしていると『ヘッドハンティングされるんちゃうか』とか『なんか企んでいるんちゃうか』とか、そういうことが噂されかねない雰囲気でした。スクラップ業界のようにコミュニケーションをとることでお互いにプラスになれる関係はいいと思います。余談ですが、パッケージ会社は包装紙や化粧箱などを作ってお客さんに納品した後、色のイメージが違うだけでひとつのロットが全て産業廃棄物になってしまいます。でも、鉄リサイクルの仕事は違いますよね。出荷して仮に『ごみが入ってる』と返品されても、そのごみさえ取り除けば再販できるので損失のリスクがかなり小さい。次世代につなぎやすいというか、強い会社になりやすい事業だと思いました」
山下「私は大同興業に入って1年目から大同特殊鋼の知多工場の生産管理室に配属されました。現場と営業の狭間のような立ち位置です。当時は企業という縦割りの中のひとつの役割を担当するという感覚でしたが、家業に入った時には『こんなにやり甲斐があるんだ』と思いました。中小企業だから、私の判断で会社が変わるわけです。一人一人の成長が会社全体の成長に直につながるともいえる。挑戦し甲斐のある業界だと思います」
槙岡「スクラップ業界は、大変縄張り意識の強い業界だなと感じます。ポジティブに言うならば役割分担がしっかり決まっている。マイナビにいたころは、同業者と契約を取った・取られたの戦いでした。競合と業界トップを争っていたので上司からは『競合から切り替える契約を取ってくるまで帰ってくるな』とよく言われました。それに比べるとリサイクル業界は皆で共存していくようなやり方ができているように思います。加えて、トレーサビリティ(原料から製品に至るまでの追跡可能性)が担保されにくい業界とも言える。今は、なかなかそういうわけにはいかないですが、昔はスクラップをプレスして中に不純物やごみを混ぜときゃええわ、といったケースもあったと聞きます。これが正解だと教えてくれる教科書を作るのが難しい業界だと思います」
――経営者候補が商社やメーカーで働くメリットは何だと思われますか。
澤「客観的にスクラップの仕事を体験できる点ではないでしょうか。私は商社さんでの研修前に信和で少し現場仕事をしたのですが、みんないきなり来た社長の息子が何もできないから扱いに困ったと思います。研修期間は三井物産メタルズ堺事業所(現:共英マテリアル)で現場作業を経験させて頂いたのですが、その時はいい意味でこき使ってくれましたので現場作業の実務を覚えるのには非常に恵まれた環境でした。現場のことを理解した上で会社に戻って、それでようやく自分の会社の仲間になれたという感じがしました。若い時からずっと自分の会社で一緒に仲間として成長してこられた後継者の方もいらっしゃるので、もちろんそれはそれで強いと思いますが」
斉藤「経営者候補は自分の子どもでも従業員でもいいですが、学校を卒業してすぐ家業に入るよりは、業種を問わずどこか違うところで経験してほしいです。何かしらの人生の経験になりますし」
山下「メリットはあると思います。私自身、外でいろいろと経験して今でもその縁で仕事をいただいています。人脈も築けますし。『可愛い子には旅をさせよ』というように息子には外で修行してほしいですね。星空を見上げながら夜中まで仕事したことも今となってはいい経験。自分の会社だとどうしても息子に甘くなりそうですから」
――息子さんの話が出ましたが、皆さんは次世代の経営者候補はいらっしゃいますか。
山下「息子は今11歳ですが、将来的には継いでほしいです。息子に選んでもらえる会社でありたいという思いもあり、業界の嫌な部分や会社の直すべきところを少しずつ改善してきました。とはいえ、私がルートを決めるのではなく『親父の会社を継ぎたい』と本人に言わせたい。これもひとつの戦いですね(笑)」
槙岡「息子は今年10歳ですが、今のところは子どもに継がせたいとは思っていません。自分の夢を見つけて走っていってほしいです。私はそれができなくてこうして帰って来ているので。あと、息子には私と同じ思いをさせたくないというのも感じています」
山下「それもわかります(笑)」
槙岡「つらい思いをすることが多いかもしれないですね」
山下「業界の未来は明るいと思うのですが、経営者は24時間常に仕事のことを考えてしまう」
澤「私は子どもがいませんが、血縁で会社を継ぐことだけが全てではないかなと思っています。先代のころと比べて今は会社を守っていくだけでも大変になっていますし、次世代のことを想像すると、より環境は厳しいと思います。将来、子どもが『この会社を継ぎたい』と思ってもらえたらいいですけど、大変なことの方が多そうで。商売としては続けられると思いますが、どうやって人を雇うのかという問題に始まり、経営者や管理層の方がかなりしんどい思いをする時代になってきそうです」
――従業員が経営者候補になる可能性はありますか。
澤「意欲的な人がいれば、もちろんあります。実際に、一般社員が役員になって株式を保有しており、柔軟に対応できる準備はある程度進めています。でも、今の時代は若い子ほど管理職に対してすごく抵抗感があるのではないでしょうか。仕事はとても真面目にやってくれているけれど……。若い世代にもリーダーシップがある方もいますが、そういう人を雇っていくのもなかなか難しいです」
斉藤「うちは息子が2人いて、上の子が小学3年生。継ぐ・継がないの問題ですが、息子には大富豪になってもらって気楽な老後を過ごしたいという夢があります(一同、笑)。この夢を叶えるには、おそらくうちの会社では厳しい。真面目な話、北海道の20―30年後を想像した時に地方都市の今後の形がもうなんとなく見えてしまっているという感覚がある。当社は1918年の創業で、いわゆる100年企業ですが、今の時代、長ければいいのかと切実に思います。それを考えるとなかなか夜も眠れず……、昨日は8時間寝ましたが(笑)」
――次は各地区の課題をお尋ねします。まずは不適正ヤードについて、ヤード運営規制条例制定が進展している関東からお願いします。
 山下「ひとくちに規制条例といっても自治体によって届出制や許可制と内容が全然違います。特に千葉県は非常に厳しい規制でヤード運営の許可を取らないという決断をする業者も多いと聞きます。実際に許可を取得した業者に話を聞いたところ『ただ淡々と規制を守っていれば許可を取得するのは難しくない』とも言っていました。適正ヤードという『ライセンス』を取ることで襟を正すことができますし、時代のひとつの転換点というか、そう捉えている業者さんも多いのではないかな。先人が行政に不適正な業者への規制を働きかけてきた経緯もありますから」
山下「ひとくちに規制条例といっても自治体によって届出制や許可制と内容が全然違います。特に千葉県は非常に厳しい規制でヤード運営の許可を取らないという決断をする業者も多いと聞きます。実際に許可を取得した業者に話を聞いたところ『ただ淡々と規制を守っていれば許可を取得するのは難しくない』とも言っていました。適正ヤードという『ライセンス』を取ることで襟を正すことができますし、時代のひとつの転換点というか、そう捉えている業者さんも多いのではないかな。先人が行政に不適正な業者への規制を働きかけてきた経緯もありますから」
――規制条例に思うところは。
山下「要は『ライセンス』を取得するっていうことなんですが、むしろ電炉メーカーなどの需要家に対して不適正ヤードから原料を買わないなどの毅然とした対応を取ってほしいです」
――関西はいかがでしょうか。
 澤「錆年会との合同勉強会を通じて申請に厳しいハードルがあることや、みなさんが苦労されていることを肌で感じました。ただ、関西は規制条例がまだないので、なんとも言えません。不適正ヤードの拡大による実害もあまりなく、条例制定の必要性が今のところ感じられないという雰囲気です。ただ、幹事会では話題に出ており条例が全国的に広がる可能性はあるだろうなという緊張感は持っています。客観的に見て、条例は業者にとってデメリットの方が多そうでメリットが見えてこない。置き場の整備とか、そのために業者が負担を強いられるコストのほうが気になります。山下さんが『電炉メーカーは不適正ヤードと認定された業者から原料を買わないでほしい』とおっしゃいましたが、たとえばスクラップの発生工場や解体業者がライセンスを持っていないスクラップ業者に母材を売らないという流れになることはおそらくない。特に関西は価格勝負という風潮がある。発生工場や解体業者が率先して適正なスクラップ業者を選ぶのであれば条例が制定される意味があるかもしれませんが、今の状態で全国的に条例が広がるのは好ましくないです」
澤「錆年会との合同勉強会を通じて申請に厳しいハードルがあることや、みなさんが苦労されていることを肌で感じました。ただ、関西は規制条例がまだないので、なんとも言えません。不適正ヤードの拡大による実害もあまりなく、条例制定の必要性が今のところ感じられないという雰囲気です。ただ、幹事会では話題に出ており条例が全国的に広がる可能性はあるだろうなという緊張感は持っています。客観的に見て、条例は業者にとってデメリットの方が多そうでメリットが見えてこない。置き場の整備とか、そのために業者が負担を強いられるコストのほうが気になります。山下さんが『電炉メーカーは不適正ヤードと認定された業者から原料を買わないでほしい』とおっしゃいましたが、たとえばスクラップの発生工場や解体業者がライセンスを持っていないスクラップ業者に母材を売らないという流れになることはおそらくない。特に関西は価格勝負という風潮がある。発生工場や解体業者が率先して適正なスクラップ業者を選ぶのであれば条例が制定される意味があるかもしれませんが、今の状態で全国的に条例が広がるのは好ましくないです」
――中四国はいかがでしょうか。
 槙岡「既存の業者への影響があるため、適正ヤード推進委員会の活動は活発化しています。広島の部会では、県警との情報連絡会を四半期に1回くらいやろうという動きはあります」
槙岡「既存の業者への影響があるため、適正ヤード推進委員会の活動は活発化しています。広島の部会では、県警との情報連絡会を四半期に1回くらいやろうという動きはあります」
――北海道は不適正ヤードが少ないイメージですが。
斉藤「条例云々の話は出ていないと聞いています。他県は、加工設備や重機の騒音に対する住民運動から行政が動いたところが多いと思うのですが、北海道は土地が広大でヤードも点在しているので近隣からのクレームは警察にもほとんどきていないようです。だから関東の自治体にならって規制条例を制定しても、あまり意味がない。もし条例ができれば既存業者はお金をかけて設備を整えるだろうけど、不適正ヤードは違うところへ移るだけでしょう。もっと踏み込んだ政策をしないと私たちが本当に退場させたい業者に届く規制は難しいんじゃないかな。土地や建物の取得方法や税制であったり。たとえば日本国籍を持つヤード運営者を優遇するとか。そういう国籍のところまで踏み込む必要があるように感じます」
――「国籍のところまで踏み込む」という点について詳しく伺えますか。
 斉藤「北海道は鉄資源やスクラップに限らず土地を海外の人に買われています。どういった方法で買っているかはともかく事実として買われている。外国人が円安の影響でどんどん不動産を買って荒らして、日本の利益にならない状態になってしまうというニュースも報じられています。スクラップに話を戻すと、年間数100万トンが輸出されていますが全てを国内循環すべきというつもりはないです。過度な規制は自由競争に反することも理解しています。ただ、国内で発生した資源物を国の政策の下に守らないと土地のようにどんどん資本があるところに流れかねない。某地のように地元の人が働かなくなって荒れた状態になってしまう。これと同じことが鉄リサイクル業にも起こることを恐れています。われわれの業界団体だけでの話ではなくなってきているのかな、という思いもあり先ほどのような発言をしました」
斉藤「北海道は鉄資源やスクラップに限らず土地を海外の人に買われています。どういった方法で買っているかはともかく事実として買われている。外国人が円安の影響でどんどん不動産を買って荒らして、日本の利益にならない状態になってしまうというニュースも報じられています。スクラップに話を戻すと、年間数100万トンが輸出されていますが全てを国内循環すべきというつもりはないです。過度な規制は自由競争に反することも理解しています。ただ、国内で発生した資源物を国の政策の下に守らないと土地のようにどんどん資本があるところに流れかねない。某地のように地元の人が働かなくなって荒れた状態になってしまう。これと同じことが鉄リサイクル業にも起こることを恐れています。われわれの業界団体だけでの話ではなくなってきているのかな、という思いもあり先ほどのような発言をしました」
槙岡「私は国籍は特に気にしていないです。それよりも同じ土俵にいるのかが問題です。適正・不適正という言い方を借りるならば、たとえ日本の業者でも運営方法が不適正ならば適正ヤードに変える必要があります。国籍ではなく同じ土俵で戦える環境を整えた上で競争するべきです」
山下「槙岡さんの意見に同感です。戦略として日本籍以外のヤード運営者と協業することが吉ならば、それはそれでいい。同じ土俵に立ってはじめて自社の強みを生かすとか違う強さをつけるといった正しい競争原理が働く」
澤「槙岡さんと山下さんの意見とおおむね変わらないです。実際のところ納税面ではわれわれと同じ土俵に立ってないのではと思うところはある。競合他社として末恐ろしいが、一方で商売相手として外資系業者との取引が必要な選択肢のひとつにもなり得る。業界の緊張感を得るためには必要な要素ではないかな。この業界がどういうふうに整理されていくのがベストなのかの判断は難しいところです」
――ほかに各地区が抱えている問題はありますか。
澤「関西は価格競争でしょうか。特に解体案件は整理されてないというか、単体では採算が合わない様な商材でダスト引きもできない様な案件もある。解体だけやっているスクラップ業者は今後どうなるのだろうと正直感じるところがあります」
斉藤「北海道は会員が毎年1社ずつぐらい減っています。支部長と『これ以上減らすわけにはいかないよね』と話しており、支部長中心に声がけしているのですが、なかなか会員増には繋がっていないのが現状です」
槙岡「中四国は人手不足かな。若手社員がいない企業も増えており、例えば私が『青年部会にメンバーを出してください』と他社にお願いしても『うちに45歳以下はおらんわ』と返ってくる。こういう企業が何社もいる。若手採用のための広報の重要性を感じている会社が多いと思います」
――広報活動や採用活動について皆さんはどのように対策していますか。
山下「当社は年間休日を120日に増やし、ホームページも刷新しました。実際に若手も採用できました。同業者や似たような業種で働いていた方からすると選ばれやすい環境にはなったかな。ただ、都市部だとどうしても賃金が採用活動に影響してくる。例えば倉庫管理や運送の仕事で月給35万円のところには勝てない。福利厚生を打ち出ししても、やっと同レベルになったくらいだと思います」
――初任給はいくらに設定されていますか。
山下「当社は中途採用がほとんどですが、年齢問わず23万―24万円、残業代や諸手当を付けて額面で30万いかないくらい」
澤「当社は年間休日を一昨年くらいに120日に増やし、土曜日に出てもらう場合は休日出勤手当も出している。まわりの業者の給与体系も確認して、その業種の中でトップと同等レベル以上の給与を出せるようにしています。効果があるかわからないですが、社員旅行を年に1回実施し、クリスマスにはケーキを配るなど、ただ働くだけじゃなくてプラスαの楽しみを提供できるようには心がけています。でも、最近は本当に何が社員にとっていいかわからなくなってます。飲み会や社員旅行がない会社を選ぶ人もいるし、少しでもこの業界で楽しんでもらえるようにはしたいと思っているのですが」
斉藤「うちは中途がメインなので決まった初任給は設定できなくて年齢や保有資格によって変わります。本当は定期採用をして人員を整えていきたいですが、人手が不足してはじめて採用活動をするという流れになる現状がありまして、なかなか理想と現実がうまくマッチしていない状態です」
――槙岡さんは何か具体的な広報・採用活動をされていますか。
槙岡「当社は広報に力を入れています。社員は約290人いますが、そのなかで若手を中心とした9人のメンバーを広報のプロジェクトチームに任命し、インスタグラムやブログサイトのnoteを使って発信しています。採用に特化というよりは企業としての広報です。『毎月1万円の手当をつけるから兼業してくれないか』と応募をかけたら集まってくれました。昨年からプレスリリース配信サービスのPR TIMESにも社の取り組みを投稿するようにしており、それがきっかけで産業新聞や地元新聞にも当社の話題を取り上げていただきました。また、当社で働いているメンバーにもっと誇りを持ってもらいたいという思いから社内報にも力を入れ、年2回の発行から年6回に増やしています」
――先ほど山下さんが「業界の未来は明るい」と話されましたね。
槙岡「サーキュラーエコノミーやカーボンニュートラルの考え方で言うならば鉄リサイクル業界は本当に優等生だと思います。確実に発展していくし社会に必要不可欠な存在。業界規模として大きくなっていくだろうと思っています。ただ、日本の鉄スクラップの発生が極端に減っていくとも考えられます。そうなった時に国内だけで供給ソースが足りるかを踏まえると、やはり海外に目を向けていかなければいけない。20年後どころか5―10年後には鉄スクラップを輸入しなければいけないような状況になる可能性もある。その時に今のスクラップ業者各社が海外に出て戦えるかと考えると、今の実力ではなかなか厳しいのではないでしょうか。ですから、同業者と協業をしたり商社の力を借りたり、さまざまなやり方で対応をしていく必要がある。繰り返しになりますが、地方の人手不足の問題は深刻です。特に鉄リサイクル業界は人気の業界とはいえないので。条件を向上させていく必要があります。そのためにはもっと利益率を上げて、有り体にいえば稼げる業界にならないと未来は開けません。だから業界全体が何らかの変化を遂げなければいけないのではないでしょうか。経営者として変化に対する覚悟を持って貫き通すことを大事にしています。また、これだけ物価が上がると社長の私ですらしんどい。従業員の皆さんはそれ以上にしんどいでしょうから、賃上げは経営者としての責任だと感じています。そういう意味で責任は重たい」
――鉄スクラップの輸入の可能性を含めて20—30年後の業界の未来予想図について。
斉藤「30年後は70歳か……」
槙岡「もう引退していたいですね(笑)」
澤「扶和メタルが東京ベイの運営を開始する際に最終的に輸入に対応できることを前提とされていたと聞いたことがあります。東京製鉄のサテライトヤード展開などを踏まえても輸出が今後減少する可能性は高く、将来的には各メーカーも輸入の展望はあるかもしれません。20―30年後の業界はどうなるかというお尋ねですが、私自身はあまり先の未来のことをあまり考えないようにしています。例えば10年前、鉄スクラップがこんな値段になっているなんて、想像もつかなかったじゃないですか。20年先はこうなっているからこうしようって思っても、2―3年後に大幅に修正しないといけない、私はよく従業員にこういう話をします。『ぼくは常に2-3年後に100%の状態で会社が回るように考えて動いている。だから従業員の皆には1カ月後くらいのことを任せたいので常に考えて動いてほしい』と。それくらいの範囲なら予測は可能だから。2-3年先の未来でいうと、輸入どうこうというよりは高炉メーカーさんや鋳物メーカーさんの動きの方に注目しています」
山下「必要なところに必要なものを届ける手段を今準備しておく必要がある、ということは言えますね。槙岡さんがいる中四国は高炉メーカーの電炉転換が進むことで今後、鉄スクラップの不足地域になると思いますが、一方で北海道や関東は余剰地区です。日本全体でオープンに原料を回していければいいのではないでしょうか」
斉藤「いまAIを使った鉄スクラップ検収や重機の遠隔操作が取り沙汰されていますが、スクラップ業のいいところのひとつに『誰でもできる』という点があります。もちろん資格が必要な部分はありますが。でも、たとえばその先進技術がないと業として成り立たないようになると、仕事ができにくくなる懸念があります。遠隔操作が可能な重機を例に挙げてみると、小さいスクラップ業者でも導入できるような価格帯ならいいですが、そうならない可能性の方が高い。すると業界のなかで大きい会社と小さい会社の差が広がってしまって業界としていびつになってしまう。業界全体と考えるとよろしくないとも思います。『いい設備や技術を、値段を抑えて導入したい』だなんて甘い発想だといわれるかもわかりませんけれど」
山下「重機は、地域や企業のニーズやコストによって注目度が変わると思います。私としてはどちらかというと販売の方を変えたいです。中央集権型じゃなくて限りあるパイをみんなで享受するような枠組みがあるといいですが。実は今日、皆さんに提案したかったことがあります。以前、錆年会の有志企業が集まって東京製鉄の田原工場向けに内航船で鉄スクラップを出荷したのですが、多くの学びがありました」
槙岡「あれはすごかったですね。正直なところ、これはトラブルになるだろうと思って見てました。実際やってみてどうでしたか」
山下「採算の読みが甘く、結果としては赤字でしたが、トラブルというほどのことはなく、それ以上に学びが多かった。有志で取り組んだのですが、当社が窓口になって電炉メーカーの声を直に聞くことができました。今後、鉄リサイクル業界が世界と戦う上で、まず日本の業者が一体にならなきゃいけないと思います。中四国、具体的には倉敷周辺が鉄スクラップの不足地域になる可能性があり、理想を言うならこのエリアで消費される鉄スクラップは国内で発生したものであるべきです。先ほど申し上げた提案につながるのですが、いま流行りの2港積みや3港積みを、この青年部のメンバーを中心に企画してみませんか? たとえば北海道から出船して関東、関西の港に寄港し、最終的に中四国に運ぶ。現実的には難しいかも知れませんし、課題があるのは承知の上ですが、その地域がどういう特性を持って、どういう思いでやっているかを知るためにも、われわれがたすきをつないで鉄スクラップを運ぶようなことができればと思っています」
槙岡「先ほどの東鉄田原向けの内航船のこともそうですが、青年部の活動として実際の仕事につなげることは重要だと思います。中四国支部では勉強会や見学会などにとどまっていたのが実情だったので。実際に協働して内航船の船積みを実現したことは本当に尊敬します。業者同士の信頼がなければできないことです。だから、そういったことがもし全体で出来るなら、とても面白い取り組みです」
澤「ちょっとずれるかもしれませんが、大阪ですと解体由来のスクラップをまったく扱わない鉄スクラップ加工業者などがいまして、商材ごとに業者が多様化している流れがあります。私は以前からHSはHSを扱っている会社だけで話し合いをして船積みができたら面白いと思っていました。新断は新断を扱う業者だけ、ヘビーはヘビーだけ、というように。たとえば鉄鋼製品だと厚板だけの組合がありますが、スクラップはひとくくりになっています。これから貴重な国産資源として扱われていく中で商材ごとに組合みたいなのがあっても面白いんじゃないかな。他地域との連携や融通の話が出れば、山下さんが提案された共同でひとつの船に鉄スクラップを積んで、といった話もできます。こういう新しいことをすると談合しているとの懸念も出てきそうですが……」
山下「それも含めて学びですよ(笑)」
斉藤「北海道は余剰地域で発生した母材の6割ぐらいが道外に出ている状態ですから、2―3港積みを工業会内部でできるのは、とても魅力的です。あとは同じ地区内で設備や重機の共同購入とかもできたらいいですね」
山下「槙岡さんのおっしゃるように、稼ぐことが一番の近道だと思います。賃上げという形で経営者の責任を果たす意味でも、鉄スクラップ販売の未来を自分たちで、今なら作れるんじゃないでしょうか」
――最後に、10年後のご自身へのメッセージを。
槙岡「この会社、そして自分自身も生き延びていてください(笑)」
斉藤「しっかりと企業の血肉として頑張ってほしい」
山下「世界と戦いたいので社名を『ヤマシタグローバルメタル』とかに改名しておいてほしいです(笑)」
澤「私はこの業界に入って小さな失敗はたくさんしましたが、大きな後悔は何ひとつしていないつもりです。その考えのままやっていてほしいです」
【参加者略歴】
▽関東支部錆年会・山下耕平会長(やました・こうへい、ヤマシタ社長)=2008年学習院大法卒、大同興業入社、10年ヤマシタ入社。厚木工場長、寄居工場長、取締役を歴任。21年から現職。86年1月8日生まれ、東京都出身。
▽関西支部青年交流会・澤将也会長(さわ・まさや、信和鋼材社長)=09年近大産業理工卒、パッケージ業界に就職後、11年信和入社。16年取締役、23年グループ会社信和鋼材の社長を兼任。87年2月24日生まれ、大阪府出身。
▽北海道支部青年部・斉藤孝治郎会長(さいとう・こうじろう、斉藤商店社長)=10年早大人間科学卒、産業振興入社。総務、人事などを経験し、19年斉藤商店入社。22年から現職。86年9月14日生まれ、北海道出身。
▽中四国支部青年部会・槙岡達也部会長(まきおか・たつや、こっこー社長)=08年武蔵大経卒、毎日コミュニケーションズ(現マイナビ)入社。10年日新総合建材(現:日鉄鋼板)入社。15年こっこー入社、16年常務執行役員・生活環境事業部長兼鉄鋼建材営業部長、取締役常務執行役員、17年より現職。85年6月6日生まれ、広島県出身。

――自己紹介と、各会の活動状況をお聞かせください。まずは関東支部から。
 山下「錆年会の第3代会長の山下です。当会を設立して7年がたち、これまでの期間で同業者間の信頼関係の構築や各社の強みを共有できたのではないかと感じています。最近はスクラップユーザーの声を聞きたいという声を受けて、千代田鋼鉄工業さん(以下、敬称略)や東京製鉄などの電炉メーカーをお呼びしてご講演いただいたり、当会の有志で東京製鉄の田原工場向けに鉄スクラップを内航船で出荷したり、一歩踏み込んだチャレンジをしています。本年度は海外の知識を深めるためにコンテナ輸送の勉強会や韓国の視察を検討しています」
山下「錆年会の第3代会長の山下です。当会を設立して7年がたち、これまでの期間で同業者間の信頼関係の構築や各社の強みを共有できたのではないかと感じています。最近はスクラップユーザーの声を聞きたいという声を受けて、千代田鋼鉄工業さん(以下、敬称略)や東京製鉄などの電炉メーカーをお呼びしてご講演いただいたり、当会の有志で東京製鉄の田原工場向けに鉄スクラップを内航船で出荷したり、一歩踏み込んだチャレンジをしています。本年度は海外の知識を深めるためにコンテナ輸送の勉強会や韓国の視察を検討しています」 澤「関西支部青年交流会の澤です。6代目の会長になります。関西青年交流会は15年の歴史がありコロナ禍は活動が途絶えていたのですが、昨年の就任以降、自分が青年交流会で得た経験を若手に体験してもらおうと思い視察や研修などを再開しました。昨年11月には姫路のヤマトスチールとマキウラ鋼業、茨木金属商会の工場を見学させていただき、今年3月は錆年会との合同勉強会を企画して関東に出向き、扶和メタル東京ベイやナンセイスチールの千葉のヤードを見学させてもらいました。先月は津田聰一朗執行役員をはじめ東京製鉄の皆様を講師に招いて講習会を実施し、来年3月には海外視察を計画しています」
澤「関西支部青年交流会の澤です。6代目の会長になります。関西青年交流会は15年の歴史がありコロナ禍は活動が途絶えていたのですが、昨年の就任以降、自分が青年交流会で得た経験を若手に体験してもらおうと思い視察や研修などを再開しました。昨年11月には姫路のヤマトスチールとマキウラ鋼業、茨木金属商会の工場を見学させていただき、今年3月は錆年会との合同勉強会を企画して関東に出向き、扶和メタル東京ベイやナンセイスチールの千葉のヤードを見学させてもらいました。先月は津田聰一朗執行役員をはじめ東京製鉄の皆様を講師に招いて講習会を実施し、来年3月には海外視察を計画しています」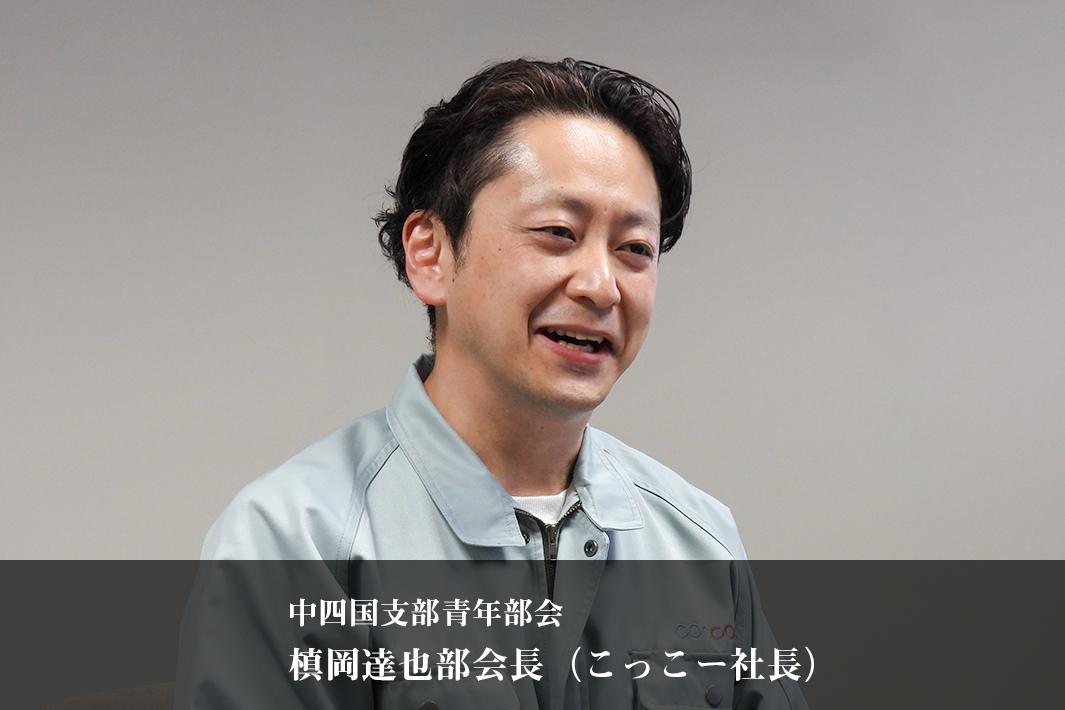 槙岡「中四国支部の槙岡です。この座談会にいらっしゃる方は、これまで当社に来ていただいたり私からお伺いしたり、そういったお付き合いのある方々ですが、改めて自己紹介します。当会は21年に発足し、私が初代会長です。前支部長の丸本陽章・丸本鋼材社長からの強いご指名を受けまして、そういう運びとなりました。同時に親会は平林実支部長(平林金属社長)が就任され、平林支部長の指導のもと活動しています。見事に諸先輩方の『策略』にはめられて今この場にいるのですが、お世話になった方々のご子息が当会に入られていることもあり『親から受けた恩は息子に返さないかん』と思っている次第です(笑)。とはいえ、この活動を通じて、たくさんの新たな経験と出会いがあったので、お二方には感謝しています。活動実績としては、今年2月に北海道のマテックや鈴木商会の工場見学を行いました。北海道支部の全国大会実行委員会の方々とも交流でき充実した3日間でした。ほかには、業界が抱える人手不足の課題を踏まえて広報に関する知識をつけようと、SNSで活躍中の『鉄くず兄さん』こと藤岡寛大・イチイ産業社長に話を聞く場を設けたり、錦麒産業の社長をお招きしたパネルディスカッションをしたりなど、青年部だからこそできる活動を行っています。年明けにベトナムを視察したいと検討しており、目下、とある商社さんと相談中です」
槙岡「中四国支部の槙岡です。この座談会にいらっしゃる方は、これまで当社に来ていただいたり私からお伺いしたり、そういったお付き合いのある方々ですが、改めて自己紹介します。当会は21年に発足し、私が初代会長です。前支部長の丸本陽章・丸本鋼材社長からの強いご指名を受けまして、そういう運びとなりました。同時に親会は平林実支部長(平林金属社長)が就任され、平林支部長の指導のもと活動しています。見事に諸先輩方の『策略』にはめられて今この場にいるのですが、お世話になった方々のご子息が当会に入られていることもあり『親から受けた恩は息子に返さないかん』と思っている次第です(笑)。とはいえ、この活動を通じて、たくさんの新たな経験と出会いがあったので、お二方には感謝しています。活動実績としては、今年2月に北海道のマテックや鈴木商会の工場見学を行いました。北海道支部の全国大会実行委員会の方々とも交流でき充実した3日間でした。ほかには、業界が抱える人手不足の課題を踏まえて広報に関する知識をつけようと、SNSで活躍中の『鉄くず兄さん』こと藤岡寛大・イチイ産業社長に話を聞く場を設けたり、錦麒産業の社長をお招きしたパネルディスカッションをしたりなど、青年部だからこそできる活動を行っています。年明けにベトナムを視察したいと検討しており、目下、とある商社さんと相談中です」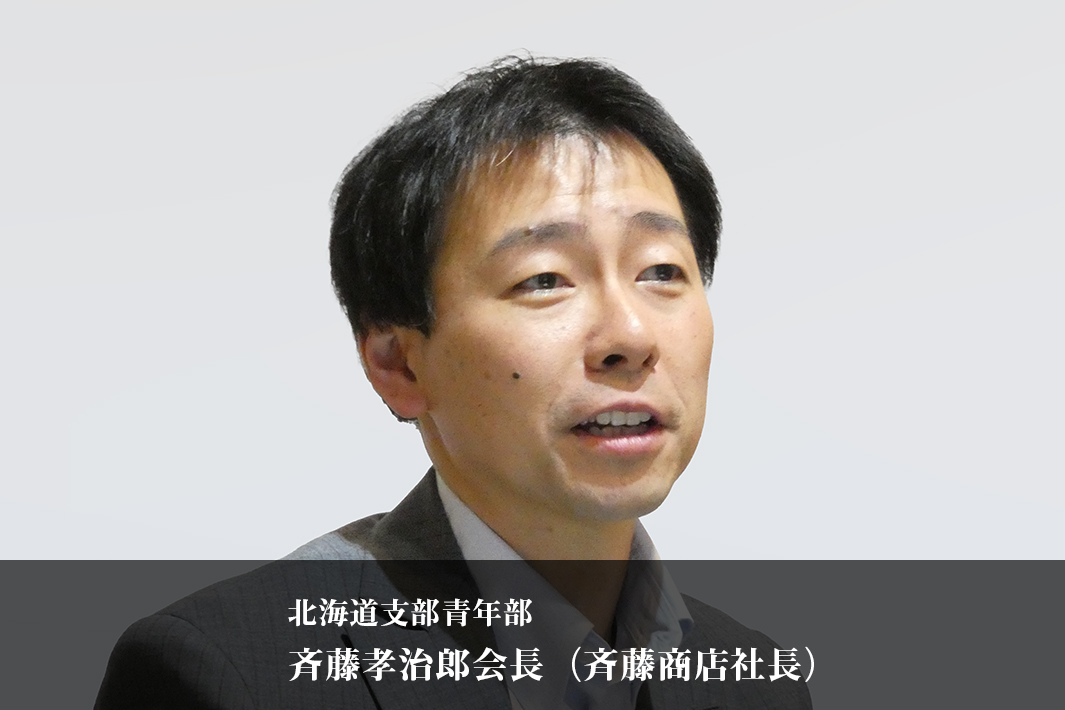 斉藤「北海道支部青年部長の斉藤商店、斉藤孝治郎です。北海道の東にある北見市でスクラップ屋を営んでおります。私が部長になったのは2023年。19年に工業会の全国大会が関西で行われた際、前日に青年部のパネルディスカッションがあり、それをきっかけに北海道も青年部を作ろうという機運が高まりました。コロナ禍の数年は活動が停滞していましたが23年から再始動し、中四国・中部・関東の各支部の方々と交流の場を設けました。今後も、道内の企業訪問や他支部との交流などの活動は続けていきたいですが、今のところは北海道支部主管の全国大会の総仕上げに尽力中という感じです(笑)」
斉藤「北海道支部青年部長の斉藤商店、斉藤孝治郎です。北海道の東にある北見市でスクラップ屋を営んでおります。私が部長になったのは2023年。19年に工業会の全国大会が関西で行われた際、前日に青年部のパネルディスカッションがあり、それをきっかけに北海道も青年部を作ろうという機運が高まりました。コロナ禍の数年は活動が停滞していましたが23年から再始動し、中四国・中部・関東の各支部の方々と交流の場を設けました。今後も、道内の企業訪問や他支部との交流などの活動は続けていきたいですが、今のところは北海道支部主管の全国大会の総仕上げに尽力中という感じです(笑)」――親会との関係はいかがですか。
槙岡「中四国はしがらみなどは全く無いです。支部長の平林さんに『わしが責任を持ってやるから』とおっしゃっていただいているので、ありがたいことに自由にやらせてもらっています。これまで青年部の活動に対して『ご意見』を寄せられることもあったらしいのですが、平林さんから『わしのところで止めておくから』と言っていただいています。もちろん活動についてはいろいろな面から考えますが、現状ではやりたいことが実施できています」

2025年3月、東西の若手会は合同で扶和メタル東京ベイ(千葉県袖ケ浦市)などを視察した
澤「先ほど話した関東視察に関連するのですが、私が以前、錆年会に所属していたという経緯があり、関東の取り組み方を関西の会員にも是非知ってほしいという気持ちが強くありました。やりたいことは沢山あり、関東視察を実現したいという話も以前からしていたのですが、ゼロから業界の視察を企画したことがなかったのでどこまでやっていいかよくわかりませんでした。そんな折、業界の重鎮から『青年交流会じゃないとできないことやった方がいいよ』と後押ししていただいた。若手会としていろんな形を見せていけたらと思っています」
山下「私は実施後に反応を見ています(笑)。1年間活動して途中くらいから『錆年会の活動を関東支部の上の世代の方々が応援してくれている』という雰囲気を感じるようになりました。会費を年間40万円から80万円に倍増していただきたいということも理解してくださいました。谷平竜幸関東支部長をはじめとする方々に背中を押してもらい、『良い活動をしているね』というお言葉をいただいています」

2025年2月、中四国の若手会が北海道を訪問。マテックのヤードを見学した
斉藤「北海道は、スクラップ業者を取り巻く環境が他地区と少し違うところがあります。会員企業が広範囲に点在しているので、気軽に『数か月に1回集まろう』というのが難しく、どうしても前もって『何か月後のこの時に情報交換しましょう』という感じになってしまいます。北海道には大手業者が2社ありますが、その他は中小規模の会社が多い地区です。組織の力や会社のバックアップという面で他地区より恩恵を受け難い事情もあります。今のところ尖った企画を充分にできていないという反省がありますが、みなさん集まったら集まったで楽しく仕事の話をして交流できているのも事実です。まずはこのあたりを積み重ねていくことも大事だと思っています」
――海外視察の検討の話が出ましたが、今、注目している国はどこでしょうか。
澤「東南アジアで特にベトナムですかね」
山下「インドやトルコも気になります。関東は鉄スクラップの余剰地域なので、今後は大型船での船積みが輸出のトレンドになりそう。現実的に行けるかっていうと難しいですが錆年会で行けるなら面白いと思います」
澤「バングラデシュにも関心はありますが、会の事業として実施するにはハードルが高い。会員全員を安全に日本に帰すという責任を伴いますから。関西は実務の多い若手の方が多いので、必然的に自社の仕事を止めていられる期間も短くなる。休日を絡めて予定を組んで、かつ行き先の国の鉄鋼メーカーが稼働している日程で、となると長期視察は難しいかもしれないです」
――みなさんは商社など他の企業で働かれた経験はありますか。
澤「就職活動をして鉄鋼業とまったく関係ない包装会社で2年ほど働きました。その後、信和に転職し出向するかたちで三井物産メタルズ(現エムエム建材)にもお世話になりました」
山下「私は鉄鋼関係の仕事をしたいと思って就職活動をして大同特殊鋼グループの大同興業で働きました」
斉藤「産業振興で9年ほど。家業を特段意識せず普通に就活をして入社しました。結局はこうなっちゃったのですが(笑)」
槙岡「私は大卒後、毎日コミュニケーションズ (現:マイナビ)に入り、その後は日新製鋼(現:日本製鉄)の子会社の日新総合建材(現:日鉄鋼板)で約5年。その後、当社に入りました」
――企業風土の違いは感じますか。
斉藤「産業振興は鉄リサイクル業と近い会社ですが、会社の雰囲気や規模感は本当に真逆でした。複数の事業部制で運営されており従業員も1400人近くいます。コンプライアンスや組織運営などは自社に落とし込みにくいですが、安全面の取り組みなどは吸収しようと心がけています」
澤「スクラップ業界は同業者とコミュニケーションを積極的に取りますよね。これはかなり珍しいと思いました。前職の包装業界は同業団体がなかったですし、他の業者と仲良くしていると『ヘッドハンティングされるんちゃうか』とか『なんか企んでいるんちゃうか』とか、そういうことが噂されかねない雰囲気でした。スクラップ業界のようにコミュニケーションをとることでお互いにプラスになれる関係はいいと思います。余談ですが、パッケージ会社は包装紙や化粧箱などを作ってお客さんに納品した後、色のイメージが違うだけでひとつのロットが全て産業廃棄物になってしまいます。でも、鉄リサイクルの仕事は違いますよね。出荷して仮に『ごみが入ってる』と返品されても、そのごみさえ取り除けば再販できるので損失のリスクがかなり小さい。次世代につなぎやすいというか、強い会社になりやすい事業だと思いました」
山下「私は大同興業に入って1年目から大同特殊鋼の知多工場の生産管理室に配属されました。現場と営業の狭間のような立ち位置です。当時は企業という縦割りの中のひとつの役割を担当するという感覚でしたが、家業に入った時には『こんなにやり甲斐があるんだ』と思いました。中小企業だから、私の判断で会社が変わるわけです。一人一人の成長が会社全体の成長に直につながるともいえる。挑戦し甲斐のある業界だと思います」
槙岡「スクラップ業界は、大変縄張り意識の強い業界だなと感じます。ポジティブに言うならば役割分担がしっかり決まっている。マイナビにいたころは、同業者と契約を取った・取られたの戦いでした。競合と業界トップを争っていたので上司からは『競合から切り替える契約を取ってくるまで帰ってくるな』とよく言われました。それに比べるとリサイクル業界は皆で共存していくようなやり方ができているように思います。加えて、トレーサビリティ(原料から製品に至るまでの追跡可能性)が担保されにくい業界とも言える。今は、なかなかそういうわけにはいかないですが、昔はスクラップをプレスして中に不純物やごみを混ぜときゃええわ、といったケースもあったと聞きます。これが正解だと教えてくれる教科書を作るのが難しい業界だと思います」
――経営者候補が商社やメーカーで働くメリットは何だと思われますか。
澤「客観的にスクラップの仕事を体験できる点ではないでしょうか。私は商社さんでの研修前に信和で少し現場仕事をしたのですが、みんないきなり来た社長の息子が何もできないから扱いに困ったと思います。研修期間は三井物産メタルズ堺事業所(現:共英マテリアル)で現場作業を経験させて頂いたのですが、その時はいい意味でこき使ってくれましたので現場作業の実務を覚えるのには非常に恵まれた環境でした。現場のことを理解した上で会社に戻って、それでようやく自分の会社の仲間になれたという感じがしました。若い時からずっと自分の会社で一緒に仲間として成長してこられた後継者の方もいらっしゃるので、もちろんそれはそれで強いと思いますが」
斉藤「経営者候補は自分の子どもでも従業員でもいいですが、学校を卒業してすぐ家業に入るよりは、業種を問わずどこか違うところで経験してほしいです。何かしらの人生の経験になりますし」
山下「メリットはあると思います。私自身、外でいろいろと経験して今でもその縁で仕事をいただいています。人脈も築けますし。『可愛い子には旅をさせよ』というように息子には外で修行してほしいですね。星空を見上げながら夜中まで仕事したことも今となってはいい経験。自分の会社だとどうしても息子に甘くなりそうですから」
――息子さんの話が出ましたが、皆さんは次世代の経営者候補はいらっしゃいますか。
山下「息子は今11歳ですが、将来的には継いでほしいです。息子に選んでもらえる会社でありたいという思いもあり、業界の嫌な部分や会社の直すべきところを少しずつ改善してきました。とはいえ、私がルートを決めるのではなく『親父の会社を継ぎたい』と本人に言わせたい。これもひとつの戦いですね(笑)」
槙岡「息子は今年10歳ですが、今のところは子どもに継がせたいとは思っていません。自分の夢を見つけて走っていってほしいです。私はそれができなくてこうして帰って来ているので。あと、息子には私と同じ思いをさせたくないというのも感じています」
山下「それもわかります(笑)」
槙岡「つらい思いをすることが多いかもしれないですね」
山下「業界の未来は明るいと思うのですが、経営者は24時間常に仕事のことを考えてしまう」
澤「私は子どもがいませんが、血縁で会社を継ぐことだけが全てではないかなと思っています。先代のころと比べて今は会社を守っていくだけでも大変になっていますし、次世代のことを想像すると、より環境は厳しいと思います。将来、子どもが『この会社を継ぎたい』と思ってもらえたらいいですけど、大変なことの方が多そうで。商売としては続けられると思いますが、どうやって人を雇うのかという問題に始まり、経営者や管理層の方がかなりしんどい思いをする時代になってきそうです」
――従業員が経営者候補になる可能性はありますか。
澤「意欲的な人がいれば、もちろんあります。実際に、一般社員が役員になって株式を保有しており、柔軟に対応できる準備はある程度進めています。でも、今の時代は若い子ほど管理職に対してすごく抵抗感があるのではないでしょうか。仕事はとても真面目にやってくれているけれど……。若い世代にもリーダーシップがある方もいますが、そういう人を雇っていくのもなかなか難しいです」
斉藤「うちは息子が2人いて、上の子が小学3年生。継ぐ・継がないの問題ですが、息子には大富豪になってもらって気楽な老後を過ごしたいという夢があります(一同、笑)。この夢を叶えるには、おそらくうちの会社では厳しい。真面目な話、北海道の20―30年後を想像した時に地方都市の今後の形がもうなんとなく見えてしまっているという感覚がある。当社は1918年の創業で、いわゆる100年企業ですが、今の時代、長ければいいのかと切実に思います。それを考えるとなかなか夜も眠れず……、昨日は8時間寝ましたが(笑)」
――次は各地区の課題をお尋ねします。まずは不適正ヤードについて、ヤード運営規制条例制定が進展している関東からお願いします。
 山下「ひとくちに規制条例といっても自治体によって届出制や許可制と内容が全然違います。特に千葉県は非常に厳しい規制でヤード運営の許可を取らないという決断をする業者も多いと聞きます。実際に許可を取得した業者に話を聞いたところ『ただ淡々と規制を守っていれば許可を取得するのは難しくない』とも言っていました。適正ヤードという『ライセンス』を取ることで襟を正すことができますし、時代のひとつの転換点というか、そう捉えている業者さんも多いのではないかな。先人が行政に不適正な業者への規制を働きかけてきた経緯もありますから」
山下「ひとくちに規制条例といっても自治体によって届出制や許可制と内容が全然違います。特に千葉県は非常に厳しい規制でヤード運営の許可を取らないという決断をする業者も多いと聞きます。実際に許可を取得した業者に話を聞いたところ『ただ淡々と規制を守っていれば許可を取得するのは難しくない』とも言っていました。適正ヤードという『ライセンス』を取ることで襟を正すことができますし、時代のひとつの転換点というか、そう捉えている業者さんも多いのではないかな。先人が行政に不適正な業者への規制を働きかけてきた経緯もありますから」――規制条例に思うところは。
山下「要は『ライセンス』を取得するっていうことなんですが、むしろ電炉メーカーなどの需要家に対して不適正ヤードから原料を買わないなどの毅然とした対応を取ってほしいです」
――関西はいかがでしょうか。
 澤「錆年会との合同勉強会を通じて申請に厳しいハードルがあることや、みなさんが苦労されていることを肌で感じました。ただ、関西は規制条例がまだないので、なんとも言えません。不適正ヤードの拡大による実害もあまりなく、条例制定の必要性が今のところ感じられないという雰囲気です。ただ、幹事会では話題に出ており条例が全国的に広がる可能性はあるだろうなという緊張感は持っています。客観的に見て、条例は業者にとってデメリットの方が多そうでメリットが見えてこない。置き場の整備とか、そのために業者が負担を強いられるコストのほうが気になります。山下さんが『電炉メーカーは不適正ヤードと認定された業者から原料を買わないでほしい』とおっしゃいましたが、たとえばスクラップの発生工場や解体業者がライセンスを持っていないスクラップ業者に母材を売らないという流れになることはおそらくない。特に関西は価格勝負という風潮がある。発生工場や解体業者が率先して適正なスクラップ業者を選ぶのであれば条例が制定される意味があるかもしれませんが、今の状態で全国的に条例が広がるのは好ましくないです」
澤「錆年会との合同勉強会を通じて申請に厳しいハードルがあることや、みなさんが苦労されていることを肌で感じました。ただ、関西は規制条例がまだないので、なんとも言えません。不適正ヤードの拡大による実害もあまりなく、条例制定の必要性が今のところ感じられないという雰囲気です。ただ、幹事会では話題に出ており条例が全国的に広がる可能性はあるだろうなという緊張感は持っています。客観的に見て、条例は業者にとってデメリットの方が多そうでメリットが見えてこない。置き場の整備とか、そのために業者が負担を強いられるコストのほうが気になります。山下さんが『電炉メーカーは不適正ヤードと認定された業者から原料を買わないでほしい』とおっしゃいましたが、たとえばスクラップの発生工場や解体業者がライセンスを持っていないスクラップ業者に母材を売らないという流れになることはおそらくない。特に関西は価格勝負という風潮がある。発生工場や解体業者が率先して適正なスクラップ業者を選ぶのであれば条例が制定される意味があるかもしれませんが、今の状態で全国的に条例が広がるのは好ましくないです」――中四国はいかがでしょうか。
 槙岡「既存の業者への影響があるため、適正ヤード推進委員会の活動は活発化しています。広島の部会では、県警との情報連絡会を四半期に1回くらいやろうという動きはあります」
槙岡「既存の業者への影響があるため、適正ヤード推進委員会の活動は活発化しています。広島の部会では、県警との情報連絡会を四半期に1回くらいやろうという動きはあります」――北海道は不適正ヤードが少ないイメージですが。
斉藤「条例云々の話は出ていないと聞いています。他県は、加工設備や重機の騒音に対する住民運動から行政が動いたところが多いと思うのですが、北海道は土地が広大でヤードも点在しているので近隣からのクレームは警察にもほとんどきていないようです。だから関東の自治体にならって規制条例を制定しても、あまり意味がない。もし条例ができれば既存業者はお金をかけて設備を整えるだろうけど、不適正ヤードは違うところへ移るだけでしょう。もっと踏み込んだ政策をしないと私たちが本当に退場させたい業者に届く規制は難しいんじゃないかな。土地や建物の取得方法や税制であったり。たとえば日本国籍を持つヤード運営者を優遇するとか。そういう国籍のところまで踏み込む必要があるように感じます」
――「国籍のところまで踏み込む」という点について詳しく伺えますか。
 斉藤「北海道は鉄資源やスクラップに限らず土地を海外の人に買われています。どういった方法で買っているかはともかく事実として買われている。外国人が円安の影響でどんどん不動産を買って荒らして、日本の利益にならない状態になってしまうというニュースも報じられています。スクラップに話を戻すと、年間数100万トンが輸出されていますが全てを国内循環すべきというつもりはないです。過度な規制は自由競争に反することも理解しています。ただ、国内で発生した資源物を国の政策の下に守らないと土地のようにどんどん資本があるところに流れかねない。某地のように地元の人が働かなくなって荒れた状態になってしまう。これと同じことが鉄リサイクル業にも起こることを恐れています。われわれの業界団体だけでの話ではなくなってきているのかな、という思いもあり先ほどのような発言をしました」
斉藤「北海道は鉄資源やスクラップに限らず土地を海外の人に買われています。どういった方法で買っているかはともかく事実として買われている。外国人が円安の影響でどんどん不動産を買って荒らして、日本の利益にならない状態になってしまうというニュースも報じられています。スクラップに話を戻すと、年間数100万トンが輸出されていますが全てを国内循環すべきというつもりはないです。過度な規制は自由競争に反することも理解しています。ただ、国内で発生した資源物を国の政策の下に守らないと土地のようにどんどん資本があるところに流れかねない。某地のように地元の人が働かなくなって荒れた状態になってしまう。これと同じことが鉄リサイクル業にも起こることを恐れています。われわれの業界団体だけでの話ではなくなってきているのかな、という思いもあり先ほどのような発言をしました」槙岡「私は国籍は特に気にしていないです。それよりも同じ土俵にいるのかが問題です。適正・不適正という言い方を借りるならば、たとえ日本の業者でも運営方法が不適正ならば適正ヤードに変える必要があります。国籍ではなく同じ土俵で戦える環境を整えた上で競争するべきです」
山下「槙岡さんの意見に同感です。戦略として日本籍以外のヤード運営者と協業することが吉ならば、それはそれでいい。同じ土俵に立ってはじめて自社の強みを生かすとか違う強さをつけるといった正しい競争原理が働く」
澤「槙岡さんと山下さんの意見とおおむね変わらないです。実際のところ納税面ではわれわれと同じ土俵に立ってないのではと思うところはある。競合他社として末恐ろしいが、一方で商売相手として外資系業者との取引が必要な選択肢のひとつにもなり得る。業界の緊張感を得るためには必要な要素ではないかな。この業界がどういうふうに整理されていくのがベストなのかの判断は難しいところです」
――ほかに各地区が抱えている問題はありますか。
澤「関西は価格競争でしょうか。特に解体案件は整理されてないというか、単体では採算が合わない様な商材でダスト引きもできない様な案件もある。解体だけやっているスクラップ業者は今後どうなるのだろうと正直感じるところがあります」
斉藤「北海道は会員が毎年1社ずつぐらい減っています。支部長と『これ以上減らすわけにはいかないよね』と話しており、支部長中心に声がけしているのですが、なかなか会員増には繋がっていないのが現状です」
槙岡「中四国は人手不足かな。若手社員がいない企業も増えており、例えば私が『青年部会にメンバーを出してください』と他社にお願いしても『うちに45歳以下はおらんわ』と返ってくる。こういう企業が何社もいる。若手採用のための広報の重要性を感じている会社が多いと思います」
――広報活動や採用活動について皆さんはどのように対策していますか。
山下「当社は年間休日を120日に増やし、ホームページも刷新しました。実際に若手も採用できました。同業者や似たような業種で働いていた方からすると選ばれやすい環境にはなったかな。ただ、都市部だとどうしても賃金が採用活動に影響してくる。例えば倉庫管理や運送の仕事で月給35万円のところには勝てない。福利厚生を打ち出ししても、やっと同レベルになったくらいだと思います」
――初任給はいくらに設定されていますか。
山下「当社は中途採用がほとんどですが、年齢問わず23万―24万円、残業代や諸手当を付けて額面で30万いかないくらい」
澤「当社は年間休日を一昨年くらいに120日に増やし、土曜日に出てもらう場合は休日出勤手当も出している。まわりの業者の給与体系も確認して、その業種の中でトップと同等レベル以上の給与を出せるようにしています。効果があるかわからないですが、社員旅行を年に1回実施し、クリスマスにはケーキを配るなど、ただ働くだけじゃなくてプラスαの楽しみを提供できるようには心がけています。でも、最近は本当に何が社員にとっていいかわからなくなってます。飲み会や社員旅行がない会社を選ぶ人もいるし、少しでもこの業界で楽しんでもらえるようにはしたいと思っているのですが」
斉藤「うちは中途がメインなので決まった初任給は設定できなくて年齢や保有資格によって変わります。本当は定期採用をして人員を整えていきたいですが、人手が不足してはじめて採用活動をするという流れになる現状がありまして、なかなか理想と現実がうまくマッチしていない状態です」
――槙岡さんは何か具体的な広報・採用活動をされていますか。
槙岡「当社は広報に力を入れています。社員は約290人いますが、そのなかで若手を中心とした9人のメンバーを広報のプロジェクトチームに任命し、インスタグラムやブログサイトのnoteを使って発信しています。採用に特化というよりは企業としての広報です。『毎月1万円の手当をつけるから兼業してくれないか』と応募をかけたら集まってくれました。昨年からプレスリリース配信サービスのPR TIMESにも社の取り組みを投稿するようにしており、それがきっかけで産業新聞や地元新聞にも当社の話題を取り上げていただきました。また、当社で働いているメンバーにもっと誇りを持ってもらいたいという思いから社内報にも力を入れ、年2回の発行から年6回に増やしています」
――先ほど山下さんが「業界の未来は明るい」と話されましたね。
槙岡「サーキュラーエコノミーやカーボンニュートラルの考え方で言うならば鉄リサイクル業界は本当に優等生だと思います。確実に発展していくし社会に必要不可欠な存在。業界規模として大きくなっていくだろうと思っています。ただ、日本の鉄スクラップの発生が極端に減っていくとも考えられます。そうなった時に国内だけで供給ソースが足りるかを踏まえると、やはり海外に目を向けていかなければいけない。20年後どころか5―10年後には鉄スクラップを輸入しなければいけないような状況になる可能性もある。その時に今のスクラップ業者各社が海外に出て戦えるかと考えると、今の実力ではなかなか厳しいのではないでしょうか。ですから、同業者と協業をしたり商社の力を借りたり、さまざまなやり方で対応をしていく必要がある。繰り返しになりますが、地方の人手不足の問題は深刻です。特に鉄リサイクル業界は人気の業界とはいえないので。条件を向上させていく必要があります。そのためにはもっと利益率を上げて、有り体にいえば稼げる業界にならないと未来は開けません。だから業界全体が何らかの変化を遂げなければいけないのではないでしょうか。経営者として変化に対する覚悟を持って貫き通すことを大事にしています。また、これだけ物価が上がると社長の私ですらしんどい。従業員の皆さんはそれ以上にしんどいでしょうから、賃上げは経営者としての責任だと感じています。そういう意味で責任は重たい」
――鉄スクラップの輸入の可能性を含めて20—30年後の業界の未来予想図について。
斉藤「30年後は70歳か……」
槙岡「もう引退していたいですね(笑)」
澤「扶和メタルが東京ベイの運営を開始する際に最終的に輸入に対応できることを前提とされていたと聞いたことがあります。東京製鉄のサテライトヤード展開などを踏まえても輸出が今後減少する可能性は高く、将来的には各メーカーも輸入の展望はあるかもしれません。20―30年後の業界はどうなるかというお尋ねですが、私自身はあまり先の未来のことをあまり考えないようにしています。例えば10年前、鉄スクラップがこんな値段になっているなんて、想像もつかなかったじゃないですか。20年先はこうなっているからこうしようって思っても、2―3年後に大幅に修正しないといけない、私はよく従業員にこういう話をします。『ぼくは常に2-3年後に100%の状態で会社が回るように考えて動いている。だから従業員の皆には1カ月後くらいのことを任せたいので常に考えて動いてほしい』と。それくらいの範囲なら予測は可能だから。2-3年先の未来でいうと、輸入どうこうというよりは高炉メーカーさんや鋳物メーカーさんの動きの方に注目しています」
山下「必要なところに必要なものを届ける手段を今準備しておく必要がある、ということは言えますね。槙岡さんがいる中四国は高炉メーカーの電炉転換が進むことで今後、鉄スクラップの不足地域になると思いますが、一方で北海道や関東は余剰地区です。日本全体でオープンに原料を回していければいいのではないでしょうか」
斉藤「いまAIを使った鉄スクラップ検収や重機の遠隔操作が取り沙汰されていますが、スクラップ業のいいところのひとつに『誰でもできる』という点があります。もちろん資格が必要な部分はありますが。でも、たとえばその先進技術がないと業として成り立たないようになると、仕事ができにくくなる懸念があります。遠隔操作が可能な重機を例に挙げてみると、小さいスクラップ業者でも導入できるような価格帯ならいいですが、そうならない可能性の方が高い。すると業界のなかで大きい会社と小さい会社の差が広がってしまって業界としていびつになってしまう。業界全体と考えるとよろしくないとも思います。『いい設備や技術を、値段を抑えて導入したい』だなんて甘い発想だといわれるかもわかりませんけれど」
山下「重機は、地域や企業のニーズやコストによって注目度が変わると思います。私としてはどちらかというと販売の方を変えたいです。中央集権型じゃなくて限りあるパイをみんなで享受するような枠組みがあるといいですが。実は今日、皆さんに提案したかったことがあります。以前、錆年会の有志企業が集まって東京製鉄の田原工場向けに内航船で鉄スクラップを出荷したのですが、多くの学びがありました」
槙岡「あれはすごかったですね。正直なところ、これはトラブルになるだろうと思って見てました。実際やってみてどうでしたか」
山下「採算の読みが甘く、結果としては赤字でしたが、トラブルというほどのことはなく、それ以上に学びが多かった。有志で取り組んだのですが、当社が窓口になって電炉メーカーの声を直に聞くことができました。今後、鉄リサイクル業界が世界と戦う上で、まず日本の業者が一体にならなきゃいけないと思います。中四国、具体的には倉敷周辺が鉄スクラップの不足地域になる可能性があり、理想を言うならこのエリアで消費される鉄スクラップは国内で発生したものであるべきです。先ほど申し上げた提案につながるのですが、いま流行りの2港積みや3港積みを、この青年部のメンバーを中心に企画してみませんか? たとえば北海道から出船して関東、関西の港に寄港し、最終的に中四国に運ぶ。現実的には難しいかも知れませんし、課題があるのは承知の上ですが、その地域がどういう特性を持って、どういう思いでやっているかを知るためにも、われわれがたすきをつないで鉄スクラップを運ぶようなことができればと思っています」
槙岡「先ほどの東鉄田原向けの内航船のこともそうですが、青年部の活動として実際の仕事につなげることは重要だと思います。中四国支部では勉強会や見学会などにとどまっていたのが実情だったので。実際に協働して内航船の船積みを実現したことは本当に尊敬します。業者同士の信頼がなければできないことです。だから、そういったことがもし全体で出来るなら、とても面白い取り組みです」
澤「ちょっとずれるかもしれませんが、大阪ですと解体由来のスクラップをまったく扱わない鉄スクラップ加工業者などがいまして、商材ごとに業者が多様化している流れがあります。私は以前からHSはHSを扱っている会社だけで話し合いをして船積みができたら面白いと思っていました。新断は新断を扱う業者だけ、ヘビーはヘビーだけ、というように。たとえば鉄鋼製品だと厚板だけの組合がありますが、スクラップはひとくくりになっています。これから貴重な国産資源として扱われていく中で商材ごとに組合みたいなのがあっても面白いんじゃないかな。他地域との連携や融通の話が出れば、山下さんが提案された共同でひとつの船に鉄スクラップを積んで、といった話もできます。こういう新しいことをすると談合しているとの懸念も出てきそうですが……」
山下「それも含めて学びですよ(笑)」
斉藤「北海道は余剰地域で発生した母材の6割ぐらいが道外に出ている状態ですから、2―3港積みを工業会内部でできるのは、とても魅力的です。あとは同じ地区内で設備や重機の共同購入とかもできたらいいですね」
山下「槙岡さんのおっしゃるように、稼ぐことが一番の近道だと思います。賃上げという形で経営者の責任を果たす意味でも、鉄スクラップ販売の未来を自分たちで、今なら作れるんじゃないでしょうか」
――最後に、10年後のご自身へのメッセージを。
槙岡「この会社、そして自分自身も生き延びていてください(笑)」
斉藤「しっかりと企業の血肉として頑張ってほしい」
山下「世界と戦いたいので社名を『ヤマシタグローバルメタル』とかに改名しておいてほしいです(笑)」
澤「私はこの業界に入って小さな失敗はたくさんしましたが、大きな後悔は何ひとつしていないつもりです。その考えのままやっていてほしいです」
【参加者略歴】
▽関東支部錆年会・山下耕平会長(やました・こうへい、ヤマシタ社長)=2008年学習院大法卒、大同興業入社、10年ヤマシタ入社。厚木工場長、寄居工場長、取締役を歴任。21年から現職。86年1月8日生まれ、東京都出身。
▽関西支部青年交流会・澤将也会長(さわ・まさや、信和鋼材社長)=09年近大産業理工卒、パッケージ業界に就職後、11年信和入社。16年取締役、23年グループ会社信和鋼材の社長を兼任。87年2月24日生まれ、大阪府出身。
▽北海道支部青年部・斉藤孝治郎会長(さいとう・こうじろう、斉藤商店社長)=10年早大人間科学卒、産業振興入社。総務、人事などを経験し、19年斉藤商店入社。22年から現職。86年9月14日生まれ、北海道出身。
▽中四国支部青年部会・槙岡達也部会長(まきおか・たつや、こっこー社長)=08年武蔵大経卒、毎日コミュニケーションズ(現マイナビ)入社。10年日新総合建材(現:日鉄鋼板)入社。15年こっこー入社、16年常務執行役員・生活環境事業部長兼鉄鋼建材営業部長、取締役常務執行役員、17年より現職。85年6月6日生まれ、広島県出身。















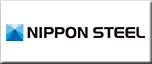
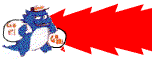
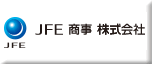

















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ


















