2025年6月25日
非鉄新経営 描き挑む成長のビジョン/東邦亜鉛社長/伊藤正人氏/鉛・銀増産、副産物も強化/電解鉄、セカンドグレード生産
東邦亜鉛は昨年12月、事業再生計画を取りまとめた。豪鉱山の売却が完了し、資源事業からは完全撤退。亜鉛製錬事業は主要設備の操業を2024年度末までに停止し、金属リサイクル主体への転換により再建を図る。鉛・銀製錬事業は拡大し、電子部材と電解鉄も成長を期待する。伊藤正人社長に事業再生計画の重要施策や長期的な会社の成長に向けた展望を聞いた。
――亜鉛製錬の主要設備を停止した。
「かつて製錬事業のための鉱石の長期安定確保と製錬に代わる収益源を求めて資源事業に進出した。自社鉱山の鉱石を使い製錬するのは良い考え方だと思うが、資源は当社の規模と体力からは非常に重い事業だった。また亜鉛製錬は電力コストが非常に高く、近年は電力代高騰で収益性が厳しさを増す。リサイクル原料の使用量を増やすことなどにもトライしたが、資源事業にお金がかかりすぎて亜鉛製錬に研究開発や事業転換をするための資金が回せないという状況で、亜鉛製錬事業はこのまま続けられないと判断した。生き残りを図りながらのソフトランディングができれば良かったが、資源の失敗で財務体質が悪化したこともあり、このような選択しかなかった」
――需要家への対応は。
「亜鉛については、事業再生計画を発表してから、高炉などの大ユーザーに理解していただけるよう説明にうかがった。皆様には何とか納得していただき、高炉向けについては6月末くらいをめどに、他社に供給を引き継いでもらえるめどが立った。継続予定である化成品を除いた亜鉛製品の需要家にも、調達先を切り替えていただける見通しがついた。海外工場で当社の亜鉛を使用していただいている需要家には、海外の製錬メーカーからの調達に切り替えていただく例もあった。販売先から『とんでもないことしてくれましたね』と直接言われたこともあり、大変責任を感じている。需要家の操業が止まるようなことが起こらず、無事に撤退できたことは良かった」
――亜鉛の安中製錬所(群馬県)は金属リサイクル事業に転換する。
「27年度に安中で導入する予定の炉はリサイクル原料から酸化亜鉛を生産する。年間処理能力は3万トン規模を想定。鉄と亜鉛が混在する鋼滓がメインの原料になる。このほかにも様々なリサイクル原料を処理し、その他有価金属なども回収していきたい。導入検討している設備の小型試験機は5年ほど前に導入しており、廃基板類やシュレッダーダストなども処理できることを確認している。当社は小名浜製錬所(福島県)で電炉ダストからの酸化亜鉛生産をすでに行っており、鉛バッテリーリサイクルなどで様々な回収ノウハウもある。海外でも使えそうな原料があることも把握しており、これらを安定して集められれば事業として成立すると思う」
――従来の亜鉛製錬事業は売上高が約300億円あった。金属リサイクルでどの程度カバーできるか。
「売上高では考えていない。当社の今年度の経常利益見通しは41億円で、26年度は52億円を見込む。28年度には70億円を超える計画だが、約20億円増える中心が鉛・銀製錬事業と金属リサイクル事業というイメージだ」
――小名浜の酸化亜鉛はタイヤ向けに半ばしているが、安中は。
「安中で生産する酸化亜鉛は亜鉛製錬メーカー、あるいは亜鉛を使った加工品メーカーなどに販売する予定だ」
 ――鉛製錬は基盤事業に位置付け、28年に溶融設備を入れる。
――鉛製錬は基盤事業に位置付け、28年に溶融設備を入れる。
「東邦契島製錬(広島県)の鉛製錬は生産能力にまだ余裕があり、メインのユーザーから増量要請もあるが、これまで十分な人員配置ができていなかった。今年度は最適な人員配置などを実施し、24年度より6000トン多い8万8000トンを計画する。今後は、これまで投資できなかったDX技術も活用して生産効率を上げていきたい。」
――廃バッテリーの集荷量はどう増やす。
「事業再生計画で当社のスポンサー企業となったアドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンドは鉛蓄電池メーカーのエナジーウィズにも投資しており、同業の古河電池にも投資を予定している。当社は鉛バッテリーの需要家、鉛バッテリーメーカーや回収業者等のバリューチェーン各社との連携を強化し、そのループでメインストリームを占めたい」
――契島の銀製錬は。
「高銀鉱の手当ては順調で、今年度の銀生産量は上期だけで前年同期比10トン増える計画だ。今後については、有望なリサイクル原料ソースが見つかっている。これをうまく鉱石と配合すれば、処理できることも分かってきた。銀は相場が上がっており、生産能力はまだまだ余裕があるため、原料集荷を増やせれば収益貢献が大きい。原料調達では業務提携している阪和興業とも連携していきたいと考えている」
――今年度は鉛・銀製錬で180億円の増収を見込む。
「副産物の価格上昇も大きい。これまでそれほどの回収量ではなかったが、人手をかけて回収しても採算が取れる領域にきている。シフトアップや工程改善により回収量を増やし、技術開発にも取り組む。将来的な設備投資も視野に入れる」
――電子部材は電気自動車(EV)市場成長鈍化の影響を受けている。
「かなりの上向きを期待していたので、いまのなだらかな伸びは想定外で、厳しい時期に入ってしまった。ただ当社の電子部材は電源部品がメインで、電源を使わない電子機器はない。データセンターなどの成長分野もある。EV向けも30年モデル向けなどの新規案件も寄せられており、産機とEVという両方の成長分野で伸ばしていきたい」
 ――電解鉄はどう伸ばす。
――電解鉄はどう伸ばす。
「当社は航空機部品などに使われる高機能な電解鉄を生産しているが、ユーザーによってはそこまでの高品質を求めず、ほかの安価な材料と混合して使用しているところもある。そこで、セカンドグレードの電解鉄も生産して幅広いユーザーの品質ニーズに対応できるようにする」
――LiBリサイクル事業の収益化は。
「始まったばかりの事業で参入メーカーも多く、事業展望がはっきりしてくるのは少し先かなと思う。ただ需要があるのは間違いなく、当社は廃バッテリーを回収するノウハウも豊富なため、収益事業としての展開は可能だと考えている」
――事業再生計画の成長投資について。
「第三者割当増資で調達した75億円を使う。大きなものは安中のリサイクル熔融炉が35億円、電解鉄のセカンドグレード対応設備が12億円、DX等プロジェクト費用が28億円となっている。このほかに設備の維持・更新などで年間10億―15億円の投資が必要だとみている」
――事業再生計画後の事業ポートフォリオのイメージを。
「従来の売上比率は亜鉛、鉛、銀がそれぞれ300億円程度だった。亜鉛がなくなり、鉛、銀、酸化亜鉛、電解鉄、電子部品が増えていくイメージ。今後5年くらいは売上高900億円くらいで推移するとみているが、その後の展望については今後2年位経てば見えてくるのではないか」
――廃バッテリーの集荷価格が上がっている。
「24年度は廃バッテリー価格が非常に高く、少し異常な時期だった。調達コストの増加は減益要因になった。ただ相場はひとまず頭打ちとなったため、今年度は改善の方向に進むのではないか。今後はリサイクルループの構築も合わせて調達環境が改善すると考えている」
――原料高に対して鉛製品販価のプレミアム(割増金)は引き上げているか。
「原材料だけでなく人件費なども含めたトータルコストが上がっているため、販売先には毎年お願いをしており、ある程度の理解はいただいている。ただ、供給先と完全に意思疎通が図れているとは言えず、本当に丁寧に説明していかないといけない」
――事業再生計画を発表してから、会社の雰囲気は変わったか。
「非常に士気が上がっている印象だ。4月に100日計画をキックオフした。これは事業再生計画に沿って実務部隊が何をしていくのか、一人一人が何をするのかをまとめるもの。事業部だけでなく管理部門なども含め、1000件を超えるアイデアが上がってきている。コストダウンや新製品、歩留まり改善など様々なテーマが寄せられている。6月末までに具体的な計画を取りまとめ、7月からスタートする。コンサルタントなどと一緒に考えて実施した初めての試みだが、ボトムアップで士気が高まっていることをうれしく感じている」

――亜鉛製錬の主要設備を停止した。
「かつて製錬事業のための鉱石の長期安定確保と製錬に代わる収益源を求めて資源事業に進出した。自社鉱山の鉱石を使い製錬するのは良い考え方だと思うが、資源は当社の規模と体力からは非常に重い事業だった。また亜鉛製錬は電力コストが非常に高く、近年は電力代高騰で収益性が厳しさを増す。リサイクル原料の使用量を増やすことなどにもトライしたが、資源事業にお金がかかりすぎて亜鉛製錬に研究開発や事業転換をするための資金が回せないという状況で、亜鉛製錬事業はこのまま続けられないと判断した。生き残りを図りながらのソフトランディングができれば良かったが、資源の失敗で財務体質が悪化したこともあり、このような選択しかなかった」
――需要家への対応は。
「亜鉛については、事業再生計画を発表してから、高炉などの大ユーザーに理解していただけるよう説明にうかがった。皆様には何とか納得していただき、高炉向けについては6月末くらいをめどに、他社に供給を引き継いでもらえるめどが立った。継続予定である化成品を除いた亜鉛製品の需要家にも、調達先を切り替えていただける見通しがついた。海外工場で当社の亜鉛を使用していただいている需要家には、海外の製錬メーカーからの調達に切り替えていただく例もあった。販売先から『とんでもないことしてくれましたね』と直接言われたこともあり、大変責任を感じている。需要家の操業が止まるようなことが起こらず、無事に撤退できたことは良かった」
――亜鉛の安中製錬所(群馬県)は金属リサイクル事業に転換する。
「27年度に安中で導入する予定の炉はリサイクル原料から酸化亜鉛を生産する。年間処理能力は3万トン規模を想定。鉄と亜鉛が混在する鋼滓がメインの原料になる。このほかにも様々なリサイクル原料を処理し、その他有価金属なども回収していきたい。導入検討している設備の小型試験機は5年ほど前に導入しており、廃基板類やシュレッダーダストなども処理できることを確認している。当社は小名浜製錬所(福島県)で電炉ダストからの酸化亜鉛生産をすでに行っており、鉛バッテリーリサイクルなどで様々な回収ノウハウもある。海外でも使えそうな原料があることも把握しており、これらを安定して集められれば事業として成立すると思う」
――従来の亜鉛製錬事業は売上高が約300億円あった。金属リサイクルでどの程度カバーできるか。
「売上高では考えていない。当社の今年度の経常利益見通しは41億円で、26年度は52億円を見込む。28年度には70億円を超える計画だが、約20億円増える中心が鉛・銀製錬事業と金属リサイクル事業というイメージだ」
――小名浜の酸化亜鉛はタイヤ向けに半ばしているが、安中は。
「安中で生産する酸化亜鉛は亜鉛製錬メーカー、あるいは亜鉛を使った加工品メーカーなどに販売する予定だ」
 ――鉛製錬は基盤事業に位置付け、28年に溶融設備を入れる。
――鉛製錬は基盤事業に位置付け、28年に溶融設備を入れる。「東邦契島製錬(広島県)の鉛製錬は生産能力にまだ余裕があり、メインのユーザーから増量要請もあるが、これまで十分な人員配置ができていなかった。今年度は最適な人員配置などを実施し、24年度より6000トン多い8万8000トンを計画する。今後は、これまで投資できなかったDX技術も活用して生産効率を上げていきたい。」
――廃バッテリーの集荷量はどう増やす。
「事業再生計画で当社のスポンサー企業となったアドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンドは鉛蓄電池メーカーのエナジーウィズにも投資しており、同業の古河電池にも投資を予定している。当社は鉛バッテリーの需要家、鉛バッテリーメーカーや回収業者等のバリューチェーン各社との連携を強化し、そのループでメインストリームを占めたい」
――契島の銀製錬は。
「高銀鉱の手当ては順調で、今年度の銀生産量は上期だけで前年同期比10トン増える計画だ。今後については、有望なリサイクル原料ソースが見つかっている。これをうまく鉱石と配合すれば、処理できることも分かってきた。銀は相場が上がっており、生産能力はまだまだ余裕があるため、原料集荷を増やせれば収益貢献が大きい。原料調達では業務提携している阪和興業とも連携していきたいと考えている」
――今年度は鉛・銀製錬で180億円の増収を見込む。
「副産物の価格上昇も大きい。これまでそれほどの回収量ではなかったが、人手をかけて回収しても採算が取れる領域にきている。シフトアップや工程改善により回収量を増やし、技術開発にも取り組む。将来的な設備投資も視野に入れる」
――電子部材は電気自動車(EV)市場成長鈍化の影響を受けている。
「かなりの上向きを期待していたので、いまのなだらかな伸びは想定外で、厳しい時期に入ってしまった。ただ当社の電子部材は電源部品がメインで、電源を使わない電子機器はない。データセンターなどの成長分野もある。EV向けも30年モデル向けなどの新規案件も寄せられており、産機とEVという両方の成長分野で伸ばしていきたい」
 ――電解鉄はどう伸ばす。
――電解鉄はどう伸ばす。「当社は航空機部品などに使われる高機能な電解鉄を生産しているが、ユーザーによってはそこまでの高品質を求めず、ほかの安価な材料と混合して使用しているところもある。そこで、セカンドグレードの電解鉄も生産して幅広いユーザーの品質ニーズに対応できるようにする」
――LiBリサイクル事業の収益化は。
「始まったばかりの事業で参入メーカーも多く、事業展望がはっきりしてくるのは少し先かなと思う。ただ需要があるのは間違いなく、当社は廃バッテリーを回収するノウハウも豊富なため、収益事業としての展開は可能だと考えている」
――事業再生計画の成長投資について。
「第三者割当増資で調達した75億円を使う。大きなものは安中のリサイクル熔融炉が35億円、電解鉄のセカンドグレード対応設備が12億円、DX等プロジェクト費用が28億円となっている。このほかに設備の維持・更新などで年間10億―15億円の投資が必要だとみている」
――事業再生計画後の事業ポートフォリオのイメージを。
「従来の売上比率は亜鉛、鉛、銀がそれぞれ300億円程度だった。亜鉛がなくなり、鉛、銀、酸化亜鉛、電解鉄、電子部品が増えていくイメージ。今後5年くらいは売上高900億円くらいで推移するとみているが、その後の展望については今後2年位経てば見えてくるのではないか」
――廃バッテリーの集荷価格が上がっている。
「24年度は廃バッテリー価格が非常に高く、少し異常な時期だった。調達コストの増加は減益要因になった。ただ相場はひとまず頭打ちとなったため、今年度は改善の方向に進むのではないか。今後はリサイクルループの構築も合わせて調達環境が改善すると考えている」
――原料高に対して鉛製品販価のプレミアム(割増金)は引き上げているか。
「原材料だけでなく人件費なども含めたトータルコストが上がっているため、販売先には毎年お願いをしており、ある程度の理解はいただいている。ただ、供給先と完全に意思疎通が図れているとは言えず、本当に丁寧に説明していかないといけない」
――事業再生計画を発表してから、会社の雰囲気は変わったか。
「非常に士気が上がっている印象だ。4月に100日計画をキックオフした。これは事業再生計画に沿って実務部隊が何をしていくのか、一人一人が何をするのかをまとめるもの。事業部だけでなく管理部門なども含め、1000件を超えるアイデアが上がってきている。コストダウンや新製品、歩留まり改善など様々なテーマが寄せられている。6月末までに具体的な計画を取りまとめ、7月からスタートする。コンサルタントなどと一緒に考えて実施した初めての試みだが、ボトムアップで士気が高まっていることをうれしく感じている」














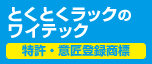


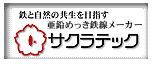

















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ


















