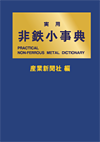2022年4月20日

日本の特殊鋼/世界に誇る技術の粋/(1)/業界の将来展望を聞く(上)/特殊鋼倶楽部・藤岡高広会長/製販一体で強固な供給網/時代読み、技術・国際競争力を向上

国際的に社会・経済のあり方が大きく変わる中、世界最先端の技術を誇る日本の特殊鋼は自動車や建設機械など産業を支える素材としての重要度を増すばかりだ。自動車の電動化で需要が減少する一方、電動化で使用が増える特殊鋼部品があり、さらには再生可能エネルギーや航空宇宙など高度な特殊鋼を要する新たな市場が広がっていく。「大きな戦略を描き、果敢にチャレンジしていきたい」。カーボンニュートラル(CN)やデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みに力を注ぎ、業界全体の競争力向上を目指す特殊鋼倶楽部の藤岡高広会長(愛知製鋼社長)に特殊鋼業界の将来展望を聞いた。
――特殊鋼倶楽部では技術の粋(すい)を「粋(いき)」と称して業界の「計らい」を表している。日本の特殊鋼が持つ強みとは何か。
「特殊鋼は日本の鉄鋼業の最先端技術の『粋(いき)』であり、『最後の砦』とも言われる。自動車や産機など各需要家の非常に高い要求レベルに応えるためにすり合わせ技術などを培い、新技術、新商品を開発してきた。日本の製造業の高いグローバル競争力を支えている。高度で精密な技術の開発を絶え間なく行っており、特に自動車や部品メーカーなど顧客と一体になったすり合わせ技術は顧客の製品開発の初期から製造方法と要求する品質を聞きながら、完成まで一貫して造り上げている。削りやすさなどわずかな違いが生じるため、同じ品種の鋼材であっても他の特殊鋼メーカーには容易に切り替えることはできない。多品種小ロット、熱処理、高度な生産プロセスを通じて良品廉価なものづくりができる。2つめの強みは特殊鋼メーカーとして生産対応を行っている点だ。自動車メーカーなどから、ある製品の製造依頼や急な増産要請にあうんの呼吸で対応している。長年にわたって築き上げてきたすり合わせ技術と生産対応、商社・流通とともに製販一体で構築してきた強固なサプライチェーンは日本の産業界になくてはならないもの。特殊鋼業界の連携力、改善提案力は非常に素晴らしく、海外の特殊鋼製品は簡単に入ってこられない」

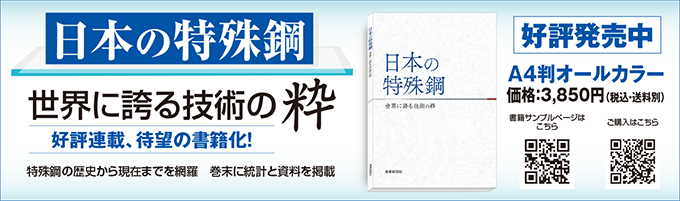

――特殊鋼倶楽部では技術の粋(すい)を「粋(いき)」と称して業界の「計らい」を表している。日本の特殊鋼が持つ強みとは何か。
「特殊鋼は日本の鉄鋼業の最先端技術の『粋(いき)』であり、『最後の砦』とも言われる。自動車や産機など各需要家の非常に高い要求レベルに応えるためにすり合わせ技術などを培い、新技術、新商品を開発してきた。日本の製造業の高いグローバル競争力を支えている。高度で精密な技術の開発を絶え間なく行っており、特に自動車や部品メーカーなど顧客と一体になったすり合わせ技術は顧客の製品開発の初期から製造方法と要求する品質を聞きながら、完成まで一貫して造り上げている。削りやすさなどわずかな違いが生じるため、同じ品種の鋼材であっても他の特殊鋼メーカーには容易に切り替えることはできない。多品種小ロット、熱処理、高度な生産プロセスを通じて良品廉価なものづくりができる。2つめの強みは特殊鋼メーカーとして生産対応を行っている点だ。自動車メーカーなどから、ある製品の製造依頼や急な増産要請にあうんの呼吸で対応している。長年にわたって築き上げてきたすり合わせ技術と生産対応、商社・流通とともに製販一体で構築してきた強固なサプライチェーンは日本の産業界になくてはならないもの。特殊鋼業界の連携力、改善提案力は非常に素晴らしく、海外の特殊鋼製品は簡単に入ってこられない」

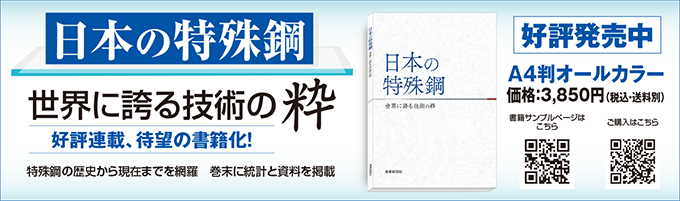














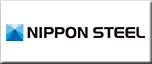

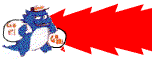
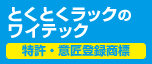

















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ