2025年5月27日
経営戦略を聞く/ジェコス 野房喜幸社長/山留分野と土木工事強化/ベトナム現法、利益上積み図る
ジェコスは2025年度から新中期経営計画をスタートした。利益重視へ舵を切り、野房喜幸社長は「この2年間取り組んできた採算性を重視した受注活動の成果がでてきている」と強調、今後は事業領域の拡大とポートフォリオの多様化への取り組みを進める。みずほリースとの協業を推進するとともに、オトワコーエイとの連携強化による土木工事の拡大を実践。海外ではシンガポールの展開を強める。野房社長に取り組みを聞いた。
――24年度の業績を振り返って。
「2024年度業績は連結で売上高1115億5000万円(前年同期比13%減)、営業利益68億5100万円(同9・7%増)、経常利益67億9400万円(同2・9%増)で利益面は想定を上回った。単体では経常利益で過去最高益を計上できた。鉄構加工・橋梁ではこれまでやってきた取り組みが実を結び、増収増益。仮設工事も売り上げ減となったものの、採算性を重視した受注活動の成果により、営業利益は増益となった」
――25年度見通しについては。
「業績予想は連結で売上高1110億円(前年度比0・5%減)、営業利益67億円(同2・2%減)、経常利益70億円(同3%増)。24年度に利益を押し上げた鉄構加工・橋梁はシールド関連の鉄構加工物件が端境期となるため、今年度は抑えた予想とした。また、本来であれば、年度下期に向けて業績が伸びる傾向だが、トランプ関税の影響などにより日本経済の動向が不透明なこともあって保守的に見ている。ただ、需要は堅調に推移しており、環境的にも悪くないことから、期中の積み増しを目指す」
――25年度業績見通しで、トランプ関税の影響が拡大する可能性も。
「どの程度影響するか読めず、保守的な見方にとどめている。ただ、当社の売上のほとんどが国内であり、海外からの材料購入や輸出もない。直接的な影響はないといっていいが、心配なのは日本経済全体が減速し、建設需要が抑えられることだ。また、中国経済がこの影響で減速し、鋼材市況がマイナスの方向に推移すると、賃貸価格の交渉に多少の影響が生じるかもしれない」
――27年度に向けて重仮設セグメントにおける売上高推移について。
「採算性の低い流通販売取引について、計画的に抑制してきたので売上高が減少したが、一定のめどが立ち、更に下がり続けることはなく今後は事業領域拡大により増加に転じると考えている。2027年度に向けて、仮設鋼材の収益力向上及び価格適正化の取り組みや設計費等のサービス対価取得、首都圏での施工能力向上、鉄構加工・橋梁の需要取り込み、山留周辺分野における事業規模拡大を目指し、27年度は1180億円に伸ばす」
――シンガポールの重仮設業者、FUCHI(フチ社)など海外展開は。
「フチ社は、諸物価の高騰を反映した新単価の受注比率が上がり、業績も改善してきた。同社の将来的な連結子会社化を検討しており、当社からの出向社員を2名増やし、4名とした。24年度決算は会計方針を当社に準じた運用に変更したため、一過性のマイナスの要因も生じたが、需要も堅調であり本年度は改善できる」
「ベトナムの現地法人について、ODA(政府開発援助)案件が減少しているが設計事業における取り組みが、実を結んできた。現地スタッフを15名体制に拡充し、そのうち現在2名来日しているが、日本での研修に参加するなど、実力は着実に向上している。当社の全設計図面業務のうち20%程度はベトナムで対応しており、国内の技術部では、より付加価値の高い技術サービスをお客様に提供している。23年度に初めて黒字化し、24年度も黒字を維持、25年度はさらに利益の上積みを図っていきたい。」
――国内を含め、設計にも力を入れていくことに。
「当社の設計部門は、付加価値の高い設計サービスを提供しており、これらに準じた対価についても、お客様の理解を得られつつあると手応えを感じている」
――4月の組織改正で、山留周辺分野強化のためのジオ・エンジニアリング部と、労働生産性向上のための業務改革推進部の2部署が発足しました。
「ジオ・エンジニアリング部と業務改革推進部にはそれぞれ3人を配置した。中期経営計画の3カ年で掲げた目標を実現すべく取り組んでいく。業務改革推進部では労働生産性の24年度比10%向上を目指す。業務プロセスを可視化し、業務そのものを見直したうえで必要に応じてDXで改善していく」
「組織改正ではインフラメンテナンス事業推進部を加工事業部へ統合・移管し、インフラメンテナンスグループとした。ここで本設橋のH形鋼橋梁(GHB)を本格的に事業展開を進めていく。お客様の関心も高く手ごたえを感じている。」
――中期経営計画では基礎工事などを手掛けるオトワコーエイとの連携強化による土木工事の強化を掲げています。
「オトワコーエイは、当社の子会社となった影響も多少あると思うが、採用活動への効果も現れてきている。人材確保が進みつつあり、業績も上がると見込む」
「国土強靭化も我々にはプラスだ。建築に比べ、土木は弱い部分もあり、これを強化する。人口減で中長期的な需要の落ち込みが予想される民間建築に対し、土木は安定した需要が見込める。特殊な土木工事に強いオトワコーエイからノウハウを吸収し、土木工事の強化を図る。」
――人員採用は。
「新卒採用は安定して続けていく。本年度は約20名を採用、前年度も約20名を採用しており、20ー30名を継続的に採用する。足りない部分はキャリア(中途)採用で補うことにしており、技能を持つ人の採用を進めている。少子高齢化の中、日本人の新卒だけに頼らず、中途採用や、外国籍の方々を含めて採用活動に積極的に取り組んでいきたい」
――資本提携しているみずほリースとの取り組みは。
「取り組みの1つとして鋼材検収作業の自動化技術を共同開発している。既に実証試験に入っており、我々の技術にみずほリースの知見を活かして、1年位で実用化させたい。建機については、みずほリース保有資産を当社グループ会社レンタルシステムの拠点で運用・管理するスキームも検討していく。」
――スタートした新中計で掲げる成長戦略について。
「鉄構加工・橋梁は24年度の売上高が増加して手応えを感じている。橋梁も西日本地区に岡山ヤードができ、認知度も上がってきた。新設のジオ・エンジニアリング部を活かし、山留周辺分野を強化することにより、計測管理、水処理、地盤改良など需要を取り込んで、一つの現場から上げられる利益を高めていく。仮設鋼材を維持しながら、他の部門を伸ばし、全体のバランスを良くすることにより、どのような環境でも利益をあげられる体制を構築する」

――24年度の業績を振り返って。
「2024年度業績は連結で売上高1115億5000万円(前年同期比13%減)、営業利益68億5100万円(同9・7%増)、経常利益67億9400万円(同2・9%増)で利益面は想定を上回った。単体では経常利益で過去最高益を計上できた。鉄構加工・橋梁ではこれまでやってきた取り組みが実を結び、増収増益。仮設工事も売り上げ減となったものの、採算性を重視した受注活動の成果により、営業利益は増益となった」
――25年度見通しについては。
「業績予想は連結で売上高1110億円(前年度比0・5%減)、営業利益67億円(同2・2%減)、経常利益70億円(同3%増)。24年度に利益を押し上げた鉄構加工・橋梁はシールド関連の鉄構加工物件が端境期となるため、今年度は抑えた予想とした。また、本来であれば、年度下期に向けて業績が伸びる傾向だが、トランプ関税の影響などにより日本経済の動向が不透明なこともあって保守的に見ている。ただ、需要は堅調に推移しており、環境的にも悪くないことから、期中の積み増しを目指す」
――25年度業績見通しで、トランプ関税の影響が拡大する可能性も。
「どの程度影響するか読めず、保守的な見方にとどめている。ただ、当社の売上のほとんどが国内であり、海外からの材料購入や輸出もない。直接的な影響はないといっていいが、心配なのは日本経済全体が減速し、建設需要が抑えられることだ。また、中国経済がこの影響で減速し、鋼材市況がマイナスの方向に推移すると、賃貸価格の交渉に多少の影響が生じるかもしれない」
――27年度に向けて重仮設セグメントにおける売上高推移について。
「採算性の低い流通販売取引について、計画的に抑制してきたので売上高が減少したが、一定のめどが立ち、更に下がり続けることはなく今後は事業領域拡大により増加に転じると考えている。2027年度に向けて、仮設鋼材の収益力向上及び価格適正化の取り組みや設計費等のサービス対価取得、首都圏での施工能力向上、鉄構加工・橋梁の需要取り込み、山留周辺分野における事業規模拡大を目指し、27年度は1180億円に伸ばす」
――シンガポールの重仮設業者、FUCHI(フチ社)など海外展開は。
「フチ社は、諸物価の高騰を反映した新単価の受注比率が上がり、業績も改善してきた。同社の将来的な連結子会社化を検討しており、当社からの出向社員を2名増やし、4名とした。24年度決算は会計方針を当社に準じた運用に変更したため、一過性のマイナスの要因も生じたが、需要も堅調であり本年度は改善できる」
「ベトナムの現地法人について、ODA(政府開発援助)案件が減少しているが設計事業における取り組みが、実を結んできた。現地スタッフを15名体制に拡充し、そのうち現在2名来日しているが、日本での研修に参加するなど、実力は着実に向上している。当社の全設計図面業務のうち20%程度はベトナムで対応しており、国内の技術部では、より付加価値の高い技術サービスをお客様に提供している。23年度に初めて黒字化し、24年度も黒字を維持、25年度はさらに利益の上積みを図っていきたい。」
――国内を含め、設計にも力を入れていくことに。
「当社の設計部門は、付加価値の高い設計サービスを提供しており、これらに準じた対価についても、お客様の理解を得られつつあると手応えを感じている」
――4月の組織改正で、山留周辺分野強化のためのジオ・エンジニアリング部と、労働生産性向上のための業務改革推進部の2部署が発足しました。
「ジオ・エンジニアリング部と業務改革推進部にはそれぞれ3人を配置した。中期経営計画の3カ年で掲げた目標を実現すべく取り組んでいく。業務改革推進部では労働生産性の24年度比10%向上を目指す。業務プロセスを可視化し、業務そのものを見直したうえで必要に応じてDXで改善していく」
「組織改正ではインフラメンテナンス事業推進部を加工事業部へ統合・移管し、インフラメンテナンスグループとした。ここで本設橋のH形鋼橋梁(GHB)を本格的に事業展開を進めていく。お客様の関心も高く手ごたえを感じている。」
――中期経営計画では基礎工事などを手掛けるオトワコーエイとの連携強化による土木工事の強化を掲げています。
「オトワコーエイは、当社の子会社となった影響も多少あると思うが、採用活動への効果も現れてきている。人材確保が進みつつあり、業績も上がると見込む」
「国土強靭化も我々にはプラスだ。建築に比べ、土木は弱い部分もあり、これを強化する。人口減で中長期的な需要の落ち込みが予想される民間建築に対し、土木は安定した需要が見込める。特殊な土木工事に強いオトワコーエイからノウハウを吸収し、土木工事の強化を図る。」
――人員採用は。
「新卒採用は安定して続けていく。本年度は約20名を採用、前年度も約20名を採用しており、20ー30名を継続的に採用する。足りない部分はキャリア(中途)採用で補うことにしており、技能を持つ人の採用を進めている。少子高齢化の中、日本人の新卒だけに頼らず、中途採用や、外国籍の方々を含めて採用活動に積極的に取り組んでいきたい」
――資本提携しているみずほリースとの取り組みは。
「取り組みの1つとして鋼材検収作業の自動化技術を共同開発している。既に実証試験に入っており、我々の技術にみずほリースの知見を活かして、1年位で実用化させたい。建機については、みずほリース保有資産を当社グループ会社レンタルシステムの拠点で運用・管理するスキームも検討していく。」
――スタートした新中計で掲げる成長戦略について。
「鉄構加工・橋梁は24年度の売上高が増加して手応えを感じている。橋梁も西日本地区に岡山ヤードができ、認知度も上がってきた。新設のジオ・エンジニアリング部を活かし、山留周辺分野を強化することにより、計測管理、水処理、地盤改良など需要を取り込んで、一つの現場から上げられる利益を高めていく。仮設鋼材を維持しながら、他の部門を伸ばし、全体のバランスを良くすることにより、どのような環境でも利益をあげられる体制を構築する」














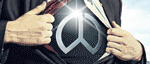
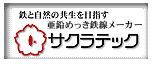
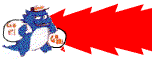
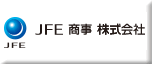

















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ


















