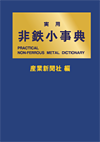2025年6月27日
商社の経営戦略 10年先を見据えて/伊藤忠丸紅鉄鋼 石谷誠社長/北米で川下事業拡張検討/新興向け出資、DX化提案加速
――2030年代の経営環境を見据え、「鉄鋼流通におけるグローバルトップを目指す」長期ビジョンを描いている。
「得意としてきたトレード中心のビジネスの延長線上の発想では、ビジョンの実現は不可能。事業投資に対する社員の意識改革を全社運動として展開し、ビジネスモデルを大きく転換させていく」
――ビジョン実現のファーストステージとして第8次中期経営計画(24―26年度)を推進している。
「『Trade×Investment』をスローガンとし、市況や為替に左右されない基礎収益力の強化、DXやGXをリードするトレードの機能強化、次世代のMISI(伊藤忠丸紅鉄鋼)を担う人材の育成の三つの重点施策に取り組んでいる」
――いかに基礎収益力を強化していくのか。
「トレードで培った知見と人脈を活かして、戦略的投資の機会を創出し、厳選した上で実行し、投資リターンを中心とする収益力を底上げしていく。5つの営業本部に昨年4月1日付で『開発室』をそれぞれ設置して専任者を配置。併せて営業本部、海外現地法人の投資案件の発掘をバックアップする『投資推進チーム』を事業総括部に設置し、M&Aのスキルを持った社外人材を迎え入れて、投資リスクの低減と早期収益化を図っていく。足下の収益拡大に直結する投資、将来の種まきとしての先行投資を同時に本格化している」
――社員の意識をどう変えていく。
「社員には目線を上げて、取引先の経営層と需給や業界構造の変化に関する議論を重ねながら信頼関係を構築し、事業投融資や合弁事業の機会創出に取り組んでいくよう指示している。事業投資意識を高めるための社長主催の勉強会を開始。長期ビジョンや中計の位置づけから、投資機会のチャンスとリスクに関する研修を役員、本部長、部長級と開催し、30歳以上の全社員を対象に続けていく。社内教育制度、事業会社への派遣、海外留学などを通じて、個人の意識改革を風土改革へと結び付けていく」
――成長投資のターゲット分野、地域は。
「鉄鋼流通事業、建材製造などの川下分野、サプライチェーンの機能強化につながる事業、カーボンニュートラル対応の4つをターゲット分野に設定。北米、欧州、豪州、日本など先進国と、インド、中東、アフリカの成長市場で投資案件を発掘していく」
――欧州ではスペインの鋼板メーカーに出資するなど積極投資を展開している。
「スペインの独立系最大手のネットワーク・スチール・リソーシズに出資し、持分法適用会社とした。NSRは、イベリア半島の7カ所にカラー鋼板や亜鉛鉄板など建設鋼材の製造・加工・販売拠点を持ち、年間100万トン規模のサプライチェーンを構築している。今回の出資を通じて欧州における事業領域を大きく拡大していく」
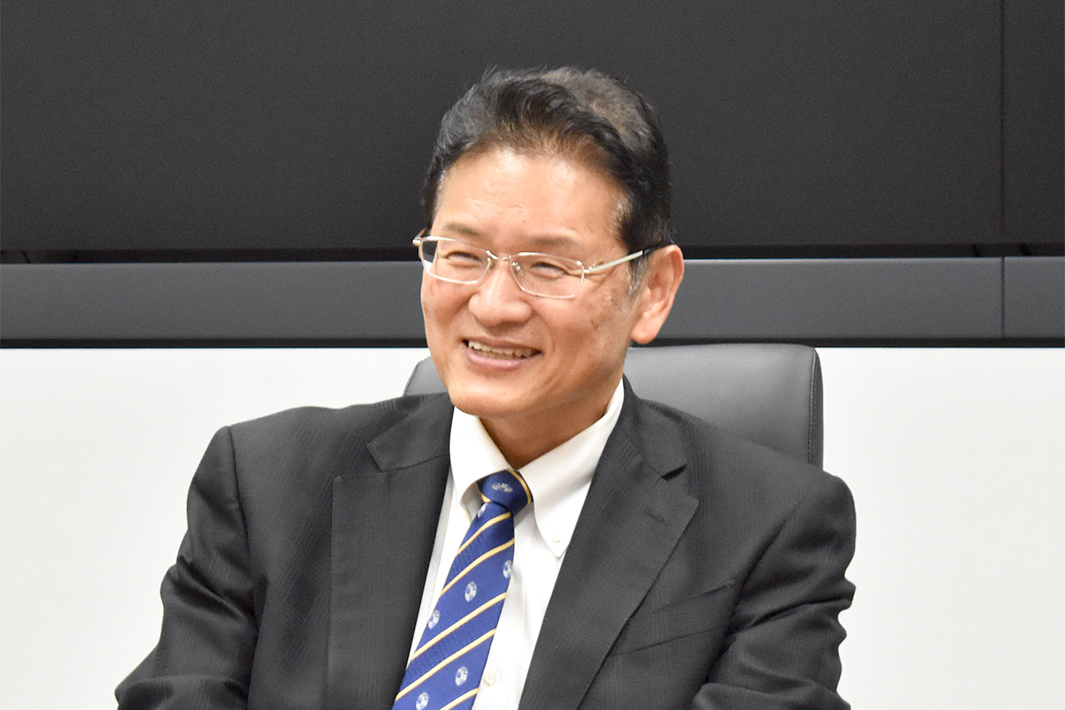 ――スコットランドの厚板加工会社を買収した。
――スコットランドの厚板加工会社を買収した。
「先行して買収した英国の建設・インフラ・エネルギー用鋼材の加工・流通企業、バークレイ&マシソン(B&M)を通じて、アンガス社の全株式を24年10月に取得した。アンガス社は、グラスゴー近郊の拠点に、最新鋭の厚板加工設備を保有し、高強度鋼板の加工・在庫販売を行っている。B&Mと協業しながら、スコットランド、北部イングランドを中心に石油・ガス、再生エネルギー関連マーケットでビジネスを拡大していく」
――アイルランドの洋上風力関連部材メーカーにも出資した。
「サブシー・マイクロパイルズは、スコットランドを中心に洋上風力や石油・ガス掘削用リグ向けの係留アンカーの開発・製造・据え付けサービスを提供。巨大な碇やチェーンで構成しているアンカーを大幅に軽量化し、作業船を含めたコストの低減と短工期化を実現する特許技術を保有している。スコットランド国立投資銀行と共同出資し、欧州で普及が加速する浮体式洋上風力向けビジネスを拡充していく」
――米国では建材の川下事業投資を実施した。
「現地の建材会社CDBSを通じて、オクラホマ州のスタッズ・アンリミテッドを買収した。CDBSは、中西部、西海岸などに15拠点を持ち、商業施設などの建築用スチールフレームで全米の4割強のシェアを握っている。スタッズの買収は、人口増加が見込まれる南西部の製造拠点を確保するのが狙い」
――インドは総代表ポジションを新設した。
「インドは人口増加に伴い鉄鋼需要が2億トン、3億トンへ拡大すると期待されている。中国の鋼材輸出の影響を受けにくい政治事情もあって、需給がバランスし、マーケットは安定している。現地高炉大手のJSWスチールとは自動車鋼板用のコイルセンターを4カ所で展開しているが、年間取扱量が100万トンを超えて、追加の設備投資が検討課題になっている。TWBやメカニカルチューブ、電磁鋼板の現地事業も展開している。インド総代表が現地企業トップとの信頼関係を強化しながら、ビジネスチャンスを大きく拡充していく」
――中東、アフリカ市場へのアプローチも加速している。
「ケニアにナイロビ支店を設立し、ドバイに中東現地法人を開設した。インドに加え、中東、アフリカへのサプライチェーン、市場開拓を進めていく」
――国内ではコイルセンターの再編の検討を開始した。
「広島県にあるマツダスチールと紅忠サミットコイルセンターの事業統合の検討を開始している。いずれも住友商事グローバルメタルズとの共同出資会社で、多様化する社会の課題に対して柔軟に対応する。国内の鋼材需要の縮小を見据え、メーカー系、商社系、オーナー系を問わず健全な市場を維持するための加工・物流機能の再編を進めていく」
――本年度の投資テーマは。
「中計3年間の投融資はとくに枠を設定せず、あらゆる成長機会を探っていく。大きな事業基盤を持つ北米では川下分野の事業拡張を検討していく」
――USスチールは重要なビジネスパートナー。
「北米では、米国のスーナーとCTAP、カナダのトライマークが問屋機能を持って油井管市場をカバーしている。スーナーが販売する油井管の半分はUSスチールから調達している。CDBSのパートナーで大手鋼材流通のワージントン・インダストリーズとUSスチールが共同運営するコイルセンター事業群のうち、ミシガン州のジャクソン工場を22年に買収しており、USスチールとの関係はさらに深まっている」
――DXやGXをリードするトレードの機能強化の進捗状況は。
「市場環境が刻々と変化する中、マーケットインの発想で、鉄鋼業界の未来に貢献する付加価値の創出と深化に取り組んでいく。カーボンニュートラルの大きな潮流への対応、デジタルを駆使した鉄鋼流通のソリューション提供にも取り組んでいく」
――GXについて。
「サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量を算定し、可視化して分析するクラウドサービスを提供する脱炭素トータルソリューション『MIeCO₂』をNTTコミュニケーションズ、環境情報開示システムのウェイストボックスとの3社共同事業として23年9月に立ち上げた。採用実績がここにきて加速しており、大手中堅企業を中心に120社以上の企業に導入いただいている」
――採用を増やしている。
「総合職は20人前後の採用を続けてきた。実績は21年4月が18人、22年は14人、23年が25人。24年が29人、25年は47人。一般職は24年が23人、25年は33人。中途採用は24年実績が12人となった」
 ――本年5月、本社を東京駅前に移転し、長期ビジョンの実現に向けて新たな舞台を設けた。
――本年5月、本社を東京駅前に移転し、長期ビジョンの実現に向けて新たな舞台を設けた。
「東京駅八重洲口に直結しており、国内外からのアクセスが改善した。社内のコミュニケーションを充実させるためレイアウトを工夫し、2フロアに分かれていた営業を34階の1フロアに集約。景色が素晴らしい窓側にはミーティングにも使えるフリースペースを数多く設置した。管理部門が33階に入り、32階は共有スペースとして応接室や会議室を増やした。内階段を設置し、社員は3フロアを自由に行き来することができる。内階段を囲むように設置した『MISIカフェ』は100人程度が同時利用可能で、組織の垣根を越えた交流の場としての有効利用と成果を期待している」
――第7次中計の3年間の連結純利益は626億円、955億円、803億円で、為替や鋼材価格にある前提を置いた基礎収益力を分析し、第8次中計では基礎収益力で200億円の上積みを目指している。
「24年度は連結純利益が前年度比36%減の514億円だった。北米の鋼管市況の下落と建材事業の減益、中国のデフレ輸出による海外鋼材市況の下落などが重なった。収益が5328億円減の3兆2111億円、売上総利益が371億円減の2305億円となり、人件費の増加や為替影響による販管費の増加によって営業利益は477億円減の897億円にとどまった」
――25年度の市場環境と収益改善策について。
「中国のホットコイル輸出価格はトン500ドルを切るレベルが続き、いずれ破綻すると見ていた。ところが現地鉄鋼メーカーの1-3月の業績が原料安要因で改善しており、中国の安値輸出と海外鋼材市況低迷はしばらく続く可能性がある。米国トランプ政権の関税政策の影響もあって世界中に輸入制限措置が広がっており、相対的に価格が高値で安定している日本市場に中国材が流入してくるリスクが高まっている。厳しい環境が続く見通しだが、基礎収益力の強化に引き続き注力する。本年度はトレードを起点とした成長投資案件の発掘を続け、リスク管理をさらに徹底し、新たに既存取引の利益率改善に取り組む。既存取引については、加工・物流を含めコストが大幅に上がっている。コスト削減など自助努力を重ねる一方で、健全なサプライチェーンを維持・拡充するため適正な加工賃や物流費についてはご負担いただくよう丁寧な説明を続けていく」
――商社にとって売上総利益率はひとつの経営指標となる。
「米国鉄鋼流通大手のワージントンやリライアンスは総利益率が20%を超えている。同じ目線で比較すると当社はかつての7%台から6%台に低下している。売上高が3兆円を超えており、総利益率を1%改善すれば300億円超の利益回復が可能となる。加工や物流でスポットに特別対応をすることがあるが、それらは無償のサービスではなく、付加価値であることへの理解と対価を求めていく」
――財務体質は健全。
「24年度末の自己資本比率は33・1%と1年前の29・9%から改善して30%を超え、ネットDERは1・14倍から0・95倍と1倍を切った。ヒューストンに新設した北米の財務統括会社による資金運用が借入金の削減に寄与しており、海外の他地域にも横展開していく」
――2030年代に向けての課題と展望を。
「長期ビジョンの実現に向けて、高度な専門性に加えて、グローバルな視野、ビジネスをコーディネートする総合力を備えた経営人材、世界で戦える人材を育成していく必要がある。若手社員の事業会社への出向、30歳代の海外事業会社の社長への登用などストレッチ・アサインメントなどを実施。課長級以上は全員、ハーバードを始めとするビジネススクールに、1カ月から半年の短期で参加している。総合職600人のうち昨年は35人を派遣している。DX関連では、ディープテック、フィンテック、AIなどへの投資・支援を行う、スパイラル・キャピタル・ジャパン・ファンドの3号投資事業有限責任組合に出資し、スタートアップやベンチャー企業が持つシーズを活用した鉄鋼流通改革や新規事業の創出に取り組んでいる。また伊藤忠テクノロジーベンチャーズが運営するITやディープテックなどのセクターに投資する6号投資事業有限組合にも出資した。これらの出資を通じて、オープンイノベーションを加速し、トレードの競争力向上、高付加価値ソリューションの提供を目指していく。また、ITツールによる業務改革を推進する狙いで立ち上げた社内コンテスト『BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)CUP』による成果が大きく広がっており、取引先の業務改善にも寄与する提案を高く評価している。先進国は人口減少による労働力不足が深刻化していく。地球温暖化対策は、欧米中心に動きが鈍化しているものの大きな流れとしては変わらない。建設分野で事業を広く展開する米国では、省人化、工期短縮につながる部材や設計デザイン、ソフトウェアなどの開発に着手。欧州のサブシー・マイクロパイルズは、再生可能エネルギーとして期待される浮体式洋上風力のコスト低減、短工期化に貢献できると見込んで先行投資した。10年先を見据えた戦略投資を続けていく」(谷藤 真澄)

「得意としてきたトレード中心のビジネスの延長線上の発想では、ビジョンの実現は不可能。事業投資に対する社員の意識改革を全社運動として展開し、ビジネスモデルを大きく転換させていく」
――ビジョン実現のファーストステージとして第8次中期経営計画(24―26年度)を推進している。
「『Trade×Investment』をスローガンとし、市況や為替に左右されない基礎収益力の強化、DXやGXをリードするトレードの機能強化、次世代のMISI(伊藤忠丸紅鉄鋼)を担う人材の育成の三つの重点施策に取り組んでいる」
――いかに基礎収益力を強化していくのか。
「トレードで培った知見と人脈を活かして、戦略的投資の機会を創出し、厳選した上で実行し、投資リターンを中心とする収益力を底上げしていく。5つの営業本部に昨年4月1日付で『開発室』をそれぞれ設置して専任者を配置。併せて営業本部、海外現地法人の投資案件の発掘をバックアップする『投資推進チーム』を事業総括部に設置し、M&Aのスキルを持った社外人材を迎え入れて、投資リスクの低減と早期収益化を図っていく。足下の収益拡大に直結する投資、将来の種まきとしての先行投資を同時に本格化している」
――社員の意識をどう変えていく。
「社員には目線を上げて、取引先の経営層と需給や業界構造の変化に関する議論を重ねながら信頼関係を構築し、事業投融資や合弁事業の機会創出に取り組んでいくよう指示している。事業投資意識を高めるための社長主催の勉強会を開始。長期ビジョンや中計の位置づけから、投資機会のチャンスとリスクに関する研修を役員、本部長、部長級と開催し、30歳以上の全社員を対象に続けていく。社内教育制度、事業会社への派遣、海外留学などを通じて、個人の意識改革を風土改革へと結び付けていく」
――成長投資のターゲット分野、地域は。
「鉄鋼流通事業、建材製造などの川下分野、サプライチェーンの機能強化につながる事業、カーボンニュートラル対応の4つをターゲット分野に設定。北米、欧州、豪州、日本など先進国と、インド、中東、アフリカの成長市場で投資案件を発掘していく」
――欧州ではスペインの鋼板メーカーに出資するなど積極投資を展開している。
「スペインの独立系最大手のネットワーク・スチール・リソーシズに出資し、持分法適用会社とした。NSRは、イベリア半島の7カ所にカラー鋼板や亜鉛鉄板など建設鋼材の製造・加工・販売拠点を持ち、年間100万トン規模のサプライチェーンを構築している。今回の出資を通じて欧州における事業領域を大きく拡大していく」
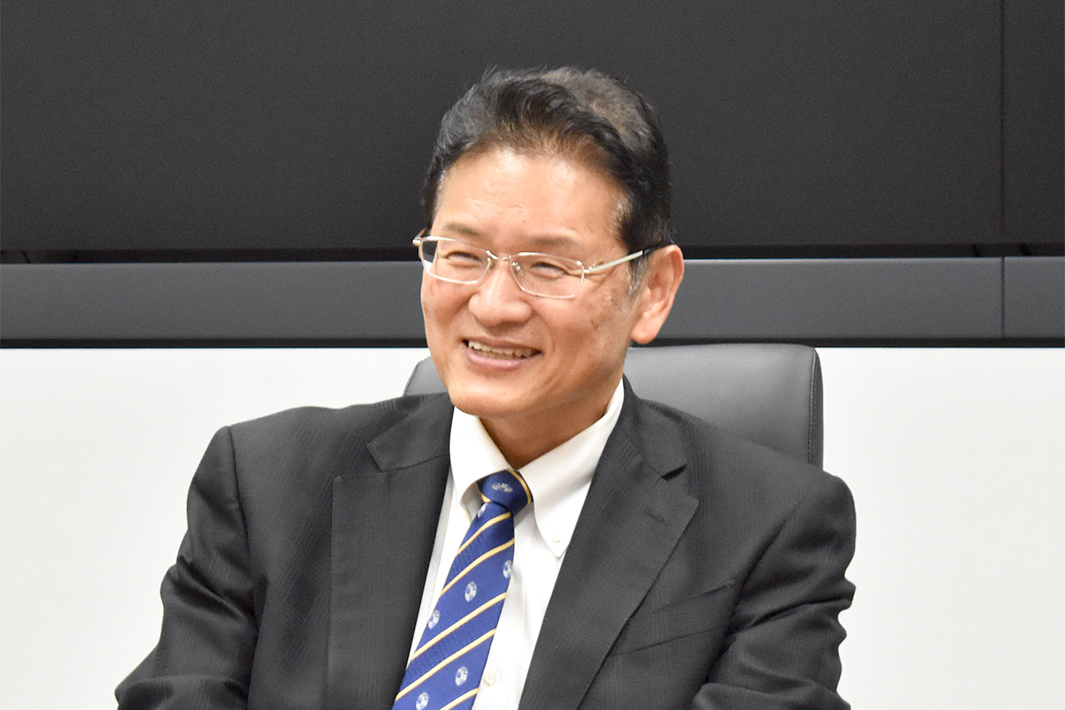 ――スコットランドの厚板加工会社を買収した。
――スコットランドの厚板加工会社を買収した。「先行して買収した英国の建設・インフラ・エネルギー用鋼材の加工・流通企業、バークレイ&マシソン(B&M)を通じて、アンガス社の全株式を24年10月に取得した。アンガス社は、グラスゴー近郊の拠点に、最新鋭の厚板加工設備を保有し、高強度鋼板の加工・在庫販売を行っている。B&Mと協業しながら、スコットランド、北部イングランドを中心に石油・ガス、再生エネルギー関連マーケットでビジネスを拡大していく」
――アイルランドの洋上風力関連部材メーカーにも出資した。
「サブシー・マイクロパイルズは、スコットランドを中心に洋上風力や石油・ガス掘削用リグ向けの係留アンカーの開発・製造・据え付けサービスを提供。巨大な碇やチェーンで構成しているアンカーを大幅に軽量化し、作業船を含めたコストの低減と短工期化を実現する特許技術を保有している。スコットランド国立投資銀行と共同出資し、欧州で普及が加速する浮体式洋上風力向けビジネスを拡充していく」
――米国では建材の川下事業投資を実施した。
「現地の建材会社CDBSを通じて、オクラホマ州のスタッズ・アンリミテッドを買収した。CDBSは、中西部、西海岸などに15拠点を持ち、商業施設などの建築用スチールフレームで全米の4割強のシェアを握っている。スタッズの買収は、人口増加が見込まれる南西部の製造拠点を確保するのが狙い」
――インドは総代表ポジションを新設した。
「インドは人口増加に伴い鉄鋼需要が2億トン、3億トンへ拡大すると期待されている。中国の鋼材輸出の影響を受けにくい政治事情もあって、需給がバランスし、マーケットは安定している。現地高炉大手のJSWスチールとは自動車鋼板用のコイルセンターを4カ所で展開しているが、年間取扱量が100万トンを超えて、追加の設備投資が検討課題になっている。TWBやメカニカルチューブ、電磁鋼板の現地事業も展開している。インド総代表が現地企業トップとの信頼関係を強化しながら、ビジネスチャンスを大きく拡充していく」
――中東、アフリカ市場へのアプローチも加速している。
「ケニアにナイロビ支店を設立し、ドバイに中東現地法人を開設した。インドに加え、中東、アフリカへのサプライチェーン、市場開拓を進めていく」
――国内ではコイルセンターの再編の検討を開始した。
「広島県にあるマツダスチールと紅忠サミットコイルセンターの事業統合の検討を開始している。いずれも住友商事グローバルメタルズとの共同出資会社で、多様化する社会の課題に対して柔軟に対応する。国内の鋼材需要の縮小を見据え、メーカー系、商社系、オーナー系を問わず健全な市場を維持するための加工・物流機能の再編を進めていく」
――本年度の投資テーマは。
「中計3年間の投融資はとくに枠を設定せず、あらゆる成長機会を探っていく。大きな事業基盤を持つ北米では川下分野の事業拡張を検討していく」
――USスチールは重要なビジネスパートナー。
「北米では、米国のスーナーとCTAP、カナダのトライマークが問屋機能を持って油井管市場をカバーしている。スーナーが販売する油井管の半分はUSスチールから調達している。CDBSのパートナーで大手鋼材流通のワージントン・インダストリーズとUSスチールが共同運営するコイルセンター事業群のうち、ミシガン州のジャクソン工場を22年に買収しており、USスチールとの関係はさらに深まっている」
――DXやGXをリードするトレードの機能強化の進捗状況は。
「市場環境が刻々と変化する中、マーケットインの発想で、鉄鋼業界の未来に貢献する付加価値の創出と深化に取り組んでいく。カーボンニュートラルの大きな潮流への対応、デジタルを駆使した鉄鋼流通のソリューション提供にも取り組んでいく」
――GXについて。
「サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量を算定し、可視化して分析するクラウドサービスを提供する脱炭素トータルソリューション『MIeCO₂』をNTTコミュニケーションズ、環境情報開示システムのウェイストボックスとの3社共同事業として23年9月に立ち上げた。採用実績がここにきて加速しており、大手中堅企業を中心に120社以上の企業に導入いただいている」
――採用を増やしている。
「総合職は20人前後の採用を続けてきた。実績は21年4月が18人、22年は14人、23年が25人。24年が29人、25年は47人。一般職は24年が23人、25年は33人。中途採用は24年実績が12人となった」
 ――本年5月、本社を東京駅前に移転し、長期ビジョンの実現に向けて新たな舞台を設けた。
――本年5月、本社を東京駅前に移転し、長期ビジョンの実現に向けて新たな舞台を設けた。「東京駅八重洲口に直結しており、国内外からのアクセスが改善した。社内のコミュニケーションを充実させるためレイアウトを工夫し、2フロアに分かれていた営業を34階の1フロアに集約。景色が素晴らしい窓側にはミーティングにも使えるフリースペースを数多く設置した。管理部門が33階に入り、32階は共有スペースとして応接室や会議室を増やした。内階段を設置し、社員は3フロアを自由に行き来することができる。内階段を囲むように設置した『MISIカフェ』は100人程度が同時利用可能で、組織の垣根を越えた交流の場としての有効利用と成果を期待している」
――第7次中計の3年間の連結純利益は626億円、955億円、803億円で、為替や鋼材価格にある前提を置いた基礎収益力を分析し、第8次中計では基礎収益力で200億円の上積みを目指している。
「24年度は連結純利益が前年度比36%減の514億円だった。北米の鋼管市況の下落と建材事業の減益、中国のデフレ輸出による海外鋼材市況の下落などが重なった。収益が5328億円減の3兆2111億円、売上総利益が371億円減の2305億円となり、人件費の増加や為替影響による販管費の増加によって営業利益は477億円減の897億円にとどまった」
――25年度の市場環境と収益改善策について。
「中国のホットコイル輸出価格はトン500ドルを切るレベルが続き、いずれ破綻すると見ていた。ところが現地鉄鋼メーカーの1-3月の業績が原料安要因で改善しており、中国の安値輸出と海外鋼材市況低迷はしばらく続く可能性がある。米国トランプ政権の関税政策の影響もあって世界中に輸入制限措置が広がっており、相対的に価格が高値で安定している日本市場に中国材が流入してくるリスクが高まっている。厳しい環境が続く見通しだが、基礎収益力の強化に引き続き注力する。本年度はトレードを起点とした成長投資案件の発掘を続け、リスク管理をさらに徹底し、新たに既存取引の利益率改善に取り組む。既存取引については、加工・物流を含めコストが大幅に上がっている。コスト削減など自助努力を重ねる一方で、健全なサプライチェーンを維持・拡充するため適正な加工賃や物流費についてはご負担いただくよう丁寧な説明を続けていく」
――商社にとって売上総利益率はひとつの経営指標となる。
「米国鉄鋼流通大手のワージントンやリライアンスは総利益率が20%を超えている。同じ目線で比較すると当社はかつての7%台から6%台に低下している。売上高が3兆円を超えており、総利益率を1%改善すれば300億円超の利益回復が可能となる。加工や物流でスポットに特別対応をすることがあるが、それらは無償のサービスではなく、付加価値であることへの理解と対価を求めていく」
――財務体質は健全。
「24年度末の自己資本比率は33・1%と1年前の29・9%から改善して30%を超え、ネットDERは1・14倍から0・95倍と1倍を切った。ヒューストンに新設した北米の財務統括会社による資金運用が借入金の削減に寄与しており、海外の他地域にも横展開していく」
――2030年代に向けての課題と展望を。
「長期ビジョンの実現に向けて、高度な専門性に加えて、グローバルな視野、ビジネスをコーディネートする総合力を備えた経営人材、世界で戦える人材を育成していく必要がある。若手社員の事業会社への出向、30歳代の海外事業会社の社長への登用などストレッチ・アサインメントなどを実施。課長級以上は全員、ハーバードを始めとするビジネススクールに、1カ月から半年の短期で参加している。総合職600人のうち昨年は35人を派遣している。DX関連では、ディープテック、フィンテック、AIなどへの投資・支援を行う、スパイラル・キャピタル・ジャパン・ファンドの3号投資事業有限責任組合に出資し、スタートアップやベンチャー企業が持つシーズを活用した鉄鋼流通改革や新規事業の創出に取り組んでいる。また伊藤忠テクノロジーベンチャーズが運営するITやディープテックなどのセクターに投資する6号投資事業有限組合にも出資した。これらの出資を通じて、オープンイノベーションを加速し、トレードの競争力向上、高付加価値ソリューションの提供を目指していく。また、ITツールによる業務改革を推進する狙いで立ち上げた社内コンテスト『BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)CUP』による成果が大きく広がっており、取引先の業務改善にも寄与する提案を高く評価している。先進国は人口減少による労働力不足が深刻化していく。地球温暖化対策は、欧米中心に動きが鈍化しているものの大きな流れとしては変わらない。建設分野で事業を広く展開する米国では、省人化、工期短縮につながる部材や設計デザイン、ソフトウェアなどの開発に着手。欧州のサブシー・マイクロパイルズは、再生可能エネルギーとして期待される浮体式洋上風力のコスト低減、短工期化に貢献できると見込んで先行投資した。10年先を見据えた戦略投資を続けていく」(谷藤 真澄)














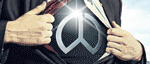
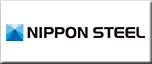
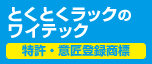
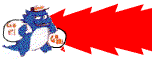

















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ