2025年6月25日
商社の経営戦略 10年先を見据えて/阪和興業 中川洋一社長/重点領域で新供給網創出/構造変化、鋼材流通の再編リード
――2030年度以降を見据え、「鉄鋼商社からサプライチェーン創造型商社への変革」に取り組んでいる。
「ウクライナ、中東、米中対立、台湾問題など緊迫する国家間情勢や関税政策の応酬などサプライチェーンの分断リスクが高まっている。地球温暖化対策やそれに伴う需要構造変化が進展しており、社会や企業のニーズもダイナミックに変化している。鉄鋼主力商社として鋼材や原材料のトレードの機能拡充に注力してきたが、不確実性が高まる中、あらゆるビジネスのサプライチェーンの創造に挑むことで企業としての成長を続け、同時に持続可能な社会の実現に貢献する存在を目指していく」
――第2フェーズとなる「第10次中期経営計画」(23-25年度)では、「経営基盤の強化」「事業戦略の発展」「投資の収益化」の3つの基本方針を前中計から継承し、連結経常利益700億円を目標にかかげている。
「経常利益は初年度482億円、24年度597億円で、25年度予想を550億円に設定した。中国の鉄鋼過剰生産・輸出の長期化によって国際鉄鋼市場環境が悪化。トランプ大統領が過激な関税政策を発動し、世界経済は大混乱に陥っている。日本国内も人手不足や物流問題、資材費高騰などを背景に鋼材需要の回復が遅れている。3年前の前提条件に比べて外部環境は想定外の状況で総じて悪い方向に大きく振れているが、24年度は経常利益を100億円規模で上乗せできた。今中計の定量目標の700億円の実現は難しい状況だが、成長投資による収益拡大、事業ポートフォリオの拡充、リスクマネジメント強化など定性面の取り組み、及び将来への種まきについては手応えを得ている」
――確かに事業ポートフォリオの拡充が収益を押し上げている。
「主力の鉄鋼が24年度でいうと経常利益331億円と全社利益の5割以上をしっかり稼いでいる。石油製品やバイオマス燃料が柱となるエネルギー・生活資材は100-120億円規模へ拡大。中国やアジアで鉄鋼、リサイクル関連ビジネスを展開する海外販売子会社は70-80億円に成長。輸入木材などの住宅資材、レジャー施設や産業機械がメインのその他事業も20-30億円規模に育ってきている。相場商品を扱うため変動が大きかったプライマリーメタル、リサイクルメタル、食品も収益が安定してきた」
――中計3年間で800億円の投融資を計画する。
「投資の収益化、キャッシュの創出力強化という観点で、鉄鋼をはじめとする『既存ビジネス』への投資を引き続き積極展開している。併せて新たなサプライチェーンを創出する狙いで、『環境配慮型資源ビジネス』『二次電池関連ビジネス』『高付加価値加工品ビジネス』『地産地消ビジネス』を重点領域に設定し、既存ビジネスとのシナジーも織り込みながら投資を本格化している。23年度が156億円、24年度は321億円の投資を実行しており、戦略的に投資を続けていく」
――「既存ビジネス」への投資では、兼松トレーディングの株式を4月に取得した。
「兼松トレーディングとその子会社で厚板溶断の協和スチール、チタン製品販売の永和金属、サッシ・建具製造の建鋼社、協和スチール子会社の協和運輸をグループ化した。阪和興業は、鉄鋼流通加工ビジネスを経営の一丁目一番地として継続・拡大しており、兼松トレーディングの事業価値を最大化できるベストオーナーであると判断。今回の株式取得は、鋼材流通の再編をリードしていく決意の狼煙であり、その成果とシナジーを引き出し、次の展開に結びつけていく」
 ――国内の鉄鋼需要は縮小傾向にある。
――国内の鉄鋼需要は縮小傾向にある。
「鉄鋼メーカーが先行して生産設備の集約を加速している。鉄鋼需要構造の大きな変化も見込まれる中、鉄鋼流通企業として、新たなサプライチェーンの創造に積極果敢に取り組み、業界をリードしていく。関東における条鋼流通については、習志野にある阪和流通センターの水深12㍍の岸壁を有効活用し、西日本からの船便による大型形鋼を荷揚げし、阪和ダイサンやグループ化した田中鉄鋼販売を通じてスピーディーに販売するサプライチェーンを構築した。本社の新・基幹システム稼働に続いて、グループ全体で在庫・加工・物流に関する情報・データの共有・効率化を進めていく」
――トレーラーハウスデベロップメントへも一部出資した。
「鋼板など資材・加工品の安定供給に加えて、トレーラーハウスの販売面でも協業していく。災害時対応に加えて、レジャー・ホテル業界への拡販を見込んでいる」
――鉄骨工事、屋根壁工事の現場施工管理会社、エスケーエンジニアリングの社名を変更した。
「建築士や建築施工管理技士、鉄骨製作管理技術者はじめ数多くの資格保有者を東名阪、東北、九州の拠点に配置し、幅広い物件で実績を積み重ねてきた。これに、レジャー部門で独自に雇用していた専門部隊を統合。社名を阪和エンジニアリングとすることで阪和グループの機能会社であることを前面に押し出し、グループ全体でのシナジーを追求していく」
――住宅資材部を立ち上げた。
「木材事業は年間売上高が1000億円規模になってきた。プレハブメーカーやパワービルダーなど住宅向けの木製・鋼製部材をワンストップで供給する態勢を整えた。住宅用の輸入木材ではトップグループにあり、住宅分野向けの基礎鉄筋など鋼製部材の拡販も進めている」
――東邦亜鉛と業務提携契約を結んだ。
「電気鉛、鉛合金で国内トップシェアを誇る東邦亜鉛とは、原料・製品両面で長年の取引関係にある。精鉱などの一次原料やリサイクル原料の安定供給、製品の販売ルート拡大などで協業関係を強化していく」
――新たなサプライチェーンを創出するテーマのひとつ「地産地消ビジネス」のコンセプトは。
「例えばASEANでは『東南アジアに第二の阪和を』をテーマに国内同様のビジネスモデルで事業を拡充してきている。とくにインドネシアでは鉄鋼、プライマリーメタル、リサイクルメタル、食品、エネルギーなどがすでに幅広いビジネスを展開している」
――そのインドネシアにおける事業内容を。
「阪和インドネシアの社員はローカルスタッフを含め250人に達している。世界最大のステンレスメーカーとなった中国の青山実業グループがスラウェシ島で展開するニッケル銑鉄、ステンレス精練・圧延事業に出資し、原料調達から製品販売に参画している。中国最大のリサイクル企業であるGEM、世界最大の電池メーカーであるCATLグループ企業や青山実業との合弁事業で高純度ニッケル・コバルト化合物を一貫生産するQMBニューエナジー・マテリアルズにも参画。鉄鋼ビジネスでは、中国の徳龍鋼鉄との合弁、徳信鋼鉄がスラウェシ島で高炉3基体制を確立し、ビレット、丸棒、線材、スラブを現地生産している」
――現地事業をさらに拡充している。
「大和工業が、現地メーカーの事業を分割・継承する形で立ち上げたガルーダ・ヤマト・スチールに15%出資した。年産100万トンの電炉・形鋼ミルで、インドネシアにおける地産地消に対する調達・販売能力を大幅に強化できた」
――現地で米(こめ)ビジネスも本格化した。
「精米加工・販売会社を現地の食品流通大手と設立した。現地に進出する日系スーパーやレストランのジャポニカ米需要に応えるもので、水産加工品とのシナジーも引き出しながら、食品事業における地産地消ビジネスを拡充していく」
――ジャカルタ先物取引所へのメンバー登録の狙いを。
「インドネシアは錫地金の世界の供給の2割を占める重要なソースとなっており、先物取引所に登録することで錫の安定調達を図る」
――広い事業基盤を持つ中国における事業戦略は。
「売上高は伸びているが、利益面では苦戦している。上海の現地法人を拠点に、蘇州、東莞、広州などで鋼材加工ビジネスを継続している。世界最大の市場で、大明国際など現地の大手加工・流通との協業をベースとした地産地消ビジネスを拡大していく。中国企業とのビジネスをアフリカや中東の市場開拓にも結び付けていきたいと考えている」
――「環境配慮型資源ビジネス」について。
「バイオマス・リサイクル燃料、RPF(古紙・廃プラ固形燃料)など再資源化資源のサプライチェーンの拡充を進めている。日本製鉄、JFEスチールなど高炉メーカーの電炉プロセス導入による冷鉄源需要の拡大を見据えたサプライチェーンの創出も進めている。新設した製鉄資源部が中心となってグループ会社や納入先からのリターンスクラップの回収・調達を拡大している。建設リサイクル営業部が請け負う風力発電設備、石油精製プラントなど大型構造物の解体事業からのスクラップ調達も強化している」
――HBI(ホット・ブリケット・アイアン)のソースを獲得した。
「このほど一部出資したシンガポールのグリーン・イ―・スチールが、マレーシアで年産80万トン規模の直接還元鉄プラントを操業しており、HBIの販売権の一部を取得した。同社は低品位の鉄鉱石を使いこなす選鉱技術を保有しており、エネルギーコストを含め高い競争力に期待しており、東マレーシアで計画中の年産250万トンの新工場からの販売権も獲得し取扱いを増やしていく。マレーシアでは、一部出資するOMホールディングスが水力によるグリーン電力でフェロシリコンやマンガン系合金鉄を生産している」
――バイオマス燃料のサプライチェーンも拡充している。
「インドネシアなどでPKS(パーム椰子殻)や木質ペレットを調達し、日本国内の電力会社へ長期契約で納入している。PKS輸入は24年度が115万トン、25年度は120万トンを計画しており、国内トップシェアを伸ばしている。安定供給とフレート対策を目的とする3隻の専用船が就航している」
――「高付加価値加工品ビジネス」への投資について。
「産業機械強化のために、静岡県内に本社工場を持ち、鋼材や木材の加工機械を製造・販売するシンクスの株式100%を取得した。コラムやH型鋼、厚板の開先加工機、木材のランニングソーの分野で高いシェアを握り、国内13カ所にサービス拠点を展開している。人手不足による加工機械の自動化、省力化ニーズが高まる中、阪和興業グループのネットワークを通じて国内外にサプライチェーンを広げるとともに、メンテナンス関連ビジネスへの本格参入も図る。住宅建材分野における鋼材・木材の拡販でもシナジーを追求していく」
 ――航空宇宙マネジメントシステム規格を取得した。
――航空宇宙マネジメントシステム規格を取得した。
「『AS9120B』は航空宇宙産業のサプライチェーンにおける品質を確保する国際規格。欧米を中心とした航空宇宙関連企業向けに金属素材を供給する新たなビジネスを開拓していく」
――食品事業でも投資を実施した。
「稚内のマルゴ福山水産の株式80%を取得した。ホタテなど北海道の海産物を冷凍加工販売している。輸入品のトレード主体のビジネスから脱却すべく加工機能の強化、国産加工品の輸出など高付加価値化を図りながら新たなサプライチェーンを創出していく」
――ゲームセンター事業を展開するハローズは3月に全株式を譲渡した。
「事業ポートフォリオの見直しを進める中で、ハローズの事業については、ベストオーナーになり得ないと判断し、知見やノウハウを蓄積する企業に譲り渡すことを決めた」
――北米、インドは鉄鋼ビジネスを含めて成長余地を大きく残す。
「米国の事業としてはサンディエゴにコイルセンターを保有するが、金属スクラップや合金鉄のトレード中心だ。米国、カナダではブラックマスなど電池資源関連ビジネスの拡充を進めている。インドは現地からの合金鉄の輸出がメインで、ムンバイ、ニューデリー、チェンナイの現地法人による市場開拓を進めている。日本製鉄、JFEスチールはじめ日本の鉄鋼メーカーが米国、インドの現地事業を拡大しており、鉄鋼やプライマリーメタル、リサイクルメタルの資源ソースを活用しながら新たなサプライチェーンを創出していきたい」
――欧州でも市場開拓を進めている。
「ロンドン支店を現地法人化し、イタリアでも営業機能を強化している。グリーン鋼材の日本からの輸入に加え、海外材の調達先を増やしながらサプライチェーンの創出を進めていく」
――「第10次中計」では、ROE(株主資本利益率)12%以上、ネットDER1倍以下などの財務目標を掲げている。
「ROEは12.4%、DERも0・8倍で目標を達成している」
―—東証プライム上場企業としてPBR(株価純資産倍率)1倍以上が必達目標。
「PER(株価収益率)は5倍超まで改善しているが、PBRは0・5倍を超えたところで伸び悩んでいる」
――株主還元方針を大きく転換した。
「株主資本に対する配当を示すDOE2・5%を下限とする安定的で累進的な配当政策を打ち出した。1株当たりの配当額は、成長投資を優先してきた前中計が20年度60円、21年度100円、22年度130円。今中計は23年度185円、24年度225円で、25年度は250円を予想しており、DOEは3%程度となる。政策保有株式の売却による追加的な利益やキャッシュインも踏まえ、自己株式取得についても24年度は20億円、25年度は50億円を予定している」
――次期中計で目指す財務指標は。
「経常利益700億円以上、自己資本5000億円、PBR1倍以上の三つを明確な目標としたい。自己資本は3800億円を超えており、利益を積み上げていくことで達成できる。課題はPBR1倍以上であり、次期中計における事業戦略の発展と投資の収益化による成果を業績にしっかり反映させていく。安定的で累進的な配当政策を軸とした株主還元方針の株式市場における理解・浸透に努めていく。次期中計以降で経常利益1000億円も目指していく」
――事業拡大に伴い、高水準の採用を続けている。
「新卒者の採用は23年度119人、24年度129人、25年度98人で、26年度も100人前後を見込んでいる。中途採用は23年度118人、24年度76人だった」
――採用した人材の育成も重要。
「『サプライチェーン創造型商社への変革』を実現するには、『人材』が最も大事な経営基盤となる。『PROFESSIONAL&GLOBAL』という人材像を掲げ、社員一人ひとりが専門性を磨き、自ら考え行動してビジネスを創造し、国内外問わず活躍できる人材の育成に取り組んでいる。その一環として開校した企業内大学『HANWA BUSINESS SCHOOL(HKBS)』が3年目を迎え、多様な人材の育成に寄与している。人事制度とも密に連携しており、スクール内のカリキュラムの受講を昇格の条件としており、学ぶことの動機づけやモチベーションの向上に直結させ、成長意欲がある人が評価されるフェアな人事制度の実現にもつなげている」
――HKBSの概要を。
「学長は篠山専務、副学長が松原専務、本田常務、鶴田執行役員で、学部長は部長級が務め、企画や運営は現場の社員が関わっている。文学部、理工学部、経営学部、キャリアデザイン学部、外国語学部、商学部、法学部、教養学部の8学部で構成。WEB講座中心で、対面講座もあり、所属部署や職種に関係なく関心がある学部の口座を受講できる。自分から学ぶ環境・風土を醸成し、現場ですぐに役立つ実学をベースとして社員同士の学び合いも促進している」
――各学部の内容は。
「例えば商学部は経理・財務、貿易実務などの知識を体系的に習得できるカリキュラムを設定。法学部は与信管理、債権保全、契約実務などを学ぶことができる」
――社員研修について。
「新入社員研修、OJT、新人フォローアップ研修に加えて、希望者には海外事務所で実務を学ぶ6カ月間の海外トレーニー研修、海外大学で学ぶ1年間の海外語学留学研修や国内MBA派遣を実施している」
――評価制度にROICを取り入れるなど透明性を高めてきている。
「トレーダーとして数量やシェアを重視しているが、同時にスプレッドや利益額、さらに資本コストや株価を意識させるためROICを一つの経営指標として導入した。国内需要が縮小する中、社員のマインドをリセットする狙いもある。ROICについては事業の特性を考慮し、結果のみならず工夫や努力などプロセスも評価する制度としていく」(谷藤 真澄)

「ウクライナ、中東、米中対立、台湾問題など緊迫する国家間情勢や関税政策の応酬などサプライチェーンの分断リスクが高まっている。地球温暖化対策やそれに伴う需要構造変化が進展しており、社会や企業のニーズもダイナミックに変化している。鉄鋼主力商社として鋼材や原材料のトレードの機能拡充に注力してきたが、不確実性が高まる中、あらゆるビジネスのサプライチェーンの創造に挑むことで企業としての成長を続け、同時に持続可能な社会の実現に貢献する存在を目指していく」
――第2フェーズとなる「第10次中期経営計画」(23-25年度)では、「経営基盤の強化」「事業戦略の発展」「投資の収益化」の3つの基本方針を前中計から継承し、連結経常利益700億円を目標にかかげている。
「経常利益は初年度482億円、24年度597億円で、25年度予想を550億円に設定した。中国の鉄鋼過剰生産・輸出の長期化によって国際鉄鋼市場環境が悪化。トランプ大統領が過激な関税政策を発動し、世界経済は大混乱に陥っている。日本国内も人手不足や物流問題、資材費高騰などを背景に鋼材需要の回復が遅れている。3年前の前提条件に比べて外部環境は想定外の状況で総じて悪い方向に大きく振れているが、24年度は経常利益を100億円規模で上乗せできた。今中計の定量目標の700億円の実現は難しい状況だが、成長投資による収益拡大、事業ポートフォリオの拡充、リスクマネジメント強化など定性面の取り組み、及び将来への種まきについては手応えを得ている」
――確かに事業ポートフォリオの拡充が収益を押し上げている。
「主力の鉄鋼が24年度でいうと経常利益331億円と全社利益の5割以上をしっかり稼いでいる。石油製品やバイオマス燃料が柱となるエネルギー・生活資材は100-120億円規模へ拡大。中国やアジアで鉄鋼、リサイクル関連ビジネスを展開する海外販売子会社は70-80億円に成長。輸入木材などの住宅資材、レジャー施設や産業機械がメインのその他事業も20-30億円規模に育ってきている。相場商品を扱うため変動が大きかったプライマリーメタル、リサイクルメタル、食品も収益が安定してきた」
――中計3年間で800億円の投融資を計画する。
「投資の収益化、キャッシュの創出力強化という観点で、鉄鋼をはじめとする『既存ビジネス』への投資を引き続き積極展開している。併せて新たなサプライチェーンを創出する狙いで、『環境配慮型資源ビジネス』『二次電池関連ビジネス』『高付加価値加工品ビジネス』『地産地消ビジネス』を重点領域に設定し、既存ビジネスとのシナジーも織り込みながら投資を本格化している。23年度が156億円、24年度は321億円の投資を実行しており、戦略的に投資を続けていく」
――「既存ビジネス」への投資では、兼松トレーディングの株式を4月に取得した。
「兼松トレーディングとその子会社で厚板溶断の協和スチール、チタン製品販売の永和金属、サッシ・建具製造の建鋼社、協和スチール子会社の協和運輸をグループ化した。阪和興業は、鉄鋼流通加工ビジネスを経営の一丁目一番地として継続・拡大しており、兼松トレーディングの事業価値を最大化できるベストオーナーであると判断。今回の株式取得は、鋼材流通の再編をリードしていく決意の狼煙であり、その成果とシナジーを引き出し、次の展開に結びつけていく」
 ――国内の鉄鋼需要は縮小傾向にある。
――国内の鉄鋼需要は縮小傾向にある。「鉄鋼メーカーが先行して生産設備の集約を加速している。鉄鋼需要構造の大きな変化も見込まれる中、鉄鋼流通企業として、新たなサプライチェーンの創造に積極果敢に取り組み、業界をリードしていく。関東における条鋼流通については、習志野にある阪和流通センターの水深12㍍の岸壁を有効活用し、西日本からの船便による大型形鋼を荷揚げし、阪和ダイサンやグループ化した田中鉄鋼販売を通じてスピーディーに販売するサプライチェーンを構築した。本社の新・基幹システム稼働に続いて、グループ全体で在庫・加工・物流に関する情報・データの共有・効率化を進めていく」
――トレーラーハウスデベロップメントへも一部出資した。
「鋼板など資材・加工品の安定供給に加えて、トレーラーハウスの販売面でも協業していく。災害時対応に加えて、レジャー・ホテル業界への拡販を見込んでいる」
――鉄骨工事、屋根壁工事の現場施工管理会社、エスケーエンジニアリングの社名を変更した。
「建築士や建築施工管理技士、鉄骨製作管理技術者はじめ数多くの資格保有者を東名阪、東北、九州の拠点に配置し、幅広い物件で実績を積み重ねてきた。これに、レジャー部門で独自に雇用していた専門部隊を統合。社名を阪和エンジニアリングとすることで阪和グループの機能会社であることを前面に押し出し、グループ全体でのシナジーを追求していく」
――住宅資材部を立ち上げた。
「木材事業は年間売上高が1000億円規模になってきた。プレハブメーカーやパワービルダーなど住宅向けの木製・鋼製部材をワンストップで供給する態勢を整えた。住宅用の輸入木材ではトップグループにあり、住宅分野向けの基礎鉄筋など鋼製部材の拡販も進めている」
――東邦亜鉛と業務提携契約を結んだ。
「電気鉛、鉛合金で国内トップシェアを誇る東邦亜鉛とは、原料・製品両面で長年の取引関係にある。精鉱などの一次原料やリサイクル原料の安定供給、製品の販売ルート拡大などで協業関係を強化していく」
――新たなサプライチェーンを創出するテーマのひとつ「地産地消ビジネス」のコンセプトは。
「例えばASEANでは『東南アジアに第二の阪和を』をテーマに国内同様のビジネスモデルで事業を拡充してきている。とくにインドネシアでは鉄鋼、プライマリーメタル、リサイクルメタル、食品、エネルギーなどがすでに幅広いビジネスを展開している」
――そのインドネシアにおける事業内容を。
「阪和インドネシアの社員はローカルスタッフを含め250人に達している。世界最大のステンレスメーカーとなった中国の青山実業グループがスラウェシ島で展開するニッケル銑鉄、ステンレス精練・圧延事業に出資し、原料調達から製品販売に参画している。中国最大のリサイクル企業であるGEM、世界最大の電池メーカーであるCATLグループ企業や青山実業との合弁事業で高純度ニッケル・コバルト化合物を一貫生産するQMBニューエナジー・マテリアルズにも参画。鉄鋼ビジネスでは、中国の徳龍鋼鉄との合弁、徳信鋼鉄がスラウェシ島で高炉3基体制を確立し、ビレット、丸棒、線材、スラブを現地生産している」
――現地事業をさらに拡充している。
「大和工業が、現地メーカーの事業を分割・継承する形で立ち上げたガルーダ・ヤマト・スチールに15%出資した。年産100万トンの電炉・形鋼ミルで、インドネシアにおける地産地消に対する調達・販売能力を大幅に強化できた」
――現地で米(こめ)ビジネスも本格化した。
「精米加工・販売会社を現地の食品流通大手と設立した。現地に進出する日系スーパーやレストランのジャポニカ米需要に応えるもので、水産加工品とのシナジーも引き出しながら、食品事業における地産地消ビジネスを拡充していく」
――ジャカルタ先物取引所へのメンバー登録の狙いを。
「インドネシアは錫地金の世界の供給の2割を占める重要なソースとなっており、先物取引所に登録することで錫の安定調達を図る」
――広い事業基盤を持つ中国における事業戦略は。
「売上高は伸びているが、利益面では苦戦している。上海の現地法人を拠点に、蘇州、東莞、広州などで鋼材加工ビジネスを継続している。世界最大の市場で、大明国際など現地の大手加工・流通との協業をベースとした地産地消ビジネスを拡大していく。中国企業とのビジネスをアフリカや中東の市場開拓にも結び付けていきたいと考えている」
――「環境配慮型資源ビジネス」について。
「バイオマス・リサイクル燃料、RPF(古紙・廃プラ固形燃料)など再資源化資源のサプライチェーンの拡充を進めている。日本製鉄、JFEスチールなど高炉メーカーの電炉プロセス導入による冷鉄源需要の拡大を見据えたサプライチェーンの創出も進めている。新設した製鉄資源部が中心となってグループ会社や納入先からのリターンスクラップの回収・調達を拡大している。建設リサイクル営業部が請け負う風力発電設備、石油精製プラントなど大型構造物の解体事業からのスクラップ調達も強化している」
――HBI(ホット・ブリケット・アイアン)のソースを獲得した。
「このほど一部出資したシンガポールのグリーン・イ―・スチールが、マレーシアで年産80万トン規模の直接還元鉄プラントを操業しており、HBIの販売権の一部を取得した。同社は低品位の鉄鉱石を使いこなす選鉱技術を保有しており、エネルギーコストを含め高い競争力に期待しており、東マレーシアで計画中の年産250万トンの新工場からの販売権も獲得し取扱いを増やしていく。マレーシアでは、一部出資するOMホールディングスが水力によるグリーン電力でフェロシリコンやマンガン系合金鉄を生産している」
――バイオマス燃料のサプライチェーンも拡充している。
「インドネシアなどでPKS(パーム椰子殻)や木質ペレットを調達し、日本国内の電力会社へ長期契約で納入している。PKS輸入は24年度が115万トン、25年度は120万トンを計画しており、国内トップシェアを伸ばしている。安定供給とフレート対策を目的とする3隻の専用船が就航している」
――「高付加価値加工品ビジネス」への投資について。
「産業機械強化のために、静岡県内に本社工場を持ち、鋼材や木材の加工機械を製造・販売するシンクスの株式100%を取得した。コラムやH型鋼、厚板の開先加工機、木材のランニングソーの分野で高いシェアを握り、国内13カ所にサービス拠点を展開している。人手不足による加工機械の自動化、省力化ニーズが高まる中、阪和興業グループのネットワークを通じて国内外にサプライチェーンを広げるとともに、メンテナンス関連ビジネスへの本格参入も図る。住宅建材分野における鋼材・木材の拡販でもシナジーを追求していく」
 ――航空宇宙マネジメントシステム規格を取得した。
――航空宇宙マネジメントシステム規格を取得した。「『AS9120B』は航空宇宙産業のサプライチェーンにおける品質を確保する国際規格。欧米を中心とした航空宇宙関連企業向けに金属素材を供給する新たなビジネスを開拓していく」
――食品事業でも投資を実施した。
「稚内のマルゴ福山水産の株式80%を取得した。ホタテなど北海道の海産物を冷凍加工販売している。輸入品のトレード主体のビジネスから脱却すべく加工機能の強化、国産加工品の輸出など高付加価値化を図りながら新たなサプライチェーンを創出していく」
――ゲームセンター事業を展開するハローズは3月に全株式を譲渡した。
「事業ポートフォリオの見直しを進める中で、ハローズの事業については、ベストオーナーになり得ないと判断し、知見やノウハウを蓄積する企業に譲り渡すことを決めた」
――北米、インドは鉄鋼ビジネスを含めて成長余地を大きく残す。
「米国の事業としてはサンディエゴにコイルセンターを保有するが、金属スクラップや合金鉄のトレード中心だ。米国、カナダではブラックマスなど電池資源関連ビジネスの拡充を進めている。インドは現地からの合金鉄の輸出がメインで、ムンバイ、ニューデリー、チェンナイの現地法人による市場開拓を進めている。日本製鉄、JFEスチールはじめ日本の鉄鋼メーカーが米国、インドの現地事業を拡大しており、鉄鋼やプライマリーメタル、リサイクルメタルの資源ソースを活用しながら新たなサプライチェーンを創出していきたい」
――欧州でも市場開拓を進めている。
「ロンドン支店を現地法人化し、イタリアでも営業機能を強化している。グリーン鋼材の日本からの輸入に加え、海外材の調達先を増やしながらサプライチェーンの創出を進めていく」
――「第10次中計」では、ROE(株主資本利益率)12%以上、ネットDER1倍以下などの財務目標を掲げている。
「ROEは12.4%、DERも0・8倍で目標を達成している」
―—東証プライム上場企業としてPBR(株価純資産倍率)1倍以上が必達目標。
「PER(株価収益率)は5倍超まで改善しているが、PBRは0・5倍を超えたところで伸び悩んでいる」
――株主還元方針を大きく転換した。
「株主資本に対する配当を示すDOE2・5%を下限とする安定的で累進的な配当政策を打ち出した。1株当たりの配当額は、成長投資を優先してきた前中計が20年度60円、21年度100円、22年度130円。今中計は23年度185円、24年度225円で、25年度は250円を予想しており、DOEは3%程度となる。政策保有株式の売却による追加的な利益やキャッシュインも踏まえ、自己株式取得についても24年度は20億円、25年度は50億円を予定している」
――次期中計で目指す財務指標は。
「経常利益700億円以上、自己資本5000億円、PBR1倍以上の三つを明確な目標としたい。自己資本は3800億円を超えており、利益を積み上げていくことで達成できる。課題はPBR1倍以上であり、次期中計における事業戦略の発展と投資の収益化による成果を業績にしっかり反映させていく。安定的で累進的な配当政策を軸とした株主還元方針の株式市場における理解・浸透に努めていく。次期中計以降で経常利益1000億円も目指していく」
――事業拡大に伴い、高水準の採用を続けている。
「新卒者の採用は23年度119人、24年度129人、25年度98人で、26年度も100人前後を見込んでいる。中途採用は23年度118人、24年度76人だった」
――採用した人材の育成も重要。
「『サプライチェーン創造型商社への変革』を実現するには、『人材』が最も大事な経営基盤となる。『PROFESSIONAL&GLOBAL』という人材像を掲げ、社員一人ひとりが専門性を磨き、自ら考え行動してビジネスを創造し、国内外問わず活躍できる人材の育成に取り組んでいる。その一環として開校した企業内大学『HANWA BUSINESS SCHOOL(HKBS)』が3年目を迎え、多様な人材の育成に寄与している。人事制度とも密に連携しており、スクール内のカリキュラムの受講を昇格の条件としており、学ぶことの動機づけやモチベーションの向上に直結させ、成長意欲がある人が評価されるフェアな人事制度の実現にもつなげている」
――HKBSの概要を。
「学長は篠山専務、副学長が松原専務、本田常務、鶴田執行役員で、学部長は部長級が務め、企画や運営は現場の社員が関わっている。文学部、理工学部、経営学部、キャリアデザイン学部、外国語学部、商学部、法学部、教養学部の8学部で構成。WEB講座中心で、対面講座もあり、所属部署や職種に関係なく関心がある学部の口座を受講できる。自分から学ぶ環境・風土を醸成し、現場ですぐに役立つ実学をベースとして社員同士の学び合いも促進している」
――各学部の内容は。
「例えば商学部は経理・財務、貿易実務などの知識を体系的に習得できるカリキュラムを設定。法学部は与信管理、債権保全、契約実務などを学ぶことができる」
――社員研修について。
「新入社員研修、OJT、新人フォローアップ研修に加えて、希望者には海外事務所で実務を学ぶ6カ月間の海外トレーニー研修、海外大学で学ぶ1年間の海外語学留学研修や国内MBA派遣を実施している」
――評価制度にROICを取り入れるなど透明性を高めてきている。
「トレーダーとして数量やシェアを重視しているが、同時にスプレッドや利益額、さらに資本コストや株価を意識させるためROICを一つの経営指標として導入した。国内需要が縮小する中、社員のマインドをリセットする狙いもある。ROICについては事業の特性を考慮し、結果のみならず工夫や努力などプロセスも評価する制度としていく」(谷藤 真澄)














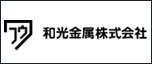

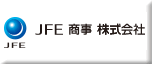
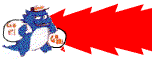

















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ


















