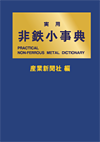2025年6月30日
メタルワン「シン・経営計画2027」/渡邉善之社長/課題解決力ナンバーワン/4つの重点領域、成長投資加速
メタルワンは2025―27年度の「シン・経営計画2027」を始動した。昨年に策定したパーパス「世界中の『つくる』をつなぎ、価値創造を追求し続けることで、ものづくりの可能性を広げる。」を「北極星」に据え、「2030年の目指す姿」に向かう中期3カ年の計画と位置付けた。企業の成長に向けて3つのシンカ(1)深化(既存ビジネスの磨き込み)(2)進化(既存ビジネスに高機能・高付加価値を追加)(3)新化(これまでにない新規ビジネスへの挑戦)をコンセプトに掲げ、既存事業の強靭化と新事業モデルの創出に取り組む。
シン・経営計画2027は「社員」「事業」「組織」を目指す姿の実現に向けた3つの柱とし、事業領域とレイヤー、地域の3つの切り口で事業ポートフォリオを変革する。「事業」は4つの重点領域(インフラ・建設、モビリティ、GX・エネルギー、新成長領域)に地域戦略を加え、成長投資を実行する。「2030年に目指す姿を『課題解決力ナンバーワン』と定め、その姿に向かう3年間と位置づけた。計画の実行に力を注ぎ、お客様からいち早く相談される存在になる。そのために人財がなにより重要だ」と語る、渡邉善之社長に取り組む施策と計画の実行に懸ける想いを聞いた。
――シン・経営計画2027の策定に役員の間で相当に議論したという。抱える課題、目指す姿とはどのようなものか。
「お客様から相談される立場にあるかどうか、強い問題意識を持っている。会社設立当初から国内ナンバーワンの鉄鋼総合商社としての自覚と責任を持ち、課題解決力を軸に据えて事業を展開してきた。現在もその自覚は変わっておらず、収益だけではなく、質を追う。目標とする収益額などは公表していないが、鋼材市況に依存して利益の増減を論じるのではなく、事業の中身を重視している。『課題解決力ナンバーワン』を目指し、高い機能を結果的に収益に結びつける。パーパスで意識するのは『世界中のつくるをつなぐ』こと。様々なプレーヤーをトレーディングでつなぎ、新しい価値を創る。ものづくりの可能性は広く、課題を解決できれば自ずと収益につながっていく」
――多様な課題の解決には株主との連携が有用だが、これまで以上の連携とは。
「株主をもっと活用しなければならない。三菱商事、双日のビジネスパートナーは国内外のあらゆる分野に存在しているので、当社としても素早くコネクトできる。具体的な協業案件という『場』を多く作ることが大事であり、当社の専門性に基づく機能を磨き、両株主と連携して課題に向き合うことで、解決策がグレードアップする。その結果、お客様から相談される内容が変わる。鉄鋼はもちろんのこと、お客様はいろいろなことを悩まれているので視野を広げ、協業案件という場をつないでいくと次のソリューションのチャンスが生まれる。両株主に加えて、メタルワングループとそのお客様・ビジネスパートナーが持っているソリューションを一つの形にして提供すると課題解決力の幅が広がる」
「状況が変わり、人手不足や物流など従来のオペレーションでは対応しきれない課題が多くなってきている。以前は中国を中心とするグローバルサプライチェーンも踏まえ、ビジネスを考える必要があったが、今後、中国という不確定要素を除いた形で新しい販路や新たなサプライチェーンを作る必要がある。課題が多いからこそ商機がある」
――4つの重点領域をどのように攻めていくのか。
「インフラ・建設は地産地消が進むなど課題が大きい領域であり、チャンスを取り込める可能性がある。老朽化・機械化に伴うメンテナンス需要の高まりを受けて、地域ごとに取り組みつつ、大きな構えでの組織対応を考える。人手不足も新たなチャンスとして捉える。モビリティは自動車の造り方が変わり、素材の調達が従来型の集中購買から変化し、メガティア1の発言力が高まるなどの動きがチャンスとなる。GX・エネルギーは水素など大きな案件ほど株主のネットワークを生かせる」
「レイヤーについては、シンカのコンセプトに基づき、それぞれ『深化』『進化』『新化』の3ステージに対応している。レイヤー1(深化)については、国内市場が小さくなる中で既存の物流加工機能を強靭化する必要がある。レイヤー2(進化)は、デジタルなどを加え、機能を高めて高い付加価値を提供する。レイヤー3(新化)は、新しい成長領域と機能という切り口から産業課題の解決なども意識したサービスを考える」
――成長のカギを握る海外戦略は。
「米国にある事業拠点を軸にさらなる現地化を進めている。成長市場の中でビジネスチャンスを捉えていく。インドは元々三菱商事、旧日商岩井ともに強い地域。市場のポテンシャルは高く、4つの重点領域に優先順位を決めて取り組む。アジアは中国のサプライチェーンが大きく変わる中で既存のアセットを生かしながら変化に対応した事業を展開する」
――独自のデジタルプラットフォームの採用が増えている。どう発展させていくのか。
「鉄鋼流通の業務効率化に寄与するメタルエックスユーピーはグループ会社も含めて1200社超が利用している。ペーパーレスや27年の手形決済終了、人材不足の中で業界全体の効率化につながるサービスを追求する。メタルエックスは自動車業界におけるお客様の煩雑な事務業務の効率化を実現し、コアの事業に集中いただくことで一緒に成長していく」
――「組織」の力をいかに発揮するか。
「『ワン・メタルワン』を掲げ、メタルワングループを所属組織や部署を超えたシンカが発揮できる組織にしていく。メタルワングループで連携し、各々の価値を掛け合わせ、お客様のビジネスを広げる。メタルワン設立時に策定したビジョン・ミッションに含まれている『マーケットをメイクする、バリューをオプティマイズ(最適化)する』と言っていたことが今、取引先から期待されている」
――重要テーマの「人財戦略」をどう進めるのか。
「メタルワン設立以後入社した社員が8割以上を占める。複雑な案件が多くなり、経験がより必要となっている。若い社員は手触り感のある小規模な案件は経験しているが、中・重量級の案件にはまだまだ十分に接していない。2030年に向けて自立自走を意識し、自分ゴトとして事業を創っていく。取引先や鉄鋼業界に貢献できるメタルワンであり続けるために、人財の育成にしっかりと取り組んでいきたい」(植木 美知也)

シン・経営計画2027は「社員」「事業」「組織」を目指す姿の実現に向けた3つの柱とし、事業領域とレイヤー、地域の3つの切り口で事業ポートフォリオを変革する。「事業」は4つの重点領域(インフラ・建設、モビリティ、GX・エネルギー、新成長領域)に地域戦略を加え、成長投資を実行する。「2030年に目指す姿を『課題解決力ナンバーワン』と定め、その姿に向かう3年間と位置づけた。計画の実行に力を注ぎ、お客様からいち早く相談される存在になる。そのために人財がなにより重要だ」と語る、渡邉善之社長に取り組む施策と計画の実行に懸ける想いを聞いた。
――シン・経営計画2027の策定に役員の間で相当に議論したという。抱える課題、目指す姿とはどのようなものか。
「お客様から相談される立場にあるかどうか、強い問題意識を持っている。会社設立当初から国内ナンバーワンの鉄鋼総合商社としての自覚と責任を持ち、課題解決力を軸に据えて事業を展開してきた。現在もその自覚は変わっておらず、収益だけではなく、質を追う。目標とする収益額などは公表していないが、鋼材市況に依存して利益の増減を論じるのではなく、事業の中身を重視している。『課題解決力ナンバーワン』を目指し、高い機能を結果的に収益に結びつける。パーパスで意識するのは『世界中のつくるをつなぐ』こと。様々なプレーヤーをトレーディングでつなぎ、新しい価値を創る。ものづくりの可能性は広く、課題を解決できれば自ずと収益につながっていく」
――多様な課題の解決には株主との連携が有用だが、これまで以上の連携とは。
「株主をもっと活用しなければならない。三菱商事、双日のビジネスパートナーは国内外のあらゆる分野に存在しているので、当社としても素早くコネクトできる。具体的な協業案件という『場』を多く作ることが大事であり、当社の専門性に基づく機能を磨き、両株主と連携して課題に向き合うことで、解決策がグレードアップする。その結果、お客様から相談される内容が変わる。鉄鋼はもちろんのこと、お客様はいろいろなことを悩まれているので視野を広げ、協業案件という場をつないでいくと次のソリューションのチャンスが生まれる。両株主に加えて、メタルワングループとそのお客様・ビジネスパートナーが持っているソリューションを一つの形にして提供すると課題解決力の幅が広がる」
「状況が変わり、人手不足や物流など従来のオペレーションでは対応しきれない課題が多くなってきている。以前は中国を中心とするグローバルサプライチェーンも踏まえ、ビジネスを考える必要があったが、今後、中国という不確定要素を除いた形で新しい販路や新たなサプライチェーンを作る必要がある。課題が多いからこそ商機がある」
――4つの重点領域をどのように攻めていくのか。
「インフラ・建設は地産地消が進むなど課題が大きい領域であり、チャンスを取り込める可能性がある。老朽化・機械化に伴うメンテナンス需要の高まりを受けて、地域ごとに取り組みつつ、大きな構えでの組織対応を考える。人手不足も新たなチャンスとして捉える。モビリティは自動車の造り方が変わり、素材の調達が従来型の集中購買から変化し、メガティア1の発言力が高まるなどの動きがチャンスとなる。GX・エネルギーは水素など大きな案件ほど株主のネットワークを生かせる」
「レイヤーについては、シンカのコンセプトに基づき、それぞれ『深化』『進化』『新化』の3ステージに対応している。レイヤー1(深化)については、国内市場が小さくなる中で既存の物流加工機能を強靭化する必要がある。レイヤー2(進化)は、デジタルなどを加え、機能を高めて高い付加価値を提供する。レイヤー3(新化)は、新しい成長領域と機能という切り口から産業課題の解決なども意識したサービスを考える」
――成長のカギを握る海外戦略は。
「米国にある事業拠点を軸にさらなる現地化を進めている。成長市場の中でビジネスチャンスを捉えていく。インドは元々三菱商事、旧日商岩井ともに強い地域。市場のポテンシャルは高く、4つの重点領域に優先順位を決めて取り組む。アジアは中国のサプライチェーンが大きく変わる中で既存のアセットを生かしながら変化に対応した事業を展開する」
――独自のデジタルプラットフォームの採用が増えている。どう発展させていくのか。
「鉄鋼流通の業務効率化に寄与するメタルエックスユーピーはグループ会社も含めて1200社超が利用している。ペーパーレスや27年の手形決済終了、人材不足の中で業界全体の効率化につながるサービスを追求する。メタルエックスは自動車業界におけるお客様の煩雑な事務業務の効率化を実現し、コアの事業に集中いただくことで一緒に成長していく」
――「組織」の力をいかに発揮するか。
「『ワン・メタルワン』を掲げ、メタルワングループを所属組織や部署を超えたシンカが発揮できる組織にしていく。メタルワングループで連携し、各々の価値を掛け合わせ、お客様のビジネスを広げる。メタルワン設立時に策定したビジョン・ミッションに含まれている『マーケットをメイクする、バリューをオプティマイズ(最適化)する』と言っていたことが今、取引先から期待されている」
――重要テーマの「人財戦略」をどう進めるのか。
「メタルワン設立以後入社した社員が8割以上を占める。複雑な案件が多くなり、経験がより必要となっている。若い社員は手触り感のある小規模な案件は経験しているが、中・重量級の案件にはまだまだ十分に接していない。2030年に向けて自立自走を意識し、自分ゴトとして事業を創っていく。取引先や鉄鋼業界に貢献できるメタルワンであり続けるために、人財の育成にしっかりと取り組んでいきたい」(植木 美知也)















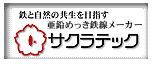
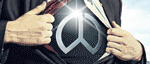
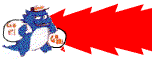

















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ