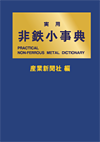2025年7月3日
商社の経営戦略/10年先を見据えて/丸紅 田口誠二執行役員金属部門長/成長領域で付加価値提供/川中・川下も太く 供給網を強化
丸紅の金属部門は2027年度までの中期計画で資源の拡充に加え、サプライチェーンの付加価値拡充に取り組む。新規投資含め資源も拡充しながら川中、川下も太くしたいという田口誠二部門長に方針を聞いた。
――24年度の総括を。
「連結純利益が1235億円と前年度より下がった。銅、アルミが期初の想定より相場が良かったが鉄鋼原料系が中国経済の低迷の影響を受けた。鉄鋼全般が悪かったので伊藤忠丸紅鉄鋼(MISI)も想定より利益が上がらなかった。」
――新戦力は。
「(23年度末実施の)ロスペランブレス銅山権益買い増し、パンパシフィック・カッパー(PPC)出資部分がプラス。投資はセンチネラ銅鉱山の拡張だ。今ある選鉱プラントをもう1ライン作る」
――25年度は減益。
「1130億円。予算策定時期にトランプ関税とか不透明なことがあり保守的に見ざるを得ない。実際に中国経済は回復に時間がかかる感触が強くなっている。中国は不動産を中心に国内の景気が動き出さないと厳しい。インドは調子いい。ただインドの伸びだけでは中国の低迷をカバーできない。時間が経てばインドと東南アジアが伸びてくる」
――24年度に実施した新規投資は。
「イギリスで廃電池リサイクルプロジェクトを技術検証している。ベトナムでアルミ再生地金を生産しているNM2にも少額出資した」
――新中計で全社は最高益を掲げる。
「会社は中期経営戦略で年平均成長率10%を目標に掲げている。我々も年率10%の成長を目標にするが金属部門の最高益には届かない。相場に関わらず一定の収益を出せる体制にしたい。資源だけでなく、川中、川下の方でもある程度事業を大きくしたい」
――中計3カ年での資源新規投資への資本配分は2000億円。
「新規も機会があればやりたい」
 ――ロイヒル鉄鉱山の拡張は。
――ロイヒル鉄鉱山の拡張は。
「事業性を見極めている。需要自体は伸びる。高炉から電炉への置き換えのスピード、どこまで置き換わるか流動的だ。悩みながら次の手を考えている」
――中計で全く新規の案件もあるか。
「金属部門の中核事業である銅鉱山、鉄鉱山、原料炭鉱で、事業の強化、グリーン化を図る。脱炭素社会ではCO2排出を減らさないと鉱山として競争力を失うのでグリーン化は取り組まなければならない。加えて競争力のある金属資源を確保、拡充していく。新規も探している。もう1つが金属のサプライチェーンを強化する。成長分野を取り込んでいく。丸紅全体で中期経営戦略で力を入れるのは戦略プラットフォーム型事業。成長領域で高付加価値を提供してかつビジネスモデルの拡張性があるという3つの要素があるビジネス。中期経営戦略3カ年での資源新規投資への資本配分は2000億円だが、戦略プラットフォーム型事業には1・2兆円投資枠が用意されている。鉱山以外金属サプライチェーンの川中・川下ビジネスもプラットフォーム型事業に相当するビジネスがあるので広げていきたい」
――新しい資源は3年でやる。
「やりたい。鉱山は採掘が進むと資源量が減っていく。今後10年間は大丈夫としても10年後以降に持分生産量が減るのを補うためには、数年以内に競争力のある新規案件の開発を開始しないと間に合わない」
――銅はアントファガスタと連携して今後も開発し続ける。
「現在チリ・センチネラ銅鉱山で拡張プロジェクトを推進している」
――違う地域も。
「南米もチリしかやっていない。探鉱事業としてはカナダやアラスカで取り組んでいる。米州とかオーストラリアも可能性はある。銅だけではない」
――アルミもアロエッテ製錬所の拡張は。
「経済性があるかだ。水力発電を利用してグリーンアルミを生産しているので活用は考えたい。日本でもグリーンアルミはリオティントと組んで拡販している。グリーンアルミのマーケットを広げてきている。自動車などでグリーンアルミの重要性が増していくので力を入れる」
――グリーンアルミの調達先はリオティントの他にも広げるか。
「証明書も付けているのはリオティントのアルミだ。リオティントは鉱山、アルミ製錬、全部通しでカーボンフットプリントを出してくれている。需要家の要望に応じて様々な低炭素アルミを安定供給できる体制を構築していく」
――リサイクルアルミも案件も増やす。
「増やしたい。グリーンアルミよりリサイクルアルミの方がCO2排出は少ない」
――プラットフォーム型の事業を伸ばす。
「MISIは戦略プラットフォーム型事業と認識している。鉄の需要は確実にある。昔はひも付きの商売に入っていたが、自分でコイルセンターを構えて切るとか打ち抜くだけでなく、パイプだったら特殊な継手を加工する。また、MISIは地産地消ビジネスに取り組んでおり、例えば米国内で完結するような建材事業をやっている。これらは欧州など他の地域でも展開できる拡張性も持っている。経済がブロック化し、地場に根差したビジネスを追いかけると、MISIの現地の取引先、ネットワークは価値あるものになる。グリーンスチールは、原料からカーボンフットプリントでつないでいく必要があり、原料を扱っている本社と、製品を扱っているMISIの流れが大事になる。協業は増える」
 ――冷鉄源の強化は。
――冷鉄源の強化は。
「国内だと丸紅テツゲンが取り組んでいる。高炉メーカーが建てる電炉もだし、電炉メーカーも拡張したり設備を入れ替えて増強したりするので、冷鉄源をどう確保するか力を入れている」
――スクラップは海外から調達する。
「国内から輸出されている部分もある。うまく仕分けできれば一部はもっと価値が出て国内で使えるかもしれない。設備投資をすればある程度できるか検討している。海外調達も考えたい」
――新規でレアメタルなどは。
「バッテリー関連のメタルは検討対象だ。特にリチウム。全固体電池でも半固体電池でもリチウムだけは基本的に使われる。30年後はナトリウムや他の金属になるかもしれないが、10―20年はリチウム主体だろう」
――希土類は。
「ニッチ過ぎる。トレードはやるし、川下の例えばパンパシフィックカッパー(PPC)に参画したことでJX金属との関係も深まり、同社との協業も検討したい」
――PPCに出資して連携は進んだか。
「銅地金トレードにおける連携や情報交換だけでなく、株主としてPPCの価値向上にも積極的に取り組んでいる。情報交換とか、彼らが求める原料とか、ビジネスの種になりそうなもののすり合わせは積極的に行う」
――丸紅メタルのリサイクル事業と本体の連携は。
「海外のソース開拓は本社のネットワークを使いながら広げられないかとやっている。銅、貴金属が入っているEスクラップだ」
――リチウムイオン電池(LiB)リサイクルはサーバとアルティリウムに出資しているが、時間がかかるか。
「サーバはブラックマスを作っている。能力4倍のプラントも一部稼働し始めたのでこのビジネスはまず回したい。このあと硫酸塩をつくる。現在プラントの詳細設計中。」
――アルティリウムは。
「ブラックマスから前駆体ないし正極材を造る。パイロットプラントがほぼ出来上がるくらい。技術検証してスケールアップする」
――脱炭素案件は。
「カナダのCCS案件は今年小規模パイロット操業を開始する。バイオ炭材の研究もしている。竹とか残渣でも汚泥とかでも良い。昇熱材や加炭材で転炉、電炉に入れるものをバイオに変えればその分CO2を減らせる」(正清 俊夫、田島 義史)

――24年度の総括を。
「連結純利益が1235億円と前年度より下がった。銅、アルミが期初の想定より相場が良かったが鉄鋼原料系が中国経済の低迷の影響を受けた。鉄鋼全般が悪かったので伊藤忠丸紅鉄鋼(MISI)も想定より利益が上がらなかった。」
――新戦力は。
「(23年度末実施の)ロスペランブレス銅山権益買い増し、パンパシフィック・カッパー(PPC)出資部分がプラス。投資はセンチネラ銅鉱山の拡張だ。今ある選鉱プラントをもう1ライン作る」
――25年度は減益。
「1130億円。予算策定時期にトランプ関税とか不透明なことがあり保守的に見ざるを得ない。実際に中国経済は回復に時間がかかる感触が強くなっている。中国は不動産を中心に国内の景気が動き出さないと厳しい。インドは調子いい。ただインドの伸びだけでは中国の低迷をカバーできない。時間が経てばインドと東南アジアが伸びてくる」
――24年度に実施した新規投資は。
「イギリスで廃電池リサイクルプロジェクトを技術検証している。ベトナムでアルミ再生地金を生産しているNM2にも少額出資した」
――新中計で全社は最高益を掲げる。
「会社は中期経営戦略で年平均成長率10%を目標に掲げている。我々も年率10%の成長を目標にするが金属部門の最高益には届かない。相場に関わらず一定の収益を出せる体制にしたい。資源だけでなく、川中、川下の方でもある程度事業を大きくしたい」
――中計3カ年での資源新規投資への資本配分は2000億円。
「新規も機会があればやりたい」
 ――ロイヒル鉄鉱山の拡張は。
――ロイヒル鉄鉱山の拡張は。「事業性を見極めている。需要自体は伸びる。高炉から電炉への置き換えのスピード、どこまで置き換わるか流動的だ。悩みながら次の手を考えている」
――中計で全く新規の案件もあるか。
「金属部門の中核事業である銅鉱山、鉄鉱山、原料炭鉱で、事業の強化、グリーン化を図る。脱炭素社会ではCO2排出を減らさないと鉱山として競争力を失うのでグリーン化は取り組まなければならない。加えて競争力のある金属資源を確保、拡充していく。新規も探している。もう1つが金属のサプライチェーンを強化する。成長分野を取り込んでいく。丸紅全体で中期経営戦略で力を入れるのは戦略プラットフォーム型事業。成長領域で高付加価値を提供してかつビジネスモデルの拡張性があるという3つの要素があるビジネス。中期経営戦略3カ年での資源新規投資への資本配分は2000億円だが、戦略プラットフォーム型事業には1・2兆円投資枠が用意されている。鉱山以外金属サプライチェーンの川中・川下ビジネスもプラットフォーム型事業に相当するビジネスがあるので広げていきたい」
――新しい資源は3年でやる。
「やりたい。鉱山は採掘が進むと資源量が減っていく。今後10年間は大丈夫としても10年後以降に持分生産量が減るのを補うためには、数年以内に競争力のある新規案件の開発を開始しないと間に合わない」
――銅はアントファガスタと連携して今後も開発し続ける。
「現在チリ・センチネラ銅鉱山で拡張プロジェクトを推進している」
――違う地域も。
「南米もチリしかやっていない。探鉱事業としてはカナダやアラスカで取り組んでいる。米州とかオーストラリアも可能性はある。銅だけではない」
――アルミもアロエッテ製錬所の拡張は。
「経済性があるかだ。水力発電を利用してグリーンアルミを生産しているので活用は考えたい。日本でもグリーンアルミはリオティントと組んで拡販している。グリーンアルミのマーケットを広げてきている。自動車などでグリーンアルミの重要性が増していくので力を入れる」
――グリーンアルミの調達先はリオティントの他にも広げるか。
「証明書も付けているのはリオティントのアルミだ。リオティントは鉱山、アルミ製錬、全部通しでカーボンフットプリントを出してくれている。需要家の要望に応じて様々な低炭素アルミを安定供給できる体制を構築していく」
――リサイクルアルミも案件も増やす。
「増やしたい。グリーンアルミよりリサイクルアルミの方がCO2排出は少ない」
――プラットフォーム型の事業を伸ばす。
「MISIは戦略プラットフォーム型事業と認識している。鉄の需要は確実にある。昔はひも付きの商売に入っていたが、自分でコイルセンターを構えて切るとか打ち抜くだけでなく、パイプだったら特殊な継手を加工する。また、MISIは地産地消ビジネスに取り組んでおり、例えば米国内で完結するような建材事業をやっている。これらは欧州など他の地域でも展開できる拡張性も持っている。経済がブロック化し、地場に根差したビジネスを追いかけると、MISIの現地の取引先、ネットワークは価値あるものになる。グリーンスチールは、原料からカーボンフットプリントでつないでいく必要があり、原料を扱っている本社と、製品を扱っているMISIの流れが大事になる。協業は増える」
 ――冷鉄源の強化は。
――冷鉄源の強化は。「国内だと丸紅テツゲンが取り組んでいる。高炉メーカーが建てる電炉もだし、電炉メーカーも拡張したり設備を入れ替えて増強したりするので、冷鉄源をどう確保するか力を入れている」
――スクラップは海外から調達する。
「国内から輸出されている部分もある。うまく仕分けできれば一部はもっと価値が出て国内で使えるかもしれない。設備投資をすればある程度できるか検討している。海外調達も考えたい」
――新規でレアメタルなどは。
「バッテリー関連のメタルは検討対象だ。特にリチウム。全固体電池でも半固体電池でもリチウムだけは基本的に使われる。30年後はナトリウムや他の金属になるかもしれないが、10―20年はリチウム主体だろう」
――希土類は。
「ニッチ過ぎる。トレードはやるし、川下の例えばパンパシフィックカッパー(PPC)に参画したことでJX金属との関係も深まり、同社との協業も検討したい」
――PPCに出資して連携は進んだか。
「銅地金トレードにおける連携や情報交換だけでなく、株主としてPPCの価値向上にも積極的に取り組んでいる。情報交換とか、彼らが求める原料とか、ビジネスの種になりそうなもののすり合わせは積極的に行う」
――丸紅メタルのリサイクル事業と本体の連携は。
「海外のソース開拓は本社のネットワークを使いながら広げられないかとやっている。銅、貴金属が入っているEスクラップだ」
――リチウムイオン電池(LiB)リサイクルはサーバとアルティリウムに出資しているが、時間がかかるか。
「サーバはブラックマスを作っている。能力4倍のプラントも一部稼働し始めたのでこのビジネスはまず回したい。このあと硫酸塩をつくる。現在プラントの詳細設計中。」
――アルティリウムは。
「ブラックマスから前駆体ないし正極材を造る。パイロットプラントがほぼ出来上がるくらい。技術検証してスケールアップする」
――脱炭素案件は。
「カナダのCCS案件は今年小規模パイロット操業を開始する。バイオ炭材の研究もしている。竹とか残渣でも汚泥とかでも良い。昇熱材や加炭材で転炉、電炉に入れるものをバイオに変えればその分CO2を減らせる」(正清 俊夫、田島 義史)














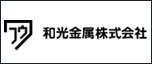

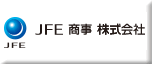
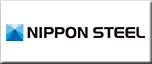

















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ