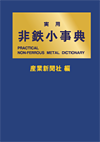2022年5月24日

日本の特殊鋼/世界に誇る技術の粋/(7)/特殊鋼メーカートップに聞く/大同特殊鋼・石黒武社長/自動車で鍛えた新規性

――特殊鋼メーカーとして自社の強みをどのように捉えるか。
「特殊鋼に求められるものは2つあり、一つは信頼性で、これを使っておけば間違いないという高信頼性だ。もう一つは新規性。パフォーマンスを上げるため、このような性質を持った特殊鋼がほしいといったニーズに応えるもの。信頼性でいえば、例えばSCM420のように何十年にもわたり使われている鋼材になる。新規性については、新たに開発されテストでは結果が出ていても、実際にはどんな問題が出るか分からない。新規性なるがゆえの信頼性の低さがある。海外の特殊鋼メーカーが得意とするのは、圧倒的に前者。確かな規格があり、その中に介在物もなく偏析もなく、きっちり造る。われわれもそこはしっかりやるが、それにプラスして新規の特殊鋼を開発する力が、当社も含めた日本の特殊鋼の強みだと思う」

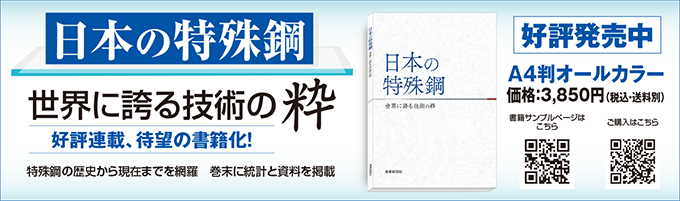

「特殊鋼に求められるものは2つあり、一つは信頼性で、これを使っておけば間違いないという高信頼性だ。もう一つは新規性。パフォーマンスを上げるため、このような性質を持った特殊鋼がほしいといったニーズに応えるもの。信頼性でいえば、例えばSCM420のように何十年にもわたり使われている鋼材になる。新規性については、新たに開発されテストでは結果が出ていても、実際にはどんな問題が出るか分からない。新規性なるがゆえの信頼性の低さがある。海外の特殊鋼メーカーが得意とするのは、圧倒的に前者。確かな規格があり、その中に介在物もなく偏析もなく、きっちり造る。われわれもそこはしっかりやるが、それにプラスして新規の特殊鋼を開発する力が、当社も含めた日本の特殊鋼の強みだと思う」

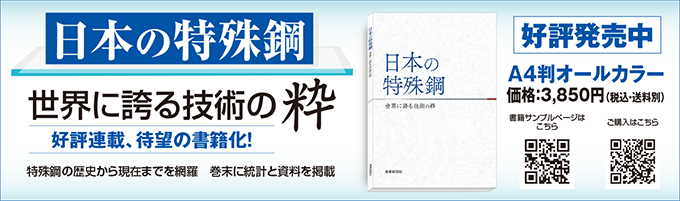














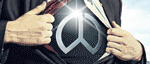
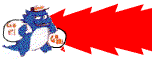
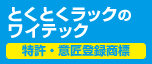


















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ