2025年3月7日
財務・経営戦略を聞く/神戸製鋼所取締役 執行役員/木本 和彦氏/機械・エンジ、高成長追求/アルミ板、新合弁で中国需要捕捉
――2024年度の連結純利益予想を1300億円と前回から上方修正した。市場が厳しい中で上積みでき、過去最高益となる要因は。
「年度当初に需要の回復基調を予想した素材系と建機は事業環境が振るわず、通期予想を厳しく見直したが、一方で操業が安定していることで見込んでいたトラブル時のコストを織り込む必要がなくなり、利益にプラスに作用した。過去最高の予想だが、実質は非常に厳しい内容と考えている。機械とエンジニアリングは円安含め事業環境が良好で電力も安定し、利益予想は前回とあまり変わらない。機械系は事業の構成や製造の仕組みなど製造現場からサプライチェーン含めて改善にかなり努力してきた成果が表れている。ポイントは素材系だ。市場が低迷し、良い話は少ない。ただ、素形材はアルミ製品において製造面での課題が解消に向かっていることや、価格転嫁が進み収益力が上がりつつあり、25年度は上向くとみている」
――粗鋼生産は600万トンと前年並みを予想するが。
「スポットの受注である程度補った。品種構成はマイナスに傾いたが、一定の数量は製造コストなどから必要になる。以前は620万ー630万トンを巡航速度と考えていたが、国内自動車生産が900万台を割り込むなど需要が減少し、前提が変わりつつある。需要の減少は予想していたことだがピッチが速い。需要回復への出口は見えず、しばらく低迷が続くとみている。今の粗鋼生産でも鉄鋼事業は利益を確保できているが、全社業績のカギはやはり素材系だ。建機の販売は不調だが、為替影響で20億円ほどのプラスがあり、利益はトントンとなる。今後はエンジン問題で落としたシェアを取り戻すことで台数の回復を見込む。機械・エンジは潜在力がなお高く、成長を追求する。取り組むべきことは多く、伸びしろは大きい」
――海外市場は中国経済の低迷がASEANなど他国に長く影響している。
「素材系は中国の影響度が最も高い。機械も一定程度中国関連の影響を受ける。中国は素材に限らず、建機も含めどの分野でも過剰能力となっている。中国の内需が悪化すると輸出が増え、国際需給が緩和する。機械も汎用品は中国の輸出の影響を受ける。政府の景気刺激策の効果も現時点では見えてきていない。米国の対中関税引き上げでモノが余り、経済が下振れする可能性がある」
――グループ会社の24年度の利益が前年を上回る。健闘している企業は。
「大きいのは米国のプロテック。原板の価格改定の関係で前年より数十億円改善した。生産量は安定し、順調に操業している。3基目のCGL(溶融亜鉛めっき設備)が23年に立ち上がり、生産能力は余力があり、数量を増やすとともに品種構成の改善を進める。他のグループ会社は概ね計画通り。建機は円安による輸出採算の改善などで利益を上方修正した。カーボンニュートラルの潮流が後退気味だが、機械系は新エネルギーと既存エネルギーの両分野でビジネスがあり、現時点では既存エネの事業が大きく、いずれにしても利益を確保できる」
――25年度の需要をどう予想し、経営の舵をどう方向づけていくか。
「これから詳細を詰めていくが、粗鋼生産600万トンの前提をさほど変えずに設定する見通しだ。最適な生産水準があり、上方・下方弾力性を考えると数量の変動を抑えたい。仮に市場が回復するとなれば市中在庫が少ないので対応できるように在庫を持ち、スポット販売を行いながら調整していく。鉄鋼のテーマは品種構成の改善だ。マーケットが低調で特殊鋼の商品特性からしても拡販や置き換えが急速に進むものではないが、徐々に改善していく。24年度の業績は中計初年度の計画をなんとか達成できる水準であり、26年度末の財務指標の目標値を変える予定はない。素材系は安定的に収益を確保できる体制を築き、機械系は一層の規模拡大を視野に入れる。コスト削減やマージン改善を続け、安定的な収益力を示し、有利子負債を削減して調達コストを下げていきたい。24年度は厳しい環境下で最高益を予想し、壁を一つ乗り越えたが油断せず、上を目指していく」
 ――トランプ政権の関税引上げ政策による影響をどうみるか。
――トランプ政権の関税引上げ政策による影響をどうみるか。
「米国向けは線条の直接輸出があるが、特殊鋼なので急激に影響を受けることはないだろう。米国の日系需要家の輸入コストに響くが、現地材に切り替えるのは容易ではない。米国の自動車生産台数が増えれば当社の量も増える可能性がある。機械関連のビジネスが米国で増える可能性もあり、チャンスもあるが状況はまだ見えない。米国の関税引上げによって中国が過剰能力の問題からASEANなどへの輸出により傾く恐れがあり、むしろ影響が懸念される」
――中国で宝山鋼鉄グループとアルミ板事業で合弁会社を設立した。狙いと期待は。
「中国のアルミ板製造拠点の神鋼汽車鋁材(天津)がこれまで少なかった中国資本の自動車メーカー向けの販売を増やすにあたって合弁パートナーの宝山鋼鉄の営業力を頼ることができるのは大きい。宝鋼にとっても鉄鋼とアルミ板を構えることができる。中国資本の自動車メーカーへの拡販について宝鋼の販売力に期待している。当社単独で事業を行うより将来性は高まった。合弁会社を設立し、1月に営業コンタクトができるようになったのでこれから事業計画を策定する」
――苦戦していたアルミサスペンションは国内、北米とも改善に向かいつつある。
「サプライヤーが限られており、自動車の生産台数が増えればかなりよくなる。課題だった生産性は向上しており、25年度は楽しみにしている。アルミ押出し品は競合が多いが、ある程度量が必要であり、営業努力を続ける」
――24年度下期にかけてアルミ板の収益が改善する。品種構成の改善や価格改定が寄与するのか。
「価格転嫁が大きい。ただ、数量は自動車向けが減少した。品種構成が改善したのはディスク材が23年度下期から戻り始め、数量が定着しているからだ」
――素形材事業の通期利益予想を引き上げた。
「コスト面が大きい。例年、操業ロスによるコスト増を想定するが安定操業が続いた。稼働が低いため、サポートコストをかけず、小さいトラブルを各ラインでその都度復旧できた。ただ、トラブルはどうしても起きるものであり、事業所ごとにコストを想定しつつ、安定操業に全力を尽くす。価格転嫁は途上であり継続するが、ここ数年でコストのフォーミュラ化がかなり進んだ。アルミ・銅の地金のコストはフォーミュラ化し、価格を転嫁している。加えて変動費のエネルギーコストをフォーミュラ化し、固定費の輸送費と労務費についても都度交渉している」
――CNの潮流に変化がみられるが、HBIの需要動向やミドレックスの受注環境をどう見ているか。
「仮にロシアから直接還元鉄の輸出が再開されても国際需給からみてそれほどの量にはならず、主に電炉の鉄源となる鉄スクラップ不足が生じ、HBIの需要が増える可能性がある。ただ、電炉転換がややスピードダウンしており、HBIの需要がどうなるか慎重にみている。ミドレックスの引き合いは足元も非常に多い。今のところ後退する様子はみられないが、調整局面は想定している」
――日本製鉄と株式の持ち合い解消を決めたが、提携関係で変わるところは。
「変化はない。元々買収防衛が目的で株の持ち合いを始めたが、提携関係を保ち、協業も複数行う中で両社ともに政策保有株を売却していく方針であり、いずれ持ち合いを解消する考えではあった。提携ありきでの解消で確認しながら合意しており、今後も提携関係は続く」(植木美知也、増岡武秀)

「年度当初に需要の回復基調を予想した素材系と建機は事業環境が振るわず、通期予想を厳しく見直したが、一方で操業が安定していることで見込んでいたトラブル時のコストを織り込む必要がなくなり、利益にプラスに作用した。過去最高の予想だが、実質は非常に厳しい内容と考えている。機械とエンジニアリングは円安含め事業環境が良好で電力も安定し、利益予想は前回とあまり変わらない。機械系は事業の構成や製造の仕組みなど製造現場からサプライチェーン含めて改善にかなり努力してきた成果が表れている。ポイントは素材系だ。市場が低迷し、良い話は少ない。ただ、素形材はアルミ製品において製造面での課題が解消に向かっていることや、価格転嫁が進み収益力が上がりつつあり、25年度は上向くとみている」
――粗鋼生産は600万トンと前年並みを予想するが。
「スポットの受注である程度補った。品種構成はマイナスに傾いたが、一定の数量は製造コストなどから必要になる。以前は620万ー630万トンを巡航速度と考えていたが、国内自動車生産が900万台を割り込むなど需要が減少し、前提が変わりつつある。需要の減少は予想していたことだがピッチが速い。需要回復への出口は見えず、しばらく低迷が続くとみている。今の粗鋼生産でも鉄鋼事業は利益を確保できているが、全社業績のカギはやはり素材系だ。建機の販売は不調だが、為替影響で20億円ほどのプラスがあり、利益はトントンとなる。今後はエンジン問題で落としたシェアを取り戻すことで台数の回復を見込む。機械・エンジは潜在力がなお高く、成長を追求する。取り組むべきことは多く、伸びしろは大きい」
――海外市場は中国経済の低迷がASEANなど他国に長く影響している。
「素材系は中国の影響度が最も高い。機械も一定程度中国関連の影響を受ける。中国は素材に限らず、建機も含めどの分野でも過剰能力となっている。中国の内需が悪化すると輸出が増え、国際需給が緩和する。機械も汎用品は中国の輸出の影響を受ける。政府の景気刺激策の効果も現時点では見えてきていない。米国の対中関税引き上げでモノが余り、経済が下振れする可能性がある」
――グループ会社の24年度の利益が前年を上回る。健闘している企業は。
「大きいのは米国のプロテック。原板の価格改定の関係で前年より数十億円改善した。生産量は安定し、順調に操業している。3基目のCGL(溶融亜鉛めっき設備)が23年に立ち上がり、生産能力は余力があり、数量を増やすとともに品種構成の改善を進める。他のグループ会社は概ね計画通り。建機は円安による輸出採算の改善などで利益を上方修正した。カーボンニュートラルの潮流が後退気味だが、機械系は新エネルギーと既存エネルギーの両分野でビジネスがあり、現時点では既存エネの事業が大きく、いずれにしても利益を確保できる」
――25年度の需要をどう予想し、経営の舵をどう方向づけていくか。
「これから詳細を詰めていくが、粗鋼生産600万トンの前提をさほど変えずに設定する見通しだ。最適な生産水準があり、上方・下方弾力性を考えると数量の変動を抑えたい。仮に市場が回復するとなれば市中在庫が少ないので対応できるように在庫を持ち、スポット販売を行いながら調整していく。鉄鋼のテーマは品種構成の改善だ。マーケットが低調で特殊鋼の商品特性からしても拡販や置き換えが急速に進むものではないが、徐々に改善していく。24年度の業績は中計初年度の計画をなんとか達成できる水準であり、26年度末の財務指標の目標値を変える予定はない。素材系は安定的に収益を確保できる体制を築き、機械系は一層の規模拡大を視野に入れる。コスト削減やマージン改善を続け、安定的な収益力を示し、有利子負債を削減して調達コストを下げていきたい。24年度は厳しい環境下で最高益を予想し、壁を一つ乗り越えたが油断せず、上を目指していく」
 ――トランプ政権の関税引上げ政策による影響をどうみるか。
――トランプ政権の関税引上げ政策による影響をどうみるか。「米国向けは線条の直接輸出があるが、特殊鋼なので急激に影響を受けることはないだろう。米国の日系需要家の輸入コストに響くが、現地材に切り替えるのは容易ではない。米国の自動車生産台数が増えれば当社の量も増える可能性がある。機械関連のビジネスが米国で増える可能性もあり、チャンスもあるが状況はまだ見えない。米国の関税引上げによって中国が過剰能力の問題からASEANなどへの輸出により傾く恐れがあり、むしろ影響が懸念される」
――中国で宝山鋼鉄グループとアルミ板事業で合弁会社を設立した。狙いと期待は。
「中国のアルミ板製造拠点の神鋼汽車鋁材(天津)がこれまで少なかった中国資本の自動車メーカー向けの販売を増やすにあたって合弁パートナーの宝山鋼鉄の営業力を頼ることができるのは大きい。宝鋼にとっても鉄鋼とアルミ板を構えることができる。中国資本の自動車メーカーへの拡販について宝鋼の販売力に期待している。当社単独で事業を行うより将来性は高まった。合弁会社を設立し、1月に営業コンタクトができるようになったのでこれから事業計画を策定する」
――苦戦していたアルミサスペンションは国内、北米とも改善に向かいつつある。
「サプライヤーが限られており、自動車の生産台数が増えればかなりよくなる。課題だった生産性は向上しており、25年度は楽しみにしている。アルミ押出し品は競合が多いが、ある程度量が必要であり、営業努力を続ける」
――24年度下期にかけてアルミ板の収益が改善する。品種構成の改善や価格改定が寄与するのか。
「価格転嫁が大きい。ただ、数量は自動車向けが減少した。品種構成が改善したのはディスク材が23年度下期から戻り始め、数量が定着しているからだ」
――素形材事業の通期利益予想を引き上げた。
「コスト面が大きい。例年、操業ロスによるコスト増を想定するが安定操業が続いた。稼働が低いため、サポートコストをかけず、小さいトラブルを各ラインでその都度復旧できた。ただ、トラブルはどうしても起きるものであり、事業所ごとにコストを想定しつつ、安定操業に全力を尽くす。価格転嫁は途上であり継続するが、ここ数年でコストのフォーミュラ化がかなり進んだ。アルミ・銅の地金のコストはフォーミュラ化し、価格を転嫁している。加えて変動費のエネルギーコストをフォーミュラ化し、固定費の輸送費と労務費についても都度交渉している」
――CNの潮流に変化がみられるが、HBIの需要動向やミドレックスの受注環境をどう見ているか。
「仮にロシアから直接還元鉄の輸出が再開されても国際需給からみてそれほどの量にはならず、主に電炉の鉄源となる鉄スクラップ不足が生じ、HBIの需要が増える可能性がある。ただ、電炉転換がややスピードダウンしており、HBIの需要がどうなるか慎重にみている。ミドレックスの引き合いは足元も非常に多い。今のところ後退する様子はみられないが、調整局面は想定している」
――日本製鉄と株式の持ち合い解消を決めたが、提携関係で変わるところは。
「変化はない。元々買収防衛が目的で株の持ち合いを始めたが、提携関係を保ち、協業も複数行う中で両社ともに政策保有株を売却していく方針であり、いずれ持ち合いを解消する考えではあった。提携ありきでの解消で確認しながら合意しており、今後も提携関係は続く」(植木美知也、増岡武秀)














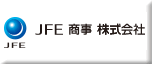

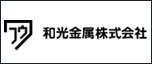


















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ


















