2025年5月30日
財務・経営戦略を聞く/神戸製鋼所取締役 執行役員/木本和彦氏/機械・エンジ、堅調持続/鉄鋼アルミ 収益強化策に注力
――厳しい市場の中で連結経常利益は1571億円と減益ながら高水準を維持し、連結当期純利益は1201億円と過去最高を記録した。
「素材系は市場が低調で利益はなお低いが、機械と電力が利益を押し上げた。鉄鋼の利益は243億円と149億円減少したが、中国が大量に鋼材を輸出し東アジア市況が落ち込むなど過去にない厳しい需要環境の中で一定の利益を出すことができたのは固定費を落とし、供給を減らし、価格の下げ圧力に対応してきたこの数年の取り組みの成果の表れ。素材系は原料など価格転嫁の仕組みづくりに粘り強く取り組み、コスト削減も進め、基礎体力がかなり上がった」
――鉄鋼事業はひも付き価格の是正や諸物価高騰分の転嫁が進み、スプレッドは改善したのか。
「鉄鋼のスプレッドは22―23年度に改善し、24年度は前年と同程度だった。市場が低迷したために増えた固定費の転嫁がさほど進まなかった。マージンは原料価格の下げ局面が重なり、期ずれで改善した。25年度は粗鋼生産の予想が前年比微減で大きくは変わらず、実力のマージンも変わらないが、原料安がマイナスに作用することでスプレッドはやや縮小する。増えている固定費については、お客様に理解を得ながら転嫁していく一方、労務費や物流費、資機材調達費の上昇に対しては、生産性の向上によってコストを下げる努力を続ける。加えて、近年は高炉の稼働が安定しており、保全費の発生を抑えられたことで、利益面にもいい影響を与えることができた。25年度も引き続き十分な保全費を確保するが、トラブルの未然防止に注力していく」
――鉄鋼アルミの海外事業会社の利益が24年度に改善した。
「米プロテックの増益が目立つが、海外事業会社はほぼ業績が改善した。プロテックは一過性益が大きく、23年度に鋼板市況が上がり、原板が上がった調整を24年度に受けた。タイは市場が低調だが、コベルコ・ミルコンスチールや棒線二次加工拠点は黒字を維持している。中国の棒線二次加工拠点は日系自動車の販売減で加工量が減っているが、操業の工夫などで耐えている。中国の自動車向けアルミパネル事業は合弁会社の立ち上げに入り、当社と宝武鋼鉄グループの営業が交流を始めている。日欧米系の自動車向けは当社、中国系は宝武グループが販売を増やしていく方針。中国市場は低調だが自動車メーカーの認証取得を進め、26年以降販売を増やしていく。宝武グループもアルミ板の販売に力を入れており、楽しみだ。鞍鋼神鋼冷延高張力自動車鋼板は一定の黒字を確保している。鞍鋼集団にとっても重要な拠点であり、中国系自動車への拡販に取り組んでいる」
――25年度の連結経常利益は1200億円と減益予想だが、米国の関税影響を織り込んでいない。
「日本政府が協議をしている最中であり、不確定な中で影響を算定するのは難しい。当社の直接輸出を考えると、鉄鋼事業の販売量に占める米国向け輸出は5%未満、アルミ板や建機関係の輸出も同程度にとどまる。米国向けの自動車生産や間接影響が見込まれ、さらに日本の自動車メーカーが米国内の製造にシフトするようであれば影響を大きく受けるが、いずれも確たるものがない中で見通しを述べるのは難しく、状況を注視する」
――米プロテックに関税政策はプラスに作用するのでは。
「米国の景気後退懸念もあり、米国の自動車生産をポジティブにはみていない。鋼材市況は上がっており、製品価格は上がるかもしれないが、現時点では不確かであり、建機や機械事業についても同様だ」
 ――アルミ板は価格転嫁が進み収益は改善基調にあるが、25年度の黒字化はやや先送りとなる見通しだ。
――アルミ板は価格転嫁が進み収益は改善基調にあるが、25年度の黒字化はやや先送りとなる見通しだ。
「原材料価格の変動についてフォーミュラ化し、価格改善が進んだ。25年度はディスクや缶材向けの販売量は少し増えるが、固定費が増えるので24年度に比べ実力の利益はそれほど変わらない。宝武との合弁事業で26年度から見込める収益貢献がポイントだ。銅板は販売先が日系自動車だけでなく、中国の自動車向けが一定の割合を占めていることもあり、販売量は増えるとみている」
――素形材事業は価格改善によって24年度は107億円と大幅な増益に。25年度は80億円と減益予想だが。
「素形材はお客様に理解をいただきながら、価格転嫁を着々と進めている。25年度はやや保守的な利益目標と思っている。素材といいながらも、部品に近い形状の製品を取り扱っていることを考えると、収益性はもっと上を目指したい。素形材事業は多様なユニットがあり、それぞれの特性を活かしながら、収益性の向上に向けた最適な経営資源の配分を進めている。将来的な成長が見込める分野には積極的な投資を行う一方、事業構造の見直しも柔軟に検討していく考え。また、様々な切り口で成長性のある取り組みを集約するなど、事業部門内でシナジーを発揮できるような方策を探っていきたい。一方、鉄粉では競争環境が厳しくなっているが、需要拡大に向けた活動を強化していく」
――子会社の日本高周波鋼業を大同特殊鋼に譲渡する狙い、効果とは。
「主力のグループ会社としていろいろと手を打ってきたが、大幅な合理化策を実施するよりは同業他社への譲渡で優良な資産を残すことを選択した。高周波鋼業の将来を考え、大同特殊鋼と協議に入り、譲渡を決めた。大同特殊鋼としても高周波鋼業を戦力化できる構想を持っている。当社は建機や機械で鋳造品を調達しているので鋳鉄事業を手掛ける高周波鋼業子会社の高周波鋳造は当社の100%子会社とすることで相乗効果を発揮していく」
――機械・エンジニアリングは24年度に増益と堅調だ。
「機械は化学・エネルギー分野の受注が伸び、能力的にも商品構成的にも最大限の受注・供給を行っている。お客様のニーズに迅速に応えるため、まずはサービス拠点の拡大を進めている。受注残高は高く、25年度も利益は400億円と74億円増える予想だ。事業は順調だが、エネルギー関連のピークアウトのサインを見逃さないよう注意している。エンジは24年度が増益で25年度は還元鉄関連事業で複数の大型案件受注を見込んでいるものの、利益は案件構成で120億円と41億円減る計画。新鉄源はカーボンニュートラル(CN)を取り巻く環境に変化が生じてきており、今後の動向を注視している。一部の案件で慎重な動きもみられる一方、複数の案件が進行中であり、その一部が成約に至れば現状の利益水準は維持できる見込みだ。建機はエンジン認証問題の補償金を24年度に受けた一方、事業活動の制限により下げたシェアや収益性の回復に時間を要している。事業環境は相当厳しく、24年度で減損損失を計上した。現在、固定費の価格転嫁を進める計画もあるが、為替がマイナスに効いてくるので25年度の利益は95億円と92億円の減少を予想している」
――電力は23年度の利益が857億円と非常に高く、24年度は523億円と本来の実力の400億円を上回ったが、25年度は340億円と減益を予想している。
「真岡発電所、神戸発電所3・4号機における定期点検日数が増えるので25年度の利益は減るが、本来の実力の350億―400億円を維持していきたい」
――設備投資額は増え、25年度は支払いベースで1500億円(24年度1132億円)を予定している。
「投資件数の増加は要因の一つだが、それ以上にコスト上昇の影響が大きい。この数年で費用は倍近くに膨らんでいる。これまで運転資本の改善や政策保有株式の売却などで財務基盤を強化し、成長投資を積極的に行える体制を十分に整えており、老朽化設備の更新やCN対応など将来に向けた投資に積極的に取り組んでいく」(植木 美知也)

「素材系は市場が低調で利益はなお低いが、機械と電力が利益を押し上げた。鉄鋼の利益は243億円と149億円減少したが、中国が大量に鋼材を輸出し東アジア市況が落ち込むなど過去にない厳しい需要環境の中で一定の利益を出すことができたのは固定費を落とし、供給を減らし、価格の下げ圧力に対応してきたこの数年の取り組みの成果の表れ。素材系は原料など価格転嫁の仕組みづくりに粘り強く取り組み、コスト削減も進め、基礎体力がかなり上がった」
――鉄鋼事業はひも付き価格の是正や諸物価高騰分の転嫁が進み、スプレッドは改善したのか。
「鉄鋼のスプレッドは22―23年度に改善し、24年度は前年と同程度だった。市場が低迷したために増えた固定費の転嫁がさほど進まなかった。マージンは原料価格の下げ局面が重なり、期ずれで改善した。25年度は粗鋼生産の予想が前年比微減で大きくは変わらず、実力のマージンも変わらないが、原料安がマイナスに作用することでスプレッドはやや縮小する。増えている固定費については、お客様に理解を得ながら転嫁していく一方、労務費や物流費、資機材調達費の上昇に対しては、生産性の向上によってコストを下げる努力を続ける。加えて、近年は高炉の稼働が安定しており、保全費の発生を抑えられたことで、利益面にもいい影響を与えることができた。25年度も引き続き十分な保全費を確保するが、トラブルの未然防止に注力していく」
――鉄鋼アルミの海外事業会社の利益が24年度に改善した。
「米プロテックの増益が目立つが、海外事業会社はほぼ業績が改善した。プロテックは一過性益が大きく、23年度に鋼板市況が上がり、原板が上がった調整を24年度に受けた。タイは市場が低調だが、コベルコ・ミルコンスチールや棒線二次加工拠点は黒字を維持している。中国の棒線二次加工拠点は日系自動車の販売減で加工量が減っているが、操業の工夫などで耐えている。中国の自動車向けアルミパネル事業は合弁会社の立ち上げに入り、当社と宝武鋼鉄グループの営業が交流を始めている。日欧米系の自動車向けは当社、中国系は宝武グループが販売を増やしていく方針。中国市場は低調だが自動車メーカーの認証取得を進め、26年以降販売を増やしていく。宝武グループもアルミ板の販売に力を入れており、楽しみだ。鞍鋼神鋼冷延高張力自動車鋼板は一定の黒字を確保している。鞍鋼集団にとっても重要な拠点であり、中国系自動車への拡販に取り組んでいる」
――25年度の連結経常利益は1200億円と減益予想だが、米国の関税影響を織り込んでいない。
「日本政府が協議をしている最中であり、不確定な中で影響を算定するのは難しい。当社の直接輸出を考えると、鉄鋼事業の販売量に占める米国向け輸出は5%未満、アルミ板や建機関係の輸出も同程度にとどまる。米国向けの自動車生産や間接影響が見込まれ、さらに日本の自動車メーカーが米国内の製造にシフトするようであれば影響を大きく受けるが、いずれも確たるものがない中で見通しを述べるのは難しく、状況を注視する」
――米プロテックに関税政策はプラスに作用するのでは。
「米国の景気後退懸念もあり、米国の自動車生産をポジティブにはみていない。鋼材市況は上がっており、製品価格は上がるかもしれないが、現時点では不確かであり、建機や機械事業についても同様だ」
 ――アルミ板は価格転嫁が進み収益は改善基調にあるが、25年度の黒字化はやや先送りとなる見通しだ。
――アルミ板は価格転嫁が進み収益は改善基調にあるが、25年度の黒字化はやや先送りとなる見通しだ。「原材料価格の変動についてフォーミュラ化し、価格改善が進んだ。25年度はディスクや缶材向けの販売量は少し増えるが、固定費が増えるので24年度に比べ実力の利益はそれほど変わらない。宝武との合弁事業で26年度から見込める収益貢献がポイントだ。銅板は販売先が日系自動車だけでなく、中国の自動車向けが一定の割合を占めていることもあり、販売量は増えるとみている」
――素形材事業は価格改善によって24年度は107億円と大幅な増益に。25年度は80億円と減益予想だが。
「素形材はお客様に理解をいただきながら、価格転嫁を着々と進めている。25年度はやや保守的な利益目標と思っている。素材といいながらも、部品に近い形状の製品を取り扱っていることを考えると、収益性はもっと上を目指したい。素形材事業は多様なユニットがあり、それぞれの特性を活かしながら、収益性の向上に向けた最適な経営資源の配分を進めている。将来的な成長が見込める分野には積極的な投資を行う一方、事業構造の見直しも柔軟に検討していく考え。また、様々な切り口で成長性のある取り組みを集約するなど、事業部門内でシナジーを発揮できるような方策を探っていきたい。一方、鉄粉では競争環境が厳しくなっているが、需要拡大に向けた活動を強化していく」
――子会社の日本高周波鋼業を大同特殊鋼に譲渡する狙い、効果とは。
「主力のグループ会社としていろいろと手を打ってきたが、大幅な合理化策を実施するよりは同業他社への譲渡で優良な資産を残すことを選択した。高周波鋼業の将来を考え、大同特殊鋼と協議に入り、譲渡を決めた。大同特殊鋼としても高周波鋼業を戦力化できる構想を持っている。当社は建機や機械で鋳造品を調達しているので鋳鉄事業を手掛ける高周波鋼業子会社の高周波鋳造は当社の100%子会社とすることで相乗効果を発揮していく」
――機械・エンジニアリングは24年度に増益と堅調だ。
「機械は化学・エネルギー分野の受注が伸び、能力的にも商品構成的にも最大限の受注・供給を行っている。お客様のニーズに迅速に応えるため、まずはサービス拠点の拡大を進めている。受注残高は高く、25年度も利益は400億円と74億円増える予想だ。事業は順調だが、エネルギー関連のピークアウトのサインを見逃さないよう注意している。エンジは24年度が増益で25年度は還元鉄関連事業で複数の大型案件受注を見込んでいるものの、利益は案件構成で120億円と41億円減る計画。新鉄源はカーボンニュートラル(CN)を取り巻く環境に変化が生じてきており、今後の動向を注視している。一部の案件で慎重な動きもみられる一方、複数の案件が進行中であり、その一部が成約に至れば現状の利益水準は維持できる見込みだ。建機はエンジン認証問題の補償金を24年度に受けた一方、事業活動の制限により下げたシェアや収益性の回復に時間を要している。事業環境は相当厳しく、24年度で減損損失を計上した。現在、固定費の価格転嫁を進める計画もあるが、為替がマイナスに効いてくるので25年度の利益は95億円と92億円の減少を予想している」
――電力は23年度の利益が857億円と非常に高く、24年度は523億円と本来の実力の400億円を上回ったが、25年度は340億円と減益を予想している。
「真岡発電所、神戸発電所3・4号機における定期点検日数が増えるので25年度の利益は減るが、本来の実力の350億―400億円を維持していきたい」
――設備投資額は増え、25年度は支払いベースで1500億円(24年度1132億円)を予定している。
「投資件数の増加は要因の一つだが、それ以上にコスト上昇の影響が大きい。この数年で費用は倍近くに膨らんでいる。これまで運転資本の改善や政策保有株式の売却などで財務基盤を強化し、成長投資を積極的に行える体制を十分に整えており、老朽化設備の更新やCN対応など将来に向けた投資に積極的に取り組んでいく」(植木 美知也)














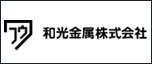
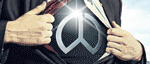
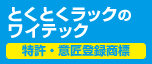


















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ


















