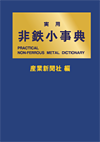2025年6月11日
中期計画進捗を聞く/神戸製鋼所 勝川四志彦社長/機械系、成長へ積極投資/効率化進め素材系競争力向上
――素材系と建機は苦戦しているが、機械・エンジニアリングと電力が利益を押し上げている。
「国内の自動車分野は認証問題以降も低い水準にとどまり、建設分野は資材高騰や人手不足を背景に低調なままだ。米国の関税問題が加わり、特に素材系のマーケット中心に厳しい状況が続く見通しだ。国内需要の縮小が足元前倒しで表れ始めており、このまま需要が戻らない可能性もある。国内の鋼材需要は5000万トンに減り、鋼材輸出も減少し、国内粗鋼生産は8000万トンを割りかねない。将来を見据えると厳しい市場を前提に考えざるを得ない。一方でエネルギー関連は堅調で24年度は機械・エンジともに史上最高益となった。受注高の水準も高く、安定した利益が見込める。米関税政策について米国向けの輸出など直接影響は把握できるが、特殊鋼にしても自動車など間接影響の範囲が広い。機械系も関税影響で海外の関連プロジェクトが停滞するなどのリスクがあり注視している。いずれも算定が困難なので25年度の業績予想には織り込んでいない」
――中期経営計画で「稼ぐ力の強化」を最重要課題の一つに掲げている。素材系の強化が欠かせない。
「マーケットが悪い中で、稼ぐ力を強化していかなければならない。粗鋼生産が一定を超えて減るとトン当たりのコストは悪化する。コストの抑制策を検討し、25年度に固め、損益分岐点を下げていく。アルミ板は中国の宝武鋼鉄グループと合弁事業を立ち上げ、早期の本格稼働を目指している。コストダウンや価格改善、宝武グループとのシナジーなどによりアルミ板全体の収益改善を図る」
――素材系の成長に向けた海外展開は。
「足元の関税影響を考慮する必要がある。新興国は地産地消が進むとみており、北米と中国、タイの当社の鉄鋼の主要海外拠点をどう強化していくかが重要だ。米国のプロテックは大型投資を行ったばかりで市場に対応する体制を整えている。米国は成長する市場として期待している。中国の市場は調整が続くが、EVの生産が増えている。自動車用冷延ハイテン製造会社の合弁パートナーである鞍鋼集団は中国自動車へのチャンネルをしっかりと持っており、事業を伸ばしていけると考えている。タイは市場が振るわないが、合弁パートナーと協力して特殊鋼線材を製造するコベルコミルコンスチールの体質強化を図る。インドは先行している機械系の事業をまずは強化していく。高い経済成長を持続しているが、既に多くの競合他社が参入しており、KOBELCOならではの事業が展開できるか、見極めていく」
――アルミ関連事業の黒字化が課題だが、米国事業は立て直しが進んでいる。
「サスペンション用アルミ鍛造のKAAPはようやく生産が安定し、24年度下期に黒字化した。一時期は生産が受注量に追い付かず、日本や中国からの生産支援により、輸送費などコストがかさんでいたが、一部自動化など設備を整え、労働生産性を上げている。押出品を製造するKPEXはまだ立て直しの途上にある。受注は増加しているものの製造キャパに余剰があり、ダウンサイジングにより最適化を目指す。国内も真岡製造所の合理化に取り組み、DXを活用して製造の整流化・省力化を図り、固定費を削減する」
――日本高周波鋼業譲渡の一方で成長投資を複数決めた。
「鉄鋼ではKOBEMAGの自社一貫生産を目的に製造設備を増強した。厚板とともに建設マーケットに積極的にアプローチしていく。溶接事業は溶接システム含め自動車向けを強化するため、パナソニックコネクトと協業し、溶材と溶接ロボットをセットで提案する。溶接ロボットは建設分野に強みを持つが、今後は自動車分野にも注力する。銅板は電動化などで自動車向けの端子の需要が増えている。半導体のリードフレーム需要の回復を下期に期待し、需要増に備え、長府製造所の能力を増強し、供給体制を整える」
――最重要課題の「成長追求」は機械とエンジの事業拡大が肝となる。具体化してくる案件とは。
「機械は欧州と中東にアクセスしやすいインドで27年度に産業機械の製造拠点を増強し、タイヤ・ゴム機械の生産能力増強に加えて非汎用圧縮機の新規生産を始める。お客様がグローバルに広がってきているので、新たに中東・サウジアラビアでアフターサービスの拠点を整える。また、米国のサービスショップの拡張工事も今年度中に完了する予定だ。将来的なエネルギー転換を見据えた水素・アンモニア関連や半導体検査装置などメニューの幅を広げ、成長を目指す。サービス拠点は投資額が小さく、短期に建設でき、早期に戦力化できるので積極的に展開していく」
――中計最終26年度のROIC目標(素材系6―8%、機械系8―10%)に対し、24年度は素材系が約4%にとどまり、機械系は約12%に上がった。
「機械は当社が高いシェアを持つメニューが多数ある。CNが進めば水素やアンモニア、CCUSなど新しいマーケット向けが増え、CNが遅れても石化・エネルギー関連向けの受注が見込める。エンジは直接還元鉄プラントのミドレックスが順調で、他にも廃プラスチックからエタノールを回収するプラントの開発など新しい展開もある。機械・エンジ・建機を合わせた機械系事業の売上高は25年度に8860億円(24年度8279億円)を見込む。CN関連の商業化で様子が変わってくると思うが、中長期目標の売上高1兆円に達するにはM&Aなどさらに工夫が要る。焦らず、案件を探っていく。機械系事業の経常利益は24年度で673億円。売上高1兆円で経常利益800億―900億円を想定し、1000億円も視野に入る」
――建機はエンジン認証問題でエンジン供給が受けられず、販売が減少した。24年度は影響が残ったが、どのように立て直していく考えか。
「遠隔操作システムのK―DIVEが浸透しつつある。建設現場は必ずしも平坦ではなく、遠隔であってもコクピットが傾き、危険予知も含めて作業できるなどの特徴を生かし、『コト売り・ソリューションビジネス』を伸ばしていく。ショベル以外にも工場内のフォークリフトや農業機械などへの応用が考えられ、お客様からも相談を受けている。『コト売り・ソリューションビジネス』含めここからエンジン認証問題の影響を取り戻していく」
――粗鋼生産は600万トン程度を維持している。需要が減る中でこの先の粗鋼の水準をどう考えているか。
「神戸製鉄所の高炉を2017年に休止したことで、当社の粗鋼生産の減少率は全国粗鋼の減少率より低く抑えることができている。ただ、関税問題などの影響で製造業の海外シフトが進み、国内需要がさらに減少するようであれば状況は変わるため、危機感を持ってみている。需要は増えず、減少する可能性も前提に考える必要がある」
――2030年代に改修時期を迎える高炉1基の電炉転換を検討している。需要に合わせた能力削減と組み合わせる考えは。
「減産との組み合わせで考えることは十分にあり得るが、需要の水準次第であり、将来のカーボンニュートラル(CN)の姿などいろいろな要件をみて検討する。需要の減少が速まり、電炉導入の条件が整えば切り替えた方がよいという判断になるかもしれない」
――中計の投資額を見直し、CN対応など減額した。直接還元鉄の取り組みなどに影響は。
「当初計画していた3000億円程度のCN関連投資に関し、昨今のCNの潮流を含めた外部環境変化を受け、経済合理性をよく見定める必要があると考え一部投資の意思決定時期を後ろ倒しにした。ただCNへの挑戦は変わらず、引き続きCO2の削減に最大限取り組む。オマーンでの直接還元鉄プロジェクトは事業化調査を進めているが販売先で脱炭素に向けた還元鉄の購入意欲がやや後退しており、プロジェクトの実行時期を見極めている。高炉でのCO2削減を目的に取り組んでいるHBIの多配合に加え、新たに微粉炭吹き込みの代替利用を前提に、UBE三菱セメントとブラックペレットの製造販売での共同事業化検討を開始した。これらは両立できるものであり、高炉工程でのCO2削減を着々と進めていく」
「『稼ぐ力の強化と成長追求』も投資額を減らしたが、案件を後ろにずらすもので中長期的にみて必要な投資という認識には変わりはない。足元の投資額を減らし、財務体質を改善することで、資金調達が有利になり、投資を増やせる可能性もある。一方で合理化・更新投資は増額した。自動化など『少人化』にチャレンジし、各製造部門で上げた効果をヨコ展開していく」
――事業ポートフォリオを最適化し、25年度予想の全社利益のうち機械系5割、素材系2割、電力3割。2030年に連結経常利益2000億円を目指しているが、30年時も同様の構成を想定しているのか。
「機械系は為替の円安が有利に働いている。円高となれば素材系にプラスに働くので一概に言えない。ただ、素材系は収益力を一段引き上げなければならない。アルミ関連が黒字化し収益力が上がってくれば変わってくる。国内需要が減少し、素材系は厳しくなるが、悲観ばかりではない。例えば、溶接は人手不足に対応して溶接工程の自動化に当社が持つノウハウやロボットを提供することでサービスの付加価値を上げていく。社会のニーズに応える新しいビジネスを展開することで収益を上げていきたい」(植木 美知也)

「国内の自動車分野は認証問題以降も低い水準にとどまり、建設分野は資材高騰や人手不足を背景に低調なままだ。米国の関税問題が加わり、特に素材系のマーケット中心に厳しい状況が続く見通しだ。国内需要の縮小が足元前倒しで表れ始めており、このまま需要が戻らない可能性もある。国内の鋼材需要は5000万トンに減り、鋼材輸出も減少し、国内粗鋼生産は8000万トンを割りかねない。将来を見据えると厳しい市場を前提に考えざるを得ない。一方でエネルギー関連は堅調で24年度は機械・エンジともに史上最高益となった。受注高の水準も高く、安定した利益が見込める。米関税政策について米国向けの輸出など直接影響は把握できるが、特殊鋼にしても自動車など間接影響の範囲が広い。機械系も関税影響で海外の関連プロジェクトが停滞するなどのリスクがあり注視している。いずれも算定が困難なので25年度の業績予想には織り込んでいない」
――中期経営計画で「稼ぐ力の強化」を最重要課題の一つに掲げている。素材系の強化が欠かせない。
「マーケットが悪い中で、稼ぐ力を強化していかなければならない。粗鋼生産が一定を超えて減るとトン当たりのコストは悪化する。コストの抑制策を検討し、25年度に固め、損益分岐点を下げていく。アルミ板は中国の宝武鋼鉄グループと合弁事業を立ち上げ、早期の本格稼働を目指している。コストダウンや価格改善、宝武グループとのシナジーなどによりアルミ板全体の収益改善を図る」
――素材系の成長に向けた海外展開は。
「足元の関税影響を考慮する必要がある。新興国は地産地消が進むとみており、北米と中国、タイの当社の鉄鋼の主要海外拠点をどう強化していくかが重要だ。米国のプロテックは大型投資を行ったばかりで市場に対応する体制を整えている。米国は成長する市場として期待している。中国の市場は調整が続くが、EVの生産が増えている。自動車用冷延ハイテン製造会社の合弁パートナーである鞍鋼集団は中国自動車へのチャンネルをしっかりと持っており、事業を伸ばしていけると考えている。タイは市場が振るわないが、合弁パートナーと協力して特殊鋼線材を製造するコベルコミルコンスチールの体質強化を図る。インドは先行している機械系の事業をまずは強化していく。高い経済成長を持続しているが、既に多くの競合他社が参入しており、KOBELCOならではの事業が展開できるか、見極めていく」
――アルミ関連事業の黒字化が課題だが、米国事業は立て直しが進んでいる。
「サスペンション用アルミ鍛造のKAAPはようやく生産が安定し、24年度下期に黒字化した。一時期は生産が受注量に追い付かず、日本や中国からの生産支援により、輸送費などコストがかさんでいたが、一部自動化など設備を整え、労働生産性を上げている。押出品を製造するKPEXはまだ立て直しの途上にある。受注は増加しているものの製造キャパに余剰があり、ダウンサイジングにより最適化を目指す。国内も真岡製造所の合理化に取り組み、DXを活用して製造の整流化・省力化を図り、固定費を削減する」
――日本高周波鋼業譲渡の一方で成長投資を複数決めた。
「鉄鋼ではKOBEMAGの自社一貫生産を目的に製造設備を増強した。厚板とともに建設マーケットに積極的にアプローチしていく。溶接事業は溶接システム含め自動車向けを強化するため、パナソニックコネクトと協業し、溶材と溶接ロボットをセットで提案する。溶接ロボットは建設分野に強みを持つが、今後は自動車分野にも注力する。銅板は電動化などで自動車向けの端子の需要が増えている。半導体のリードフレーム需要の回復を下期に期待し、需要増に備え、長府製造所の能力を増強し、供給体制を整える」
――最重要課題の「成長追求」は機械とエンジの事業拡大が肝となる。具体化してくる案件とは。
「機械は欧州と中東にアクセスしやすいインドで27年度に産業機械の製造拠点を増強し、タイヤ・ゴム機械の生産能力増強に加えて非汎用圧縮機の新規生産を始める。お客様がグローバルに広がってきているので、新たに中東・サウジアラビアでアフターサービスの拠点を整える。また、米国のサービスショップの拡張工事も今年度中に完了する予定だ。将来的なエネルギー転換を見据えた水素・アンモニア関連や半導体検査装置などメニューの幅を広げ、成長を目指す。サービス拠点は投資額が小さく、短期に建設でき、早期に戦力化できるので積極的に展開していく」
――中計最終26年度のROIC目標(素材系6―8%、機械系8―10%)に対し、24年度は素材系が約4%にとどまり、機械系は約12%に上がった。
「機械は当社が高いシェアを持つメニューが多数ある。CNが進めば水素やアンモニア、CCUSなど新しいマーケット向けが増え、CNが遅れても石化・エネルギー関連向けの受注が見込める。エンジは直接還元鉄プラントのミドレックスが順調で、他にも廃プラスチックからエタノールを回収するプラントの開発など新しい展開もある。機械・エンジ・建機を合わせた機械系事業の売上高は25年度に8860億円(24年度8279億円)を見込む。CN関連の商業化で様子が変わってくると思うが、中長期目標の売上高1兆円に達するにはM&Aなどさらに工夫が要る。焦らず、案件を探っていく。機械系事業の経常利益は24年度で673億円。売上高1兆円で経常利益800億―900億円を想定し、1000億円も視野に入る」
――建機はエンジン認証問題でエンジン供給が受けられず、販売が減少した。24年度は影響が残ったが、どのように立て直していく考えか。
「遠隔操作システムのK―DIVEが浸透しつつある。建設現場は必ずしも平坦ではなく、遠隔であってもコクピットが傾き、危険予知も含めて作業できるなどの特徴を生かし、『コト売り・ソリューションビジネス』を伸ばしていく。ショベル以外にも工場内のフォークリフトや農業機械などへの応用が考えられ、お客様からも相談を受けている。『コト売り・ソリューションビジネス』含めここからエンジン認証問題の影響を取り戻していく」
――粗鋼生産は600万トン程度を維持している。需要が減る中でこの先の粗鋼の水準をどう考えているか。
「神戸製鉄所の高炉を2017年に休止したことで、当社の粗鋼生産の減少率は全国粗鋼の減少率より低く抑えることができている。ただ、関税問題などの影響で製造業の海外シフトが進み、国内需要がさらに減少するようであれば状況は変わるため、危機感を持ってみている。需要は増えず、減少する可能性も前提に考える必要がある」
――2030年代に改修時期を迎える高炉1基の電炉転換を検討している。需要に合わせた能力削減と組み合わせる考えは。
「減産との組み合わせで考えることは十分にあり得るが、需要の水準次第であり、将来のカーボンニュートラル(CN)の姿などいろいろな要件をみて検討する。需要の減少が速まり、電炉導入の条件が整えば切り替えた方がよいという判断になるかもしれない」
――中計の投資額を見直し、CN対応など減額した。直接還元鉄の取り組みなどに影響は。
「当初計画していた3000億円程度のCN関連投資に関し、昨今のCNの潮流を含めた外部環境変化を受け、経済合理性をよく見定める必要があると考え一部投資の意思決定時期を後ろ倒しにした。ただCNへの挑戦は変わらず、引き続きCO2の削減に最大限取り組む。オマーンでの直接還元鉄プロジェクトは事業化調査を進めているが販売先で脱炭素に向けた還元鉄の購入意欲がやや後退しており、プロジェクトの実行時期を見極めている。高炉でのCO2削減を目的に取り組んでいるHBIの多配合に加え、新たに微粉炭吹き込みの代替利用を前提に、UBE三菱セメントとブラックペレットの製造販売での共同事業化検討を開始した。これらは両立できるものであり、高炉工程でのCO2削減を着々と進めていく」
「『稼ぐ力の強化と成長追求』も投資額を減らしたが、案件を後ろにずらすもので中長期的にみて必要な投資という認識には変わりはない。足元の投資額を減らし、財務体質を改善することで、資金調達が有利になり、投資を増やせる可能性もある。一方で合理化・更新投資は増額した。自動化など『少人化』にチャレンジし、各製造部門で上げた効果をヨコ展開していく」
――事業ポートフォリオを最適化し、25年度予想の全社利益のうち機械系5割、素材系2割、電力3割。2030年に連結経常利益2000億円を目指しているが、30年時も同様の構成を想定しているのか。
「機械系は為替の円安が有利に働いている。円高となれば素材系にプラスに働くので一概に言えない。ただ、素材系は収益力を一段引き上げなければならない。アルミ関連が黒字化し収益力が上がってくれば変わってくる。国内需要が減少し、素材系は厳しくなるが、悲観ばかりではない。例えば、溶接は人手不足に対応して溶接工程の自動化に当社が持つノウハウやロボットを提供することでサービスの付加価値を上げていく。社会のニーズに応える新しいビジネスを展開することで収益を上げていきたい」(植木 美知也)















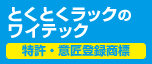
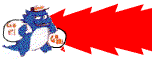


















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ