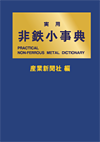2025年7月4日
商社の経営戦略/10年先を見据えて/三菱商事 今村功常務執行役員マテリアルソリューショングループCEO/多様な素材 シナジー発揮/海外で建設・エネ分野に挑戦
――マテリアルソリューショングループ発足の2024年度は厳しい船出となった。
「鉄鋼や化学品など中国の内需不振の影響を大きく受け、外部環境は厳しく、グループの純利益は683億円(前期739億円)と計画(740億円)に達しなかった。旧化学ソリューショングループと総合素材グループが統合して700人を超える大所帯となり、まずは互いのビジネスを知り、融合することを目的に施策を進めた。理解を深めるためには鉄鋼や化学の言葉ではなく、共通言語を使う必要があり、製品軸ではなくビジネスモデルで戦略を語るようにしている。『地産地消モデルの強化』、『上流ポジションの強化』、『機能素材領域における事業変革への挑戦』と各ビジネスを切り分けてコミュニケーションをしっかりとり、今年度はいよいよシナジー効果を発揮する年と位置付けている」
――24年度最終の中期経営計画で鉄鋼製品本部とメタルワンが取り組んだテーマと成果をどう評価する。
「鉄鋼製品本部イコールメタルワンだが、外部環境が厳しく、メタルワンの利益は計画に達しなかった。メタルワンの中期経営計画は『変革』と『成長』をテーマに取り組み、『変革』は内部的にも外部的にも打ち手の効果が表れ、赤字会社の数は19年度の22社から24年度に6社に縮小した。また、業務効率化を進め、社員数をマネージしながら、1人当たりの利益を大きく改善させた。『成長』は、昨年イタリアの変圧器用コア製造大手のラゴア社を子会社化し、社員を4人派遣して経営を行っている。今後さらに既存事業の延長線上ではない成長投資を数と規模ともに拡大する必要がある。米国で薄板加工サービスセンターのコイルプラスを展開しているが、建設分野でも北米で規模感のある投資を検討したい」
――25年度も厳しい市場が続く。
「鉄鋼、化学とも需要は冴えず、中国の増産ペースが保たれ、需給の構造的な弱さを引きずっている。トランプ関税が不確定要因に加わり、市場は投資判断などを控える状態が続いている。カーボンニュートラル(CN)の流れはコスト負担など現実的な議論となり、スローダウンしているが、世の中のニーズを捉えながら前進させる。グループの25年度の純利益予想は670億円。環境は厳しいが、前期並みは維持できるとみている」
――25年度開始の「経営戦略2027」のグループの重点テーマは。
「『地産地消モデルの強化』、『上流ポジションの強化』、機能素材としての『事業変革の挑戦』で共通項は『限定』だ。地産地消は経済圏を限定し、国際市場から隔絶された中で事業を行い、上流ポジションはサプライチェーン上のポジションの限定を意図し、豪州の硅砂、工業塩やバイオエタノールのビジネスを強化する。機能素材は汎用素材と比較して市場参加者の少ない分野に限定して事業を進める。鉄や化学などそれぞれの商品戦略ではなく、ビジネスモデルとして戦い方を限定し、機能とリスクを持ってどうリターンを得るかを考え、成長投資を実行する」
――地産地消、上流ポジションのビジネスモデルとは。
「北米で行っているセメント・生コンの事業は南カリフォルニアで4割のシェアを持っている。生コンは製造から短時間で使用現場に届ける必要があるため、経済圏が限定される。当事業は50カ所の供給拠点と多くのトラックを保有し、供給拠点と施工現場間を組み替えて効率よく配送することで参入障壁を築いている。このようなモデルを鉄鋼などの他素材や他地域で展開することを検討したい。素材の特性も異なり、簡単ではないが経済圏を構築できる可能性はある」
「上流ポジションは、金属資源グループは原料炭や鉄鉱石、銅など偏在資源を扱い、規模も大きいが、当グループは硅砂や工業塩などの偏在せず、開発リスクが低く、収益化が早い資源素材を取り扱う。硅砂の事業はインドネシアやマレーシアでも可能性があり、工業塩はメキシコ政府との合弁製造事業を23年度に売却したが、他地域での製造も考えている」
 ――化学品や金属など多様な素材産業に多くの機能を提供する合弁会社のビヨンドマテリアルズの取り組みに進展は。
――化学品や金属など多様な素材産業に多くの機能を提供する合弁会社のビヨンドマテリアルズの取り組みに進展は。
「出資して2年半が経つが、機能素材領域で日本の素材メーカーにサービスを展開している。自動車の領域に強い素材メーカー向けコンサルティングサービスであり、23年度に事業を始めた東洋紡との合弁会社の東洋紡エムシーに対してもサービスを提供し、自動車メーカーへの提案営業を行うサポートとなっている」
――経営戦略2027で鉄鋼製品本部が取り組む重点課題は。
「メタルワンはグループ最大で最重要の子会社、メタルワンの中期経営計画の実行をサポートしていく。多くのテーマを持ち、とりわけ成長投資の実行が3カ年のテーマとなる。既存事業の見直し、ポートフォリオのリバランスを行う。海外で展開が不十分な建設やエネルギーの分野にも挑戦する。メタルワンが強い自動車分野についても収益力を上げていく」
――前中期計画で実施してきた構造改革と異なる点とは。
「これまでは主に効率化、スリム化を目的としたものが中心だったが、これからは新規の事業を取り入れる方向に軸足を移していく。3年の間で事業の入れ替えを進め、より収益力の高い事業体に変えていく。鉄鋼としての商品戦略は当然あるが、マテリアルソリューショングループは多様な素材を持つグループであり、1つの素材にこだわらず、市場を面で捉えるビジネスモデルの取り組みをサポートしたい」
――グループ内の4本部(資源素材、鉄鋼製品、機能素材、汎用素材)間の連携をどう進め、効果を発揮していくか。
「資源素材本部は工業塩や硅砂など上流ポジションの強化にこだわる。機能素材本部は分野を機能素材に限定し、事業変革に挑む。汎用素材本部は化学品のトレーディングを主体に利益を追求する。鉄鋼製品本部は鉄鋼製品事業室と産業素材DX部、次世代素材事業部から成り、デジタルやリサイクルを本部に入れ込み、鉄鋼製品事業の幅出しをしている。1年目は融合、2年目は計画の実行を目指して組織を強くしていく。大規模な人事ローテーションを行い、700人のうち100人以上は旧組織をまたいだ異動を行ったことで、キャリアの壁は取り除いている。素材別ではなく、自動車や建設、エネルギーなど産業で捉えるとこれまでと違うアイデアが生まれる。マテリアルソリューショングループは産業の接地面が広く、幅広いビジネスが展望できるため、三菱商事の他グループとの連携も取りやすい。他グループが現在はJFEホールディングスと京浜扇島地区において電力事業とデータセンター事業を一体とした共同事業化を検討している。工場跡地の再利用はこれからいろいろなところで進む可能性があり、連携しながらよい機会に変えていく」
――経営戦略最終の27年度の利益目標にどう向かっていくか。
「市況がかつてより低い中で800億円を目指している。『磨く』、『変革する』、『創る』を定義し、孫会社含めて100社が施策を実行して収益力を上げれば大きなボリュームとなる。ポジションを変え、ビジネスモデルを起点に新しい領域に挑戦する。部門ごとに行っていた事業をつなぐような投資を実行していきたい」(植木 美知也)

「鉄鋼や化学品など中国の内需不振の影響を大きく受け、外部環境は厳しく、グループの純利益は683億円(前期739億円)と計画(740億円)に達しなかった。旧化学ソリューショングループと総合素材グループが統合して700人を超える大所帯となり、まずは互いのビジネスを知り、融合することを目的に施策を進めた。理解を深めるためには鉄鋼や化学の言葉ではなく、共通言語を使う必要があり、製品軸ではなくビジネスモデルで戦略を語るようにしている。『地産地消モデルの強化』、『上流ポジションの強化』、『機能素材領域における事業変革への挑戦』と各ビジネスを切り分けてコミュニケーションをしっかりとり、今年度はいよいよシナジー効果を発揮する年と位置付けている」
――24年度最終の中期経営計画で鉄鋼製品本部とメタルワンが取り組んだテーマと成果をどう評価する。
「鉄鋼製品本部イコールメタルワンだが、外部環境が厳しく、メタルワンの利益は計画に達しなかった。メタルワンの中期経営計画は『変革』と『成長』をテーマに取り組み、『変革』は内部的にも外部的にも打ち手の効果が表れ、赤字会社の数は19年度の22社から24年度に6社に縮小した。また、業務効率化を進め、社員数をマネージしながら、1人当たりの利益を大きく改善させた。『成長』は、昨年イタリアの変圧器用コア製造大手のラゴア社を子会社化し、社員を4人派遣して経営を行っている。今後さらに既存事業の延長線上ではない成長投資を数と規模ともに拡大する必要がある。米国で薄板加工サービスセンターのコイルプラスを展開しているが、建設分野でも北米で規模感のある投資を検討したい」
――25年度も厳しい市場が続く。
「鉄鋼、化学とも需要は冴えず、中国の増産ペースが保たれ、需給の構造的な弱さを引きずっている。トランプ関税が不確定要因に加わり、市場は投資判断などを控える状態が続いている。カーボンニュートラル(CN)の流れはコスト負担など現実的な議論となり、スローダウンしているが、世の中のニーズを捉えながら前進させる。グループの25年度の純利益予想は670億円。環境は厳しいが、前期並みは維持できるとみている」
――25年度開始の「経営戦略2027」のグループの重点テーマは。
「『地産地消モデルの強化』、『上流ポジションの強化』、機能素材としての『事業変革の挑戦』で共通項は『限定』だ。地産地消は経済圏を限定し、国際市場から隔絶された中で事業を行い、上流ポジションはサプライチェーン上のポジションの限定を意図し、豪州の硅砂、工業塩やバイオエタノールのビジネスを強化する。機能素材は汎用素材と比較して市場参加者の少ない分野に限定して事業を進める。鉄や化学などそれぞれの商品戦略ではなく、ビジネスモデルとして戦い方を限定し、機能とリスクを持ってどうリターンを得るかを考え、成長投資を実行する」
――地産地消、上流ポジションのビジネスモデルとは。
「北米で行っているセメント・生コンの事業は南カリフォルニアで4割のシェアを持っている。生コンは製造から短時間で使用現場に届ける必要があるため、経済圏が限定される。当事業は50カ所の供給拠点と多くのトラックを保有し、供給拠点と施工現場間を組み替えて効率よく配送することで参入障壁を築いている。このようなモデルを鉄鋼などの他素材や他地域で展開することを検討したい。素材の特性も異なり、簡単ではないが経済圏を構築できる可能性はある」
「上流ポジションは、金属資源グループは原料炭や鉄鉱石、銅など偏在資源を扱い、規模も大きいが、当グループは硅砂や工業塩などの偏在せず、開発リスクが低く、収益化が早い資源素材を取り扱う。硅砂の事業はインドネシアやマレーシアでも可能性があり、工業塩はメキシコ政府との合弁製造事業を23年度に売却したが、他地域での製造も考えている」
 ――化学品や金属など多様な素材産業に多くの機能を提供する合弁会社のビヨンドマテリアルズの取り組みに進展は。
――化学品や金属など多様な素材産業に多くの機能を提供する合弁会社のビヨンドマテリアルズの取り組みに進展は。「出資して2年半が経つが、機能素材領域で日本の素材メーカーにサービスを展開している。自動車の領域に強い素材メーカー向けコンサルティングサービスであり、23年度に事業を始めた東洋紡との合弁会社の東洋紡エムシーに対してもサービスを提供し、自動車メーカーへの提案営業を行うサポートとなっている」
――経営戦略2027で鉄鋼製品本部が取り組む重点課題は。
「メタルワンはグループ最大で最重要の子会社、メタルワンの中期経営計画の実行をサポートしていく。多くのテーマを持ち、とりわけ成長投資の実行が3カ年のテーマとなる。既存事業の見直し、ポートフォリオのリバランスを行う。海外で展開が不十分な建設やエネルギーの分野にも挑戦する。メタルワンが強い自動車分野についても収益力を上げていく」
――前中期計画で実施してきた構造改革と異なる点とは。
「これまでは主に効率化、スリム化を目的としたものが中心だったが、これからは新規の事業を取り入れる方向に軸足を移していく。3年の間で事業の入れ替えを進め、より収益力の高い事業体に変えていく。鉄鋼としての商品戦略は当然あるが、マテリアルソリューショングループは多様な素材を持つグループであり、1つの素材にこだわらず、市場を面で捉えるビジネスモデルの取り組みをサポートしたい」
――グループ内の4本部(資源素材、鉄鋼製品、機能素材、汎用素材)間の連携をどう進め、効果を発揮していくか。
「資源素材本部は工業塩や硅砂など上流ポジションの強化にこだわる。機能素材本部は分野を機能素材に限定し、事業変革に挑む。汎用素材本部は化学品のトレーディングを主体に利益を追求する。鉄鋼製品本部は鉄鋼製品事業室と産業素材DX部、次世代素材事業部から成り、デジタルやリサイクルを本部に入れ込み、鉄鋼製品事業の幅出しをしている。1年目は融合、2年目は計画の実行を目指して組織を強くしていく。大規模な人事ローテーションを行い、700人のうち100人以上は旧組織をまたいだ異動を行ったことで、キャリアの壁は取り除いている。素材別ではなく、自動車や建設、エネルギーなど産業で捉えるとこれまでと違うアイデアが生まれる。マテリアルソリューショングループは産業の接地面が広く、幅広いビジネスが展望できるため、三菱商事の他グループとの連携も取りやすい。他グループが現在はJFEホールディングスと京浜扇島地区において電力事業とデータセンター事業を一体とした共同事業化を検討している。工場跡地の再利用はこれからいろいろなところで進む可能性があり、連携しながらよい機会に変えていく」
――経営戦略最終の27年度の利益目標にどう向かっていくか。
「市況がかつてより低い中で800億円を目指している。『磨く』、『変革する』、『創る』を定義し、孫会社含めて100社が施策を実行して収益力を上げれば大きなボリュームとなる。ポジションを変え、ビジネスモデルを起点に新しい領域に挑戦する。部門ごとに行っていた事業をつなぐような投資を実行していきたい」(植木 美知也)














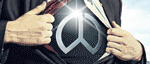

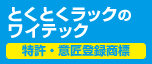
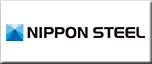

















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ